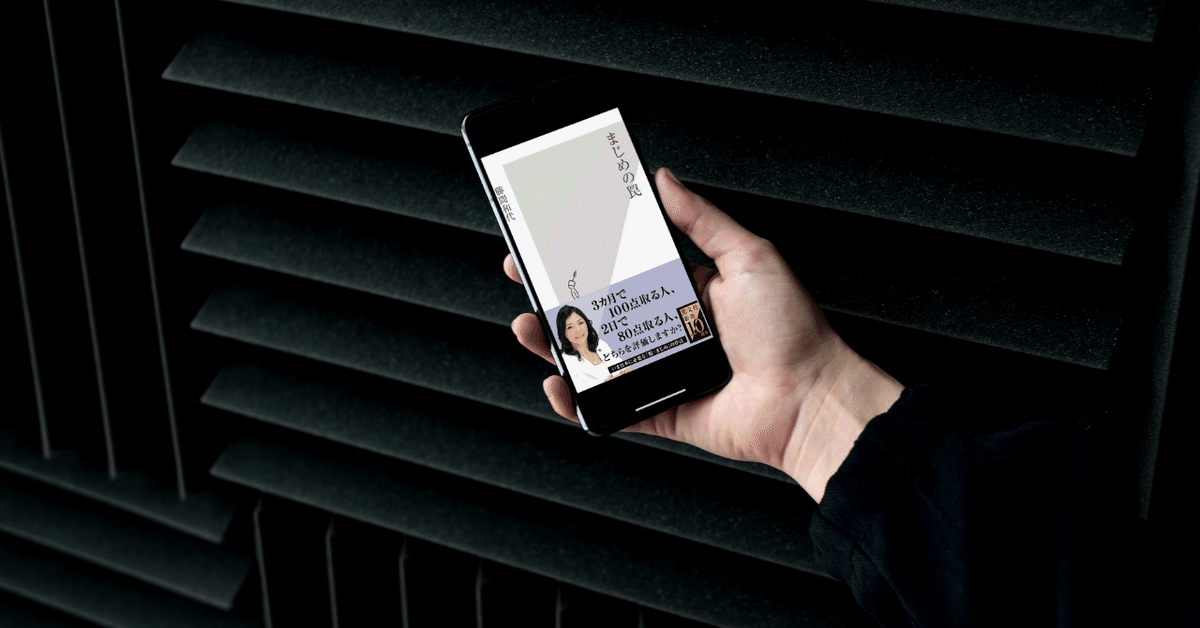
日本社会のアルゴリズムを逆手に取る|戦略的まじめ
プロフィール
1999年生まれ。東京都調布市出身。
大学を中退し、ドイツでプレーするサッカー選手。
好きなテレビ番組は「家、ついて行ってイイですか?」
勝間和代さんの書かれた『まじめの罠』という本を読んだ。
読書感想文のような形で、今日も今日とて僕が素直に思ったことをつらつらと書いていく。
「まじめ」が引き起こす弊害
ドイツに来て日本の文化を客観的に見ることができるようになった。
それによって日本の良いところも悪いところも、日本で暮らしていた時よりもはっきり見えてくる。日本にいるときは良いところだなと思っていたものが、そうではなかったり。
特に感じるのが、日本の異常さだ。
素晴らしいサービスや文化で溢れかえっている国で魅力的なのは間違いないが、それが本当に良いものなのかは疑問に感じる。この素晴らしい文化が誰かの犠牲の上に成り立っているものな気がしてならないからだ。
日本の過剰なサービス、供給過多、オーバースペック問題。少し疑問を持たねばならない社会問題だと思うようにもなってきた。
こうした日本の様々な特徴を「まじめ」という国民性の観点から観察し、問題提起をしているのが本書である。
それも主に、「まじめ」であるが故に日本に引き起こしている弊害「まじめの罠」について書かれていた。
一般的に「まじめ」は良いものとされ、日本では高く評価されるものだが、たしかにこの「まじめ」を評価することによって様々なところに弊害が出ている気がしてならない。日本で育ち、「まじめ=善」の精神が刷り込まれている僕にとって、改めて考える良いきっかけになった。
まじめを利用する
なぜ、日本では「まじめ」の文化が根付いたのか。
それは言い訳ができるからだ。
まじめに取り組んだ結果であれば成果が出なかったときに咎められずに済むのだ。「一生懸命(まじめに)やりましたが、できませんでした」と言えば、「仕方ない」となる。
しかし、目的や目標に対して、適切な方向にアプローチしたか否かなどのプロセスや努力に対してではなく、「まじめ」に取り組んだか否かという姿勢が評価されてしまうのはおかしい。
ではどうすればいいのだろうか。
僕は「まじめは利用するもの」と考えるのが良いと思う。
日本社会は、まじめであることで自分が得をするというアルゴリズムになっている。「まじめ」であることで得するのであれば、それを利用するに越したことはない。
ただ、「まじめ」であるが故の弊害もたくさんあるので、利用すると同時に「まじめ」についての罠を理解して、気をつける必要がある。
具体的にどんな罠があるのかについては本書を読んでいただきたい。たくさんの具体例が書かれている。(今ならもれなくKindle Unlimitedで読めます。)
「まじめ」になろうとすると、つい思考まで固まってしまいがちだ。しかし、「まじめ」は利用して、まじめなフリ(振る舞い)をしておくだけのもので留めておくくらいがちょうどいい。つまり、演技としてまじめを演じる。
そして、頭の中は柔軟に遊び心をもてるくらいの余白を残しておきたい。すると、まじめの罠にかからずに行動することができるようになるはずだ。
というわけで
「まじめ」の良いところだけをもらって、それを利用して生きていく。
名付けて「戦略的まじめ」だ。
この”戦略的まじめ”はドイツでも効果的に働くのだろうか。自分の身をもって検証していきたい。
ではまた!!
いいなと思ったら応援しよう!

