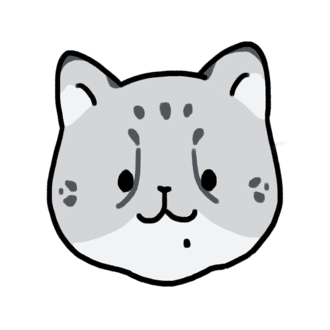具体詩と造形詩と北園克衛
少し前に、視覚詩に分類される高橋昭八郎の詩集「ぺー/ジ論」を読んだ。
高橋昭八郎は、詩人である北園克衛の実験詩のためのグループ「VOU」に参加し、詩作をスタートさせた。
北園克衛は具体詩(コンクリート・ポエトリー)や写真自体を詩であると宣言した造形詩(プラスティック・ポエトリー)を宣言し、作品を残している。
![]()
高橋昭八郎の作品を読んでから、北園克衛の作品も気になったので手にとって読んでみた。
たいした書評ができるわけではないけれど記録。
「記号説」では、文字通り、文字や記号を組み合わせた詩が特徴的。
「{}」や「【】」、ただの直線とそこに挟まれた、繋がった言葉が詩を形づくっている。
「カバンのなかの月夜―北園克衛の造型詩」では造形詩の作品がのせられている。詩といえば言葉のつらなりのイメージが強いが、そのイメージで本書を読むと肩透かしに合う。なぜなら写真自体を詩であるとしいるため、出てくる作品は写真だからだ。切り抜いた新聞紙、菓子箱、糸くずといったものが並べられ作品となっている。
![]()
正直なところ、作品群を眺めて読んでみて「なるほど...」という気持ちが精一杯。例えば谷川俊太郎の作品のような読んで共感できたり情景が想像できたりという詩より、アートに近い。
わけのわからなさがあるけれど、パラパラと眺めて見るのも良い。
研究者や批評家がまともな解釈をつけているだろうし、そちらを読むと詩集と時代背景からなぜこういった詩が生まれたのか理解が捗りそうだ。
ただ、高橋昭八郎が
「解釈することによって人間は衰退する」
と述べていたように、ページをめくって出会った詩にどう感じたかが大事で、別に解釈しようと努める必要はないかも。
「まったくわからん」や「この言葉とこの言葉の繋がりが素敵」と感じるだけでも儲けものだと思う。
「VOU」に参加した詩人の作品をさらに読み進めれば、お気に入りの作品で出会えそう。
あっ、でも歴史的な経緯を含めて知っていればより楽しめるのかもしれない。
いいなと思ったら応援しよう!