
部隊の戦闘力は指揮の構造だけで大きく変化する『軍事力を指揮する』の紹介
戦場における部隊の戦闘力を評価する際には、兵士や装備などを単位とした数量で比較しがちです。しかし、多くの研究者が定量的指標で見落とされがちな部隊の編成、兵士の士気、あるいは作戦の基本となるドクトリンの内容なども戦闘力に及ぼす影響が大きいと報告しており、それぞれの分野で因果メカニズムの分析が進められてきました。
指揮も注目されることが多いトピックです。近年では情報革命の成果を取り入れ、戦闘部隊の戦闘力を飛躍的に向上させることが期待されているのですが、具体的にどのような指揮関係を設定すれば、部隊の作戦行動にとって最適と言えるのか、議論は定まっていません。
ライアン・グラウアーの著作『軍事力を指揮する(Commanding Military Power)』(2016)はこの議論に貢献した業績です。彼は戦争ではなく、個々の戦闘における指揮のあり方が部隊の戦闘力に及ぼす影響を分析しようとしています。その研究の基礎に置かれているのは行政学、経営学で1970年代に盛んに研究された状況適合理論(contingency theory)です。
状況適合理論は状況の変化が激しい場合と乏しい場合とでは最適な組織の構造が違うことを説明した理論ですが、グラウアーも戦いの様相によって最適な部隊の指揮関係がまったく異なると主張しています。
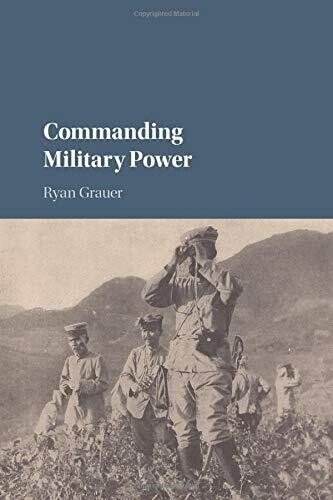
著者は戦闘の勝敗を説明するために構築された既存の理論は3つのタイプに分かれることを確認するところから議論を始めています。著者の区分の仕方は、軍事理論の研究で知られているビドルの著作『軍事力(Military Power)』に依拠しており、兵力や装備の数的優勢で勝敗を説明する理論、技術の効率性によって勝敗を説明する理論、そして兵力の運用方法によって勝敗を説明する理論の3系統に分かれています。
著者はこれらの既存の理論だけでも多くの戦闘の結果を説明することが可能であると認めています。1917年から2003年までに発生した戦闘の事例を調査すると、70%近くの事例が兵力や装備の数的優勢で戦闘結果を説明できるためです。しかし、著者は残りの30%の事例を説明できるように理論を修正することを目指しています。経営学、行政学で研究されてきた状況適合理論(contingency theory)を軍事的文脈に応用することで、興味深い研究成果を導き出しています。
もともと状況適合理論は軍隊に限らず組織全般の能率を説明するために作られた理論です。そこでは組織の能力を低下させる原因として、その組織が置かれている環境の不確実さに対し、情報の伝達が上手くいっていないことが挙げられています。組織がその能力を発揮するためには、情報の伝達を最適化できるような情報伝達がなければならないためです。
著者は「作戦環境の不確実さが相対的に増加するにつれて」「意思決定の権限を下位階層の指揮官に委ねること」が必要であると主張しています(p.4)。これとは反対に作戦環境の確実さが増しているのであれば、意思決定の権限を上位階層の指揮官に委ね、より安定した指揮系統を確立しなければなりません。著者はこうした自らの考えを指揮構造理論(command structure theory)としてまとめました。
著者が提案した指揮構造理論によれば、あらゆるタイプの指揮構造を(1)命令や情報が組織の内部を移動するために通過しなければならない階層の多さと(2)戦闘で戦術部隊を運用するために必要な権限が部下にどれほど与えられているかという2種類の基準を使って類型化できます。
例えば、その組織で一名の上官が管理責任を負う部下の人数が多くなり、統制限界(span of control)が大きくなるほど、その組織の階層は縮減しますが、上官の負担はそれだけ増大します。反対に統制限界が小さなると、上官が指揮下に置く部下の人数は少なくなるので、組織の階層は増加し、命令や報告の伝達に時間がかかります。
統制限界の規模とは別に、戦術部隊の作戦運用に関する意思決定の権限をどの階層の指揮官が握るかも指揮構造の特徴に影響を及ぼします。基本的に上位階層の指揮官に権限が集まるほど、計画的な兵力運用が可能になりますが、事態の急変に対して応急的な兵力運用が必要になる場合には不利になります。応急的な兵力運用では下位階層の各級指揮官が現地の状況に応じた指揮をとることが有利です。
著者はこれら2種類の基準を適用する際に3段階評価を行っており、全部で3×3=9パターンの指揮構造の類型を作っていますが、どれが任務遂行にとって望ましいかは組織の規模、技術の特性、さらに状況の流動性によります。組織の大規模化、技術の複雑化、状況の流動性に伴って不確実性は増大しますが、これを最小化できる指揮構造を採用していれば、敵に対して優位に立つことができるようになります。
著者の事例研究の一つに1904年8月に起きた遼陽会戦があります。これは日露戦争の最中に起きた戦闘であり、最終的に日本軍の勝利に終わりました。著者はこの戦闘の結果を説明するために、兵力の優劣、兵士の士気、装備の性能、作戦運用を分析していますが、注目すべきは指揮構造の違いであると論じています。
当時のロシア軍の指揮構造を調査すると、総司令官アレクセイ・クロパトキン(1848~1925)が集権的な指揮構造を重視していたことが分かります。戦闘が開始した時点でクロパトキンは独立行動をとる3個の騎兵部隊と、8個の軍団を指揮下に置いて、頻繁に長文の命令を下達し、部下に独断で動くことを厳しく禁じました(p. 85)。クロパトキンのロシア軍では戦術行動の意思決定を各級指揮官に委任されない指揮構造が採用されていました(pp. 83-4)。「理論的には、遼陽の作戦環境において、このような措置は不確実性を減少させるどころか、むしろ増加させてしまい、能率を低下させると考えられる」と著者は述べています(p. 86)。
ロシア軍とは対照的に日本軍の指揮構造は適度な意思決定の分散を組み入れた形態を採用していました。当時、指揮をとっていた総司令官の大山巌(1842~1916)は統制限界を狭くし、階層構造が高い指揮構造を採用していました。大山が直接的に指揮下に置いた部下は3名にすぎず、戦闘前に作戦命令を下達してからは、各級指揮官がそれぞれの状況判断に基づいて意思決定を下すことを期待していました。ロシア軍の報告では、日本軍が下士官でさえ指揮をとることがあったとされており、その戦術行動が下位階層に委任されていたことが伺われます。
遼陽会戦で日本軍が勝利を収めたことは、兵力の数的優劣で説明がつかない事例ですが、著者は指揮構造理論であれば日本軍の勝利を説明できるだけでなく、重要な因果メカニズムを捉えることが可能だと主張しています。クロパトキンは個人的に数多くの部隊の行動を統制しようとしたために、前線から上がる報告が総司令部に達し、必要な命令が下達されるまでの間に時間を要しました。しかし、大山は自分の作戦構想を踏まえて、戦闘で前線付近に位置する各級指揮官が独断専行により機敏に部隊を指揮することを期待したのです。そのことが両軍の戦闘効率に違いをもたらし、物的、人的な戦闘力の比較で予測できない結果になったと著者は説明しています。
この著作では、さらに指揮構造理論の妥当性を調べるために、国共内戦の淮海戦役(1948~1949)や朝鮮戦争の事例分析も行っているのですが、ここではその紹介は割愛します。全体を読み通してみると、指揮構造理論の妥当性を裏付ける証拠はまだわずかしかないことが分かります。おそらく、歴史上の軍隊の指揮構造に関するデータが包括的に集められ、統計的な分析ができるようになるまでには時間がかかるでしょう。
しかし、これは有望な理論であり、作戦部隊の編成に関する研究で広く受け入れられる可能性があります。情報通信技術の発達によって、一名の指揮官の統制限界を広げ、部隊の階層構造を大幅に縮減することができるかもしれませんが、それに伴って戦術行動に関する意思決定の権限を上級の指揮官に集めれば、かえって部隊行動の速さは低下し、流動的な状況に対処することが難しくなるかもしれません。このような視点は今後の軍制改革を考える上でも重要だと思います。
ちなみに、第二次世界大戦におけるアメリカ軍とドイツ軍の戦闘効率の違いをさまざまな組織的特性の組み合わせから説明した研究として、マーティン・ファン・クレフェルトの『戦闘力(Fighting Power)』(1982)があります。ファン・クレフェルトの分析を併せて読むと、戦闘効率に対する理解が理解がさらに深まると思います。
見出し画像:U.S. Department of Defense
関連記事
いいなと思ったら応援しよう!

