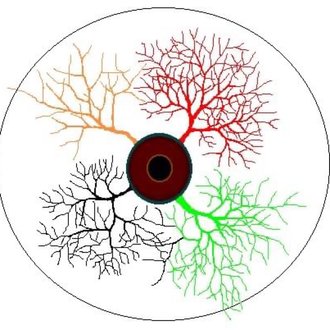★我楽多だらけの製哲書(44)★~本日開会式のイベントと三島由紀夫~
"Ich verkünde die Spiele von Berlin zur Feier der XI. Olympiade neuer Zeitrechnung als eröffnet!"
(第11回近代オリンピアードを祝い、ここにオリンピックベルリン大会の開会を宣言します)
85年前、当時ドイツの国家元首として総統の地位にあった人物が、このような開会宣言をした。
この人物はオリンピックというものをプロパガンダ(宣伝戦略)に利用したとされている。その戦略の重要な部分を占めたのが、この大会から始まった「聖火リレー」であった。このときのオリンピック自体、「平和の祭典」との整合性に疑義があったものの、その後、聖火リレーはオリンピックの欠かせない要素と考えられるようになっていくことになる。ただし、4年後の1940年と1944年は第二次世界大戦中で開催されることがなかった。そして終戦後の1948年のロンドンオリンピックでは、ドーバー海峡を聖火が渡ることができるように船を利用して、聖火リレーという要素は引き継がれた。
その間、1940年に開催が予定されていた都市は東京だったが、1937年に激化した日中戦争の影響から1938年の段階で開催は取り下げられていた。1944年の開催予定都市はロンドンで、こちらは4年後に先送りで開催されることとなった。
1940年の開催が取り下げられ、また悲惨な戦争に足を踏み入れ引くに引けないまま敗戦となった日本は、そのあと20年以上の時間が経ち、アジア初として、敗戦国の戦後復興として、ようやくオリンピック開催にたどり着いたのである。
「開会式は最後のクライマックスを迎える。聖火リレー最終走者、坂井義則(19)が、トーチを掲げてきたゲートからトラックに走り込んできたのだ。スタンドは総立ちにならんばかりの歓呼と拍手だ。白煙をひいて聖火がトラックをまわる。聖火とともにスタンドの歓呼が、北側から正面に、そして南側からバックスタンドに、津波のように大きくまわってわきあがる。坂井君は、聖火台に向かって一直線につくられた緑の会談の下で一瞬、息をととのえたのかもしれない。階段の中央に敷かれた濃緑のジュウタンの上を、坂井君は一気にかけあがる。はるか高い聖火台のわきに立って、高々とトーチを掲げる坂井君。トラックのわきにとび出して声援をおくる選手たち、スタンドの観衆、グラウンドにすえられた三つの大きな雅楽の火えん太鼓が、万雷のように鳴らされる。オレンジ色の巨大な炎が、聖火台にどっと燃えあがる。アジアに初めて燃えるオリンピアの火である。」
当時の読売新聞は、聖火リレーのクライマックスを、最終走者の躍動感に、色と音の描写を交えてこのように表現した。
今となっては当たり前になった聖火リレーであるが、1936年のベルリンの後、開催都市はロンドン(1948年)、ヘルシンキ(1952年)、メルボルン(1956年)、ローマ(1960年)であり、ほとんどがヨーロッパで、メルボルンについてもかつてのイギリスの植民地で多くのイギリスからの移民によって都市が作られたことを考えると、1936年から1960年までのオリンピックの聖火は、アテネから西洋文化圏の都市に届けられたものと見なすことができる。
その意味では、1964年の聖火リレーによって初めて聖火が西洋文化圏を離れた場所に届けられたと考えることができるだろう。
「オリンピック反対論者の主張にも理はあるが、今日の快晴の開会式を見て、私の感じた率直なところは、『やっぱりこれをやってよかった。これをやらなかったら日本人は病気になる』ということだった。思いつめ、はりつめて、長年これを一つのシコリにして心にかかえ、ついに赤心は天をも動かし、昨日までの雨天にかわる秋日和に開会式が開かれる。これでようやく日本人の胸のうちから、オリンピックという長年鬱積していた観念が、見事に解放された。式の終わりに大スタジアムの空を埋める八千羽の放鳩を見、その翼のきらめき、その飛翔のふくらみを目にしたとき、私は日本人の胸からこうしてオリンピックという固定観念が、解き放たれ、飛び去り、何ものかから癒されたいという感じがした。もっとも、放たれた鳩の一羽が、一向飛び立とうとせず、緑のフィールドに頑固に座っていた。こういう鳩もあっていい。日本人は宗教的に寛容な民族であるが、そこにはまた、微妙な宗教感覚があって、外国のお祭りで日本で本当に歓迎されるのは、クリスマスでもオリンピックでも、程度の差こそあれ、異教起源のお祭りである。小泉八雲が日本人を『東洋のギリシャ人』と呼んだときから、オリンピックはいつか日本人に迎えられる運命にあったといってよい。クーランジュによればギリシャの聖火はもともと家の神の竈の火で、聖火の宗教は、ギリシャ人・イタリア人・インド人の区別がまだなかった遠い太古に始まり、東洋と西洋の未分の時期に生まれたものであるから(これがナチスの始めた行事であるなしにかかわりなく)坂井君によって聖火台に点ぜられた聖火は、再び東洋と西洋を結ぶ火だともいえる。」
これは三島由紀夫が東京オリンピックの期間中に毎日新聞で発表した『東洋と西洋を結ぶ火』という作品の一節である。ここでは聖火によって、世界が西洋と東洋という区分けを乗り越えて、一つに結びついたことが述べられている。実際それまでのオリンピックが、西洋文化に根差す都市のみで開催され、そこに世界各国の代表が呼ばれて集まるというのは、西洋中心主義の象徴的イベントという枠内に留まるものだったかもしれないが、東洋(アジア)において初めてオリンピックが開催され、聖火がもたらされたことで、近代オリンピックを提唱したピエール・ド・クーベルタンがそこに求めた精神(オリンピズム)が真の意味で具現化したといえるだろう。
「スポーツを通して心身を向上させ、文化・国籍などさまざまな違いを乗り越え、友情、連帯感、フェアプレーの精神をもって、平和でよりよい世界の実現に貢献すること」
オリンピックの舞台が西洋に限定されず、東洋でも開催されることとなり、様々な文化・国籍の地を通って聖火がたどり着き、それに導かれるように世界各国の代表が開催都市に集まることによって、文化・国籍といった隔たりよりも、世界という一つの空間が優位なものになったといえるだろう。
本来、オリンピックが目指すものは、「世界という一つの空間を世界の人々が感じ取れること」だろう。しかし、近年のオリンピックが商業主義化の傾向にあると指摘されるように、「どのような状態で開催されているか」よりも「どこで開催されているか」または「開催によって何を求めるか」が重視されてしまっている。
「どのような状態で開催されているか」は、「世界が一つであることを感じ、平和を意識した状態」となっているかどうかが最も大切な関心事で、「その状態の実現(Unite、ユナイト)に関わるオリンピックそれ自体」が目的になるのだが、これに対して「どこで」にしても「何を」にしても、「特定の国家・都市の威信(Pride、プライド)」や「経済効果(Merit、メリット)」が目的となり、オリンピックの開催はそのための手段でしかないのである。
1964年の東京オリンピックは、アジア初の開催という点から考えれば、西洋と東洋の垣根を無くし世界が一つになったと言えるので、そこに注目すると「Unite、ユナイト」に関わるものであるといえる。しかし、三島由紀夫が「『やっぱりこれをやってよかった。これをやらなかったら日本人は病気になる』ということだった。思いつめ、はりつめて、長年これを一つのシコリにして心にかかえ、ついに赤心は天をも動かし、昨日までの雨天にかわる秋日和に開会式が開かれる。これでようやく日本人の胸のうちから、オリンピックという長年鬱積していた観念が、見事に解放された。」と表現したように、日本人にとってこのオリンピックは、純粋に「Unite、ユナイト:以下U」だけを考えていたわけではないと考えられるのである。かつての戦争の敗戦国である日本の名誉挽回という「Pride、プライド:以下P」が関わっていただろうし、その戦争で浪費したり破壊されたりした日本の豊かさを取り戻すという「Merit、メリット:以下M」も同様に関わっていただろう。
残念ながら、日本にとってこのオリンピックは「U<P・M」だったわけである。そう考えると、皮肉なものである。オリンピックは平和な世界・世界の一体化という「U」を目指すものであるが、日本は「U」を破壊・否定する戦争という出来事の中で、自国が失った「P」や「M」というものを、「U」を目指すオリンピックを利用して取り戻そうとしたからである。
戦争は「U」に含まれず、「U」の補集合と考えられるので「Ū」と表すことができる。そして日本は「Ū」によって「P」や「M」を失ったので、「Ū=-(P+M)」であった(式①)。その後、日本はオリンピックによってそれらを取り戻そうとしたので、「U=P+M」であった(式②)。式②を式①に代入すると、「Ū=-U」となる。さらにこの数式を整理すると、「U+Ū=0」となるが、この数式の意味するところは、「日本が戦争で失ったものをオリンピックというイベントを利用して取り戻す行為は、オリンピックが目指す目的を失わせゼロにしてしまう」ということになるので、それを私は皮肉なものと考えたわけである。
これに対して、2021年の夏に東京で行われたオリンピックはどのように捉えることができただろうか。先ほど述べたように、PとMを取り戻すことを、日本は一種の「国益」として考え、その目的のための手段に1964年のオリンピックを位置づけたわけである。「国益」に注目するならば、2021年のオリンピックもその実現の手段として位置づけられていたるように思える。
しかし「国益」という言葉は多義的である。私はこの言葉は次の4つの要素に分けられると考えている。その4つとは、「民衆益」「財界益」「特権益」「政府益」である。まず「民衆益」とは、その名の通り民衆の願いや幸福の実現が国家にとって大切であるという意味である。次に「財界益」とは、一般の企業や個人商店などの経済活動が健全に行われることが国家にとって大切であるという意味である。それから「特権益」とは、一部の大企業などにとって都合の良い状態が国家にとって大切であるという意味である。最後に「政府益」とは、政府の存在意義に関わる威信のようなものが国家にとって大切であるという意味である。
例えば、15年戦争中の日本にとっての「国益」について考えてみると、当初は4つの要素全てを含むものであっただろう。しかし欧米諸国、特にアメリカとの物資の差は明白であったが、それを強引に埋めるため、国内のあらゆる物資は戦争に振り向けられることとなり次第に「民衆益」は見捨てられていった。1938年4月の国家総動員法や1940年10月の大政翼賛会によって、民衆の物質的な自由も精神的な自由も奪われていったわけである。続いて、物資の埋め合わせは「財界益」にも暗い影を落とすことになる。それが1940年11月の大日本産業報国会である。そのようにして、「国益」はいつしか「政府益」や「特権益」中心のものとなっていくのである。
そして欧米諸国と肩を並べなければならずアジアにおいては指導的立場であるべきと考える「政府益」と、資源や市場の獲得によって暴利を貪ろうとする「特権益」との利害一致が、「国益」の名の下で戦線の無謀な拡大を引き起こし、戦況は悪化していくことになる。
その悪化は、さらに「民衆益」や「財界益」の犠牲を求める方向へ進んでいく。そして戦線の拡大が難しくなっていくと、「特権益」も失われてしまう。それでも撤退を受け入れず、捕虜となることを恥じとし、玉砕や特攻を指示し続けたのは、プライドという「政府益」にしがみついた結果であろう。
それゆえ合理的な判断はなされず、多くの尊い命が犠牲となり、街は破壊され、泥沼のような戦争が継続されたわけである。
さて、1964年のオリンピックにおける「国益」に話を戻すと、そこでは敗戦国の日本が失ったものを取り戻そうという思いがあり、4つの要素全てを含んでいたように思える。
では2021年の夏のオリンピックはどうであっただろうか。緊急事態宣言・まん延防止等重点措置に基づく「様々な自粛」「時短営業」「イベント中止」「罰則」といったものを駆使することで実現を手繰り寄せたオリンピックに関わる「国益」には、「民衆益」や「財界益」は果たしてどれくらい含まれているだろうか。そしてスポンサーに対する「特権益」も無観客開催によって削らざるを得なかった。
そうして最後に残ったのは「政府益」だとされる報道も目についた。これが、2021年のオリンピックに関わる政治の在り方と、15年戦争に関わるそれが似ていると指摘される所以だと私は考えている。そのようなオリンピックも過ぎ去り、気づけば今日は2022年北京冬季オリンピックの開会式である。2021年の夏季オリンピックと同じように、観客などの制限があって、2008年の北京夏季オリンピックとは雰囲気もかなり異なるものになるのは間違いがないだろう。
コロナ禍であることを考えれば仕方のないことなので、それを受け入れつつ、しかしオリンピック特有の華やかさを、せめて理念の世界でイメージするために、1964年のオリンピックの新聞記事を載せておこうと思う(記事はネットオークションで手に入れたものである)。
また、商業主義偏重であったり、人権問題であったりと、近年はオリンピックの意義について考えさせられる場面が多いのだが、オリンピックには依然として「Unite、ユナイト」の精神が宿っていることを信じたい。
#哲学 #三島由紀夫 #聖火リレー
#オリンピック #東京オリンピック #北京オリンピック
#スポーツ観戦記
(以下に、1964年当時の新聞記事を紹介)
この記事が参加している募集
この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?