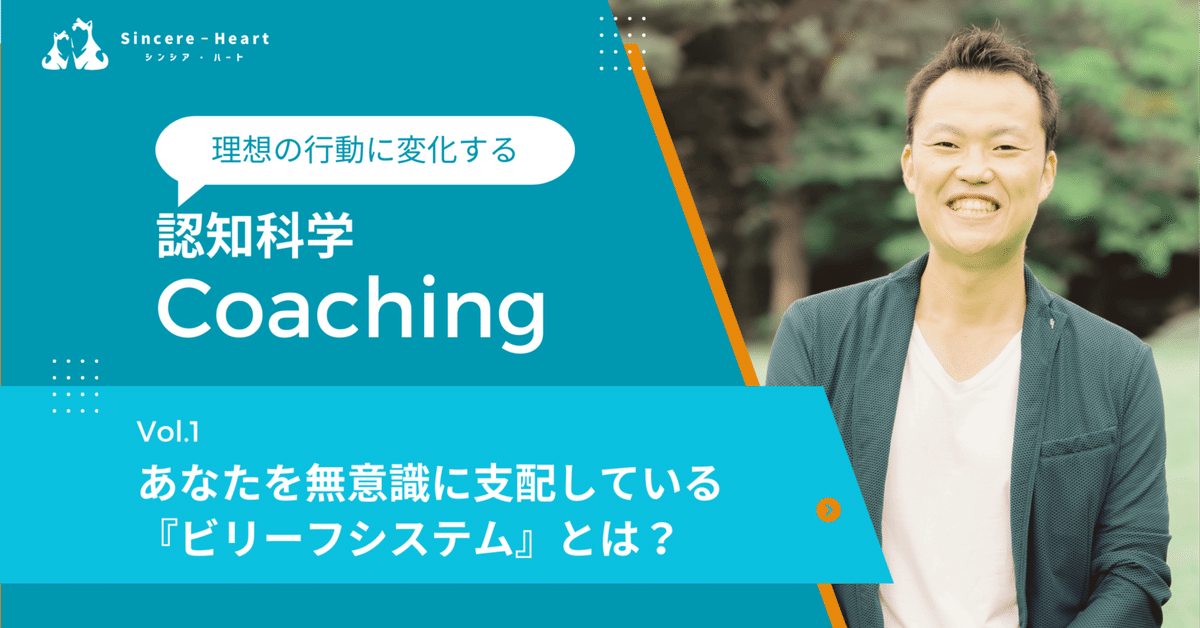
あなたを無意識に支配している『ビリーフシステム』とは?~認知科学コーチング Vol.2~
こんにちは。株式会社シンシア・ハートで代表取締役をしている堀内猛志(takenoko1220)です。
こちらのnoteでは、認知科学に基づいたコーチングについて、知っておくべき用語の解説、コーチングの実践方法、コーチングの事例を解説しています。
堀内は何者か、なぜコーチングを始めたのかは以下のnoteをご確認ください。
さて、今回から数回にわたり、認知科学コーチングを実践するコーチ、コーチングセッションを受けるクライアント両者が知っておくべき用語について解説していきます。
今回は『ビリーフシステム』について解説します。
『ビリーフシステム』とは?
常識とは18歳までに身に着けた偏見のコレクション
ノーベル物理学賞を受賞したアルベルト・アインシュタイン氏は言いました。
常識とは18歳までに身につけた偏見のコレクションのことだ。
(Common sense is the collection of prejudices acquired by age 18.)
あなたが今まで生きてきた中で経験した様々なことは、あなたの心と脳に無意識レベルで書き込まれており、それがあなたにとって重要な基準となって物事を判断しているのです。
このような、あなたの脳と心が認識している「モノの見方」とは、意識的・無意識的に寄せ集められた価値観の集合体であり、これを『ビリーフシステム』と呼びます。
例えば、この写真を見てあなたはどんな言葉や感情があふれてきますか?

(美味しそう!) ☞ 『飲みたい!』
このように思って言葉を発したAさんは、過去の経験でワインを美味しく飲み楽しんだ経験があり、「ワイン=素敵なモノ」という見方をしています。
一方で、
(毒だ!) ☞ 「見たくもない!」
このように思って言葉を発したBさんは、過去の経験でワインが飲めなのに無理やり飲まされて苦しんだ経験があるのかもしれません。よって「ワイン=良くないモノ」という見方をしています。
このように、物理世界では同じ物体を見ているにも関わらず、そのモノの見方が人によって違うわけです。
心が動くと頭が動き、頭が動くと身体も動く
思考よりも感情の方が早く動きます。よって、感情がポジティブに動けば、思考もポジティブに動くため、体にすぐに動くよう命令を出します。
逆に感情がネガティブに動いた場合、思考はネガティブな事象を回避するために動き出します。結果、身体には動かないで良いという命令を出します。

つまり、受験勉強や仕事など、一般的に辛いと思われがちなモノを辛いと思いながらも「でも頑張ろう!」と奮い立たせようとしても効率が悪いわけです。「やりたくない」というココロと「やらなきゃ」というアタマが戦っているわけですもんね。非常にストレスです。そんな状態ではカラダはうまく動けません。
認知科学では、心と脳のことを合わせてマインドと呼びます。マインドには上記を含めたような様々なカラクリがあり、そのカラクリをうまく利用することで、効率よく身体を動かします。「やらなきゃ」ではなく「やりたい」と思って動くと楽しいし、効率的ですよね。
インプットからアウトプットまでの流れを図解化したのが下記です。インプットとアウトプットの間のプロセスをビリーフシステムだと覚えてください。

「マインドのカラクリを利用してビリーフシステムを書き換えましょう」
認知科学コーチはよくこのような言葉を発しますが、言い換えると、
「心と脳の特性を利用して、あなたのモノの見方を変えましょう」
ということを言っているのです。
コーチングにおいて言葉の認識をそろえることは、コミュニケーションの上で大切なことですので覚えておいてくださいね。
脳は2つある?
感情は思考よりも早いと前述しました。心理学・行動経済学の分野では、「思考には早い思考と遅い思考の2つのモードがある」という理論があります。学術的には二重システム理論と呼ばれます。
詳しく知りたい人は以下の「ファスト&スロー」を読んでみてください。
読まなくても概要はわかるように簡単に説明します。
早い思考のことをシステムⅠ、遅い思考のことをシステムⅡと言います。人間の思考はシステムⅠがデフォルトです。
九九と計算を考えてください。
6✖️7=?
8✖️9=?
5✖️5=?
日本人なら一瞬で答えられると思います。それは九九を丸暗記しているからであり、頭の中で難しい計算をしなくても直感的にわかるからです。この時あなたの中で使っている思考がシステムⅠです。
それに対して、
3456✖️5945=?
ソロバンをやっていない人じゃないとこの問題を一瞬で解くことはできないと思います。しかし、時間をかけて筆算を使って計算すればほとんどの人が回答できますよね。この時あなたの中で使っている思考がシステムⅡです。
計算だけではなく、ランチに食べたいメニューを選ぶときなど、様々な場面で人はシステムⅠを使っています。数あるメニューを全部並べ、値段、カロリー、好み、頻度、エシカルなど様々な指標を考慮し、最適解を選ぶような思考をしていますか?そんな面倒なことをせずに「ん〜じゃあカレーで」「あ、じゃあ私も!」とか言ってますよね?システムⅠをデフォルトで使うことで、思考体力を無意識に温存しているんです。
蛇足ですが、定食屋も「今日のおすすめ」とか「日替わり定食」などを活用していますよね。これは、いちいちシステムⅡで全てのメニューを見て比較されるとオーダーに時間を要するので、システムⅠでおススメや日替わりを直感的に選んでね!ってことなんです。
システムⅠとかシステムⅡとかは使い慣れていないので、あなたの中には象と象使いがいると思っておいてください。象は直感的でパワフルです。食べたいと思ったら食べるし、寝たいと思ったら寝ます。それを阻止するのが象使いです。「まだ食べるな!」「まだ寝るな!」と命令します。しかし、象の方が人間の象使いよりも圧倒的にパワフルですよね。だからなかなか止められないんです。

このシステムⅠの象のパワフルさを利用するのもまたマインドのカラクリの一種です。少しややこしくても解説したのは「システムⅠというマインドのカラクリをよく活用する」からなんです。
『ビリーフシステム』は変わるのか?
ビリーフシステムを書き換えると過去も変えられる?
「変えられるのは自分と未来」「変えられないのは他人と過去」というような言い方をしますよね。しかし、ビリーフシステムを使えば過去だって変えることができるのです。
正確に言うと「過去の体験の捉え方(モノの見方)を変えることで、自分の中の心のトゲを抜くことができる」ということです。
幼少期の辛い原体験がトラウマになり、ビリーフシステムに書き込まれているために行動が抑圧されている人がいます。逆に言うと、ビリーフシステムを書き換えれば、過去体験はトラウマではなくなり、行動が変わっていくということです。
ここでは方法論には触れませんが、ビリーフシステムを書き換えるという力の強大さを認識してもらえればと思います。
ビリーフシステムを書き換えるために必要な『ゴール設定』
ビリーフシステムを書き換えるためにあなたがまず行うことは『ゴール設定』です。認知科学コーチングはゴールを設定するところからスタートします。
ゴールの設定と聞くと反射的に返ってくるのが「やりたいことがない」という声です。認知科学コーチングでは「やりたいこと」を「want to」と言い換えて対話をしますが、自分の中のwant toを見つけることはゴール設定において欠かせない要素のひとつです。
「え?じゃあwant toがないとやばいじゃん?」って思った方は安心してください。ゴール設定や自分のwant toの見つけ方は別のnoteで解説していきたいと思います。
自分1人だけではビリーフシステムを書き換えられないからこそコーチが必要
用語の解説や簡単な方法論はnoteで解説をします。しかし「知っている」と「できる」が違うように、コーチングの理論を知っても自分一人だけではできないことがほとんどです。だからこそコーチ自身も自分のコーチをつけている人が多いのです。
自分以外の誰か=コーチの存在があるので、『現場の外側にあるゴール設定』が可能になります。先が見通せないVUCAの時代にコーチの需要が増しているのもうなづけますね。
コーチングのモニターを募集します
ここまでのnoteを読んでいただき興味を持っていただいた方、これから書き連ねる他のnoteを読んでコーチングを受けてみたいと思った方に対してモニターセッションを実施させていただきたく思っています。
もし興味をお持ちいただいた方は、以下のフォームからご応募ください。
モニターセッションでは友人知人の方も大歓迎です。本番のコーチングではお互い深い関係じゃない方がコーチングの効力を発揮するため、友人からのご依頼はお断りすることになりますが、モニター期間中は大歓迎です。
また、僕と全く面識がない方からのご応募もお待ちしています。当然、知らない人にコーチングをお願いするのは躊躇いもあると思いますので、僕はモニターセッション開始前に自己開示を兼ねて認知科学コーチングについてのアウトプットを始めることにしました。デビュー前にファンを作るジャニーズJr.戦略です(笑)僕のことを知らなかったけど、僕のアウトプットを見て興味を持った方は、是非、以下のフォームからご応募ください。
モニターセッションも、これからのアウトプットも皆様の為になるように精進します。是非、お楽しみにしてください。
それでは今日も素敵な一日を!
