
Books, Life, Diversity #16
どのみち病気で今月には亡くなるだろう誰かが通院する途中で轢き逃げされて亡くなったとして、今月の死者の総数としては変わらないのだから構わない、とはなりませんよね。そしてそういった目に遭いやすいのは、身体的、社会的に弱い立場の人である可能性が高いでしょう。データは社会から切り離して考えることはできないという単純な事実は、客観性を否定するためのものではなく、創造性や想像力の必要性を訴えるためのものです。だから、理系とか文系とかって線引きにそこまで固執しないで、どっちも大切にしながらこの世界のリアルを見通す力を持てるようになれば良いよね、と私は思います。そんなこんなで第16回は死について。
「新刊本」#16

フレデリック・ベグベデ『世界不死計画』中村佳子訳、河出書房新社、2019年
フランス人作家ベグベデによる、半分サイエンスノンフィクション、半分フィクションの形を取った、不死に取りつかれた男の物語です。主人公は娘を連れて世界中の研究者やほとんどカルトのようにも思える医療施設を訪れ、人間が不死になる可能性について根掘り葉掘りと訊いて回ります。小説としては面白いというほどではありませんが、重いテーマをどたばたと追い求める主人公は(嫌な奴でもあるのですが)ユーモラスで、読みやすい物語になっています。不死を目指す技術の現状をざっと眺めるには良い本です。ネガティブな意味ではなく、しっかりしたコンセプトに基づくポップサイエンスはこれからますます重要になってくるジャンルですし、私もいつか、専門分野と物語を繋ぐ虚実入り混じったお話を書きたいなあと思っているので、こういう本って好きです。不死を巡る物語としては何千年も前に書かれた『ギルガメシュ叙事詩』(矢島文夫訳、ちくま学芸文庫版が簡単に手に入ります)がもっとも知られていますが、改めて、人は人である限り変わらないのだなあと感じますね。
「表紙の美しい本」#16

テッド・ピータース、ロバート・J・ラッセル、ミヒャエル・ヴェルカー編『死者の復活 神学的・科学的論考集』小河陽訳、日本キリスト教団出版局、2016年
2001年にハイデルベルクで開かれた国際学術フォーラムにおいて、自然科学と神学の分野から第一級の学者チームが集められ、「復活」問題を巡って一連の会議が開催された。それはキリスト教神学と自然科学の間の創造的対話を目的としたものであり、本書は翌年にその成果として出版された。(「訳者あとがき」より)
私は神学も情報科学も中途半端なままに終えてしまった人間ですが、けれども、安直なポストヒューマン思想が溢れるこの時代において、真正面から復活について論じ尽くそうというこの本のような試みには、心から賛同します。「けれどもももしおまえがほんとうに勉強して実験でちゃんとほんとうの考とうその考とを分けてしまえばその実験の方法さえきまればもう信仰も化学と同じようになる」(宮沢賢治『ポラーノの広場』新潮文庫)という言葉の、現時点における到達点のひとつでしょう。かなり分厚い本ですが、論文集なので興味のあるところから読んでも大丈夫です。私がもっとも好きなのはヘルツフェルドによる章です。
科学と技術の中心的目的は客観的、物理的な世界を理解しかつ制御することである。〔中略〕そのような世界においては、サイバネティックス的不死は「より多くの時間」となり得るだけである。物理的宇宙の限界ということを考えれば、それは終わりのない時間ではなく、またわれわれはそれがそうあって欲しいと望むだろうと私は推定することもできない。〔中略〕地上の命は天国でも地獄でもない。それは、大きな苦難が大きな喜びと並んで存在する中間の領域である。Alle Menschen müssen sterben. 全ての人は死なねばならない。命は、そのようでなければ、その味わいを失うだろう。(ノリーン・ヘルツフェルド「サイバネティックス的不死対キリスト教的復活」p.264)
美しい装丁は桂川潤氏によるもの。私たちの生を俯瞰する視点、それがどこにあるのかは分かりませんが、私たちがいつか通るであろうその場を予感させるようです。
「読んでほしい本」#16
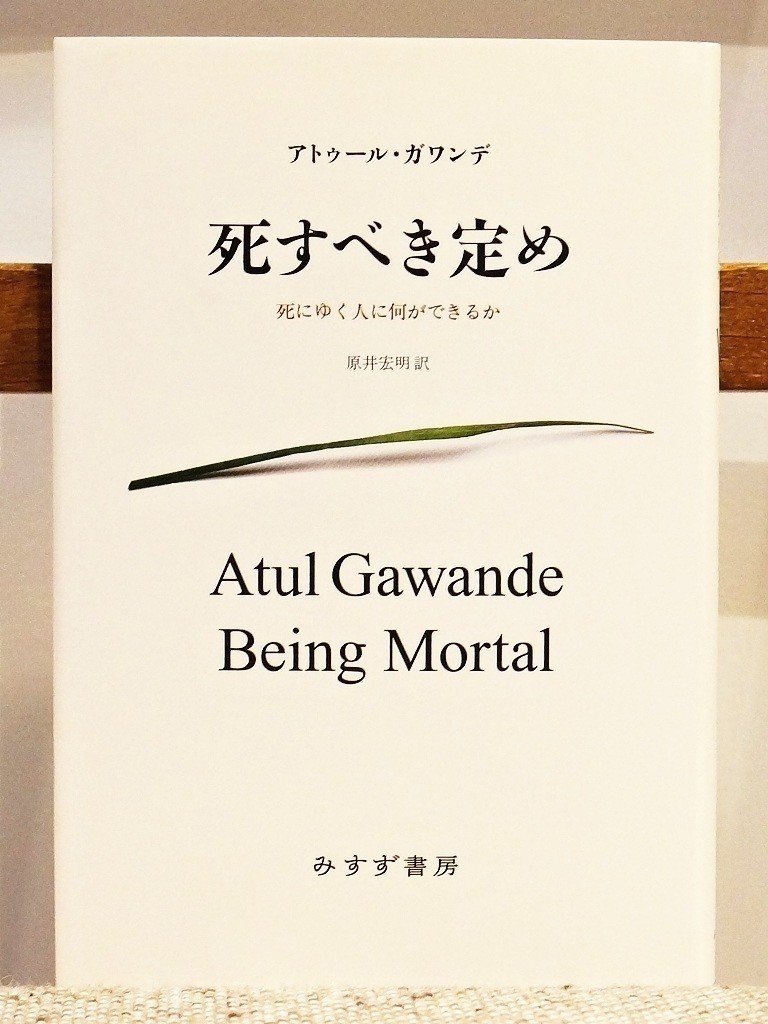
アトゥール・ガワンデ『死すべき定め 死にゆく人に何ができるか』原井宏明訳、みすず書房、2016年
本書は、米国の外科医でもあるガワンデが、彼自身の人生や経験、あるいは様ざまな事例を引きつつ、人が尊厳をもって死ぬとは、いえ、もっと正しく言えば人が「人間らしく」死ぬとはどういうことなのかについて語った、ヒューマニズムの美しい結晶とも言える思想の書です。これは本当に読んでいただきたい本です。ちょっと、だらだら書こうと思ったのですが、4年前に自分のブログで紹介していた文章がいま書くよりもよほどましなので、表記のみ少し変えて貼りつけてしまいます。これを書いたの、もう4年前か……。もっとちゃんと生きなきゃな……。
*
最近、A・ガワンデ著『死すべき定め―死にゆく人に何ができるか』(原井宏明訳、みすず書房、2016年)を読みました。これが素晴らしかった。中でも、第5章「よりよい生活」で紹介されている、1990年代、NYのとあるナーシング・ホームにおけるビル・トーマスの試みの紹介がとても良いのです。トーマスは彼が務めることになったナーシング・ホームの入居者たちが、何故これほどまでに絶望的な余生を送っているのか、素朴にも疑問に感じました。そしてそれを改善していこうという精神力とアイデア、そこに人を巻き込んでいく人間的魅力において、トーマスは非常に優れていました。彼が試みたことは、ホームに生命(動物)を持ち込むことでした。しかしそこには当然、衛生上の問題などのために、多くの規制がありました。そこで、何とかしてたくさんの動物を持ち込もうとするトーマスと所長のロバート・ハルバートとがやりとりをするのですが、それが何ともユーモラスなのです。
ニューヨーク州のナーシング・ホームに対する規制は、一匹の犬と一匹の猫だけを許可している。ハルバートはトーマスに、過去に二、三回犬を入れようとしたが、不首尾に終わったことを説明した。動物の性格が悪かったり、動物にきちんとした世話をするのが難しかったりした。しかし、ハルバートはもう一度試す気はあると話した。
それでトーマスは言った、「じゃ、犬二匹で試してみましょう」。
ハルバートは「規則では認められていません」。
トーマスは「まあ、それで申請を書いてみましょうよ」。(p.111)
ハルバートもまた度量のある人間だったのでしょう。ここで彼はナーシング・ホームにおける衛生と安全性という、これはこれで極めて重要な目的との間で葛藤します。しかしそれでも、ハルバートはトーマスの心に影響されていきます。ハルバートはトーマスとのやりとりをガワンデに語ります。
私はこう考えはじめていたんだ、「あなた方ほどには私はこれに関わることはないのだけれど、とにかく二匹の犬を持ち込むことにしよう」。
トーマスは「じゃあ、猫はどうしましょう?」と言った。
私は「猫をどうしましょう?」と返して、「とにかく二匹の犬をもちこむと申請書に書くべきです」と答えた。
トーマス「犬好きじゃない人もいるから。猫好きの人とか」
私「つまり犬と猫の両方が要るとおっしゃる?」
トーマス「とりあえず、それを書き残しましょう、議論のテーマとして」
私「オーケー、猫も加えて書きます」
「ノー、ノー、ノー。うちの施設は二階建てです。二階のそれぞれに二匹ずつの猫でどうでしょう?」
私「州保健部には、犬二匹、猫四匹と提案しようと思いますが?」
トーマス「イエス、そう書いてください」
私「了解です。そんなふうに書きましょう。話がちょっと広がりすぎた気もしますね。空を飛ぼうとかいう話じゃないはずです」
トーマス「一ついいですか。鳥はどうなんでしょう?」
規制は明確だと私は答えた、「ナーシング・ホームでは鳥は認められていません」。
トーマス「しかし、鳥はどう?」
「鳥はどうですかね?」と私。(p.112)
結局、ナーシング・ホームのスタッフはトーマスの主張に同意して申請書を書き上げ、これが補助金申請を通ってしまいます。このあとの騒動、そしてそれがナーシング・ホームに与えた影響については、ぜひ実際に読んでみてください。
また別の試みを行っている、あるホームにおける話も印象的で、特に、そこに入居しているマックオーバーという高齢の女性の話には胸を打たれます(ここはバンド・デシネの名作『皺』のラストシーンを思い出させます)。彼女は「加齢に伴う網膜変性のためほぼ失明していた」のですが、それでも著者に対してこのように言います。
「また会うときには、あなたが誰だかわからないでしょうね。あなたは灰色に見えるわ」。マックオーバーは私に話してくれた。「だけど微笑んでいるわね。それは見える」(p.126)
基本的に、この本で語られるのは、人は如何にして人間としての尊厳を持ったまま死ぬことができるのか(生きることができるのか)ということです。著者のガワンデは外科医なのですが、外科医らしい客観的、科学的な視線を保ちつつも、暖かさの溢れる文章で、死にゆく様々な人びとを描いていきます。そして、そこではひとりの人間としての自立が重要であることを示します。
ぼく個人は、人間の自立、ということに対して、それほど重きを置いてはいません。むしろ死ぬ最後の瞬間まで自立した個人であることを強要されるのであるとすれば、それはそれで相当に異常で厳しいものではないかな、と思ったりもします。だから、ガワンデが自らの父を看取ったあと、その遺骨をガンジス河に流すシーンは非常に考えさせられる、また感動的なシーンでもあります。
親がどれだけ努力しても、オハイオの小さな町で子どもをまともなヒンズー教徒に育てるのは難しい。神が人の運命を決めるという思想を私は信じる気にはならないし、これからやることで死後の世界にいる父に何か特別なことをできるとも思わない。ガンジス川は世界の大宗教の一つにとっての聖なる場所かもしれないが、医師である私にとっては、世界でもっとも汚染された川の一つとして注意すべき場所である。火葬が不完全なままに投棄された遺体がその原因の一つである。そうしたことを知りながら、私は川の水を一口飲まなければいけなかった。ネットでバクテリアの数を調べておいて、事前に抗生物質を服用しておいたのだった(それだけしてもジアルジア感染症を起こした。寄生虫の可能性を見落としていた)。
だが、そのとき私は自分の役割を果たせることに感動し、深く感謝もしていた。一つには、父がそう望んだからであり、母と妹も同じだったからだ。そしてそれ以上に、骨壺と灰白色の粉になった遺灰の中に父がいると感じることはなかったのだが、悠久の昔から人々が同じ儀式を営んできたこの場所にいることで私たちを越えた何か大きなものと父を繋ぐことができたように私は感じた。〔中略〕
限界に直面したとき父がしたことの一つは、それを幻想抜きに見ることだった。状況によってはどうしようもなくなるときはあったが、限界を実際よりもよいと偽ることは決してしなかった。人生は短く、世界の中で一人が占めるスペースは狭いことを父は常にわかっていた。しかし、同時に父は自分を歴史の繋がりの中の一つの輪と見ていた。あらゆるものをのみ込む川の上に浮かんでいると、悠久の時間を越えて無数の世代が手を繋いでいるような感覚が私をとらえ、離さなかった。父は家族をここに連れてくることで、父も何千年にわたる歴史の一部であることを私たちにもわかるようにしてくれたのだった――私たち自身もその一部だ。(p.264-265)
これは、とても良く分かります。神を持たないぼくでさえ、このような感覚をどこかで共有しているからこそ、身近な人びとの死に対して、それでもなおそこに悲しみだけではない何かを抱くことができます。ぼくらは最後の最後まで自立を強要され得るような超人ではない。だけれども、さらに同時に、こうも思うのです。人間のリアルな生において真の意味での自立を貫徹することなど不可能だと研究上の立場としては思いつつ、同時に、自立への狂気にも似た妄執に駆り立てられたまま死んでいく人びとの、その個人個人でありつつも人類という種でもある何者かが抱えた悲しみと愚かさは、つまるところ個人の自立も国家や民族への帰属も不可能だと考えるぼくのような人間もまた同じように抱えているものと何も変わらないのだ、と。
*
この一連の記事では、出版支援として以下のプロジェクト/情報へのリンクを毎回貼らせていただきます。
