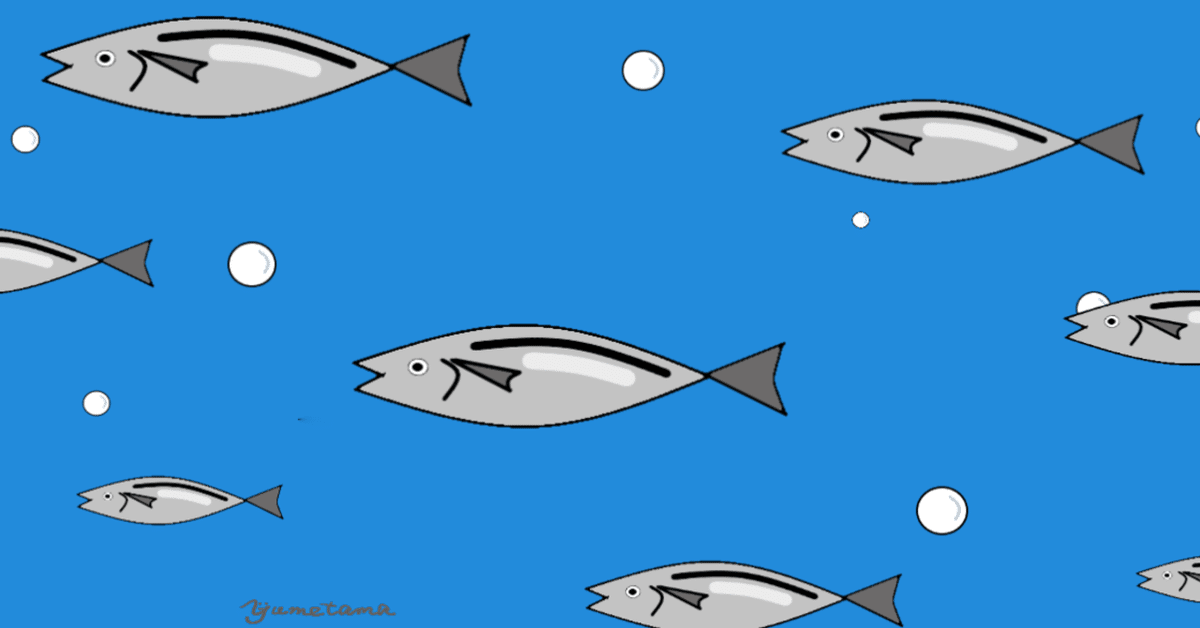
編集者の仕事はコンテクストの構築
今日は「コンテクスト」の話をします。
編集者は何をやっているのか? 当然「コンテンツを磨く」というのも大切な仕事ですが、「コンテクストの構築」もすごく重要な仕事です。
この「コンテクスト」。ちょっとわかりにくい概念なのでnoteにいつかまとめたいと思っていました。うまく説明できるかわからないですが、ちょっと挑戦してみます。うまくいかなかったらまた書きます。
ちなみにコンテクストを広辞苑でひくと「文章の前後の脈絡。文脈」と出てきますね。ただ、いまはもっと広義でとらえられているように思います。
コンテクストの要素① 誰が言うか
コンテクストの要素には、まず「誰が言うか」があります。
たとえば「大学名なんて関係ないよ」という言葉があります。
これをもしふつうの人が言ったとしたらどうでしょうか? 「うーん、まあそれもわかるけど、大学名ってやっぱブランドだからね」と思われます。
一方で、東大生が同じことを言ったら謎の説得力がうまれます。なんかカッコよく聞こえる。
「このラーメン、めちゃくちゃうまいですよ」という言葉も、そのラーメン屋のおやじが言うと「まあ、そう言うわな」と思います。一方で全国のラーメン店を食べ歩いてきたラーメン評論家が言うと「食べに行きたい!」と思うはずです。
同じ言葉なのに「誰が発するか?」「誰の言葉なのか?」ということで意味が変わってくるわけです。
「お金なんていらないよ」と一般のサラリーマンが言うのと前澤さんが言うのとでは意味や重みが違ってきます。「保育園落ちた日本死ね」というのも一般の30代女性の言葉だったからズシンと来たわけです。
まったく同じセリフでも「誰が発信するか」で意味が変わってくる。誰もが発信でき、誰もがメディアになれる時代。だからこそ、この「誰が言うか」というところまできちんと考えて、コンテクストを設計する必要があるわけです。
コンテクストの要素② どのメディアを選ぶか
「適切なメディアを選ぶ」というのもコンテクストに関わってきます。
Twitterに書くか、Facebook に書くか、メールで送るか、LINE で送るか、電話で言うか、クラブハウスで言うか。それも公開で言うか、クローズドで言うか……。
それによって同じことを言ったとしても意味合いが変わってきます。
メディアによって「重み」も変わります。
誰かに何かをお願いするとき、LINEやメッセンジャーで送ると印象は軽くなります。「そんなに大したお願いじゃないのかな?」と思われる。
でも、それをメールもしくは手紙で送ると重みが増します。しかも「よろしくお願いいたします。」と手紙に筆で大きく書かれていたら「おお!」と思うはずです。同じ文面でも意味合いは違ってくるわけです。
いまはあらゆるメディアがあるので「どのメディアを選んだか」ということ自体がメッセージになります。編集者は「どのメディアで伝えるといちばん効果があるのか」を考える必要があります。
コンテクストの要素③ どこから光を当てるか
あとは、コンテンツへの「光の当て方」です。
わかりやすく言えば「タイトル」とか「テーマ」の話になるかもしれませんが、この「光の当て方」を変えるだけでも文脈が変わって伝わり方が変わってきます。
前にツイートした内容ですが、たとえばこんな社員へのインタビューがあったとします。(内容自体は別におもしろくないと思うのでさらっと読んでください。)
社員インタビュー 営業部・田中一郎さん
営業部の田中一郎さんは2010年入社。10年間、営業部でがんばってきた。そして昨年ついに成績トップ。MVPに輝いた。
「営業ってなんか泥臭いイメ ージがあると思うんですけど、すごくクリエイティブな仕事だと思うんです。つねにお客さんのことを考えて、どうやったら喜んでもらえるかなと考える。すごく素敵な仕事だと思います」と話す。
田中さんの営業のやり方は独特だ。
「私は最初にお客さまとお会いするときは、こちらの話は一切しません。もちろん聞かれたら答えますが、まずは相手の話を聞くことに専念します。すると気づけば、お客さまは自分の悩みを話しています。そこで初めて、それをうちがお手伝いしますよ、と切り出すのです」。
田中さんはしばらく成績がふるわなかったが、このやり方にしてからどんどん注文をもらえるようになったのだという。
社内報などでふつうに関係者だけに読んでもらう場合はこれでいいでしょう。ただ、田中一郎さんを知らない普通の人はおそらく立ち止まって読むことはないでしょう。
この記事を内容は変えずに、タイトルと構成を変え「仕事術」として光を当ててみるとこうなります。
ダメ営業マンだった私がトップ営業マンになれたワケ
「営業は自分の話をしてはいけない」。トップ営業マンの田中一郎さんはこう話す。
「私が最初にお客さまとお会いするときは、こちらの話は一切しません。もちろん聞かれたら答えますが、まずは相手の話を聞くことに専念します。すると気づけば、お客さまは自分の悩みを話しています。そこで初めて、それをうちがお手伝いしますよ、と切り出すのです」。
田中さんはしばらく成績がふるわなかったが、このやり方にしてからどんどん注文をもらえるようになったのだという。
2010年入社の田中さんは10年間、営業部でがんばってきた。そして昨年、ついに成績トップ。MVPに輝いた。
「営業ってなんか泥臭いイメージがあると思うんですけど、すごくクリエイティブな仕事だと思うんです。つねにお客さんのことを考えて、どうやったら喜んでもらえるかなと考える。すごく素敵な仕事だと思います」と話す。
内容は一緒です。
しかし「仕事術」という角度から光を当てたことで読者がガラッと変わるはずです。これであれば、この会社の社員でなくても田中一郎さんを知らない人でも、仕事をしている人、営業をしている人は関心を持ってくれるかもしれません。
同じコンテンツであっても「光の当て方」を変えることで読者の数を変える。これが編集の仕事なのかなと思います。
どの川にたくさん魚が泳いでいるか
「コンテクスト」を説明するために、いいたとえを示したいと思っているのですが、、、たとえばこんなイメージはどうでしょうか?
あなたの目の前に川が何本も流れています。
大きな川、小さな川、流れの速い川、流れの停滞している川……。そしてそれぞれに魚が泳いでいます。
「適切なコンテクストを選ぶ」というのはこの「どの川にコンテンツを置くか」という話なのかなと思います。
大きな川には当然たくさんの魚が泳いでいます。なのでそこにコンテンツを置けば、多くの魚が通り過ぎてくれます。
一方、小さな川、停滞している川には魚があまり泳いでいません。そこにコンテンツを置いても、そんなに魚は来てくれません。
上の例で行くと「社員インタビュー 営業部・田中一郎さん」の記事は、小さな川に置かれたコンテンツです。小さな川なので少ししか魚はいません。
一方「ダメ営業マンだった私がトップ営業マンになれたワケ」の記事は大きな川に置かれたコンテンツです。「仕事術」「営業術」という大きな川にはたくさんの魚が泳いでいる。そこにコンテンツを置くことで多くの人に見てもらえる可能性が生まれます。
意味わかります?(伝わってなかったら、今度もう一回書きます。)
世の中にはいろんな川が流れています。
「お金の稼ぎ方」「長生きの方法」「頭がよくなる方法」みたいな川は大きな川です。たくさんの魚がいる。
一方で「弊社の新入社員紹介」「接続詞の正しい使い方」といった川は小さな川です。そんなに魚は泳いでいません。
シンプルにすると「マーケットを選ぼう」みたいな話になるのかもしれませんが、、、なんか言いたいことがわからなくなってきた。
まあとにかく、たくさん読まれたいのであれば「どこにたくさん魚が泳いでいるか?」を考え、いちばん適した場所にコンテンツを置く。
「誰が言うのか?」「どのメディアで言うのか?」「どこから光を当てるのか?」 これらのコンテクストを調整しながら、伝え方をコントロールしていく。それがこれからの編集者の役目なのかなと思います。
