
h020.システム思考のループ図をつくるワークをしてきたら、体重を減らすための構造が良く見えました(ループ図作成編)
今日は、川越での仕事を終えたのち、品川まで行き、チームビルディングの勉強会に参加してきました。
(以前、チームビルディングの勉強会でTOCを習った時の記事はこちら)
今日のテーマは、システム思考でした。
システム思考とは・・・
うーん、よくわからんw
私も、ちゃんと理解できてるかと言われると難しいですが、理解している範囲でざっくりいうと・・・
気づくとミスがどんどん増える、とか、
顧客がある一定数になると、そこから伸びなくなる、とか
なんか、変えなきゃいけないのはわかってるんだけど、なぜかうまくいかないことって、あると思います。
そんなとき。
例えば、顧客がある一定数になると、そこから伸びなくなってる、という状況があったとします。
一生懸命顧客集めがんばってます。ちゃんと集まってるはず。でも、なぜか伸びない。
じゃあ、お客様が増えることで、なにか見えてない影響があるんじゃないか?増やそうと思って頑張ってるけど、じつは、逆の影響が出てるんじゃないか、など、を見える化するために使う考え方です。
まあ、たかしんもなかなかうまく説明できませんw。
なので、今日やったワークで具体的な流れをお伝えできたらなと思います。今日は、システム思考の手法の一つ「ループ図」を作りました。
準備
用意した道具は、
・正方形の付箋
・短冊形の付箋(4色)
・大きめの紙
・ペン
です。
気になる問題を書き出す
まずは、大きな付箋に、気になること、できれば、増やしたいor減らしたい、と思っているものを書き出します。(時間は4分)

部屋の掃除(コクピット化)
仕事の整理
売上を上げる
ノートを書く時間を減らす
自分のホームページを作る
体重を減らす
群馬に使う時間を取る
時間が・・・
本を捨てる
というのがあがりました。
で、たかしん、こういうツールを使うときは、割とガチで解決するよりも、ある程度解決できそうなテーマを選びます。
だって、目的はツールを使えるようになることなので。
数学でも、最初は「なんだこれ簡単じゃん」っていう感じの基礎問題から解くと思うんです。
なので、自分の課題の中でも、割と軽めなのを選びます。
で、選んだのが、「体重を減らす」です。
要素を書く
次に、要素を書き出します。
ここでは「体重を減らす」という問題に対して、影響を与えているものを書き出します。

紙の真ん中に、体重と書いて、そこから、関連しそうな単語をどんどん書き出していきます。(時間は15分)
ちなみに、要素を書くときポイント
1.名詞にする
例えば、「おなかの肉を減らす」という風に、変化するような単語(動詞や形容詞)が入ると、この後の作業で混乱するそうです。
また、その際、増えたり減ったりがイメージできる名詞にするのがポイントです。
2.現状を表現する
「体重減らしたいな~」みたいな思いがはいると、つい、要素を出しながら、課題を解決させようとして、解決アイデアみたいなものが入るので、混乱するとのこと。
3.ある程度ループっぽいものができたら、テーマをつける
そもそも要素はいろいろなつながりがあるので、いろんなことがどんどん繋がって行ってしまいます。ある程度枚数が見えたらテーマをつけることで、広がりすぎるのを防ぐそうです。
まあ、よくわからないけど、コツを意識しながら、ペタペタ、書いては貼ってを繰り返してみました。
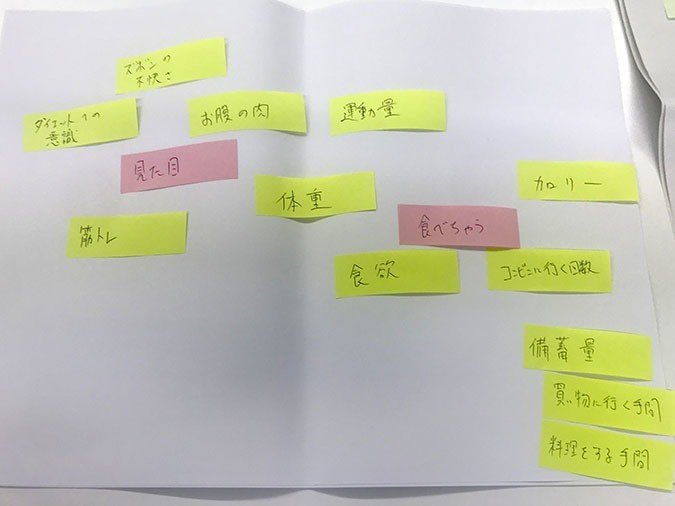
徐々に、ループらしきものが出来上がってきます。
要素をつなげる
ループができてきたら、その関係性をつなげていきます。
要素と要素が正の相関なら「同」、負の相関なら「逆」とつけます。
例えば、
体重が増える(+)と、おなかの肉が増える(+)
→+と+で同じなので「同」
筋トレが増える(+)と、体重は減る(-)
→+と-で逆なので「逆」
となります。
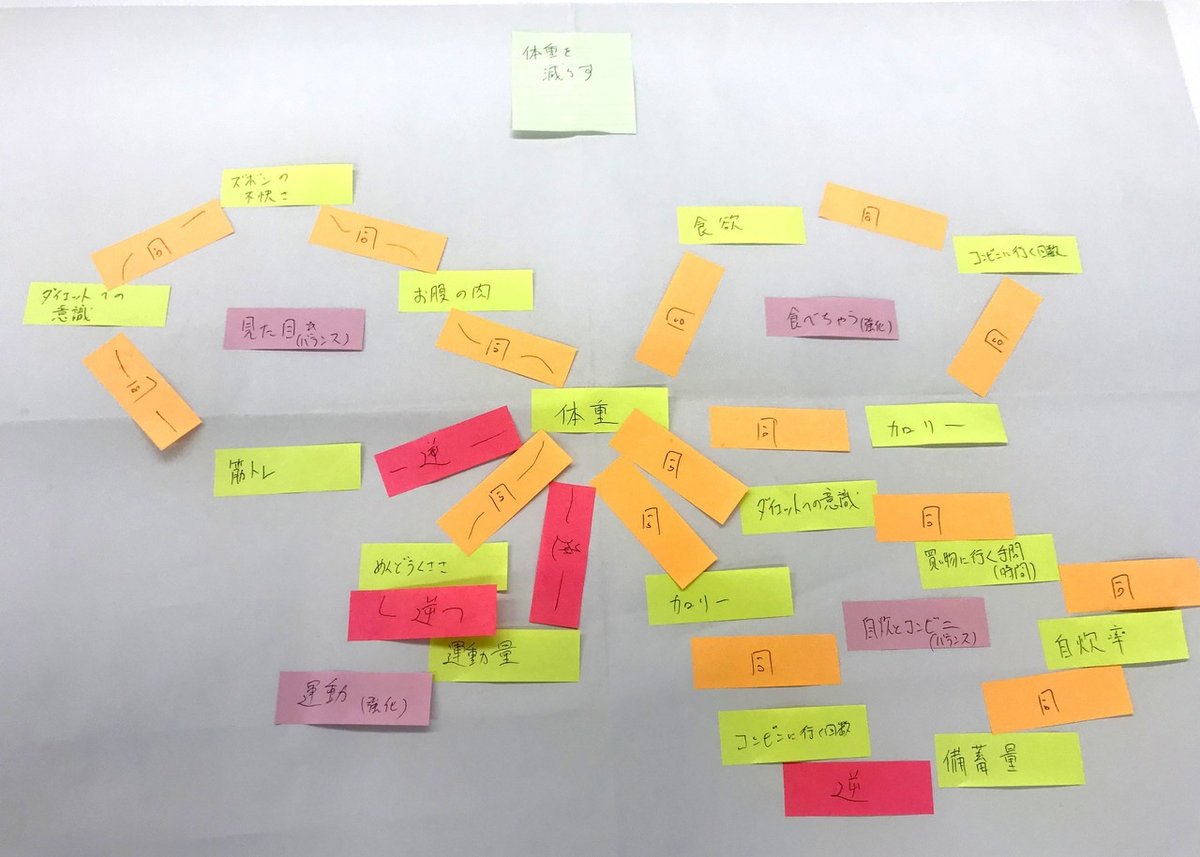
強化ループかバランスループかを見る
ループができて要素が繋がったら、そのループが強化ループ(体重が増えたら、体重が増える方向になる流れ)になっているか、バランスループ(体重が増えたら体重が減る方向になる流れ)になっているかを確認します。
この時の基準は、
一つのループの中で、逆の数が偶数なら強化ループ
一つのループの中で、逆の数が奇数ならバランスループ
です。
ちなみに、先ほどの写真では、同と逆を付箋で貼ってあったかと思います。ところが、別の色の付箋を使う必要がこの後あったのと、付箋でつながりを示すのがちょっと見づらかったので、つながりの部分をボールペンで記載しました。
というわけでできたのが、下記の写真です。

これで、ひとまずループ図が完成しました!!
まとめ
本当にこれで合っているのか?という一抹の不安は抱えつつも、まずは、ループ図っぽいものを作ることができたので良かったです(^^♪
さて、ここでできたループ図ですが、これはあくまで現状の構造を書き出したにすぎません。
このループ図をもとに、
望む結果を起こす or 望まない結果を起こさない ようにするには、どこに何をすればいいか、
といったことを見つけていく作業があります。
その必要な対策を探すために・・・という点についての説明は、次回にまわしたいと思います。ちょっとまだまとまっていないので、改めて復習したいと思います。
