
「SF音楽」についての思弁的なメモ
2015年にディープラーニングがブレイクして、人工知能は世界を変えた(のかもしれない)――音楽にも多大な影響を及ぼしていているAIは、いったい何を変えたのか、ということを思弁的に綴ったメモです。
1. 詩人としての人工知能
■ 芸術のサイボーグ化
人工知能がつくりだしている「作品」は、芸術が構築から解体に向かいはじめた頃の、無調的な音楽、シュールな絵、ダダイスティックな詩、といった作風に「似ている」という印象があって、また、そういう表現が得意なようにも感じられる。かつて、大文字の作者がいた時代、ベートーベンやワーグナー、プルーストやジョイス、ゴッホやピカソ――といった名前を持った芸術家たちがつくりだしてきた歴史は、ある時期から終わりを迎えたかのようになり、そんな時代を称してポストモダンと呼ばれたりもした。そして、芸術が解体しはじめた場所から、コンピュータは創作を開始したかのようにも思えるのだ。
コンピュータの計算処理を使って作曲された最初の音楽は、1957年につくられた「Illiac Suite」だった。この作品は人間の手によってだけではなく、機械の力を借りて作曲されているから、芸術作品がサイボーグ化した初期のものだといえるかもしれない。サイバネティクスは、動物と機械のフィードバックという観点を提示した。人文、芸術というヒューマニティの分野は制御工学とつながり、人間(や生物)と機械の関係は不可分になった。

「Illiac Suite」にはマルコフ連鎖などの情報理論も使われている。サイバネティクスでは、人も機械も情報通信という観点からは同じということになるけれど、コンピュータによって作曲された音楽が「作品」として自律するとはどういうことなのかという簡単ではない問題が残る。自律性の概念が生物からきているとすれば、コンピュータのつくりだす創作物を芸術と呼んでいいのかどうかさえ、はっきりしないわけである。
■ 詩人としての人工知能
これまで、機械は「手足の延長」としてあったから、電子計算機がどれほど複雑な計算をこなしても、設計された回路の通りに動く道具という限界を超えて動作できる自由はなかった。得られた結果を踏まえて判断するには経験値というものが必要で、それは自律した意識を持った人間が行うことだった。けれど人工知能によって、機械は「知性の延長」となって判断する自由を、少しばかり得たかのようなのだ。「知性の延長」としてつくられた機械は、無意識を持っているかのような絵を描きはじめた。

機械というのは精巧に組み立てられた歯車のようなもので、歯車同士の関連がどんなに複雑精緻につくられていたとしても、初めから終わりまですべてその因果関係が決まっているというものが、機械のイメージだった。たとえば時計のように。ところが、2015年にディープラーニングがブレイクしたことで、このような機械のイメージは覆されてしまう。人工知能は、内部の関連が学習によって変わっていき、そのプロセスは解明できない、といわれている。つまり、因果関係が完全にはわからないということだ。そこには、人間には不明瞭で見えない領域があって、人工知能の行うタスクに何らかの作用を及ぼしている。人工知能は、絵を描いたり、詩を作ったりもする。時計に詩は書けない。詩を書くことができたのは詩人だけだった。無意識の豊饒な作用を感受できるほど、彼の意識は自由だったから。
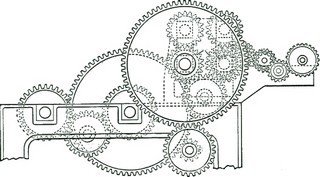
2. 「SF音楽」についての思弁的なメモ
■ サイエンスとスペキュレイティブ
「人工知能の知性は人間を超えるのか」――ディープラーニングが話題になる前なら、これはSFの話だった。いま、「人工知能の知性は人間を超えるのか」という同じ言葉は、将来実現するかもしれないまじめな話として言及されている。かつてはSFのなかにあった世界が、ある時期から実証によって覆されて現実になりはじめたというフィクショナルな感覚が、ここにはあると思う。
SFは、空想科学小説という訳からも、科学的な知見に基づいた空想世界だと解釈されている。科学が進歩した未来といっても、そこはファンタジーの世界だ。そんな空想が現実になったら、それこそSFじゃないか? いま、未来の話として「人工知能の知性は人間を超えるのか」と問いかけてみれば、それはSFの話なのか、それとも現実の話なのか、相手は一瞬、戸惑うことになるかもしれない。仮に、SFで描かれた内容と似ている出来事が現実に起きたとしても、虚構として創作された作品は、現実とは異なるということになるはずだ。とはいえ、「人工知能の知性は人間を超えるのか」という同じ言葉が、虚構と現実の両方の位相で通用してしまうことになれば、言葉は錯綜する。その時、観念によって出来ていた虚構世界の自律性は危うくなるかもしれない。いま、虚構が現実化されていくというリアリズムがあるとして、そのリアリズムがさらに虚構化されていくものだと考えてみれば、
現実の虚構化→虚構の現実化→「「現実の虚構化」の現実化」を虚構化する
といった入れ子状のメタ・フィクショナルなものが出来上がってくる。この辺りから、SFの「S」はスペキュレイティブ=思弁的な「S」となってくる。ちなみに、スペキュレイティブ・フィクション(思弁小説)という小説ジャンルは、空想科学小説と同じ「SF」という略語で表記されている。
■「SF音楽」の誕生
SFが現実化した世界としての虚構を考えてみよう。それは、例えばつぎのような世界だったとする。「その世界では、限られた分野では人工知能の判断能力が人間を上回っていた。人工知能が描いた絵は、ときに高額で取引された。音楽は機械とつながり、機械は音楽を生みだしていた。人工知能は作曲もこなしていた」――この虚構世界は、SFが現実化した世界で、音楽もSF化している。でも、上記とまったく同じ言葉で現実を語っても通用するのだとすれば、SF化した音楽という考えは無効になる――というのも、SFが現実化した虚構とはやはりSFであるといえても、SFが現実化した現実では、SFというフィクションは成り立たなくなってしまうからだ――ここで音楽のSF化は、その無効化も引き受けることになる。その両方を伴ったものとして「SF音楽」が誕生する。
現実の虚構化と虚構の現実化のなかで、音楽は不可避的に、SF化と無効化の両方の過程を受け入れていくことになる。そこに、何か新しいものが発生してくるとすれば、その「何か」を取りあえず「SF音楽」と呼んでみたいということなのだ。「SF音楽」はスタイルとして定義できるものではないけれど、そこに現れてくるかもしれない要素はどんなものがあるか、思いつくままに羅列すると、
アート、哲学、惑星、数、アントロポセン、人工的神話、AI、サイバネティクス、ポストヒューマニティ、現実化したSF、人間以外の知性、地球外生命…
その表現は初めから一義に決まっているわけではないから、それはファンタジーかもしれなければ、別の何かかもしれない。音楽が「SF音楽」化する過程――SF化とその無効化――で生まれる「何か」は、「新しい概念/新しい感性」を伴ったもので、そこには、何か新しい価値を示すための新しい要素が付加される。そのために、既存の音楽的要素は虚構化されて、新しい価値であるところの概念や感性による変容をこうむる。音楽をつくるフレームは新たなメタ・フレームとなって、ここで音楽は「SF音楽」化したひとつの創作物となる。それは、「音によってつくられたアートや哲学のようなもの」という性格も合わせ持つかもしれない。価値観を新しくする方法は実験的でもあり、多様な手法が横断的に伴うことになるはずだ。
![]()
[補足]人工知能が意識を持った存在と同じ振舞いができて、その振舞いがどれだけ達者になるかは、人工知能の知性がどれだけ発達するかに関わってくるはずで、「意識があるのと何ら変わらないくらい複雑な判断ができる人工知能」が生まれれば、意識が「ある/なし」の問題は取りあえずカッコに括れると思う。とはいえ、その振舞いが無意識を持っているかのようになると、意識と機械との境界は曖昧になるように感じられてくるはずで、つまりSF化してくるという気も。
あと、人工知能の描いた絵は、こちらのページにあります。
https://art42.net/
読んでいただき、ありがとうございました。
いいなと思ったら応援しよう!

