
とにかく使ってみるしかないっていうのは間違いないです:読書録「これからのAI、正しい付き合い方と使い方」
・これからのAI、 正しい付き合い方と使い方 「共同知能」 と共生するためのヒント
著者:イーサン・モリック 訳:久保田 敦子
出版:KADOKAWA(Kindle版)
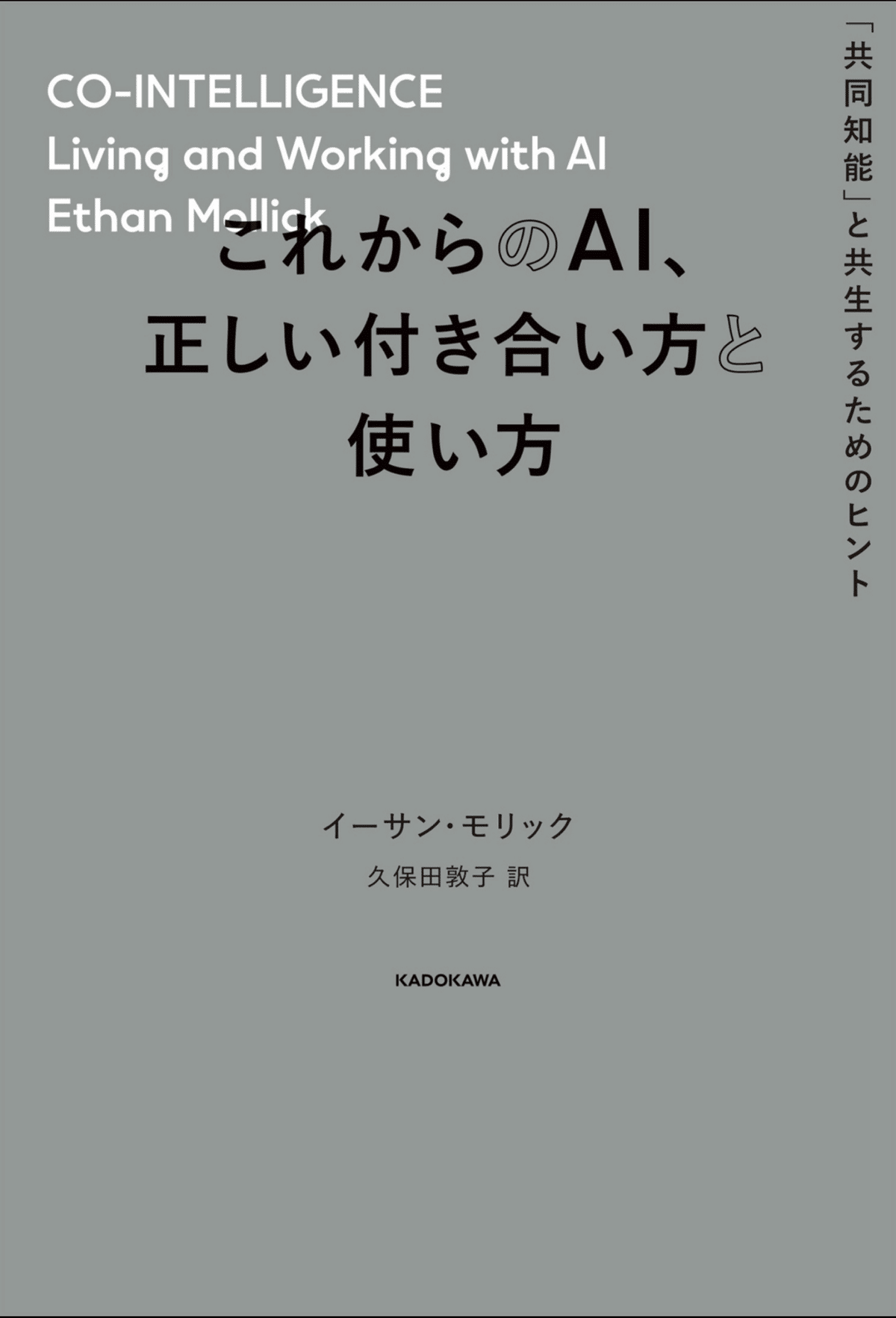
2月3日にOpenAIのサム・アルトマンとCPOのケビン・ワイルが東京大学に来て、質疑応答セッションをしたときにケビン・ワイルが進めていた本です。
<Q4.AIと人間が共進化していくという状況でしょうか?
社会とテクノロジーが共進化していくという枠組みが正しいと思います。
「AIが突然やってきて、 何もかも人間を凌駕してしまう」 という話ではなく、一歩ずつ一緒に進化していく。 そうやって私たちができることは飛躍的に増え、AIなしでは想像もつかないほどの領域に到達すると思います。100年前や1000年前と比べて、 私たちがどれだけのことを成し遂げられるかを考えてみればいい。 ツールが進化すれば、 同時に期待値も高まりますが、 上限もぐっと上がるはずです
(ケビン)ちなみに、 ウォートンのイーサン・モリックという教授が書いた『Co-Intelligence』という本があります。 100ページほどの短い本ですが、AIをどう授業に取り入れているか、 学生がどうAIと向き合えばいいかなど、非常に示唆に富んだ内容です。 読んでみると面白いと思います。>
基本的にはいろいろメリットデメリットもあるし、不安なところもあるけど、もうここまで来たらAIと付き合っていくしかないよね…まぁ、そんな感じでしょうか
実際のところそういうしかないって言うようなとこまで来ちゃってるような気がもしますw。
<概要>
「これからのAI、正しい付き合い方と使い方」は、これまでの「人工知能」という固定観念を超え、AIを人類の「共同知能(Co-Intelligence)」として捉え、人間と協働する新たな視点を提示する一冊です。以下、概要をまとめます。
主なコンセプト
• 共同知能としてのAI
従来のツール的な側面だけでなく、AIを仕事仲間、家庭教師、創造性のパートナー、コーチなど、さまざまな役割で人間と共生させる考え方が展開されています。つまり、AIは単に命令に従う存在ではなく、人間と協力して新しい価値を生み出す「共同知能」として位置づけられています。
AIと上手く付き合うための4つの原則
本書の中心となるのは、AIとの協働を実現するための具体的なルールです。特に以下の4つの原則が挙げられています:
1. 常にAIを参加させる
どんなプロセスでもAIを積極的に関与させることで、効率化や創造性を高める考え方。
2. 人間参加型(ヒューマン・イン・ザ・ループ)にする
AIだけに任せず、人間が常に最終判断を下す仕組みを維持することで、安心・安全な運用を図る。
3. AIを人間のように扱う(ただし、どんな人間かを伝えておく)
AIを単なる機械と捉えるのではなく、一定の人格や特性を持つ存在として扱い、適切なコミュニケーションを行う。
4. 「今使っているAIは、今後使用するどのAIよりも劣悪だ」と仮定する
現状の技術に満足せず、常に未来の改善・進化を念頭に置いた利用法を考える姿勢が求められます。
書籍の構成と内容
• 序章・プロローグ
著者自身の体験や、AIと向き合う上での初期の葛藤などが語られ、今後のAIとの関係性に対する期待感が示されます。
• 各章での具体的な役割の提案
• 「異星人の心」を創造する:AIの創造的な側面を引き出す方法
• 異星人を人間に適合させる:AIを人間社会に適合させるための工夫
• 続く章では、AIを「人」として、あるいは「仕事仲間」「家庭教師」「コーチ」として位置づけ、具体的な活用方法や、時にはリスク(例えば、暴走防止やAIの巧みな嘘など)についても触れています。
• 未来展望
最終章では、AIとの共生がもたらす未来のシナリオを4つほど提案し、これからの社会や仕事、教育の在り方について考察がなされています。
総評
本書は、AIが急速に進化する現代において、どのようにしてAIと上手く付き合い、協働していくかの具体的な指針を示してくれます。特に、単なるツールとしてではなく、共に働くパートナーとしての視点は、今後のビジネスや日常生活において大きな示唆を与えてくれる内容です。読者は、この本を通じて、AIの持つ可能性やリスク、そして安全かつ効果的な利用法を学ぶことができるでしょう。
(ChatGPTo3mini)
本書は、書かれているのは、ChatGPT4のタイミングになります。
その後o1が出て「推論モデル」が登場することで生成AIは大きく次のステップに踏み出しています。(現時点はo3mini)
web検索が広がってるのも大きいですし、AIエージェント(Operaterやdeep search)も登場しています。
本書でもその方向性みたいなものはコメントされてるんですけど、まあ恐るべきスピード感です。
相変わらずハルシネーションのリスクはあるんですけど、推論やWeb検索でずいぶんと抑えられようになりましたからねぇ。
まぁその分作者の危惧もかなりリアリティーを持ってきてるって言うところもあります。
本書のスタンスは、理想論でもなければ、脅威論でもなくて、非常にプラグマティックなスタンスで書かれてるって言うところじゃないかと思います。
だからChatGPT4以降の大きな進化があっても、基本的には本書が差し示す方向性に変わりはないんですよね。
まあだからこそケビン・ワイルが推薦するわけだしw。
専門知識や専門家の今後の方向性とか、新人育成の課題とか、ちょっと考えただけでも、なかなか頭の痛い事はあるんですけど、そうも言ってられないっていうのが現状でしょうね。
そう言ってる足元から次の進化がやってきちゃう訳ですし。
一方で、日本の場合なんか急速に少子高齢化が進んでて、労働人口がどんどん足りなくなってきてるって言う現実もあるわけですから、シノゴノ言わずに、こういうのをどんどんどんどん実装していくしかないというのが僕の考えでもあります。
もちろん取り残される層(その中には、僕も含まれる可能性は大なんですけど)へのサポートも忘れないように…ではありますけど。
欧米や中国・韓国に比べると日本では生成Aiを使う人が少ないって言うデータもあったみたいですけど、とにかく使ってみなきゃどうにもならないと思うんですけどね。
一方でアトムやドラえもんを産んだ日本はこういうのに欧米諸国よりは親和性があるんじゃないかとも思うんですけど。
まぁ安野貴博さんとか若い人はガンガン使ってるようです。その人たちへの支持も結構あるようですから、これから政治や社会が変わっていくかもしれません。
そこに期待したいところです。
#読書感想文
#これからのAI正しい付き合い方と使い方
#イーサンモリック
#ChatGPT
#openai
