
AIに対するネガティブ本かと思ってたら、全然違ってて、最後は「her」でした:読書録「AIにはできない」
・AIにはできない 人工知能研究者が正しく伝える限界と可能性
著者:栗原 聡
出版:角川新書(Kindle版)
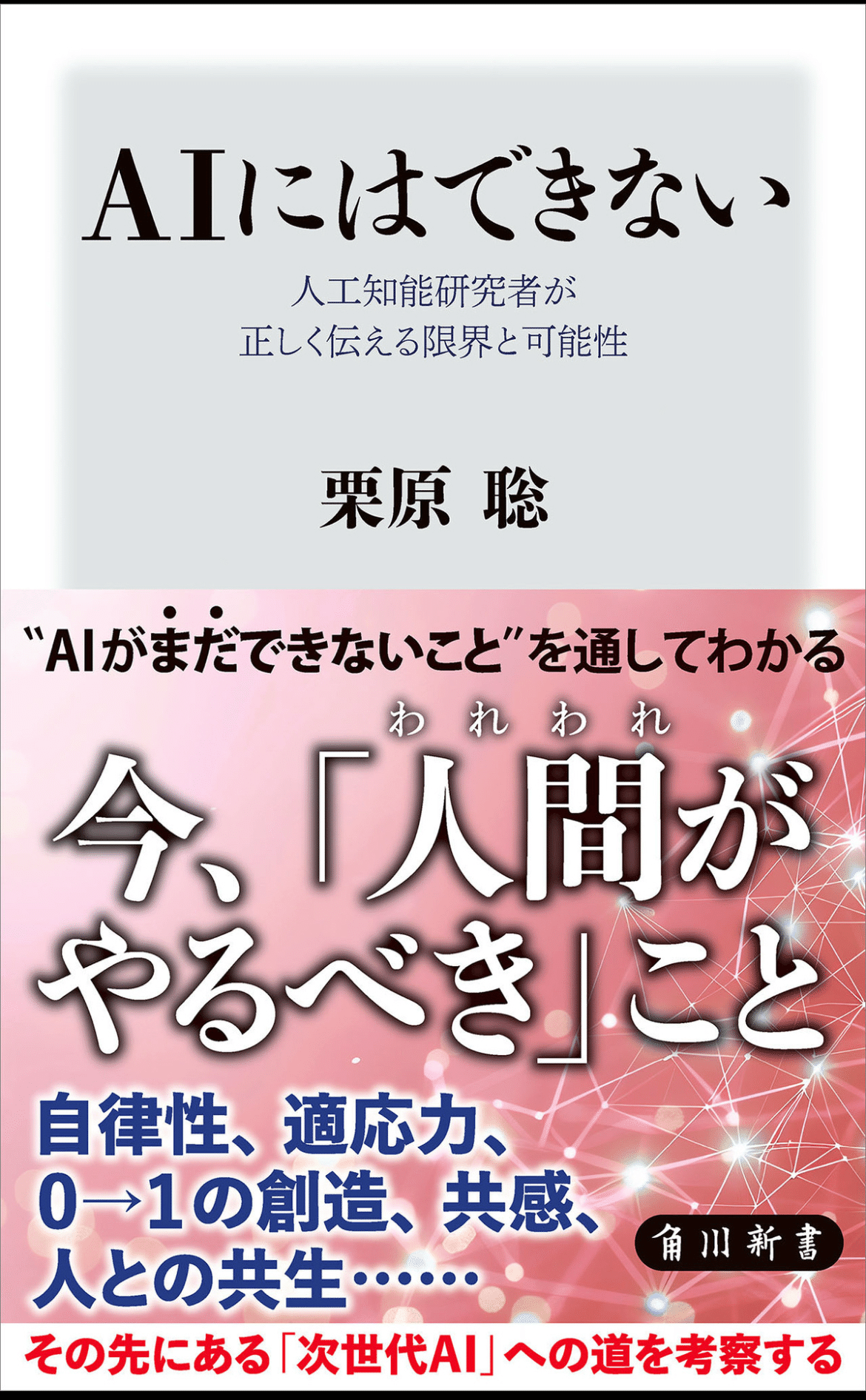
最近、どちらかと言うと「AIポジティブ」本を立て続けに読んでたし、オープンAIがバンバンバンバン、新しい機能を発表するので、気分的にも前のめりになってたところがあって、ちょっとブレーキをかけるためにチョイスした作品。
まぁ今週ちょっと体調が悪くて、フィクションとか読む気分にもなれなかったし、ちょっと保守的な本で流しておこうかなぁなんて気分もありました。
でもこれ全然保守的な本じゃなかったんですよね。
予想より前のめりな作品でした。
考えてみたら、作者の栗原聡さんて「TEZUKA2023」で、AIに新作の「ブラックジャック」を書かせるプロジェクトをやってた人です。
保守的なわけないですわ。
<概要>
『AIにはできない 人工知能研究者が正しく伝える限界と可能性』は、慶應義塾大学理工学部教授の栗原聡氏が、AIの現状と未来、そして人間との共生について深く考察した一冊です。本書では、AIの発展が私たちの社会や生活にどのような影響を及ぼすのか、またAIが得意とすることや苦手とすることを明確にし、人間が持つ独自の能力をどのように伸ばしていくべきかを探求しています。
特に第4章「AIを使うか、AIに使われるか」では、AIが仕事を奪うという懸念に対し、AIはあくまで道具であり、その活用方法次第で新たな可能性が広がると述べられています。また、情報過多の現代において、人間自身がAIのように表面的なシステムに陥る危険性を指摘し、人間固有の創造性や共感力、社会性を高める重要性を強調しています。
本書は、AIの限界と可能性を正しく理解し、人間らしさを活かす道を模索するためのガイドとなる一冊です。
(ChatGPTサーチ)
<目次>
1. AI開発の歴史は未来のためにある
2. 生成AIには何ができ、何ができないか
3. AIは経済の浮揚に寄与するのか
4. AIを使うか、AIに使われるか
5. 社会が生成AIを受け入れるための課題
6. 人とAIの共生
7. AIのスケール化と日本の未来
保守的という意味では「教育」についてはちょっと保守的なところがあるかな。
前に読んだ池谷裕二さんは、バンバン生成AIを学生に使わせるスタンスでしたがw、栗原さんは慎重な意見を述べていらっしゃいます。
もっともそれって初等教育から中学くらいの話なので、そこら辺はもしかしたら池谷さんもそういう意見かもしれないですけどね。
ただ、そういうところを取り上げて意見を述べると言う点がちょっと保守的ニュアンスがあるかもって。
教職員の事務業務に関しては、生成AIをどんどん使っていって、効率化を進めるべきって言う意見なので、何が何でも教育現場にはAI反対ってわけでもないですけど。
内容的に、例えば池谷さんの本と比べて特段特別なことが書かれているわけではないですが、イメージとしては結構しっかりと研究や技術を踏まえてコメントしようとしてるっていう感じでしょうか。
おかげで頭にすっと入ってこないところもなきにしもあらずでしたが、まぁこれは読む側の問題。
入門書としてはちょっと敷居が高いかもしれないけど、全体像がキッチリと概覧されている時点では悪くないと思います。
個人的には最終章はかなり面白かったです。
「スケール」を取り上げて、AIの今後について議論していくっていうのはなかなか興味深いところ。
その向こうにASIが見えてくるかも…とかね。
<知能のレベル向上の年表ができたとすると、人類は知能という主役がその知的レベルを向上させるある一時代を担ったという見方ができよう。これはまさに宇宙的スケールでの話であるが、これを単なる妄想と断定することもできないであろう。生物の進化は何億年というスケールで進行するダイナミクスであるが、我々人が生み出した A Iは年単位、月単位という速いスケールで進行する。今は人が世話をしている知能が、将来において A Iが世話をすることになり、あるとき、人と共生した知能は A Iが生み出した新たな知能を高める何かを拠り所として地球を離れていくのかもしれない。>
こうなると「her」の世界ですけどw。
「AIにできない」ことは何か?
<これは、人がやるべき仕事は人がやり、 A Iで済むことは A Iで済ませるという当たり前の棲み分けをするときがいよいよ来たということになる。ここで、人がやるべきタスクとは何かといえば、創造的タスクや、人の感性や感情が関与する類いのサービスに関するタスクなど、「新たな価値を生み出す領域」と「人対人に関わる領域」が該当する。
A Iは道具であり、その能力を発揮させるのは使う人次第である。 A Iの専門知識を持たずとも容易に利用可能な時代に突入しつつある状況のなかで、人がすべきことを、 A Iを道具として活用することで前に進めていけば、新たな可能性が見いだせる確度は高い。一方で、進まなければ現状維持となるだけであり、進む人々とそうでない人々との差がどんどん開いていくことになる。>
まあそうなんだけど、より根本には、
創造的タスクや、人の感性や感情が関与する類いのサービスに関するタスクなど、「新たな価値を生み出す領域」と「人対人に関わる領域」
って誰でもやれてるわけでもないよねって話。
なんならAIがやるエリアのことしか出来てない人だって…
<棲み分けを考える以前に、ここで考えなければならないのは、「我々自身が A I化しつつあるのではないか?」ということだ。>
ここら辺は格差につながっていくことでもあって、なかなか難しい問題をはらんでいます。
個人としては「AIを使う側」にいるしかないってことなんで、そうありたいと思ってるんですけどね。
社会としてはどうか…
と言うあたりが「スケール」の話だったりします。
個人スケールと社会スケールの不一致っていうのは、兵庫県知事選なんかであらわになったメディアの問題なんかにも通じるところだったりするし、リベラルが苦労してるところにも通じたりもするかなぁとか。
一歩間違えると危ない話に突っ込んでる感じもあるんですけど。
でも、そこが読みどころだったりもします。
<このような個人としてのスケールの構成要素である個々人が、一つ上の社会というスケールを客観的に観測し、そこでの出来事を分析し認識できるという、異なるスケールにまたがるやりとりを可能としたのは、少なくとも地球上においてはテクノロジーを生み出した我々人類が最初である。しかも、このことが個人のスケールにとって果たして良いのか悪いのかを理解することなく、強制的に多くの人々に社会のスケールの認識と、社会のスケールへの個人のスケールからの介入を可能としたことが、現時点では混沌を引き起こしていると言えよう。>
そして、そういう個人スケールと社会スケールの調整をAIが担うことを想定する
…う〜ん、こう来ると保守的どころか、かなりラディカル。
僕は嫌いじゃないし、あり得ると思うんですけどね。
まぁ確かに極めて日本的なスタンスではあるかもしれません。
「ドラえもん」がいる国ですからw。
今読むなら、池谷さんのとこの本はちょうどいいタイミングだと思います。
半年どころが2、3ヶ月後にはどうなってるか分かりませんけど。
まぁ、その頃には、もしかしたらAIの方がオススメの本を教えてくれるかもしれませんな。
この調子ですと。
#読書感想文
#AIにはできない
#栗原聡
