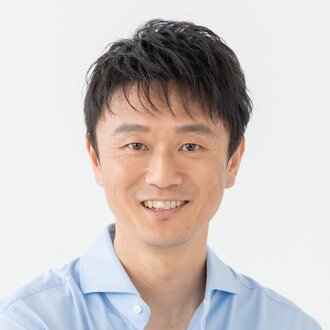「より少なく、より良く生きる」は現代のデフォルト
「より少なく、より良く生きる」の哲学を、読者の生活に丁寧に寄り添う形で何か書籍にできないだろうか?
ある出版社からオファーがあり、どんなメッセージが世の中に求められているか、どのような形式でどういう構成にすればよいのだろう?
会話をしながら、企画を練り上げていく過程で、僕自身たくさんインスピレーションをいただきました。せっかくなので、その時の気づきを備忘録的に投稿しておきたいと思います。
1.効率化って何だろう?
日頃よりコテコテのビジネスパーソンとのつきあいが多く、何かあれば「このやり方は非効率だよね」「もっと効率的にするにはどうしよう?」という会話が日常会話として定着しています。
そこで、ふと思うことがあります。
”効率的”ってどういうことを言うのだろう?と。
デジタル化する、時間を短縮する、ムダを省く・・・色々とありますが、僕の定義はこうです。
「より少なく、より良くする」ということです。
「より少なく」偏重型・・・仕事においては、工夫により時間を短縮できてもどこかで仕事が滞っては意味がありません(隠れ残業のように)。
「より良く」偏重型・・・かといって、成果が上がったとしても、時間がかかりすぎては良いとも思えません。
あくまでも、「より少なく」×「より良く」の掛け算が大事で、いずれか一方が欠落して片輪走行になっては良くないと思うのです。
2.成果が上がる人、上がらない人
あなたは、「より少なく、より良く」を実践できていますか?
僕のクライアントでうまく成果を上げている人を見ると、意識しているか無意識かは別にしても、この哲学が頭の中にセットされているように見えます。
<成果が上がる人>
・集中すべきコトを先に見い出す
・何をやるかではなく、何を省くかを考える
・すべてを目的から考える目的思考
・アウトプット重視主義
・動きにメリハリがある
VS
<成果が上がらない人>
・色々と手を出し中途半端に終わる
・やるべきことを積み重ね、手が回らない
・目的と手段がよく入れ替わる
・インプットばかり
・やみ雲に動きがち
ざっくりとまとめると、やるべきこと・やりたいことを「引き算」することで、本当に大切なことに集中できている人が成果を出しているように見受けられます。
逆に、成果が出ない人は、あれもこれもと「足し算」していくうちに、本来集中すべきことに充分な時間と労力を割けていないということに気づきます。
では、足し算と引き算のスタイルの違いは仕事の成果だけの話なのでしょうか?
いや、自分自身や僕のまわりを見ていると、仕事もプライベートも、人生観もすべてに共通する思考であるように思えます。
3.本当に大切なことは何か?
仕事に限らず、身の回りを見渡してみるとどうでしょうか?
たとえば、人付き合い。あなたは本当は付き合いたくもない人に気をつかって時間をとられていませんか?
たとえば、お金使い。あなたは本当にお金をかけるべきところにかけず、無駄金を使っていませんか?
たとえば、時間使い。あなたは本当は時間をかけたいところに時間をさかず、ダラダラと惰性で無意味な時間を過ごしていませんんか?
たとえば、モノの片づけ。あなたは本当に必要なモノを考えずに、「いつか使うかもしれないから」と10年以上触れもしないモノを持ち続けていませんか?
たとえば、キャリアプラン。あなたは本当にやりたいことを封印して、会社名にこだわっていませんか?子どものやりたい専門性ではなく学校名を優先して進路アドバイスしていませんか?
このように、「より少なく、より良く」の哲学は、「本当に大切なことは何か?」と向き合い、それ以外はノイズである!と仕分けすることから始まります。
大切なことは日々たくさんありますが、本当に大切なことは少数のはずです。これだけ忙しい時代の中にあっては、少数だけど重要度が高い少数の大切なことにどれだけこだわれるかが、鍵を握ります。
この”鍵”こそが、ノイズに振り回されず、自分らしく生きるコツだと僕は考えていますよ。
4.Less is More (少ない方が豊かである)
かつての拙著の中で、このような一節を書きました。
20世紀に活躍したドイツ出身の建築家、ミース・ファン・デル・ローエ(1886 ~ 1969)が残した「Less is More (少ない方が豊かである)」という言葉が好きです。
意訳するなら、「少ないからこそ価値がある」「最小限のもので最大の成果を得る」となるでしょうか。
建築やデザインの世界ではよく知られる言葉で、ミニマルなデザインやシンプルなデザインを検討するときに大切になる考え方です。
シンプルさを極限まで追求することで、無駄で余分なものを省き、逆に美しく豊かな空間やデザインを生みだすという哲学です。
冒頭の写真のような「枯山水」形式の庭園が僕は好きなのですが、これもまたLess is Moreの世界観です。だって、水を用いずに岩や砂だけで山水を独自に表現してるんですよ!
華美なだけではなく、簡素だからこそ価値が出ることってあるんです。
複雑で先が見えない時代は、シンプルにしていくからこそ価値を生むもの。
あるいは、シンプルにしていくことで価値が浮き彫りになるものまで、「シンプル化=少なくする」が意味を持つことが多いのではないでしょうか?
今のような複雑な社会に生きていると、心も頭も、そして身の回りのモノも、色々と足し算式に抱え込んでしまいますよね。
やがて自分の中にノイズとして蓄積していき、ストレスになってしまうと思うのです。
こう考えると、ストレスもなく仕事も人づきあいも行うには、Less is Moreという視点を生活の中に取り入れていくことも大切なことなのです。
「より少なく、より良く」・「Less is More」という哲学は、複雑化社会を生きる上でデフォルト(標準設定)にしてもいい!
と、個人的には思うのですがどうでしょうか?
おしまい。
さて、今回の内容は
いかがだったでしょうか?
少しでもお役に立てば幸いです。
それでは、また会いましょう!
著者・思考の整理家® 鈴木 進介
P.S.
毎週水・日曜日に「メルマガ」でも思考整理のエッセンスを配信中です!
以下よりご登録ください↓↓↓

「LINE」でもショートコラムを毎朝7時に配信しています!
以下よりご登録ください↓↓↓

最新刊はこちらより↓
いいなと思ったら応援しよう!