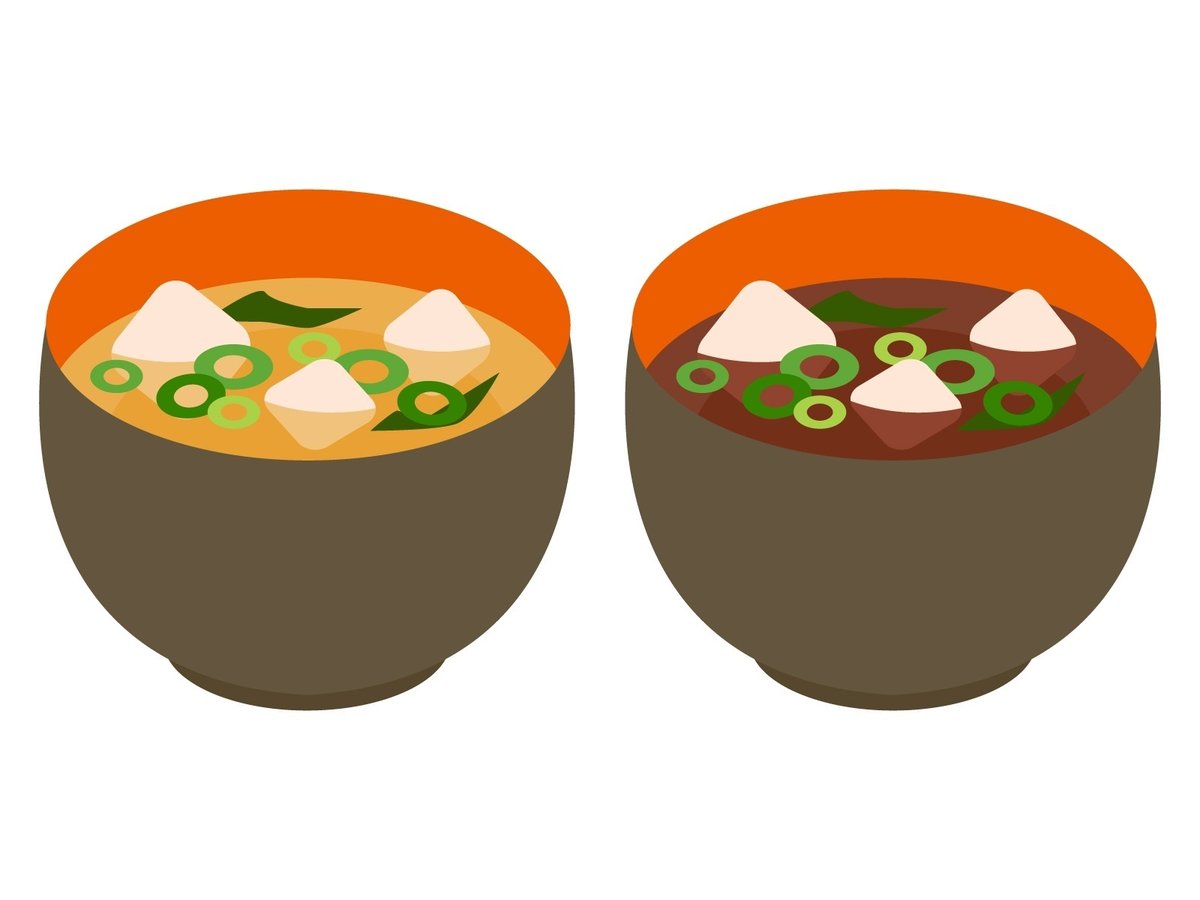ふえるわかめちゃんの恐怖?! ~ 国際海運と侵略的外来種の話
最近、こんなニュースを見ました。
においをかいだだけでヒアリの入った缶を正しく見分けるなんてすごい!
ちなみに昔、私も同じ犬種(ビーグル)を飼っていたのですが、その子はどうにも鼻がきかない子でした。。。個体差かしら。いや訓練のたまものですよね、きっと。
などという話はさておき、今夜は侵略的外来種の話題を。
1.侵略的外来種=危険生物ではない
外来種の中でも、地域の自然環境に大きな影響を与えて生物多様性を脅かすおそれのあるものを「侵略的外来種」といいます。
ヒアリも侵略的外来種のひとつですが、これはヒアリが(強い毒を持つなど)危険な生物だからではありません。在来昆虫や爬虫類、鳥など、地域にすでにある生態系や人間社会に大きな影響を及ぼすことが確認されているためです。
つまり、侵略的外来種は生物多様性を損なうという点で問題なのですね。
2.おとなしそうに見えて怖い日本原産の侵略的外来種2選
日本では「外国から日本に入ってきて、日本の生態系を荒らす」侵略的外来種が報道等でフォーカスされがちですが、実は日本原産で世界の侵略的外来生物に指定されているものもあるんですよ。
葛(くず)

根っこの部分から作られた葛粉(くずこ)は料理の素材になり、源氏物語などの文学作品にも登場するあの「葛(くず)」は、世界の侵略的外来種ワースト100にランクインしている植物でもあります。
家畜の飼料や土壌流出防止のための植物としてアメリカに渡り、野生化して今日ではアメリカにおける侵略的外来種になっています。果樹や植林木に巻き付いて著しく成長を阻害するため、生態系はもちろんのこと経済面でも大きな被害をもたらしています。文献によると、アメリカでは昆虫による生物防除を模索しているようです。
ワカメ

なんと、日本ではお味噌汁の具材や酢の物の材料として定番となっているあのワカメも、堂々(?)世界の侵略的外来種ワースト100にランクインしています。
ワカメは本来、東アジアの海域にしかいなかったのですが、日本から世界の他地域へと航行した船からワカメの胞子が拡散してしまったとのこと。現在では、アメリカ、フランス、イタリア、オーストラリア、ニュージーランド、黒海、地中海などほとんどの地域に存在しています(出典)。
そして、ワカメは(あのおとなしそうな外見にもかかわらず)現地で生態系に悪影響をもたらしたり、現地の漁業に経済的損害を与えたりしているのだそうです。。。
海外ではワカメを食べる習慣はほとんどありません。そのため、増え続けた侵入ワカメが養殖のカキや、ホタテ、ムール貝、イセエビなどの成長を阻害したり、漁業用の機械にからまったりするなど、水産業に重大な影響をもたらしています。
(ひとりごと)
突然ですが、「ふえるわかめちゃん」という商品をご存じでしょうか。
子どものころから慣れ親しんできた私にとっては、まさに乾燥カットわかめの代名詞的存在の、この商品。ですが、この話を知ってからは、「ふえるわかめちゃん」という名前が少し怖いものにみえてしまい、困っています…。
3.国際海運業に課せられる生物多様性保全
さて、葛とは異なり、ワカメは意図的に海外へ持ち出されたものではありません。それなのになぜ、世界中に散らばってしまったのか。
そこには「バラスト水」というキーワードがあります。
ワカメはもともと日本、朝鮮半島の近海に生息する海藻ですが、これまでに、アメリカ、フランス、イタリア、オーストラリア、ニュージーランド、黒海、地中海など世界中の海域に移送されて繁殖していることが確認されています。日本に荷揚げしたタンカーが船体の安定を保つために、空になった船倉に「バラスト水」として日本近海の海水を取り込んだ際にワカメの胞子が紛れ込み、世界中の海域へと運ばれたと考えられています。

バラスト水によって移動し、現地の生態系に影響を与えているのは、ワカメだけではありません。
国際海事機関(IMO)は環境に顕著な影響を及ぼす生物としてヒトデ、ゼブラ貝、ワカメ、カニ、ハゼ、赤潮プランクトン、モクズガニ、ミジンコ、クシクラゲ、コレラ菌の10種をあげているそうです。

このため、現在ではバラスト水の処理方法は国際条約で厳しく管理されるようになっています。
輸入の9割以上を船に頼っている日本にとって国際海運業はまさに生命線。その重要な産業がどのような環境下にあるのか、またひとつ学ぶことができてよかったです。
以上、サステナビリティ分野のnote更新1000日連続への挑戦・30日目(Day30) でした。それではまた明日!