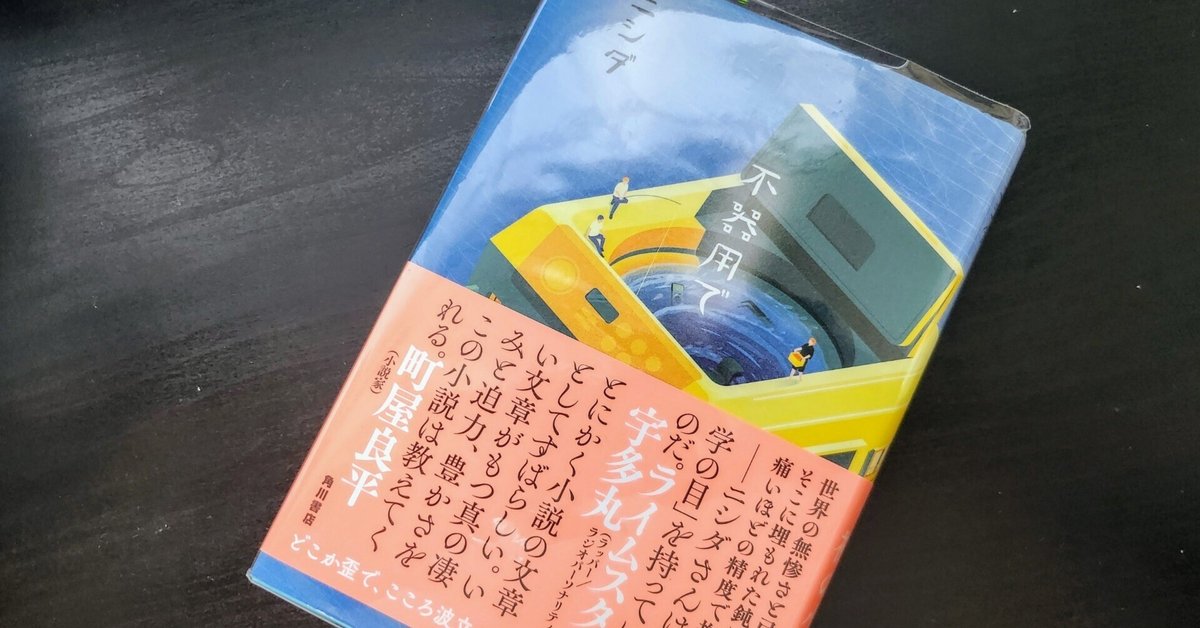
凄絶な自己否定に沈む一冊『不器用で/ニシダ(ラランド)』【読書感想文】
お笑い芸人として活躍するラランド・ニシダによる小説デビュー作。文芸誌等に発表済みの5篇を収録した短編集であり、ページ総数は208。読むスピードが速い人なら1日で読破できるボリューム(私は数日かかったが)。
※以下、作品の内容に触れています。このテの小説ではあまり気にならないかも・・・とは思いますが、事前情報なしで読みたい方はご注意ください。
「遺影」
クラスで生き残るため、自分と似た境遇の女子生徒のイジメに加担する主人公。彼は夏休み明けにその女子生徒の机に遺影を置くイタズラの担当者になってしまう。主人公は夏休み期間の学校に忍び込んで遺影の額縁を制作するが、完成させた額縁に女子生徒ではない、ある人物の写真を入れて学校を去る。
少し前に「親ガチャ」なる言葉が話題になったが、そのことを少し思い出した。主人公が自分よりさらに過酷な家庭環境(経済状況)の女子生徒のイジメに加担していたのは、「仲間外れにされる恐怖」ではなく主人公自身の「不遇な家庭環境に対する不満」をどこにぶつけていいのかわからなくなっていたからではないだろうか。
「遺影を作る」という設定も見事だが、物語の着地がなにより恐ろしい。この世から消えるべきなのは誰なのか気が付いてしまったのだろうか。主人公の若さゆえの狭量さが鬱屈した結末を導くが、この作品を一番最初に載せることでこの短編集そのものの全体のトーンを示してもいる。
「アクアリウム」
退屈な生物部に所属する高校生の主人公。同じ生物部で同学年の波多野を見下すことでプライドを保っていたが、部活動の一環で釣りに行った際、主人公と波多野は衝撃的な経験をする。数年後、大学に進学した主人公は波多野に連絡をとり、彼の近況を聞いてある場所へと向かう。
個人的に全5篇の中で最もグロテスクかつ、シビアな作品だと感じた。世間から奇妙だと思われる言動をとる人間は確かにいる。しかしその言動がモラルのある人間かどうかを示すかは関係がない。
主人公が波多野を見下していたのは人間としての道徳性だったのだが、ある真相を聞いて波多野に強い敗北感を抱く。強烈な自傷行為をしながら、よりによって「あの場所」へと向かう主人公。バスに揺られる主人公に胸が苦しくなる作品。
「焼け石」
主人公はスーパー銭湯の男性サウナの清掃係をする女子大生。本人は学業との両立もあるため仕事に不満はなく、男性の裸を見ることに抵抗もなくなっていた。しかし新入りの男性アルバイト・港くんは「女性に男性サウナの清掃をさせるのはおかしいのではないか」と社員に直訴する。
主人公は「学生だけど仕事っぽいなにかをやっていてそこそこ稼いでいるらしい」彼氏がいる。最後は彼氏ではなく港くんを選ぶことになることが示唆される、ちょっと意地悪なラブストーリーでもある。港くんの優しさには若干のマチズモを感じるのがちょっと心配ではあるが、主人公の冷めきった石が焼け石になったが最後、もう誰にも彼女を止められない。
この単行本の中では最もリラックスして読めた作品。設定が面白く、確かに自分も銭湯に行ったとき清掃で若い女性が入ってきたときに「え?いいのかしら?」と思ったことがある。男性である作者が女性を主人公にしてジェンダーを取り扱うのは勇気のいることだと思うから、実は全5篇の中で最も攻めた作品なのかもしれない。
「テトロドトキシン」
主人公は「いい歳」になったが仕事も趣味もやりがいはなく、マッチングアプリで出会った女性とワンナイトをすることだけが日常の会社員。同窓会で再会した咲子とタバコを吸いながら近況を語り合う。咲子は趣味で辞書を作っているらしい。
主人公は虫歯の治療を拒否し続けており、それを自ら「消極的自死」と呼んでいる。そう呼ぶとカッコいいのだが、結局のところ歯医者が怖いと泣いている子供と同じであり「大人になりきれていない大人」なのだ。咲子もまた実家暮らしで定職に就かず、他人には理解しがたい謎の夢に憑りつかれた「大人になりきれていない大人」ではあるが、主人公とは明らかにベクトルが異なる。その事実は主人公にとって敗北感のようなものをもたらす。
全5篇に優劣をつけるのは難しいが、「すごい」と思ったのはこれが一番かもしれない。何より「消極的自死」というフレーズが強い。ちなみにほぼ全編でタバコが小道具として出てくるが、この作品にでてくるタバコが一番好きだった(私は非喫煙者だが)。
「濡れ鼠」
アラフォーの大学講師が主人公。彼には元教え子の一回り年下の彼女がいる。身内の不幸をきっかけに精神を病んだ彼女は、バーの仕事に転職する。主人公は彼女の仕事や生き方に口出ししないつもりでいたが、昼夜逆転の生活サイクルから生じるすれ違いに日々ストレスが募っていた。
「共感」と「好き」は混同しやすい。私は読後まもなくはこの短編が一番「好き」と思ったが、良く噛み砕くと「共感」のほうが強いかもしれないと今は思う。
「相手ファースト」をジェントルに貫いていたつもりが、それが結果として自分のことも相手のことも嫌いになっていく負のスパイラルを呼び込んでしまう。正しいのか正しくないのかはさておき、本音をぶつけた「濡れ鼠」に齢30の私も思い当たる節がありグッときた。鬱屈した短編集の最後に、少なくとも表面的には明るい終わり方をする本作を持ってきたあたりも良い。
まとめ
全ての作品にみられるのは痛烈な「自己否定」である。「負い目」と言い換えてもいいかもしれない。そうした自己否定の先にあるのは「自傷行為」あるいは「自分の身体的・精神的な傷に鈍感になる」ことだと全作品に共通してみれる主張だと感じる。
ラランド・ニシダは「ネタを書かないほうの芸人が小説を書くのは異常」的なことをたしかアトロクで発言していた気がするが、いわゆる「お笑い」の要素があまりないことがむしろ芸人の書く小説としては異色に感じた。
大学を中退し、親から実家を出禁にされている等、よくニシダがバラエティやYoutubeで話すエピソードトークは「面白い」。けれどこの一冊を読み終わり、著者のエピソードと各短編を重ねていくと、彼の人生経験が反映されているのではないかと勝手に想像し、より深いところまで沈んでしまった。安易な「自己肯定」に落とさず「自己否定」が続くので結構パンチは重たい小説たちだが、だからこそ一読の価値は必ずある。
