
部分荷重練習の意義。時期・強度に最適あり
📖 文献情報 と 抄録和訳
骨癒合に及ぼす動力化時間と度合いの複合効果
Fu, Ruisen, et al. "The combined effects of dynamization time and degree on bone healing." Journal of Orthopaedic Research® 40.3 (2022): 634-643.
🔗 DOI, PubMed, Google Scholar
[背景・目的] 骨折の治癒を促進するために、固定具の硬さを硬い状態からより柔軟な状態にして、距離間運動(IFM)を増加させるダイナミゼーションが臨床的に広く用いられている。しかし、動的化の程度(固定剛性から柔軟固定への相対的な固定剛性/IFMの変化)が、様々な段階での骨癒合にどのように影響するかは、まだ不明である。この問題を解決するために、我々はファジーロジックに基づくメカノレギュレーション組織分化アルゴリズムを、羊の骨切り術治癒モデルの公開実験データに対して使用した。
[方法] 骨切り1、2、3、4週間後(R1wF、R2wF、R3wF、R4wF)に0(完全剛体固定)から0.9(剛体固定に対して90%剛性低下)まで様々な程度の力学を適用し、8週間の治癒過程において骨再生とバイオメカニクス的完全性の計算上の評価を行った。
[結果] 常時剛体固定と比較して,早期力学化(R1wF,R2wF)は骨切りした骨の橋渡しとバイオメカニクスの回復に遅れをもたらすことがわかった.しかし、早期負荷の治癒への影響は、負荷強度の程度に依存していた。具体的には、負荷の程度が高いほど(例えば、R1wFでは0.9)、骨結合の遅延が長くなり、曲げ剛性がほとんど回復しない(無傷の骨に対して48%)。一方、中程度の負荷の程度(例えば、0.5または0.7)では、骨形成と骨切り後の骨のバイオメカニクス的特性が大幅に向上した。
[結論] これらの結果は、負荷の程度とタイミングが治癒過程に相互的に影響することを示唆している。早期の負荷と適度な負荷強度の組み合わせは、骨折した骨の最終的なバイオメカニクス的回復を促進する可能性がある。
🌱 So What?:何が面白いと感じたか?
新人の頃、骨折後の部分荷重練習をもどかしく思っていた。
早く歩行練習をしたい。というか、本当に部分荷重って必要なの?理論上の建前ではないの?
そんな風に感じていた。
だが、そんなことはないのだ。
今回の研究も、強力な証拠の1つを提供してくれている。
早期に大きな骨負荷を加えれば、骨折治癒は遷延化する、どころか偽関節化する危険もある。
一方で、適度な時期に、適度な負荷を加えることは、骨折治癒を促進する。
今日は、この文献を用いて、「鼻にはつくけどドヤれる先輩になる方法」を考えてみる。
先輩:「どうして部分荷重って必要だと思う?」
新人:「骨を壊さないため?、ですか?」
先輩:「半分正解、半分不正解。この文献を見てみな。早期の大きな荷重負荷は骨を壊す危険性がある、君のいう通りだね。そしてもう1つ、適度な時期に適度な負荷を加えることは、骨折治癒を加速させる。これがもう半分というわけ。」
新人:「なるほど!、だから部分荷重が重要なんですね」
先輩:「その通り。そこしかないっていうタイミングと強度で骨に荷重ができるPTって、かっこいいと思わない?部分荷重って受動的で、保守的で、つまらないって思われがちだけど、何かを防ぐ、守るだけのものではなくて、何かをつくる、攻める治療なんだよ、な。」
新人:「先輩、すごいっす!」
「アイントシュルツの法則」、と呼ばれる刺激と応答に関する法則がある。
✅ アイントシュルツの法則とは?
弱い刺激をすることで神経機能を喚起し、中程度の刺激で神経機能を興奮させ、
強い刺激は神経機能を抑制し、最強度の刺激で静止する方法である。
~Wiki~

今回の研究では、アイントシュルツの法則に、時間軸が加わった。
すなわち、同じ刺激が、時期によって違う意味を持つのだ。
筋力の変化によって、過負荷の定義が刻々と変わるように。
同じ太陽の光も、地中深く暮らす幼虫には死を、蛹から脱皮した成虫には生を与えるように。
そして、大事なのは、その当事者の代謝状況によって、回復のタイムスケジュールはずいぶん違うだろう、ということ。
たとえば、糖尿病を合併症として有する場合、まったく同じトレーニングをしても、その効果は健常者とは大きく異なることが報告されている(📕 Minnock, 2022 >>> doi.)。
超高齢、糖尿病、がん、当事者の状況による回復のタイムスケジュールの違い。
そこを、臨床上、どのように加味したらいいのだろうか?
何らかの、マーカーがいる。
レントゲンやCTやMRIもいいだろう。だが手間であり、流石に毎日は撮れないし、理学療法士が独立して行いにくい。
超音波などで、そのあたりのマーカを得られないものか・・・。
それがあれば、毎回、超音波で確認して、「ああ、ここが〇〇になったので、1/2荷重練習をはじめますね。××になったので全荷重練習に移行しますね。」のようにタイムリーなかっこいい治療が可能となる。
誰か、知っている人がいたら教えてください🙇
○●━━━━━━━━━━━・・・‥ ‥ ‥ ‥
良質なリハ医学関連・英論文抄読『アリ:ARI』
こちらから♪
↓↓↓
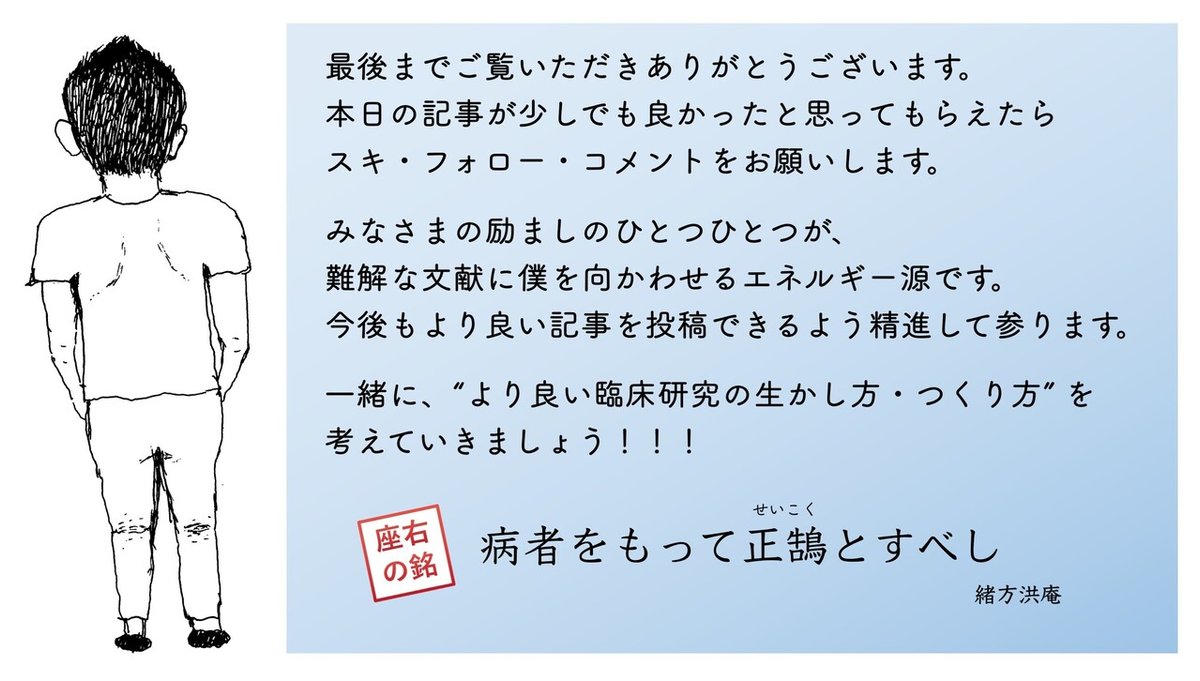
‥ ‥ ‥ ‥・・・━━━━━━━━━━━●○
#️⃣ #理学療法 #臨床研究 #研究 #リハビリテーション #英論文 #文献抄読 #英文抄読 #エビデンス #サイエンス #毎日更新 #最近の学び
