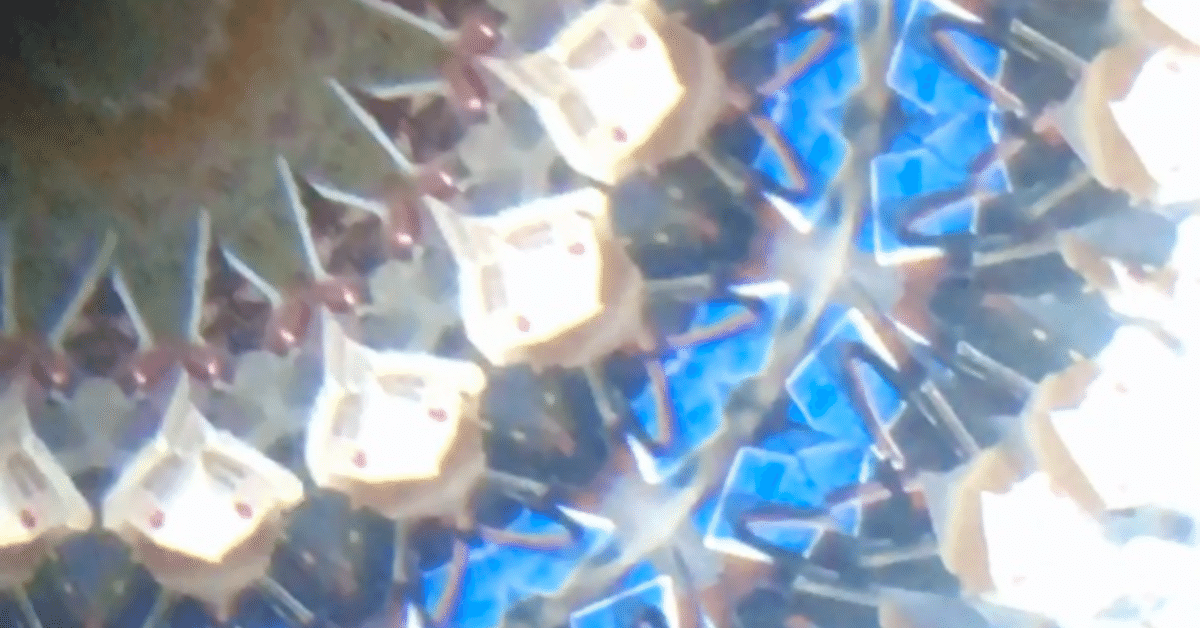
はじまりのはなし…無力感④
「一粒の身体で何が出来るのでしょう?小さな光で何が照らせるのでしょう?…消えてしまいそうで…消えてしまいたくなりそうで…ただ、ぼんやりと虚空に浮かぶばかりの私は、弱さ以外には何も持ち合わせていないのです」
目に見えて痩せ細って来た…彼女も僕も。
「今年こそ痩せるぞぉー」
それが彼女の口癖だった。でも、彼女のダイエットが続いた事は一度もない。胃袋には逆らえないと言って、いつも寝る前にはプリンやアイスを食べていたし、頑張ると言っていたホットヨガも、結局始める前に辞めてしまった。
それに深夜の通販番組で買ったダイエット器具やら妙なドリンクやら…彼女はいつの間にか実家のお母さんにプレゼントだと言って送っている事が多かった。
お母さんは何も知らずに喜んで、お礼だと言って西瓜を一玉送ってくれた事もあった。
彼女はダイエット中にも関わらず、冷蔵庫に入り切らないと言いながら、一晩で三分の一玉は軽く平らげていた。
今の彼女は、その頃からは想像もできないような華奢な身体になって、小さな夢を叶えたのかもしれない。ただ、その代償は余りにも大きい。
生きる事は何故こんなにも難しいのだろう?
つい数年前までは全てが上手くいっているように思えた…幸せな生活が当たり前だった。
それがジェンガのように、一手で簡単に崩れてしまうような…脆くて弱い人生だったのだと、今になって思う。
それは僕達の人生に限った事ではないだろう。誰の人生も一寸先は闇なのかも知れない…
どれだけお金があっても、どれだけ権力があっても、どれだけ知恵があっても…相違ないのではないだろうか…
「少し痩せたんじゃない?」
「そうかなぁ?」
「ちゃんと食べてる?」
「食べてはいるよ」
「コンビニのお弁当ばっかり食べているんでしょ?」
「コンビニのお弁当だったら太るんじゃない?」
「そっか…そうだね」
「そう言えば最近、鏡を見ると一瞬...自分だと認識出来ない時があるよ...心はまだ、痩せる前の自分なんだろうね...」
はじまりの話を語り始める時、彼女は何かに怯えたように、身体が震え出したかと思うと、突然ガリガリと親指の爪を嚙り出す事がある。
小学校低学年の頃…僕はいじめっ子側だったが、高学年になる頃には自分の所にいじめられっ子の順番が回って来た。
今思えば、勉強もスポーツも出来なかった僕には、回って来るのが遅いくらいだったと思う。それだけ僕は、いついじめられてもおかしくない少年だった。
いじめが始まった原因は些細な事だった。その頃の僕には、何か嫌な事があると親指の爪を嚙る癖があった。両親にも「いい歳して、やめなさい」と散々注意されたが、中々治らなかった。
最初はそれを見た同じクラスの女子生徒の一人に汚いと言われたのがキッカケで、他の生徒からも敬遠される様になり、そんな女生徒達に対して、何も言い返す事のない様子から、今度はそれまで仲が良いと思っていた男子のクラスメイトにまで、男の癖に弱虫だと揶揄われる様になった。
それから、高校に上がるまでの数年間は地獄の様な暗い日々が続いた。元来いじめっ子気質の僕が、それまでいじめっ子側に立っていた所為で、当然だと…自業自得だと言う空気から、誰からも同情されず、手を差し伸べられる事もなかった。
そんなある日、下校のチャイムが鳴り響いて、一斉に全校生徒が家路へと急ぐ最中である。僕は人との接触を避けて二階の教室に残り、机にへばり付きながら、窓から校門をジッと睨んでいた。すると黄色い帽子を被った黒蟻の行列の先に、いつも僕と一緒に帰っていた友達とそれまでいじめられっ子だったクラスメイトが、仲睦まじく校門から出る所が見えた。
衝撃だった。僕の人生は彼の人生と入れ替わってしまったのだと...これが因果応報なのかと、放課後の教室で一人、爪を嚙りながら泣いた。
彼女には人前で爪を嚙る様な癖はない。確かに幼い子どもの様な無邪気な所はあるが、お母さんの躾がしっかりしていたのか、出会った頃からの清潔感があって礼儀正しい印象は変わらない。だからこそ、はじまりの話を語ろうとする時のあの苦しそうに呻き声を漏らしながら爪を嚙っている姿は不自然で...その姿は彼女ではなく、唐突に再会したあの頃の弱虫だった自分の虚像に見えた。
人は鏡だと言う話を聞いた事がある。僕の人生にとってその役割を最も多く果たしてくれたのは彼女かも知れない。彼女といる事で自分の嫌な所や良い所に何度も気付かされた。
しかし、この爪を嚙る姿に限っては...鏡というよりも、鳥籠に入った下手な鸚鵡のモノマネを見せられている様で、戸惑いと嫌悪しか感じなかった。彼女には、僕がいじめられっ子だった頃の事は隠しているし、彼女の前で爪を嚙った事はない筈なのに...意図的にあの頃の記憶を思い出させようとしている様な...いや、記憶よりも感覚に近い何かを...
「爪を嚙るのは意識ではありません。退行した記憶に肉体が反応した副作用によるものなのです…理解し難いでしょう?
今のあなたには想像もつかないのでしょうから…手も足も無い…何も出来ない光の粒の無力さが…それが、どれほど苦しいのか…それが、どれほど辛いのか…あなたは忘れてしまっているのでしょうから...
光の粒どころか、子どもだった頃の身体の感覚も、母親と臍の緒で繋がっていた胎児の頃も、手も足もない小さな一つの受精卵だった頃の記憶も...全て失って、常に現在だけを指差して、それだけを自分と認識して、何でも出来るつもりになっているのですから…」
続く
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
