《連載#1》子どもを正しく”ほめる”方法①
こんにちは!タノ🦒の教育連載#1です。
この連載では「学べる」「役立つ」「たまに面白い」教育情報を
中高御三家男子校(その中でのワースト経験)→MARCH大学
個別&集団塾講師3年、小学校アシスタント2年、小学校教師7年間の経験を元に
お伝えします。
最新の教育情報と実践での効果を組み合わせて、
教育現場で働く方・先生を志す方・子育て中の方向けの記事です。
(教育業界で一生働くタノの学びの整理も兼ねています✏️)
約10回を予定している連載です。
この記事が、少しでも教育の未来のためになればと思います💡
#1のテーマは《ほめること》です。
子どもを育てる=”ほめる”という認識の方も多いかもしれません。

今回の、”子どもを正しくほめる方法①”では、
当たり前のように感じる”ほめる”を正しく理解しましょう!
1、何のために”ほめる”の?本当に”ほめて”良いの?
ステップ1は、何のために”ほめる”のかを正しく認識することです。
まず、”ほめる”を皆さんはどのように漢字で書きますか?

・・・そう、2パターンあります。「褒める」「誉める」です。
この2つは似ているようで微妙に異なります。
褒める→相手の行いを評価して良しとする。ご褒美(ほうび)の「褒」
誉める→勝利や受賞などでみんなで持ち上げて評価する。「名誉」の「誉」
1つ目は個人、2つ目はみんなで、のイメージです。
誉めるは表彰などをイメージしていただければ良いと思います。
今回は1つ目の方についての話です。
そこで少し、話を変えますが、みなさんは聞いたことがありませんか?
「アドラー心理学」や「褒めてはいけない」という言葉。
本もたくさん出版され、
体感ではここ10年ほどでよく耳や目にするようにになりました。

※参考文献
この言葉を見た時など、
「そんなバカな!褒めて伸ばせ!と言われてきたのに!」
「叱ってもだめなら何の言葉もかけられないじゃないか!」
と混乱しますよね。
この矛盾を解きます。
そもそも”ほめる”行為は、
同じ場面でも、言葉かけや意図によって効果が変わります。
2、”ほめる”を分析する(意識編)
次にステップ2です。
”ほめる”ということを分析してみましょう。
少し、”ほめる”について迷う状況の中、
具体例で考えてみましょう。
例えば、勉強を頑張っている子どもに対しての声かけです。
パターン1
宿題をしっかりやっていいて偉いね〜
パターン2
言われたことちゃんとやってて〇〇は良い子だね!
パターン3
がんばってるね!終わったら甘い物たべようね〜
パターン4
次の試験楽しみだね!
みなさんなら、どれを選ぶでしょうか?
そして、これらの声かけは、どのような意図で行っていると感じましたか?
私は、それぞの声かけの主の意図を、このように設定しました。
パターン1→これからも”ちゃんと”宿題やりなさいよ
パターン2→これからも言われたことを”ちゃんと”やる子でいなさいよ
パターン3→応援してるよ!
パターン4→頑張った結果を一緒に受け止めたいな
これらの意図の決定的な違いは、なんでしょうか。
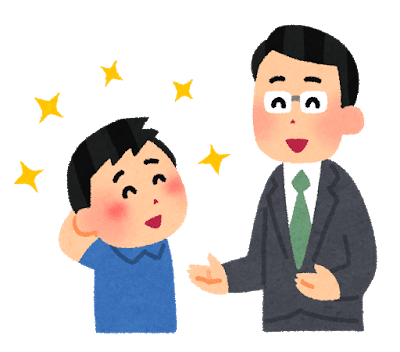
それは、”ほめる”相手をコントロールしようとしているかどうかです。

パターン1、2も「勉強をさせようと大人がコントロールする声かけ」です。
必ずしも悪いわけではありませんし、短期的には効果を発揮します。
ですが、子どもを縛る鎖になり、結局は
「勉強をしていない子ども」に対しては苛立ちが募ってしまいます。
自分だったらと考えてみると、
”コントロールされそうになる”ってイヤですよね。
そして、年齢が上がると子どもはその意図に気づけるようになります。
今までは”ほめてくれていた!”ということが、
「あれ?コントロールしようとしているだけじゃ?」
と気づかれた時、このパターン1と2は逆効果になります。
勉強を頑張っていたら”ほめられる”けれど、
頑張っていなければ”認めてもらえない”条件付きの”ほめる”だからです。
また、もう1つ弊害があり、
それは、”ほめられる”ことが目的になる危険があることです。
”勉強をしたら喜んでくれる”から勉強するとなってしまうと
歳を重ねて”大人が喜んでくれなくなった”時に意欲がなくなります。
このパターンの”ほめ方”は、ある程度の即効性はありますが、
諸刃の剣であり、子どもが年齢を重ねるといずれ効力を失うことを理解して使わなくてはいけません。
では、パターン3と4はどうでしょうか。
これらは厳密には、少し”ほめる”とは違います。
これらは「応援」や「勇気づけ」といわれる行為です。
「頑張っているあなたを見ているよ。知っているよ。応援しているよ」
という行為です。
ちなみに、「次の試験が楽しみだね」もニュアンス次第では、
「次の試験は100点がとれそうね」と
「頑張った成果が見れるのが私も楽しみにしてるよ」では大きく違います。
前者は100点がとれなければ=失敗です。ですが、
後者は成果が見られたらOKですし、もし上手くいかなかった時でも、
「あれだけ頑張っても上手くいかないこともある、
でも頑張ったことは十分知ってるよ。無駄じゃない。次がんばろうぜ」
と次につなげられます。
これが「勇気づけ」です。
大人側が「条件付きでこうなってほしい」とコントロールするのではなく、
子どもの「ありのまま」「頑張っている姿」を認めることが大切です。
そして、どの”ほめる”でもそうですが、
口先だけの言葉は相手には届きません。
パターン3・4であっても、心から言わなくては届きませんし、
パターン1・2であっても、相手を応援する行動を行っていれば、
言葉以外の部分で、相手に思いが届くでしょう。
3、とはいっても・・・(実践編)
というわけで、ステップ3です。
ここでは、実践の話をします。
正直、子どもをコントロールする必要はある。という話です。

おいおい、「散々言っといてそれかよ!」なんですが、
教員経験者からして思うことは、
「いや、コントロールしないわけにはいかない」ということと、
多分、子育てをしてらっしゃる方もそう思っているということです。
子どもたちが、自分だけの力で育つのは難しいと思っています。
主体的というと聞こえはいいですが、それは教育とは呼べないと思います。
大事なことは、
本当に相手の成長を願い応援する心と
コントロールしているように思わせない技術
という矛盾する2つを両立させることです。
そして、今回の記事でお伝えしたいことは、
”今までほめていたことに、間違いはない”という点です。
子どもの成長段階によっては、
分かりやすいパターン1、2の言葉でも良いんです。
それに、「いつもいつも応援するだけなんてできないよ!」
という思いももちろんありますよね。
「いや、やれよ!!!!」と待ってられず叫びたい時もあります。
そのような時の有効な手段もあります。
Iメッセージというものをご存知ですか?
「また部屋を散らかして!本当にだらしないな」
「ほら、早く!部屋を片付けなさい」
という相手に原因を求める。これは、YOUメッセージです。
さきほどから話している「コントロールしようとしている」
が全面に押し出されていています。
一方で、
「もう夕飯だから、部屋が散らかっていると私は落ち着かないな」
「部屋を早めに片付けてくれると私はありがたいな」
という言い方に変えることができます。
先ほどの命令ではなく、気持ちを述べているので、責める言葉ではありません。
これがIメッセージです。
命令形のYOUメッセージは、選択肢が1つしかありませんが、
Iメッセージは相手に選択権が残されていることが、大きな違いです。
最終的に相手にやってもらいたいことは同じです。
ですが、印象が違いますよね?
これだけだと少し足りない気もします。
さらに付け加えるなら、
「部屋を早めに片付けてもらえると(私は)ありがたいんだけど、
6時までだったら、何分くらいでできそう?」
という、相手の思考を具体的な方向に持っていくこともできます。
「やる」「やらない」ではなく、
「何分でやるか」という選択肢になり、「やる」ことが確定します。
さらに、
「まず、机の上を片付けて、おもちゃを箱に入れて、タンスにしまうのよね・・・
あなたなら何分くらいでできる?」
と言う風に、「試す」言葉を付け加えると、
子ども「15分!」
大人「15分?本当にできる?じゃあ、夕飯作りながらだけど見てるね!」
という流れになります。
ポイントは、
「相手に選択肢を与えている」ように見せつつ、
「やる」という選択肢に相手を誘導している点です。
#タノのことを黒いと思いますか?
実際、よく担任をしていたときは、
席替えや帰りの準備の時に、どの位でできるか時間を聞いていました。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
タノ「何分でできる?」
児童「5分」
タノ「本当?昨日は6分だったよ?」
児童「いや、できる!」
タノ「よし、じゃあ時間測ってみるよ」
児童「はい!」
タノ「どんな流れでやるのか教えて」
児童「まず〇〇して、次に△△します」
タノ「さすがですね」「では、座った人から名前を呼びます」
「全員座ったら終了だよ」「じゃあ、スタート」
〜活動終了〜
「すごい!4分20秒だ!40秒も早かった!」
「やることを頭に思い描いて動けたからだね。」
「行動が素早くできる人は、(私は)素敵だと思います。
きっと他の場所でも活躍できますね」
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
このようなやりとりは日常的にありました。
そして、1〜6年生まで、どの学年でも有効な手立てでした。
これは、
①相手がやることを具体化させる
②相手に選択の余地を残す
③終わったら良かったところをフィードバックをして、価値づける
という点が大事です。
子ども達が、
自分で考えて選択し動けるように聞いて、
それを認めて、価値づけてあげることができれば、
きっと力は伸びていきます。
コントロールしているけれど、
ここまでやるとコントロールしているようには思えないですよね。
ちなみに、根底には、
「子どもたちが自立できるように育ってほしい」があります。
なので、罪悪感はなく、心の底から言葉をかけることができます。
4、”子どもを間違わずにほめる方法①”のまとめ
今日の復習をします。
✏️ステップ1
”ほめる”には2種類の表記「褒める」「誉める」がある。
”ほめた方がいい””ほめてはいけない”という矛盾する意見がある。
✏️ポイント2
”ほめる”言葉をかけるときは、
「相手をコントロールしようとしている」のか
「認めようとしている」のかを考える
✏️ポイント3
”ほめる”時には、
相手が選択をし、その姿を認めて、応援するように意識すると良い。
※関連リンクを貼っておきます。

なんのために、”ほめる”のかを大切にしていきたいですね。
この記事を読まれるような方は、
お子さん、子どもたちのことを考えている方だと思います。
まず、その自分自身のことを認めることが大切です(*^▽^*)
自分も「勇気づけて」
子ども達との素敵な日々を送りましょう!
次の記事は、”子どもを正しくほめる方法②”です。
主に、教育現場での実践編ですが、きっと役立つ内容になると思います!
最後に有名なこの言葉を載せて終わります。
山本五十六の言葉。
やってみせ
言って聞かせて
させてみせ
褒めてやらねば
人は動かじ
次回の記事には、この続きの言葉も載せます!
今回はここまで!
読んでくださった方が行う教育が、さらに楽しいものになりますように💡
タノ🦒でした!またね!
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
「記事のここをさらに聞きたい」
「この部分が良かった」
「ここは少し分かりづらかったなあ」
というところがあったら、
お手数ですが、コメントなどで教えてくれたらありがたいです!
いただいたコメントは全て読ませていただき、
今後の教育や記事に必ず活かせていきます!
何卒宜しくお願いいたいいたします!🙇♂️
