
「レイヤーの合成」によるVTuberの再定義――主体的な生のデザインのために
VTuberのゲーム配信の画面は、よく考えてみると奇妙である。たとえばFPS(ファースト・パーソン・シューティング)ゲームの配信画面であれば、その名の通り一人称視点のゲーム画面があり、マップを邪魔しない位置のどこかに、視聴者側を向いたLive2D(平たく言えば「動くイラスト」)や3Dモデルの上半身が置かれるという構成を、基本的にとっている。

このとき、ゲームをプレイしているVTuberの顔は、本来はそのゲーム画面のほうを向いているはずだ。しかしその顔はゲーム画面ではなく、視聴者側を向いているわけである。視聴者はゲーム画面自体も観ているわけだから、そこでは異なる視線のベクトルが同居しているというか、現実的にはあり得ない特異な空間が、視聴者の脳内で合成されているということになる。
ここで、生身の人間の配信者の画面と比較してみよう。背景を切り抜いて本人の姿のみをゲーム画面に重ね合わせることも技術的には可能だが、多くはそのような処理をせず、本人が腰を落ち着けている部屋の様子ごとカメラが捉えた映像を、ゲーム画面に重ね合わせている。

ひるがえって、生身の人間の配信を観ている視聴者には、自分自身が今いる場所……自室だったり、あるいはスマホを使って外出先で観ている場合は、その空間だったりが意識されやすいだろう。そこには物理的に離れた実空間が、通信技術によって繋がっているという了解がある。ゲームコンテンツを介しているとはいえ、そこで配信者と視聴者とを取り結んでいる関係性は、ビデオ通話の延長にすぎないとも言えるだろう。
VTuberという存在との「出会い」の経験は、実空間モデルをベースにする限り、奇妙なねじれを伴っている。この事実に改めて驚いてみることから始めたい。
「VTuberが絵なら、視聴者は文字」
2022年、VTuber・月ノ美兎のある発言が話題を呼んだ。とある配信の中で「でもV(筆者註:VTuberのこと)は絵だから心なんてないぞ」というコメントがあったのに対して、「わたくしが絵なら、てめえらは文字だろうがよ!」「一次元が二次元に何言ってんだ」と言い放ったのだ。
文脈を説明すると、このとき月ノがプレイしていたのは、疲れたメイドカフェの雇われ店長のもとに、彼が愛聴しているメイド型VTuberが「受肉」して甲斐甲斐しく世話を焼くという内容の……いわゆる「ギャルゲー」である。その性質上、月ノ本人と視聴者双方から、VTuberというものに対する自己言及的な発言が飛び出しやすい状況となっていた。
先述の「煽り」を書き込んだのが仮にファンだったとしたら、通常の配信では彼ら彼女らもそんな発言はしないだろうし、仮にアンチによるコメントだったとしても、無視すればいいレベルの他愛もない内容だ。それを敢えて拾ってみせたところに、わざわざこんなメタなゲームを選んで実況プレイをした月ノの配信者としての嗅覚の鋭さがあるわけだが、ともあれここで暴かれてしまったのは視聴者という存在が、VTuber側からしたらコメント=文字にしかすぎないという事実である。
これは私たち一般的な人間どうしが、スマートフォンでテキストメッセージを送り合うのとは異なる。そこでは必ず送り先が自分の今いる実空間と地続の場所であり、生身の身体を持った主体がいることが暗に了解されているからだ。
一方VTuberの場合、視聴者にとってのコメントの送り先としての空間は不確かなものである。先に述べた「ねじれ」の構造によって、私たちはその宛先をうまく想像することができないのだ。したがって、その送り先はコメントが反映される配信画面という平面上に「とどまる」。そのコメントを配信主であるVTuberは拾うことができ、さらにその拾っている様を視聴者はVTuberの姿とともに画面として見る……という、再帰的な構造が完成する。
VTuberと視聴者のコミュニケーションのすべては三次元的な実空間モデルを介することなく、平面の「合成」として完結するのだ。視聴者がコメント=文字という、一次元的な存在であると言えるのは、このように配信画面こそを基礎的な場として捉えたときである。
「レイヤーの合成」のメカニズム
こうした「合成」が可能となるのには、技術的な背景がある。評論家の大塚英志がアニメーション作家・新海誠のデビュー作『ほしのこえ』について論じた「レイヤーの美学」(『EYESCREAM増刊 新海誠、その作品と人。』、スペースシャワーネットワーク、2016年所収)というテキストが参考になるので見ていこう。
大塚はこのテキストの中で、アニメーションといえばそれまで登場人物やオブジェクトが「活き活きと動く」ものとされていたのに対して、静止画の断続的なカットアップや背景のレイアウト設計によって特徴づけられる『ほしのこえ』は、デジタル時代ならではの新しいアニメーションの価値観を示したのであり、その中心にあるのが「レイヤー」という概念である、という旨のことを語っている。
ぼくが『ほしのこえ』を初めて見た時の驚きは、このアニメーションが、まず、一つのカットが計算された鋭角的なカメラアングルに加えて、レイヤーからなる重層的な画面の構成によって設計され(つまり映画の1カットとして徹底して設計され)、その上で、カット間でショット(ブロッキングサイズ)やアングルを大胆に変化させながら、それを一連の映像として、繋いでいき、そして、さらにその映像に少年と少女の声とメロディーが(妙な言い方だが)「重層的に重なる」構成になっていることだ。
言い方をかえれば、カットの中で風景がレイヤーの重なりとしてあり(つまり、空間内のレイヤー化)、そしてそのむしろ静止的であることが重要なカットごとの醸し出すイメージを私たちはレイヤーが次々と重なるように示され(時間軸上のレイヤー化)、そして、その映像の流れの上に少年のモノローグ、少女のモノローグ、そしてメロディーが重なる(意識、あるいは「声」のレイヤー化)のだ。そういう多元的なレイヤー技術によって新海のアニメーションはつくられていた。
とはいえ評論家として頭角を現す以前より、漫画雑誌の編集者、さらに漫画原作者というキャリアを歩んできた大塚にとって、このレイヤーという概念はまったくの新奇なものではなく、むしろ馴染み深いものであったという。
例として、漫画『ちいかわ』のある回を見てみよう。

1コマ目はちいかわの一人称視点で、ハチワレが暮らす洞窟の入口を捉えている。2コマ目はカメラがちいかわの正面に移動してこちら側に歩いてくる様を捉え、3コマ目ではちいかわの内心を描写、4コマ目では再びちいかわの姿を客体として捉える位置(洞窟の中)にカメラが移動し、5コマ目ではちいかわ・ハチワレ・うさぎの三匹をフレームに収める三人称の視点になっている。
このように、コマをまたいだ視点=人称の移動を平然と行ってみせるのが、漫画というメディアの特性である。「コマ(世界を枠づけるフレーム)」「キャラクター(客体)」「フキダシ(内心の声)」がそれぞれ異なる「レイヤー」に属しており、それを「合成」することで作品を成り立たせるシステムが、読者の柔軟な視点の移動を可能にしているのだ。
漫画の読者はキャラクターと感情を共有しつつ、同時に感情を切り離し、俯瞰的に作中世界を把握することもできる。ここで読者の中に立ち上がっているのは、実空間モデルに依存しない、「漫画の読者」としか言いようのない主体性である。ゲーム画面とVTuberの姿を同時に視界に収める視聴者の中に生じる主体性も、これに似ているところがあると言えるだろう。
このように「レイヤーの合成」という論点から考えたとき、VTuberのクリエイティビティの核心は、本人のパーソナリティやビジュアル面もさることながら、配信画面の設計にある。ゲーム画面の枠を配信画面全体の外枠と一致させるのか、それとも入れ子構造にするのか。アバターはLive2Dを使うのか、3Dモデルを使うのか。コメント欄を画面内に表示するのか、しないのか。視覚的な要素ではないが、どのようなBGMを選択し、ループさせるかというのも極めて重要だろう。「レイヤーの合成」によって可能になる、さまざまなオブジェクトの配置による仮想的な空間の設計が、視聴者とそのVTuberとの「出会い方」をデザインするのである。
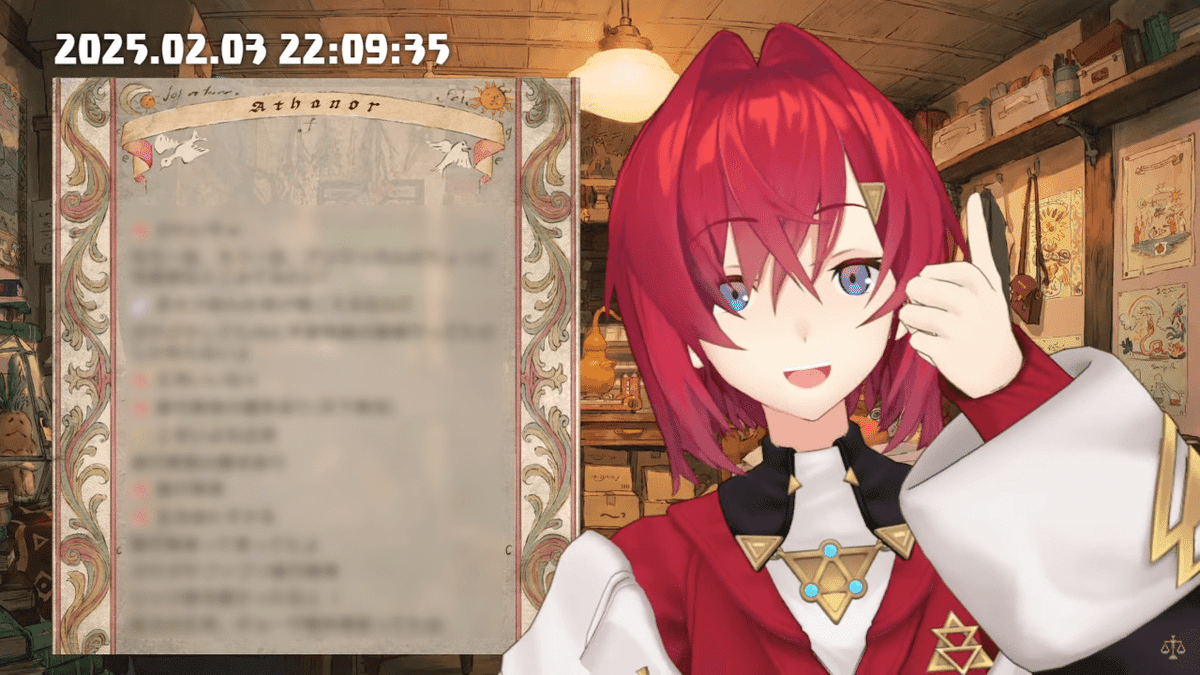
「OBS芸」と「コラボ」の本質
VTuber自身によるリアルタイムでの「レイヤーの合成」は、配信に使用されるソフトウェア・OBS Studioの名前を用いてときに「OBS芸」と呼ばれる。その最もラディカルな事例のひとつとして、不破湊が2022年の8月に毎朝行っていたラジオ体操企画に、剣持刀也がゲスト出演した際のアーカイブを挙げたい。
このラジオ体操企画では、緑生い茂る広い公園の画像を背景にセミの鳴き声をBGMとして流すことで仮想的な三次元空間を演出し、そこに立った不破がゲストを迎えるという体で進行していく。
そんな中、剣持刀也はLive2Dの身体で、オプションパーツの机のオブジェクト(プラス、机に乗せているように見える足のパーツ)とともに登場し、終始不機嫌なヤンキーのような態度を取り続ける。いざラジオ体操が始まると、中指を立てた腕のパーツだけが分離・増殖して空中に浮いたり、「いらすとや」でダウンロードしたヤンキーのイラストが画面を埋め尽くしたりと、「実空間に体操をしに来た」という暗黙のコードを破壊するバグのような事態を引き起こす。それを隠すように、仮想的な三次元空間に立っていたはずの不破湊も、自らの身体を平面的に操作せざるを得なくなる……これ以上は実際にアーカイブを観てもらったほうが早いだろう。
三次元の広場を仮想的に作るという不破湊のクリエイティビティに対して、あくまで平面の次元にとどまる剣持刀也のクリエイティビティが衝突し、次元間をまたぐ対立がひとつの画面上で「合成」されているのである。

異なる「レイヤーの合成」のポリシーを持つ配信者がひとつの画面上で邂逅している……ここで起きている事態は、VTuber文化において中心をなす「コラボ」という概念の本質を突くものとも言えるだろう。このケースとは逆に、Live2DならLive2Dという「レイヤーの合成」のポリシーをインターネットを介して共有することによって、画面上に単一の空間をデザインすることができる。

このとき、「オフコラボ」とは単にリアルの(私たちの身体がある、実空間の延長の)空間において一緒にいるという意味でなく、この「「レイヤーの合成」をインターネットを介して共有する」という操作がなされていない=「オフ」状態の「コラボ」として再定義することができるだろう。
「声」という特別なレイヤー
大塚英志は『ほしのこえ』に関して、漫画にはない「声」のレイヤーがあったからこそ、漫画業界での経験が長い自分にとっても画期的に感じられたのだという旨のことを述べている。遠宇宙に飛び立った少女と地上に残った少年の言葉は交わらない、しかし心はともにあるのだという錯覚を視聴者に起こさせたのが、まさにこのレイヤーの存在だった(クライマックスでの「ここにいるよ。」という発話のシンクロは、視聴者にしか聞こえない)。
大塚はそこに、本作が自主制作の作品であるということ、制作者の新海自身がキャラクターボイスを吹き込んだという情報を重ね合わせる。孤独に制作作業を続けていた新海が、どこにいるかもわからなかった自作の視聴者に向けて、多層的なレイヤーの操作をもって「作品=メッセージの届かなさ」と「祈り」を主題とした物語を描いたことに、形式と内容の完璧な一致が見られる。だからこそ、同作は奇跡的な傑作と評価するに値するのだと。
視聴者に同時性を錯覚させる「声」の重要性は、アニメーション作品よりもリアルタイム性が重視されるVTuberのライブ配信において、いっそう高まることになる。先述のような、一見すると悪夢のようなシュルレアリスム的光景をエンターテインメントとして視聴者が楽しむことができるのも、VTuber(ここでは剣持刀也)の「声」が視聴者と関係を取り結ぶものとしてそこにあるからだ。
冒頭に述べた、VTuberのゲーム実況の画面に感じる奇妙さを改めて思い出そう。視聴者の視線はVTuberの視線と決して交わらないし、コメントの送り先もうまく想像できない。それでも自分とVTuberが特別な関係を結べていると視聴者が錯覚できるのは、ひとえに彼ら彼女らの「声」があるからである。
VTuberはLive2Dであったり3Dであったり、グッズなどに描かれるイラストであったり、グラデーション的にさまざまなレイヤーにまたがって存在している。そこに「確かに彼ら彼女らは彼ら彼女らである」という同一性をもたらすのが「声」なのである。彼ら彼女らが「視聴者」ではなく「リスナー」という呼称を用いることが多いのは、このことを彼ら彼女ら自身も無意識にであれ自覚しているからだろう。
「レイヤー的な生」を芸術に
「声」を中心に、「レイヤーの合成」によって自らの生きる時空間をさまざまにデザインするということ。この論点から特に注目すべきVTuberが、「甲賀流忍者ぽんぽこ」と「ピーナッツくん」のコンビ、通称「ぽこピー」である。
3Dの身体を持っているのはもちろん、パペットの姿を手に入れて旅行動画を上げたり、着ぐるみの姿でイベントに登場したり、自らが旗振り役となってバーチャル遊園地「ぽこピーランド」を建設するなど、VR空間上での活動にも意欲的だ。そもそも、彼女たちは最初からVTuberだったわけではなく、自主制作アニメーション作品『おしゃれになりたい!ピーナッツくん』を出自としている。
そのようにして常に移動可能なレイヤーを拡張しながら、しかしそのすべてを貫通するものとして「ぽこピー」という存在をプレゼンテーションし続けている。企業に所属しない、いわゆる「個人勢」である(アバターの肖像権を自らが保有している)ことや、家族の概念を拡張している(ぽんぽことピーナッツくんはぽんぽこの実兄・通称「兄ぽこ」を介して関係を取り結んでいる)こと、3D撮影スタジオなどバーチャル関連施設が集中する東京ではなく、地方(滋賀)を拠点に活動していることといったもろもろの要素も込みで、「生き方」のレベルで「レイヤーの合成」を実践しているのがぽこピーだと言えるだろう。
この上で特筆したいのが、ピーナッツくんがヒップホップミュージシャンとして音楽活動を行っている点である。リアルのライブハウスで開催される彼のワンマンライブでは、上記のほとんどのレイヤー(着ぐるみ、2Dアニメ、3Dモデル)におけるピーナッツくんの姿がステージ上で網羅される。バーチャル空間から実空間に「受肉」したことを印象づけるのであれば、着ぐるみだけでも十分にもかかわらず複数の姿をとるところには、彼が「レイヤーの合成」を「生き方」として実践していることへの矜持を見て取ることができる。



なお、ピーナッツくんはこれまでに2回、XR(クロス・リアリティ)ライブと呼ばれるVRゴーグルでの視聴が推奨される配信ライブを開催しており(モニタでも視聴可能)、そこでは3Dのアバターが仮想的なカメラの追従する形で縦横無尽に飛び回る、まさにバーチャル空間ならではのスペクタクル的な演出がなされていた。
ピーナッツくんは「レイヤーの合成」によって実現される自らの生を、芸術にまで昇華している。その中心にあるのは、やはり彼の持つ固有の「声」である。ピーナッツくんのパフォーマンスはその最もラディカルな例だが、VTuberがショーアップされた場で歌唱パフォーマンスを中心にすることが多いのは、やはり「声」こそがその存在の中心にあるからだろう。
そして改めて明記しておきたいのは、VTuberの存在論の核を「レイヤーの合成」に見る私たちにとって「声」が特別なのは、それが発せられる物理的な基盤の存在を根拠とした――つまり「肉声」であるからではない。私たちはVTuberの「声」の発信源を具体的にイメージすることはできず、Live2Dや3Dモデルや着ぐるみに「重なる」ものとしてしか認識することができない。逆に言えば「声」とは、それ自体があらゆるレイヤーを貫通する、いわば「メタ・レイヤー」だからこそ特別なのである。
私たちも「レイヤー」の中に生きている
このように「生き方」の次元まで「レイヤーの合成」という論点を拡張したとき見えてくるのは、VTuberという存在が現代の私たち一般の生のモデルを示しているという可能性である。
たとえば喫茶店で友人と話している最中に、スマホでSNSの相互フォロワーからのリプライに返事をするような状況を考えてみよう。そこで起きているのは「私」の物理的な分割というよりは、二つの「私」がレイヤー状に重なっているという事態である。あるいは、見知らぬ街に降り立ったときにGoogleマップの位置情報を重ね合わせて歩き始めるような状況はどうか。こちらは逆に物理的な現実空間に地図情報が重なっており、二つのレイヤーの狭間を縫うようにして「私」が移動していると考えられる。
このインターネットが遍く普及した世界において、私たちは常に多重レイヤー的な現実感の中に存在している。VTuberを、私たちと異なる特殊な存在として認識してしまうのは、こちらが物理的な肉体を持っているのに対して、アニメキャラクター風のアバターを持っているということ、また物理的なモニタを介してしか彼ら彼女らを知覚できないという非対称性によるものであって、「レイヤーの合成」によって世界が成り立っているという見地に立てば、その「存在のあり方」に違いはないのである。
「キャラクター」から「スタイル」へ
VTuberと私たちの「存在のあり方」に違いはない。このように考えたとき、「私」を「私」たらしめるもの……つまり個々のVTuberを峻別する個性とは何かという問いが、改めて重要なものとなってくる。
これまでVTuberの個性は、視覚的で静的な要素によって規定される、「キャラクター」という概念で分析されることが多かった。しかしそれはVTuberが、私たち実空間に生きる人間に「眼差される」対象として捉えられる限りにおいてである。
本稿のこれまでの議論に照らせば、VTuberは「レイヤーの合成」によって存在する。この論点が『ほしのこえ』というアニメーション作品の分析から導き出されていたことを思い出してほしい。そこにはどのようなレイヤーをいくつ、どのような順番で組み合わせれば時間的な構造が生じるのかという、動的なプロセスへの注目が含まれている。「レイヤーの合成」とはそれを適用する分析対象に、時間というパラメータを導入する分析枠組みなのだ。
ここで「キャラクター」とは異なるもうひとつの軸として、「スタイル」という軸を提案したい。たとえば、毎日決まった時間に配信を行う、雑談を中心に活動する、歌配信をメインにする、といった行為の積み重ねがVTuberの「活動スタイル」を形成する。「スタイル」とは単なる静的な情報の列挙ではなく、時間というパラメータに対する介入のバリエーションと言える。
この「スタイル」という概念は、現代を生きる私たちすべての生を捉え直す上でも有用なものだ。デジタルプラットフォームに包囲され、アルゴリズムによって最適化されたコンテンツが際限なく供給される現代において、誰もが自身の可処分時間をどう消費するかという命題に向き合わざるを得ない。こうした状況において、VTuberをコンテンツの「送り手」、視聴者を「受け手」とする従来のモデルでは見落とされてしまうものがある。デジタルプラットフォームの立場からすれば、「送り手」も「受け手」も等しく「ユーザー」であり、情報資源を生み出す「エネルギー源」にすぎないのだ。
こうした一元論的な世界観から脱する手立てを、「スタイル」という概念は与えてくれるだろう。たとえば「朝活」をやっているVTuberの配信だったら、受け手の側もセロトニンの分泌が活性化された状態で視聴するから、深夜に視聴する配信とは受け取り方が変わってくるといったことが起きる。そこでコンテンツの性質を決めるのは、朝に配信をするVTuber自身でもあり、早起きしてその配信を視聴する脳の持ち主=視聴者でもある。
ある特定の「スタイル」がコンテンツとして成立する背景には、VTuberと視聴者の生活習慣の交差がある。その交差は確かにYouTubeというデジタルプラットフォーム上で実現しているものだが、同時にそれは画面の手前にあるそれぞれの生へと折り返され、生そのものを新たに駆動し直すリズムともなるのだ。
なお、「キャラクター」と「スタイル」は対立する概念ではなく、相互補完的なものであるということは付記しておきたい。たとえば、2024年8月16日に活動を開始した七瀬すず菜は、デビュー日の翌朝以来、ほぼ毎朝決まった時間に「朝活」を行っているというVTuberだが、その「キャラクター」としてのプロフィールは「カフェレストランの朝担当の従業員」というものである。ここまで両者がシンクロしている例はVTuber全体を見渡しても珍しいが、たとえシンクロ度合いが低かったとしても、その「噛み合っていなさ」具合が個性として視聴者に認識されていくはずだ。
主体的な生のデザインに向けて
改めてまとめよう。VTuberとは、高度に情報化された現代の多重レイヤー的な現実感における、新たな主体性のモデルである。
一方でVTuberとは狭義には、あくまでYouTubeというプラットフォームの画面上において、専用のソフトウェアを使ってデジタルレイヤーを操作し、仮想空間を設計することに長けた職業人にすぎない。
私たちは彼ら彼女らを真似してVTuberになってもいいし、もちろんVTuberになどならなくてもいい。ただし、VTuberという存在の根幹に関わる「レイヤーの合成」という論点を意識することが、私たちの生を再設計する契機にもなることは、知っておいて損はない。
VTuberという存在を前にして自覚するべきは、私たち自身もまた、「レイヤーの合成」によって生をデザインし直すことができるということだ。自らの生を構成する諸要素をレイヤーとして認識し、空間と時間の再設計を図っていくこと。その絶えざる選択こそが、自分にしかない生を形作っていくのである。
※本稿は、2023年に刊行された同人誌『青春ヘラver.7「VTuber新時代」』に寄稿した論考「〈レイヤー合成〉による新たな主体性の創出――〈バーチャルライバー〉原論のために」を元に改稿を加えたものです。
