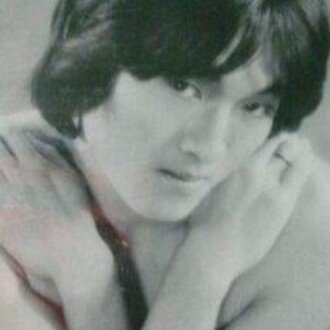東京ブレンバスター15 LGBTQとフェミニズムとGAY 性を選ぶのは誰か
そもそもgenderとは
いわゆるLGBT運動と現代フェミニズムは、左翼リベラル界隈の二大潮流になりつつある。現にこの二つの勢力は、夫婦別姓、同性婚推進において共闘関係にあるようだ。
しかし、両者は根本的な部分で相容れぬ者同士であり、共闘が進むほどにその矛盾が明らかになるはずだ。今回はそんな話からしてみたい。
LGBT運動のおかげか、最近はジェンダーという言葉が一般にも浸透してきた印象がある。しかし、その使い方はかなり拡大的で、本来の意味とは少し違ってきている。
そもそもgenderとは「後天的・社会的に作られた性差」を指し、sex=「先天的・肉体的な性差」の対義語として、80年代ごろからさかんにフェミニスト界隈で使われ出した言葉である。もう少しわかりやすくいえば、「男の体は全体的にゴツく髭があり声は低い」「女の体は全体的にまろく乳房があり声は高い」という身体的特徴に見る性差がsexであり、一方、「男性(女性)はこうあるべき」という社会通念によってつくられた性差をgenderと定義づけている。男女の給料格差や職業区分に始まって、極端な例では「男の子は黒いランドセル、男の子は赤いランドセル」という決まりや「おじいさんは山に芝刈りに、おばあさんは川に選択に」というお伽話のフレーズさえ、ジェンダーによる男女の「らしさ」や「役割分担」の強制であると認識されるのである。フェミニストの唱える「ジェンダーフリー」とは、そういった社会通念上の性差からの解放を意味する。
したがってフェミニストにとってのgenderは克服すべきものであって、genderによってsexが抑圧されてならないとし、genderという言葉自体はネガティヴな文脈で語られることがほとんどである。
ライオンの昼寝
「女性(あるいは男性)だから」という理由で、社会的不利益を受けるようなことはあってはならないのは当然だが、一方、「性差」をsexとgenderに分け、対立概念的にすべてを語るのも性急というものであろう。そもそも両者はきれいに分かれるものなのだろうか。
たとえば、人が石槍をもってマンモスを追いかけていた時代、狩りは体力的体格的にそれに適していた男の仕事だった。女は授乳などの関係から、外敵からの攻撃を避けるためにも洞穴での生活が長くなったわけである。いわば、sexによる役割分担である。これを基準として、何千年何百年かけて現在のgenderが形成されたとみるのが自然ではないか。ちなみに、ライオンのオスのあの優美なたてがみは、狩りをするのにははなはだ不向きで、ライオンの群では狩りはもっぱらメスの仕事であり、オスはその間、のんびりと昼寝を楽しんでいることが多いそうだ。これをgenderによる役割分担の強制とはいわないだろう。
半ば固定化させた職業区分であっても、文明や技術の進化がそれを解消するケースも多々あるもので、その意味で平等化は進んでいる。戦国時代の築城作業で、重い石垣の運搬を担うのは当然、男でなくてはいけなかった。しかし、ユンボやクレーンな重機が発達した現代の建築現場は、必ずしも体力が絶対的なものではなく、それら工作機械の操縦技術によるところが大きい。これならば、女性でも充分活躍することは可能だ。近い将来、工事現場で檄を飛ばす女性現場監督の存在も珍しいものでなくなるだろうし、その日のくるのを歓迎したい。
おそらく、現代において、女性が付けない職業というものはほとんどないはずだ。よろこばしいことである。しかし、それと「らしさ」の否定は別次元の話だと思う。
それぞれの「性」の定義
以上、僕なりにフェミニズムの説くジェンダーフリー論についての疑問を述べてみた。
さて、LGBTである。もはや説明する必要もないと思うが、L=レズビアン、G=ゲイ、B=バイセクシャル、T=トランスジェンダーといった性的マイノリティーの総称だ。
トランスジェンダーというのは「生まれた時に割り当てられた性別にとらわれない性別のあり方を持つ人」(大阪市HP「LGBTをご存じですか」より)のことで、簡単にいうと、「体は男だが、心は女」「体は女だが、心は男」という、アレである。近年になってクローズアップされてきた概念であり、最近ではこれにQを加えてLGBTQなんて言い方もあるようだ。Q=クエスチョニングで「自分の性が男女どちらかにあるのかわからない」人を指すのだという。
本稿で特に問題にしたいのはLGBTのうちのTである。T=トランスジェンダーは「性自認」と和訳されることも多い。T活動家は「生物学的な性が男性であろうと、自分が女性だと思えば、社会は女性として受け入れるべきである」という持論を展開する。LGBT運動を主導する中心勢力は、実はTであり、彼らがLGBT運動を過激、急進的なものにしている。ありていにいえば、政治運動化である。
LGBT思想とフェミニズムとの連携は政治運動としてのものであるが、フェミニズムの根幹にある、sex(生まれながらの性)とgender(社会の固定概念によってモデル化された性)との対立構造に、LGBT(というかT)が主張する「自認する性」がどう絡んでくるのか、それによって生じる混乱にフェミニスト側は、おそらくまだ回答を用意できていないのではないか。
そして「自認する性」は、本来sex(肉体的な性)が優先されるべき領域であるスポーツの世界にも越境しようとしている。女子の大会への自認女子の参加だ。
現在、当たり前になりつつある通勤時の女性専用車両の導入に少なからずのフェミニストの尽力があっただろう。その女性車両に女装した中年男性が乗り込んできたら彼女たちはどう思うのか。今、女装と書いたが、女装の有無は性自認とは無関係だという主張も当然出てくるだろう。「あくまで通勤着として背広とネクタイを着用しているのであって、心が女であることは変わりない」と言われればそれまでだ。通勤時だけパートタイムの自認女性も認めなければ差別、という主張も起きてくるのではないか。そうなれば、女性専用車両の意味もなくなってくる。
LGBT思想とフェミニズムがいずれ衝突するといった根拠はそこにある。
QはTよりももっと問題をふくんでいる。幼少期から思春期にかけて、自分の肉体に違和感をもったり、同性の友達に疑似恋愛的な感情をもったりすることはよくあることで、多くは、長じれば自然と異性愛に向かうものだ。つまり、誰でもQの時期があるのである。
アメリカでは、過激なLGBT活動家が教育現場に入り込み、不安定な少年期の心に付け込んで性転換手術を受けるよう誘導するという事例が多々あるという。アビゲイル・シュライアー著『トランスジェンダーになりたがる少女たち』にそのことが詳しい。
活動家が少年少女の性を決定する、もはや性自認ですらない、“性他認”ではないか。子供たちは活動家の自己満足のための実験動物ではないのだ。

トランプのYMCA
トランプ大統領は大統領選において、「性別は2つしかない」とし、「女子スポーツから男性を締め出す」と公言していた。早晩、それは実現されるだろう。案の定一部からはこの発言を差別だという声もあったようだが、これは性志向であるLGBとT(性自認)を意図的にゴッチャにさせた主張である。わが国の心あるゲイ複数からもLGBとTを明確に分けるべきだという意見を聞いている。
トランプは決して同性愛差別者ではない。先の大統領選でヴィレッジ・ピープルの『YMCA』をイメージソングに使用したことは、ゲイ有権者への彼なりのアピールだと思っている。「YMCAに行けば楽しい仲間が待っている」というあの曲の歌詞を額面どおり解釈したのは日本の某歌手だけだろう。
性は2つしかない。男と女が愛し合うか、男と男(女と女)が愛し合うだけの問題だ。

(初出)『表現者クライテリオン』2025年1月号

いいなと思ったら応援しよう!