
小説『水蜜桃の涙』
「最終章 春の日の誓い」
この章の登場人物:
成沢清之助・・・・・高等師範学校の最終学年に通う都会育ちの青年
石田 律・・・・・・清之助の同級生・石田英二の従妹で、女子高等師範学校の学生
桜井 たえ・・・・・石田律の同志で、東京の私立高等女学校の教師
輝子・・・・・・・・悲劇の中心にいる女性
桃子・・・・・・・・清之助の娘
清太郎・・・・・・・清之助の息子
昭和五年。
まだ少し風が冷たい中、春の日差しは縁側を柔らかく照らしておりほんのり暖かい休日を親子でゆっくりすごしていた。もうすぐ桃の節句である。
我が家の娘・桃子も十歳になる。母親が毎年「これは女の子の成長を祝う日だから」と必ずひな人形を座敷に飾り、やや奮発した料理を拵えてくれる。
今年は僕の休みの日に合わせて早めのお祝いのご馳走づくりをしてくれたのだ。
息子の清太郎は七歳だがまだまだ甘えん坊なのか、縁側に座る僕の背中に寄りかかって本を読んでくれとせがんでくる。
「お父様、今年は節句のご馳走がちょっぴり寂しいみたい。お母様がごめんなさいって」
桃子が食卓に飾るはずの花桃の枝を持ってこちらへやってきた。まだ早い時期なのだろう、蕾しかつけていない。
「残念だけど仕方ないね。去年米国で恐慌が起こって、我が国でも不況が始まったんだ。困っている人たちがたくさんいるから、我が家だけ贅沢はできないんだよ。お母様の手伝いはもういいのかい?父さんは片付けと掃除はすっかり終わったよ」
すると輝子が前掛けをはずしながら台所から出てきて、
「もうほとんどお食事の用意は出来上がったわ。あらあら、桃子ったら桃の枝はちゃんと花瓶にさしてあげてちょうだいね。うーん、桃の花はまだ早かったわね。でも好きだわ、桃の花」
輝子は桃子の差し出した花桃の枝を受け取ると、まだ蕾なのにうっとりとした表情で鼻に近づけている。そして僕の隣に座り、ほっと一息ついたようだ。
職業婦人と言われる薬剤師として働く輝子は仕事も子育ても手抜かりなどなく、こうやって休みの日も疲れを見せず子どもたちのために家事をやってくれるけど、僕も手伝いをするのだから少しは休んでほしいと思う。
彼女はここまで本当に頑張ったのだから。
「桃ってね、気立てがいい女子のことを意味しているそうだよ。だからお前に“桃子”って名付けたんだ」
僕が娘に言うと、
「あのね、昔イザナギノミコトが黄泉の国へイザナミノミコトを追いかけて行って、恐ろしい姿のイザナミから逃げる途中、イザナギを追いかけてきた鬼に桃を投げつけて退散させたんだってさ。だから桃は“天下無敵”とも言われているんだよ」
割って入ってきたのは清太郎だ。喧嘩ではまだ負ける姉を揶揄しているのか、ニヤニヤしている。
小学校に上がってから最近は学ぶのが楽しいようで、学校で教えてもらったことを家族にもよく披露するのが好きだ。桃子は顔をゆがめ、輝子は「うふふ」と声を出して笑っている。
輝子の美しい横顔を眺めながら、何年経っても麗しさは変わらず未だにどきりとする時がある。
暖かくやわらかな日和に、家族でくつろぐこの瞬間を大事な記憶にしておきたい。
こんなに穏やかな日々が輝子と僕に訪れることを、あの頃は考えもしなかった。
輝子を東京へと連れて帰り、桜井さんと律さんが一緒に付いて病院へ輝子の体を診てもらいに行った。
幸い特別な病気は隠れていなかったようで、みな一安心した。
しかし心の問題が残っていた。ずっと輝子は話せないままでいたのだ。
しばらく入院して体をまず静養させ、その後とあるお寺の僧侶が開いている施設に移ってもらった。
そこで勉強もできるらしいし、他の年下の引き取られた子どもたちの勉強も逆に教えられるらしい。
そのうち高等教育も受けられる体制をつくっていくそうだ。
ゆっくりと東京での療養生活に慣れていくに従い、輝子の表情も次第に柔らかくなっていった頃、思い切って桜井さんが紙に吐き出したい思いを書けるだけ書いてみてほしいと輝子に告げた。すると最初はなかなか筆を取らなかった輝子だったが、律さんとも少しずつ交流を重ねていき親密になっていったところで、そろそろ気を許してくれるようになったのか、当時の思いを書き始めたのだった。
それは律さんとの交換日記という形で、彼女の秘めた思いを書き出していったものだった。
そこにはとても悲しいいきさつが書かれており、間違いを犯してしまった宗一郎君の苦悩も僕たちは知ることとなったのだった。
「おにいちゃんは本当はとても優しくて、私のことをいつも守ってくれていました。村の中でもとても優秀だったから、私に勉強を教えてくれたこともありました。あの時は…書生さんのことで少しの誤解があって、それに旦那様とは普段からあまりうまくいってないって聞いたこともあったし」
『それでもあなたに無理やりひどいことをしたのは許せないことでは?』
「確かにおにいちゃんがいつものおにいちゃんではなかったから、とてもびっくりしたしがっかりもしました。怖くてもう昔みたいには戻れないのかなと希望が持てませんでした」
『それはとても残念なことね。でももう輝子さんの気持ちの中では大丈夫なことになったの?』
「お腹の子を駄目にしたあの日は、おにいちゃんは旦那様とかなり言い合いをして、おまけに旦那様からひどい暴力を受けて顔も心も傷つけられてしまって、実は泣きながら私をひっぱたいたのがわかりました。ああ、おにいちゃんも多分悩んで心がかなり乱れていて、どうにもできなくてああするしかなかったのかな、って。私が黙っていればよかったのに、旦那様にきつく尋ねられておにいちゃんのことをしゃべってしまったから、私がいけなかったんです」
『許してあげるの?』
「いいえ、私にしたことはやっぱり許すことはできないと思います。でも私もだけど、おにいちゃんも恐らく心を傷つけられたのじゃないでしょうか。許せないけど可哀そうだなとは思います」
『そうね。宗一郎君も伊ケ谷氏もそれなりに責任は感じておられるみたいで、村のお寺に水子供養をされたと成沢さんの教授から聞いたわ』
「そうですか…」
『もうそろそろ、しゃべることはできそう?』
「おにいちゃんにひっぱたかれた時、ずっと口をつぐんでいろ、って言われてもうしゃべれないと思いました」
『なんてことなの。そんなことを言われていたなんて!苦しかったわね。辛かったわね』
このやりとりの内容を輝子には申し訳ないが大まかに聞いた僕は、何やら僕と輝子のことを宗一郎君が勘違いしていたふしがあったようで、この事件の発端の一因になってしまっていたことを知り、遅まきながら非常に申し訳なく重大な責任を負っているのだと頭の中が白くなってしまった。
輝子と会ったのはあの早朝の時一回だけだったから、もしかしたら同じ時に宗一郎君が出くわしていたのかと考えると、胃のあたりがぎゅうっと痛くなった。
「律さん、僕にもすこしばかり責任があるようだ。一度輝子と会えないものだろうか。会って謝罪をしたい」
話を聞いたからにはどうにも落ち着かなく、まだ静養中の輝子に面会できるかを尋ねてみたのだった。
「輝子さんはきっと成沢さんのことは恨みも何も抱いてないと思うわよ。でも成沢さんの気持ちを軽くしたいというだけで謝罪するというのは何か違うと思うわ」
律さんもやはり容赦ない。すっかり見透かされている。しかし言われてみて、たぶんそうなのかもしれないと反省をした。
輝子と合わせる顔がないと思いつつ、悪く思われたくないという気持ちがどこか隠れているのなら言葉や表情に出てしまうかもしれない。
確かに勘違いの一件は宗一郎君の勝手だったのだから、僕が変に謝罪することでは全くないのだ。
やはり輝子の中に僕という存在がどのくらい占めているのかを確かめに行きたいだけなのだろう。
それでもいい。もう一度彼女にただただ会いたい。
「そうだね。僕の独りよがりな気持ちだった。ただ、それを抜きにして輝子ともう一度会って話をしたい。ああ、まだ会話が無理だというのもわかっているが、それでも会いたいんだ。こんな僕だけど心配してもいるし、彼女の体も心も労わってあげたいという気持ちは正直なものなんだ」
話す僕を見て、律さんは何か確信したような笑みを浮かべた。
「わかりました。では輝子さんにお尋ねしてみます。彼女が会ってもいいということでしたら、施設の庭で会えるかもしれませんので日時をご連絡します。…会えるといいですね」
ん?なんだ、最後の律さんの不敵な笑みは。
でもよかった。ぜひ、輝子が同意してくれればいいなと願う。
そして僕の願いは神様が聞き入れてくれたのか、輝子も会いたいという返事をしてくれたと律さんから連絡をもらい、嬉しくて約束の日まで妙に浮足立ってしまった。教鞭をとっている中学校の授業も身に入らないほどであった。授業中に思い出してつい笑みを浮かべてしまう僕を見て、学生が指摘するくらいだから始末に置けない。馬鹿な僕だ。気を引き締めろ。
そしてその日が来た。彼女が静養している施設へと向かった。どこか現実離れをしているような気持ちがした。
しかしその庭に入ると、律さんとともに椅子に座る輝子を目にとめ、彼女は確かにここにいるのだと心が高揚した。
「やあ、久しぶりだね。僕を覚えているよね?成沢清之助です。体調はもうすっかり良くなったのかな?」
近づいての第一声だった。輝子はとても穏やかな表情をしていた。
そして、“うん”と首を縦に振った。
律さんは「ゆっくり二人で話していてください」と席を外して施設の中に入っていった。
「よかった。元気を取り戻してくれたのなら安心だ。本当に辛かったね。とても、とても心配していたんだよ」
と、話していくほどに感情が高まり不覚にも涙を流してしまった。
すると輝子は手を伸ばして、僕の頬の涙を拭いてくれるのだ。彼女はどこまでも優しい。
はっとした僕は、「すまない」と言って反対を向いてから手拭いで顔を拭いた。
「そうだ。お見舞いに今日は水蜜桃を持ってきたんだよ。大好きだっただろう?」
そう言って紙袋から水蜜桃を彼女に差し出して見せた。
すると輝子は破顔し、水蜜桃を手にするとその香りを嗅いでいる。
良かった。彼女が笑ってくれた。この美しい笑顔を見られただけで満足だし僕も嬉しいのだ。
そしてしばらくして、今日のもう一つの目的を思い出した。
彼女に伝えなければならないことがあるが、彼女の笑顔が消えるかもしれないのを考えると気落ちしてしまう。
しかし意を決して話し始めた。
「言葉はね、ゆっくりと取り戻していけばいいよ。実は今日は村からの知らせを持ってきたのだけど、話しても大丈夫かな?もし嫌な気持ちになるのなら、今度にするよ。先日師範学校の時の教授から教えてもらったのだけど」
彼女の表情を窺いながら尋ねてみると、少し引き締まった顔になってうんうんと首を縦に振ってくれたので、大丈夫だという返答と確信して思い切って話し始めた。
「君の所にも実家から手紙が来ていると思うが、ご家族は全く問題なく暮らしておられるそうだから心配しなくていいようだね。あれから伊ケ谷氏からまた小作を許されているらしい。それからね、宗一郎君のことだけど」
ここまで言うと輝子の顔がやはりふっと曇った。どういう感情が今彼女の心の中に渦巻いているのかは知る由もなかったが、それでも言っておくべきことがある。
「彼は当分の間中学校へ戻って勉強を続けていたそうだが、あまり勉学に身が入らなくなってしまったらしい。成績も落ちていって、自分でもどうしようもなかったのだろうね。やはり君への罪悪感が拭えなくて相当苦しんだらしいんだ。それでだね、彼なりに決断をしたみたいで、仏門に入ったらしいよ。地元ではなくて県を超えたずいぶん離れた山奥にあるお寺らしい。伊ケ谷氏には手紙で知らせてきたそうで、煩悩を捨てるために自分を律したいということだそうだ」
すると輝子は目に涙を浮かべ嗚咽した。
その涙はどんどんあふれていき、肩をゆすって泣き出したから僕は驚いて思わず彼女を抱きしめてしまった。
「大丈夫!大丈夫だよ。彼が考えに考えて出した結論だ。君のためにも宗一郎君自身のためにもそうすることが一番の罪滅ぼしになると考えたのだと思う。傷つけてしまった君を彼はこのままでは癒すことなど無理だと思ったのだろう。過去を見つめなおして、自分をずっと厳しく自制するための判断なのだから君が案ずることはないんだ。彼が厳しい修行を成せるよう僕たちも彼のために祈ろう」
「か…かわ、か…」
輝子が泣きながら言葉を発した。
「え!?何?なんて言いたいの?」
「か…かわい、そう」
そうか。宗一郎君のことを思ってでた言葉だった。久しぶりの彼女の言葉。
「わ…私は、おにいちゃんに‥」
「ゆっくり、ゆっくりでいいんだよ。無理しなくていい。気持ちはきっと彼にも届いていると思う」
僕は彼女の複雑で切ない思いを理解しぎゅっと抱きしめた。
「大丈夫だから。君のことは僕がこれからずっと守っていくから」
あの時のことは今思い出すと本心だったのにも関わらず、すぐその後律さんが外に出てきて僕たちのことを目の当たりにしていたのを知り、いつも少し恥ずかしくなるのだった。
輝子は少しずつ元気を取り戻し、施設で勉強に励み僕が予想した通り、彼女は才覚をめきめきと現し始め高等女学校からその後新設された女子大学にまで進学したのだった。
その間僕は事あるごとに彼女に手紙を書き、体調はもちろん現況を尋ねた。
女子高等師範学校を卒業し女子中学校の教師となった律さんと女学校でますます教師の実力を発揮している桜井さんは、女性解放を論じて有名になった平塚らいてうを崇拝してやまず、輝子をぜひ職業婦人として世に出したいと言い放った。
僕も輝子の才能を埋もれさせるのは勿体ないことだと賛成した。
「でもね、桜井さんと律さんには言っておかなければならないことがあるんだ。実は輝子と僕は結婚するんだ」
「ええ~~!?」と驚きの声を上げたのは何も知らなかった桜井さんだ。
「やっぱりね。そういうことだとはとっくの昔に感じていましたけどね」とは律さん。
「では輝子さんには家のことだけをさせるおつもりなの?」
桜井さんはやや厳しい目で僕を見つめた。そんなことなら結婚は許さないとでも言いだす勢いだ。
「彼女にはやりたい仕事を思う存分してもらうつもりですよ。病院で世話になった御恩もあるといって医療系の仕事ができればいいと希望しているようですね。結婚しても仕事をしていくのはお互い様です。僕は案外進歩的な考えを持つ男なんですよ。時間が余っている方が、掃除や料理をすると彼女と約束したのだから」
僕は先進的なご婦人方を前にして少し胸を張って見せたが、まだあまり信用されていないようで、
「時々、様子を見に行かせてもらいますからね。家事だけではありませんよ。もし子どもが生まれたら子育ての細々したこともやらないといけませんよ!」
ああ~~、小姑たちにくぎを刺されてしまったが、輝子を妻にするということはそういうことだと、気が引き締まる思いだった。僕が三十歳、輝子二十二歳の年であった。
輝子は初め僕の求婚をなかなか受け入れようとはしなかった。
自分はすでに傷つけられた人間だと卑下しているようだったが、そんなことは関係ない。初めて会った時のままの美しく聡明で、僕にとってはこれ以上ない女性だと告げた。
彼女は驚いたようだったが、すぐに真っ赤になって恥ずかしそうにしていた。
それでも数日は返事を待ってくれと頼まれ、その間僕は生きた心地がしなかったのだ。そうして…。
縁側で陽の光を浴びながら並んで座る僕らを、いつの間にか離れたところから子どもたちがくすくすと笑いながら見守っていた。
僕はそれをわざと知らないふりをしていた。僕の肩に頭を預け、この暖かい日差しを体中で受け止めようと子どものように両手を伸ばしている輝子の肩を優しく抱いていた。
彼女には絶対に悲しい涙を流させまい、辛い思いなど決してさせないと改めて誓う春の日だった。
終わり
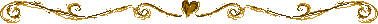
最後までこの小説を読んでくださった皆様、どうもありがとうございました。
このお話をどうにか最終章まで持ってくることができてうれしいです。
初めて書かせていただいた小説を大団円に近い形で持っていきたかったので、どうにか完結でき書き手の自分が一番ホッとしているところです。
ここを訪れて読んでくださり、スキまでくださった方々によってここまで引っ張ってもらえたのかなと思います。
見えないお力添えによって自分なりに山をひとつ越えることができたのだと確信しています。感謝しかありません。
今後果たして再び筆を取るかは今のところ全くわかりません。
今回の出来栄えも素人の域を出ていないのは百も承知です。
もしかしたらすごく稚拙な文章で笑われているかもしれませんが、今の私の精一杯です。
またたくさん本を読んで知識を得たいと思います。
ありがとうございました。
