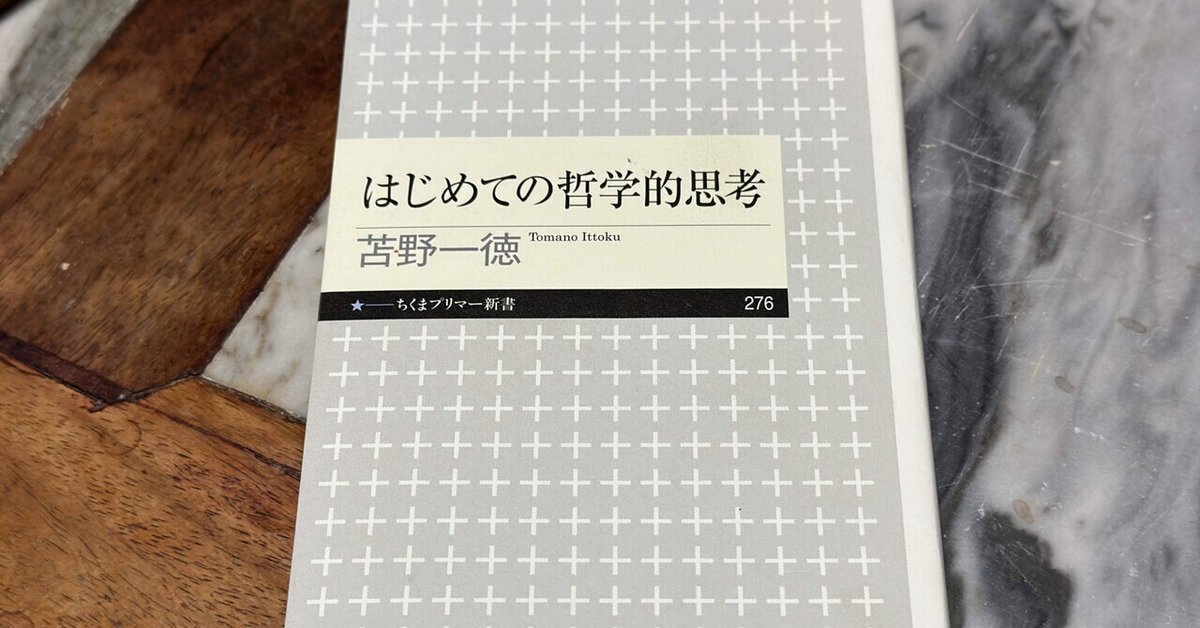
哲学は答えのない問いを考えるだけじゃない——苫野一徳さんの「共通了解志向型対話」とは
よく、哲学は答えのない問題をただぐるぐる考えているだけだといわれることがある。でもそれはまったくの誤りだ。すぐれた哲学者たちは、前の時代の哲学者たちの思考を受け継ぎ、そしてそれを確実に推し進め深めてきたのだ。
答えのない問題を考えることこそが哲学だ、ともよくいわれる。でもそれもやっぱり誤りだ。少なくとも、それは哲学の半分しかいい当てていない。
残り半分の、もっと大事な哲学の本質がある。
それは、その問題をとことん考え、そしてちゃんと"答え抜く"ことだ。
何度もいうように、それは決して絶対の正解なんかじゃない。でも、それでもなお、哲学は、できるだけだれもが納得できるような"共通了解"を見出そうと探求をつづけてきたのだ。
読んでいて痛快な本である。科学主義や自然主義が優勢なこの世の中、ソクラテスやニーチェを云々する哲学は古めかしく、分かりにくく、さらには「役に立たない」ものだと思われている。苫野さんはそれに真っ向から反対する。哲学は役に立つものだ!と。
苫野一徳(とまの いっとく、1980 - )さんは、日本の哲学者、教育学者。熊本大学大学院教育学研究科・教育学部准教授。博士(教育学)。著書に『子どもの頃から哲学者』(大和書房)、『「自由」はいかに可能か―社会構想のための哲学』(NHKブックス)などがある。哲学対話の一つである「超ディベート(共通了解志向型対話)」の推進者でもある。
苫野さんは、哲学とは何かという問いにひと言で答えるなら、それはさまざまな物事の「本質」をとらえる営みだという。現代は「相対主義」の時代である。世界には絶対に正しいことなんてなく、人それぞれの見方があるだけだという考えが、広く行き渡っている時代である。たしかに「絶対の真理」、つまり誰から見ても絶対に正しいことというのはない(分からない)。しかし、誰もが納得できる「本質的な考え方」にたどり着くことはできる。つまり、本質を捉えること、「本質観取」こそが哲学であり、哲学対話なのだという。
この世界には「事実の世界」と「意味の世界」がある。科学が明らかにするのは「事実の世界」である。それに対して哲学が探求するのは「真」「善」「美」といった人間的な「意味の世界」の本質である。「"良い"って何だろう」「"美しい"って何だろう」「人生いかに生きるべきか」。そうした意味や価値の本質こそ、哲学が解き明かすべき問いである。そして哲学が探求する「意味の世界」は「事実の世界」に原理的に先立つ。なぜなら、「事実」は私たちの「意味の世界」のアンテナにひっかからないかぎり、「事実」として認識されないからである。ニーチェが「まさしく事実なるものはなく、あるのは解釈のみ」(『権力への意志』)と言ったように、私たちの「意味の世界」に照らし出されたかぎりにおいてしか、「事実の世界」を知ることはできない。
例えば私たちが教育を考えるとき、「学力」とは何かという基本的な事実においてさえ、意見が異なることがある。つまりそこでは「事実」の相対主義が起きており、それは私たちが異なる「意味の世界」に生きているからである。ここでも哲学の出番である。「意味の世界」の「本質」を探求する哲学は、教育学などの社会科学の土台にもなるものである。
それでは、私たちはどのようにすれば、それぞれの人が異なる意見を持つ中で、共通了解が可能な「本質」にたどり着くことができるのだろうか。それが苫野さんの提唱する「超ディベート(共通了解志向型対話)」である。そこでは、まずそれぞれの人の「確信」や「信念」が異なるときに、それがなぜ起きるのかを理解する必要がある。私たちの「信念」とは実は「欲望」の別名なのである。私たちは世界を、私たちの「欲望」や「関心」に応じて認識している。これは、現象学の系譜、ニーチェ、フッサール、ハイデガー、竹田青嗣らが考えていたことである。このことを「欲望相関性の原理」という。したがって、信念対立が起きているとき、それはそれぞれの人の「欲望」や「関心」が異なるがゆえに、世界が異なって認識されているため、と考えることができる。その「欲望・関心」にまでさかのぼって、共通関心を探っていき、共通了解としての「本質」にたどり着こうというものが「共通了解志向型対話」である。
そのさらに具体的な方法については、是非、苫野さんの書籍を確認してほしい。本書『はじめての哲学的思考』や、『教育の力』(講談社現代新書)、『勉強するのは何のため?―僕らの「答え」のつくり方』(日本評論社)などに書かれている。
