
【連載】エピグラフ旅日記 第2回|藤本なほ子
「エピグラフ」とはなんぞや? ──書物をひらいたとき、扉ページの裏側やタイトルの左下などにそっと添えられている短かな(ときに長々とした)引用句。そう、アレです。〈……以下、続きはこちらの冒頭のご挨拶文をご覧ください。〉
ただいま創元社では、山本貴光さんを編著者にお迎えし、『エピグラフの本』(仮題)を制作中です(2023年2月刊行予定)。古今東西のさまざまな「作品」のエピグラフを集め、読者のみなさんと一緒にながめて愉しむ──ありそうでなかったそんな本を、ゆっくり、じっくり、みっしりと編んでおります。
出版に先行し、ウェブ連載を開始いたします。毎月15日は山本さんにエピグラフについて縦横無尽に綴っていただく「異界をつなぐエピグラフ」。末日はエピグラフ採集係の藤本なほ子による「エピグラフ旅日記」です。まずはこれらの連載にて、限りなく広がるエピグラフの宇宙のお散歩をどうぞお愉しみいただけますように。
エピグラフ旅日記(8月)
8月某日(2)のつづき
──連載第1回では、自宅からいちばん近い駅前の市民図書館で、本格的にエピグラフを探しはじめた。「まずは文学の個人全集をしらみつぶしに見てみよう」という方針で、閲覧室のいちばん端の棚、つまり日本十進分類表のおしりの990番台「その他の諸文学」、980番台「ロシア文学」の棚から確認を始め、『ドストエーフスキイ全集』(★1)の月報に惹きこまれて、早速手をとめてしまったのだった──
この図書館に所蔵されている『ドストエーフスキイ全集』では、月報はステープラー(いわゆるホッチキス)で綴じられ、表紙をひらいた最初の見開き(表見返し)に糊づけされている。つまり本全体の冒頭に置かれ、短い評論、個人的なエピソード、刊行の裏話などが綴られていて、本がつくられた当時の社会への「扉」となっている。……そう考えると、エピグラフの「きょうだい」か「いとこ」のようなものにも思えてきて、愛しさもひとしおである。(「エピグラフ =扉」説については、山本貴光さんの連載「異界をつなぐエピグラフ」第2回を参照されたい)
『ドストエーフスキイ全集』では、第2巻の月報の堀田善衛「『白夜』について」(連載第1回参照)のほかにも、幾つかの月報に読み入ってしまう。とくに第4巻『死の家の記録 ネートチカ・ネズヴァーノヴァ』月報の石原吉郎「強制された日常から」で滞留。このエッセイで石原は、冒頭にV・E・フランクル『夜と霧』(★2)の末尾の「強制収容所から解放された直後の囚人の混迷と困惑を描写した」部分を引用し、自らのシベリア抑留とそこからの帰還の経験を重ねあわせながら、次のように書いている。
……人がうしなった言葉を回復してゆく過程は、言葉を喪失して行く過程にもまして苦痛である。それはしばしば揺れもどしに似た失語状態をともないながら、あるいは性急に、あるいは緩慢に、一つの表現となって凝縮して行く。私にとってはそれが、詩を取りもどして行く過程でもあった。
(★3)
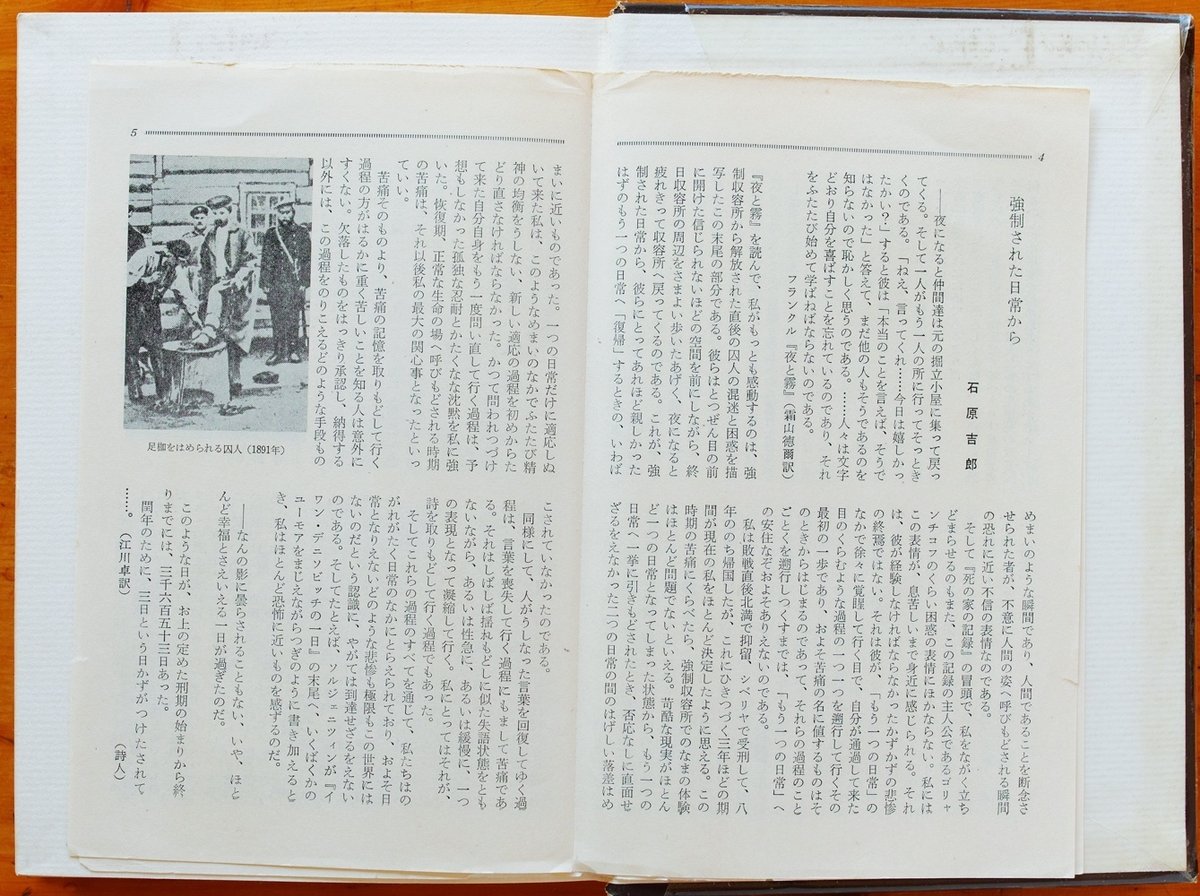
この文章には胸を刺され、しばし放心してしまった。
机に積んでいた本を両手で抱え、書棚に戻しに行く。『ドストエーフスキイ全集』の隣には同じ河出書房新社の『トルストイ全集』(★4)が並んでいる。『ドストエーフスキイ全集』(米川正夫訳)は焦げ茶色、『トルストイ全集』(中村白葉・中村融訳)はえんじ色に近い赤。前者は1969〜1971年、後者は1972〜1978年の刊行だが、いずれもそれ以前に刊行された同訳者による全集に日記、書簡、研究ノートなどを付し、「愛蔵決定版」として編み直されたもの。

ドストエフスキーもトルストイも、エピグラフを置いた作品はかなり多い。いずれも聖書からの引用が目立つのだけれど、そのニュアンスはだいぶ異なる。ドストエフスキーのものはどこか不気味で、「本文では人間の暗部や苦しみのようなものが描写されるのではないか……」と予感させられる。一方トルストイの場合、聖書からのエピグラフの多くは、「戒めの言葉」として文字どおりに受け取ってよいのだろう、と思える。エピグラフの機能のしかたとしてはトルストイのほうがわかりやすいと言えようか。
たとえば以下は、ドストエフスキー『悪霊』の巻頭に置かれたエピグラフ。
どうあがいても わだちは見えぬ、
道踏み迷うたぞ なんとしょう?
悪霊(おに)めに憑かれて 荒野のなかを、
堂々めぐりする羽目か。
………………………………
あまたの悪霊めは どこへといそぐ、
なんとて悲しく歌うたう?
かまどの神の葬いか、
それとも魔女の嫁入りか?
──A・ブーシキン
そこなる山べに、おびただしき豚の群れ、飼われありしかば、悪霊ども、その豚に入ることを許せと願えり。イエス許したもう。悪霊ども、人より出でて豚に入りたれば、その群れ、崖より湖に駆けくだりて溺る。牧者ども、起りしことを見るや、逃げ行きて町にも村にも告げたり。人びと、起りしことを見んとて、出でてイエスのもとに来たり、悪霊の離れし人の、衣服をつけ、心もたしかにて、イエスの足もとに坐しおるを見て懼(おそ)れあえり。悪霊に憑かれたる人の癒えしさまを見し者、これを彼らに告げたり。
──ルカ福音書、第八章三二−三六節
(★6)


そして以下はトルストイ『クロイツェル・ソナタ』のエピグラフ。
『されど我なんじらに告げむ、およそ婦(おんな)を見て色情を起す者は、心の中すでに姦淫したるなり。』
──マタイ伝第五章二十八節
『弟子イエスにいいけるは、もし人妻においてかくの如くば娶らざるにしかず。イエス彼等にいいけるは、この言(ことば)は人みな受納るること能わず。ただ賦(さず)けられたる者のみこれをなし得べし。』
──マタイ伝第十九章十、十一節
(★8)
2つめのエピグラフは新約聖書「マタイによる福音書」からの引用で、イエスが弟子たちに離縁について語っているくだり。この前の節でイエスが、「夫と妻は一体であり、離縁してはならない。もし、夫が妻を離縁して他の女性を妻とするのならば、それは姦通の罪である」と述べたのに対し、弟子が「もし夫婦の関係がそのようなものであるのなら、妻を迎えないほうがましです」と答えた。するとイエスは「この(私の)言葉を受け入れることができるのは、恵みを与えられた者だけである」と言った…という場面である。(★9)

『クロイツェル・ソナタ』の「あとがき」でトルストイは、「恋愛およびそれに伴う肉的関係」は「人間にとって恥ずべき動物的状態」であり、「恋愛の対象との結合によって達しられるものは一つもない」として、「姦淫」のみならず性愛そのものを強く否定し、戒めている(★10)。冒頭のエピグラフとあとがきで、激しい情欲と嫉妬の末に妻を殺した男性の物語をサンドイッチしている格好である。
トルストイの作品には、聖書からの同じエピグラフを別の作品に用いている例もちらほら見える。たとえば上の『クロイツェル・ソナタ』の1つめのエピグラフは、戯曲『闇の力』(1886)にも置かれている。『闇の力』にはもう1つ別のエピグラフ(同じマタイ伝の次の節)が並べられていて、こちらも強力。
されどわれなんじらに告げる、およそ色情をもって婦を見る者は、心のうちですでに姦淫している者である。
もし右の目なんじを罪におとさば、抉(ぬ)き出してそれを捨てよ、五体の一つを失うのは、全身を地獄におとされるよりはましだからである。
──マタイ伝第五章第二十八節、二十九節
(★11)
ドストエフスキー、トルストイの全集をひととおり見終えた。欠けている巻の作品を文庫本で確認し、文庫版の『チェーホフ全集』(★12)をいちおうすべてめくる。恐らくチェーホフの作品にはエピグラフは皆無。
エピグラフ旅日記(9月)
9月某日(1)
今日も駅前の、ショッピングモール上階の図書館へ。個人全集を探して、棚に並んだ背表紙を左から右へ順に見ていく。
『トーベ・ヤンソン・コレクション』全8巻(★13)。「ムーミン」シリーズが有名な著者の、「ムーミン」以外の作品を集めた叢書。エピグラフは第6巻『太陽の街』に1つ見つかったのみ。
何冊か置いた隣に同じトーベ・ヤンソンの単行本『島暮らしの記録』(★14)を見つけ、つい手にとってしまう。50歳を過ぎたヤンソンが、親友の芸術家トゥーティとともに、クルーヴハルという小さな島(というより「岩の床」のような岩礁)に小屋を建て、住みはじめる日々の記録。トゥーティとは、この本の挿絵を描いているトゥーリッキ・ピエティラのこと。
私は長い間この本を偏愛していて、3冊か4冊、買っては人にあげ、また買っては人にあげているうちに入手できなくなり、図書館で借りて全ページコピーしたものを手元に置いていた。何年か前に、敬愛するデザイナーとものづくり作家のお二人が東京から小さな離島に引っ越された時は、ヤンソンとトゥーティの「ものをつくりながら島に住む」姿がどうしても重なって思われて、もう1部コピーをつくって送りつけてしまった。
改めてひらいて見ると、扉の裏、つまり多くの書物でエピグラフが置かれる場所に、数字の並んだ紙片の画像が印刷されている。これは……言葉で書かれたものではないが、「もの言わぬエピグラフ」と捉えてもよいのではないか……?

この画像については、巻末、訳者の冨原眞弓さんによる「島暮らしをめぐる断章」の冒頭に記されていた。
原著のタイトルページを繰ると、茶色に古ぼけた紙片が眼にとびこんでくる。セロテープをはがした痕跡、半端な数字の羅列、「BF M/S」と手書きの注記。島暮らしには欠かせないビューフォート風力階級表だ(本書四頁参照)。海の天気はあてにならない。風の向きも強さも刻一刻と変わる。大陸の影も見えない岩礁群では、小さなボートが唯一の交通手段である。数キロ離れた本島の雑貨店に飲み水や燃料を買いだしにいくのも、自分のボートだけが頼りだ。したがって島では風向きや風力がひどく気になる。十九世紀にビューフォート海軍少将が定めた区分によると、秒速〇・三メートル未満の「静穏」から三十二・七メートル以上の「颶風(ぐふう)」にいたるまで、風の強さは十三段階に分かれる。この風力階級がよほど気に入っているのか、トーベ・ヤンソンは他の作品でもさりげなく言及する。
(★16)
これを読み、そうか、「風」もこの本の重要な登場人物であった、と改めて思う。巻頭に置かれ、島の暮らしを左右する「風」の存在と作者の思い入れを暗示しているわけで、やはりこの「ビューフォート風力階級表」の画像も、少なくとも「エピグラフ的なもの」とは言えるのではないか。
左側のページをめくると、本文が始まる。いつ、何度読んでも、心の中へゆっくり落ちてゆき、落ちすがらにととのえていってくれるような書き出し。
わたしは石を愛する。海にまっすぐなだれこむ断崖、登れそうにない岩山、ポケットの中の小石。いくつもの石を地中から剝ぎとってはえいやと放りなげ、大きすぎる丸石は岩場を転がし、海にまっすぐ落とす。石が轟音とともに消えたあとに、硫黄の酸っぱい臭いが漂う。
築くための石、またはたんに美しい石を探す。モザイク細工、砦、テラス、支柱、煙突、もっぱら構築するのが目的の壮大かつ非実用的な構築物のために。秋には海がさらってしまう桟橋を築く。それならといっそう工夫を凝らして築いた桟橋も、やはり海は根こそぎさらっていく。……
(★17)
閉館時刻が近づく中、『ゲーテ全集』(★18)をできるところまで確認して、今日は終了。
★冒頭画像
トーベ・ヤンソン『島暮らしの記録』(トゥーリッキ・ピエティラ画、冨原眞弓訳、筑摩書房、1999)p.6-7
★1 『ドストエーフスキイ全集』全20巻・別巻1(米川正夫訳、河出書房新社、1969-1971)
★2 V・E・フランクル『夜と霧 ドイツ強制収容所の体験記録』(霜山徳爾訳、みすず書房、初版1956、新装版1985) 石原が引用している箇所はp.198
★3 『ドストエーフスキイ全集4 死の家の記録 ネートチカ・ネズヴァーノヴァ』(米川正夫訳、河出書房新社、1970)付属の月報p.5
★4 『トルストイ全集』全19巻・別巻1(中村白葉・中村融訳、河出書房新社、1972-1978)
★5 (左)『ドストエーフスキイ全集1 貧しき人々 分身・プロハルチン氏・他』(米川正夫訳、河出書房新社、初版1969 写真は平成元年5月発行の18版) (右)『トルストイ全集1 幼年・少年・青年』(中村白葉訳、河出書房新社、初版1973 写真は平成元年4月発行の7版)
★6 ドストエフスキー『悪霊(上)』(江川卓訳、新潮文庫、1971)p.5,6
★7 ドストエフスキー『悪霊(上)』(米川正夫訳、岩波文庫、1989)
★8 トルストイ『クロイツェル・ソナタ』(米川正夫訳、岩波文庫、1928)p.4
★9 新約聖書「マタイによる福音書」第19章3節〜12節より。以下の日本語訳を参照した。
『聖書』聖書協会新共同訳、口語訳(下記URLの日本聖書協会ウェブサイトにて閲覧)
https://www.bible.or.jp/read/vers_search/titlechapter.html
『聖書 原文校訂による口語訳』フランシスコ会聖書研究所訳注(サン パウロ発行、2013年)
★10 トルストイ『クロイツェル・ソナタ』(米川正夫訳、岩波文庫、1928)p.151, 155
★11 『トルストイ全集12 戯曲集』(中村白葉訳、河出書房新社、1973)p.6 扉ページに掲げられたタイトルは『闇の力(五幕) あるいは「爪が一本かかっても、小鳥の命はおしまいだ」』。
★12 『チェーホフ全集』全12巻(松下裕訳、ちくま文庫、1993-1994)
★13 『トーベ・ヤンソン・コレクション』全8巻(冨原眞弓訳、筑摩書房、1995-1998)
★14 トーベ・ヤンソン『島暮らしの記録』(トゥーリッキ・ピエティラ画、冨原眞弓訳、筑摩書房、1999) なお、2022年2月24日現在は新刊で入手可能になっている。
★15 「フィンランド語」を「スウェーデン語」に修正しました。(2022年3月28日)
★16 『島暮らしの記録』p.147-148
★17 『島暮らしの記録』p.7
★18 『ゲーテ全集』全12巻(小牧健夫・大山定一・国松孝二・高橋義孝編、人文書院、1960-1962)
◎プロフィール
藤本なほ子(ふじもと なほこ)
美術作家、編集者。
美術の領域でことばに関する作品をつくっている。また、辞書や一般書籍の編集・執筆・校正に携わる。
ウェブサイト https://nafokof.net/
Facebook nahoko.fujimoto.9
Twitter @nafokof
