
Soft Rock Top 40位~36位
40位 The Al Baculis Singers「Poor Little Rich Girl」1967年

カナダ・ケベック州ラシーヌで1930年11月21日に出生したAl Baculis(本名:Joseph George Alphonse Allan)は、アルト・テナーサックス奏者・クラリネット奏者・作編曲家として活動してきたJazz系のマルチ・ミュージシャン。彼はケベック州モントリオールにあるMcGill Universityでクラリネットを 1948年~51年までの3年間学び、その後1952年~56年までの4年間は音楽に付随する概念・形式・ハーモニー・和声と対位法を用いた作曲など、包括的な音楽理論を研究。並行して1950年代にはジャズのクラリネット演奏者としてCBC Radioの放送やオールドジャズ・クインテット『Canadian All-Stars』にも参加。彼の演奏は高い評価を得て、5年連続でクラリネット奏者の最優秀賞を受賞。

1958年以降は作曲・ アレンジ・演奏を中心としてスタジオ・ワークに励みます。1963年にはソプラノ歌手のMargo MacKinnonと結婚。その2年後の1965年に男女混声のスタジオ・ヴォーカル・グループThe Al Baculis Singers【発音は「Back-You-Liss(バックを強調)】を結成し、1972年までの約7年間活動を続けます。メンバーは男女4人ずつの計8人のメンバーで、全員英語と仏語を話すバイリンガル(6名は仏語が母国語)。Alの妻Margoもソプラノで参加しており、Al御本人は作曲・アレンジなどの裏方のサポートに専念。初めはTVやRadio等の放送業界で仏語メインで演奏をしておりまして、結成1年後にほぼ全編英語で綴った記念すべき1st Albumをリリース。翌年には2枚のアルバムを発表して、計3枚のアルバムを世に残します。Al Baculisはグループ解散後もJazz界の演奏者・アレンジャー・作編曲家としてマルチに活躍していきます。
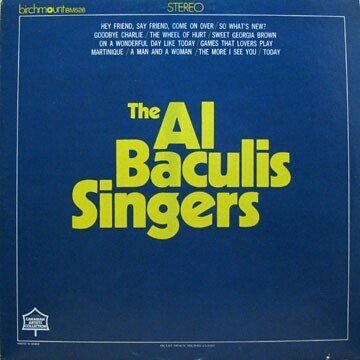
The Al Baculis Singersは、一見オーソドックスなJazz系コーラス・グループに思えますが、往年のJazzサウンドに新たな息吹をもたらした前衛的でエキセントリックなグループでもあります。その特徴たるや、Jazz系スタンダードに偏らないモダンな選曲・Margo MacKinnonによる妖精系の可愛らしいソプラノヴォーカル・ステレオ位相を巧みに駆使したアレンジ・緻密に計算された男女混声Chorus & Harmony・スウィング~ビバップ~アフロキューバン~モード系を取り入れた多様なサウンドメイク・Easy Listening系のJazz演奏…。
そしてその特色が最も顕著に表れたのが最高傑作と名高い2nd Album『Back To Baculis』。そこにはJazzサウンドにGroove感満点のラテン・ビートを取り込んだ彼ら最大の代表曲「Poor Little Rich Girl」が収録されております。この楽曲は、上記で挙げた特徴をたった1分50秒という短い尺に全てを詰め込んでおり、特にハモりとユニゾンの巧みな使い分けは驚愕レベル⇒脱帽&敬礼!!!
ちなみにこの『Back To Baculis』。The Mutual Understanding・The Luarie Bower Singers・The Sycamore Street Singers等、後の70年代前後に大量沸騰するCTL&CBC系大名盤の先駆け的な作品として位置付けられており、カナダ産Soft Rockの歴史を紐解く上で絶対欠かすことが出来ない歴史的価値ある大名盤でもあります。そういう意味で言うと、この「Poor Little Rich Girl」の功績たるや計り知れないものがあります。後世に多大なインパクトを残した大名曲…大事に聴きたいです。
39位 Dove「Gonna Leave This Town」1976年

江村幸紀氏監修のSoft Rock本に2nd Album『Love Harmony & Understanding』が掲載されたオーストラリア・ビクトリア州メルボルン出身の4人組Soft Rock系グループDove。平和の象徴である鳩(Dove)をグループ名にしておりますが、歌詞に宗教・政治や終戦を願う意味を込めた楽曲は無く、主にLove Songがメインになっており、耳馴染みの良い言葉の響きや語感に重きを置くスタイルを終始貫いております。
彼らは結成の1973年から解散する1976年末までの約4年間に、複数のレーベルからアルバム3枚、シングル11枚をリリースします。活動期間中の人員変更は無く、各メンバー名+担当演奏は下記の通り。

Sharyn Cambridge… (Guitar)・Vocals
Warwick Thomas…Bass・Vocals
Steve Gill…Drums・Percussion・Vocals
Jim Sifonios …Guitar・Keyboards・Vocals
※1st Albumだけ、Sharyn Cambridgeはヴォーカルのみ。

彼らが残した3枚のアルバムは何れも異なった魅力があり、カバー曲が多くClassicalなオージー・ポップスタイルの1st Album『Magic To Do(1974年作)』、オリジナル楽曲が増え飛躍的にSoft Rock度合いが高まった2nd Album『Love Harmony & Understanding(1975年作)』、一気に垢抜けたpreAOR的且つ鋭角的なサウンドを披露した最高傑作3rd Album『S.T.(1976年作)』。どの作品もキャッチーな胸キュン系メロディ・息の合った男女混成Chorus & Harmony・落たアレンジといったサウンド・メイクが施されています。混成コーラスに関しては、Eternity's Childrenや後期The Skyliners・The J. Silvia Singers・The Daltons・The Pleasure Fair・The Split Levelといったグループと同様の男性3名:女性1名という対比構成を取っており4声合唱効果による和声や音色、音域を駆使した広がりあるHarmonyを実現しております。
Doveが奏でるメロディ&演奏は総じてクオリティが高い上に、美メロが随所に散りばめられたハイレベルな楽曲が多いので、是非アルバムを入手して全楽曲をじっくりと聴き込んで頂いきたいのが本音ですが、手っ取り早く名曲を耳にしたいライト・リスナー向けに各アルバムのハイライト・ソングを紹介したいと思います。
★1st AlbumはA面3曲目に収録されたHawaiian Mellow「Country Girl」!!!
★2nd AlbumはKalapana風のSummer island系Soft Rock「Laughing Man」!!!
2nd Albumダイジェスト版↓
★3rd Albumは鬼甘系胸キュンポップ「Gonna Leave This Town」!!!
3rd Albumダイジェスト版↓
全アルバムを入手した方はLP未収のシングルと紅一点の女性シンガーSharyn CambridgeがThe Colin Who Band成るバンドをバックに吹き込んだ唯一の12inchシングルもGetしてみましょう!!
ちなみにシングルは計11枚(22曲)中、LP未収のシングルでしか聴けない楽曲は5曲のみ。枚数で言うとたったの4枚。個人的には1976年リリースされたGeorgie Fameのモッドジャズ・ナンバーを絶品カバーした『Gotta Get Away』を激しく推薦。年代やサックスが参加していることから3rd Album直前に制作されたかと思いますが、エネルギッシュな演奏とメンバー全員による濃厚Harmonyは特に素晴らしいです。特に1分10秒~の展開が激ヤバです。
38位 The Yin Yan「Bird Of Paradise」1977 年

「Except You」「Stranger To Love」「No One Can Love You The Way I Do」等のヒットで1960年代後半に台頭した香港のOldies系ポップ・グループ The Mod East。ファンのハートを鷲掴みにしたのは紛れもないSweetな歌声のリード・シンガーChris Sayers。正にグループの人気絶頂という時期に、彼は家庭の事情で1968年に豪州シドニーへ止む無く移住することに。現地では地道に働くつもりだった彼にとって香港を離れることは、グループの脱退だけでなく、華々しいショウビズ界からも離れることを意味していました。

丁度その頃シドニーでは、華系の血を引くポップ・グループBarbara & The Sweet Appleのシンガーが1人脱退して、新たなシンガーを探しておりました。そんなある日ベース・ プレイヤーPaul Youngは、新聞でThe Mod Eastのリード・シンガーChris Sayersがシドニ ーに移住するという記事をたまたま見つけ、すぐにChrisを探しに行きます。彼らがChrisの居所を探していた時、Chrisは既にシドニーに移り住み、就活を始め「Walton's」という小売店で社員として働き始めておりました。Chrisの居所を発見したThe Sweet Appleの面々は、早速彼にメンバー入りの話を持ち掛け、見事グループへの参加が決定。Chrisがメンバーに加わったことで、元々リード・シンガーであった後の妻になる看板娘Barbara Ann Fongとツイン・リードを取ることに。2人の息の合ったヴォーカルを売りに、その後3年間House PartyやClub Houseでのライブ演奏をして音楽活動を続けていました。


ある日、他のメンバーからHeavyなRockへと路線変更の訴えがありましたが、看板2人はEasy Listening系のポップ・ソングが自分達のSweetな歌声に合っていると主張し、最終的には方向性の不一致によりあえなく解散。残った ChrisとBarbaraはカップル・デュオとして再スタートを切ることを決断します。彼らは当時豪州で大人気だったダンスショーをメインとしたクラブに目を付け、彼らの住んでいたNew South Wales州だけでも2000を超えるミュージック・クラブが存在していた為、これは恰好のビジネス・チャンスだと考え、早速売り込み活動に着手。そして1974年に豪州で最も名高い中国系のクラブ『The Mandarin Club』でデヴューを果たすことになります。彼らは中国の血筋を引くことを一目で分かるように、東洋の印象を残す名前にしたかったとのことで「The Yin Yan(陰陽) Duo」と名乗ることに。最初期のステージではイメージし易い様に派手な中国衣装を身に纏って歌い、そのパフォーマンスが観客を多い惹き付け、あっという間に大人気デュオに。

その後、活動の幅が徐々に広がり、カジノ・ショールームやトップホテルのキャバレー劇場、さらには海外遠征も果たすことになり、バンコク・マニラ・香港・日本の一流ホテル等、国際レベルのツアーも行いました。成功を収めたのは音楽活動だけでなく、プライベートでも彼らは1974年6月24日に正式に結婚をすることに。そして彼らの人気は留まる事を知らず、オーストラリア全土まで広がりを魅せ、1975年・1976年と2年連続で「The Variety Club Award」という賞を受賞。それを受けて制作されたのが1977年リリースの彼らの唯一作『Easy In Your Company』。
【亜モノSoft Rock究極の自主制作盤】とも称されるこのアルバムでは、Karen Carpenterを彷彿させる瑞々しい歌声のBararaと最強のSweet Voiceを持つChrisが、夫婦ならではの息の合ったコンビネーションで、交互にリードを分け合ったり、サビではユニゾンやハモりで歌い上げ、表現力豊かな歌唱を魅せてくれています。アルバム自体は当時のトレンドを意識したポップ・ソングから往年のヒット・ナンバー、それに加えて中国民謡から坂本九までバラエティに富んだ選曲構成になっており、全編通して柔らかで耳に優しい軽やかなポッ プ・チューンが目白押しな作風になっております。
そして今作最大のハイライトは、美メロが胸に響く究極のSoft Rockナンバー「Bird Of Paradise」。お落なBossaリズムに乗せた軽快なポップ・サウンドがとにかく爽快!!出だしで魅せるフルートの鳴りや歌い出しのChrisの極甘ヴォーカル、0:25から登場するKaren Carpenter風なBararaの瑞々しい歌声、中盤でのラララ・コーラス等々、1曲の中で何度も即死出来る出色の出来栄え。強力レコメン!!
37位 The Leon Haines Band「It Don't Really Matter」1980年

たった1年という非常に短い活動期間(1980年~1981年)に、シングル2枚(Leon Haines名義でもう1枚)のリリースと、捨て曲が一切無い完全無欠の傑作盤『I Wanna See You Now...』を残したオランダの伝説的バンド。当初のオランダ国内ではAir Supply、Diana Ross、Olivia Newton-John等のメジャー・アーティストが人気急上昇で猛威を振るっていた為、ほとんど相手にもされず、大した成績も収められずに即解散してしまいました。しかし、再評価の機運が高まる現代に、小ヒットしたデヴュー・シングル「I Wanna See You Now(1980年4月12日リリース)」と、解散の翌年に発表したリーダー格Leon Hainesによるソロ・シングル「For You To Remember(1982年11月17日リリース)」が欧州を中心に話題になっており、特に上記2曲がラジオで頻繁にプレイされているインドネシアでは今でも根強い人気を誇っています。本国日本においては、普遍的な美しいメロディが印象的な大名曲「I Wanna See You Now」以上に、圧倒的な完成度を誇るアルバムの方が高い注目を浴びていて、各所で「Modern Pop」「Groovy AOR」「Modern Soul」「BED」「Mellow Groove」等のカテゴライズをされ、主にAOR界隈から好評を得ております。
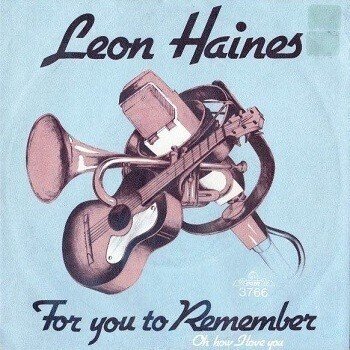
The Leon Haines Bandは、一度解散したオランダのModern PopバンドであるPartnerに、Rainbow(Ritchie Blackmoreのとは同名異バンド)のFloor Minnaart とLeon Haine、そしてThe WalkersのConny Petersが加わって結成されました。前身バンドPartnerは「爽やかさ」 「甘いメロディ」「メロー感」「重厚なコーラス」といったサウンドが特徴的でした。解散前夜に発表したラスト・アルバムでは本来の持ち味を生かせず、サウンド面で大きな衰退・陰りが見え、単調で凡庸なRockアルバムとなってしまい、竜頭蛇尾に解散。
しかし、メンバー・チェンジすることでバンド内に新しい息吹が吹き込み、弱体化したPartnerのウィーク・ポイントを見事にカバー&修正することが出来ました。新生Partner(The Leon Haines Band)に一役買ったのが、バンド名にもなったLeon Haines。彼はリード・ヴォーカル、ギター、そしてアルバム全曲の作曲までこなす、正にワンマン・バンドと呼べる活躍ぶり。特に素晴らしいのがメロディ・センス。全12曲中7曲で共作しているErwin MusperはPartnerの元メンバーであり、今作のプロデュース&エンジニアを担当しています。彼は今作では全て作詞担当ということで、アルバムに詰め込まれた美しいメロディ・ラインは全てLeon Hainesによるもの。彼の書く曲は人を虜にする甘美な魅力を放っており、鮮やかな創造性に満ちた作曲センスが楽曲の質を飛躍的に向上させています。サウンド自体はPartnerの延線上にありながらも、上記で挙げた特徴とLeon氏による上質なメロディが上手くブレンドされることで、唯一無二のMellow Popなサウンドが構築されております。

冒頭で述べた様に、唯一作『I Wanna See You Now...』は捨て曲が全く無い上に、様々な曲調の楽曲がバランス良く配分されていて、非常に聴き応えのある傑作盤です。その中でも特に激ヤバな1曲があり、それがA面3曲目に収録された「It Don't Really Matter」。Windmill(Partnerの改名前のグループ)~Partnerで追い求めてきたMellow Popサウンドの最終形態であり、彼らの魅力が全て詰まった究極の1 曲。Leon Hainesによる甘いGentle Voice、塩辛い渋みとは一切無縁の優美でキャッチーなメロディ、爽快且つ卓越したコーラス・ワーク、Mellowなハモンド・オルガン、間奏でのお洒落なサックス・ソロ、温かみのあるシロフォンの音色…全くの無駄も隙も無い3分37秒!!!正にマジカルな鬼名曲!!!
36位 Stämbandet Med Britt Johansson「Håll Igång」1975年

1946年5月5日にスウェーデン・ノルボッテン郡ネデルカリックス教区で生まれたBritt Johansson(後にMay-Britt "Maya" Wirbladhとして知られる)は、カーリクスの中心街のすぐ南にあるベルイェルスビンで育ち、幼い頃からフィンランド北部のクラブや音楽パブで女性シンガーとして歌い始めました。プロとして初めてのキャリアは1967年に結成された5人組グループ「Bäckmora Show/ Midnight Singers」の参加でした。1972年までに3枚のシングルをリリースし、同グループの活動と並行して、女性シンガーElisabeth Lordと男性4 人組を誘い1970年にStämbandetも結成(Bäckmora Showは後に自然消滅)。翌年にElisabeth Lordは脱退してしまい5ピ ースバンドに。彼らは西欧諸国を廻りながらツアー活動を続け、1975年には念願1st Album『S.T.』をリリース。

全曲オリジナルのこの意欲作は同年3月1週目にスウェーデン・ラジオ局の「Swedish LP of the Week」に選出され、これを受けて英国のレコード会社HHO傘下であるSatrilレーベルと直接契約を結べることに。「Stämbandet」はスウェーデン語で《声帯》を意味するグループ名でしたが、レコード会社からの提案で「Stardust」というグローバルな名前に改名。そして1977年には垢抜けたディスコ・サウンドを前面に打ち出した2nd Album『S.T.』をリリースし、英国の放送局BBCで当時人気番組だった生放送音楽番組『Top Of The Pops』にも出演。その後は1980年の解散までヨーロッパのナイトクラブ、 ディスコ、音楽パブ、大学内でのパーティー、ボールルーム等で演奏するクラブ・バンドとして活動します。2016年に再結成し、グループ名も「Stardust Revival」と名前を改めて3rd Albumを発表するも、翌年Britt Johanssonの他界をきっかけに正式に解散。

結局Britt Johanssonの音楽キャリアで最もSoft Rock度合いが高まった作品は、Stämbandet名義によるデヴュー作『S.T.』。正式名義が【Stämbandet Med Britt Johansson】となっているので、 ある程度察しは付くかと存じますが、アルバム全体の半数以上の楽曲でBritt嬢がリード・ ヴォーカルを担当。肝心のBritt嬢の歌声がKate Bushを彷彿させる歌唱スタイルということでSoft Rock系とは趣を異にするのですが、Stämbandetの男性陣によるChorus & Harmonyがとにかく濃厚でカッコ良く、Soft Rock度合いを格段に高めてくれています。加えて全曲オリジナルの楽曲群は英・米ポップスの影響下にありつつも、北欧の独特なメロディが絶妙にブレンドされている為、異国情緒な妙味を味わいたい方には御誂え向きな作品に仕上がっております。
アルバム最大のハイライトはA面4曲目に収録された「Håll Igång」。ハイ・テンションな高揚感・若々しい躍動感あるリズム隊・重厚感ある極上Harmony。どれをとっても一級品な素晴らしい逸品。
