
『コミュニティ』は構造。 『サードプレイス』は場所。
今日は自分でフットサルの企画と運営を始めて、約1年が過ぎたという事で『1年経って自分の中で生まれた感情』と『これから取り組んでいこうと考えている事』を書き残したいと思います。
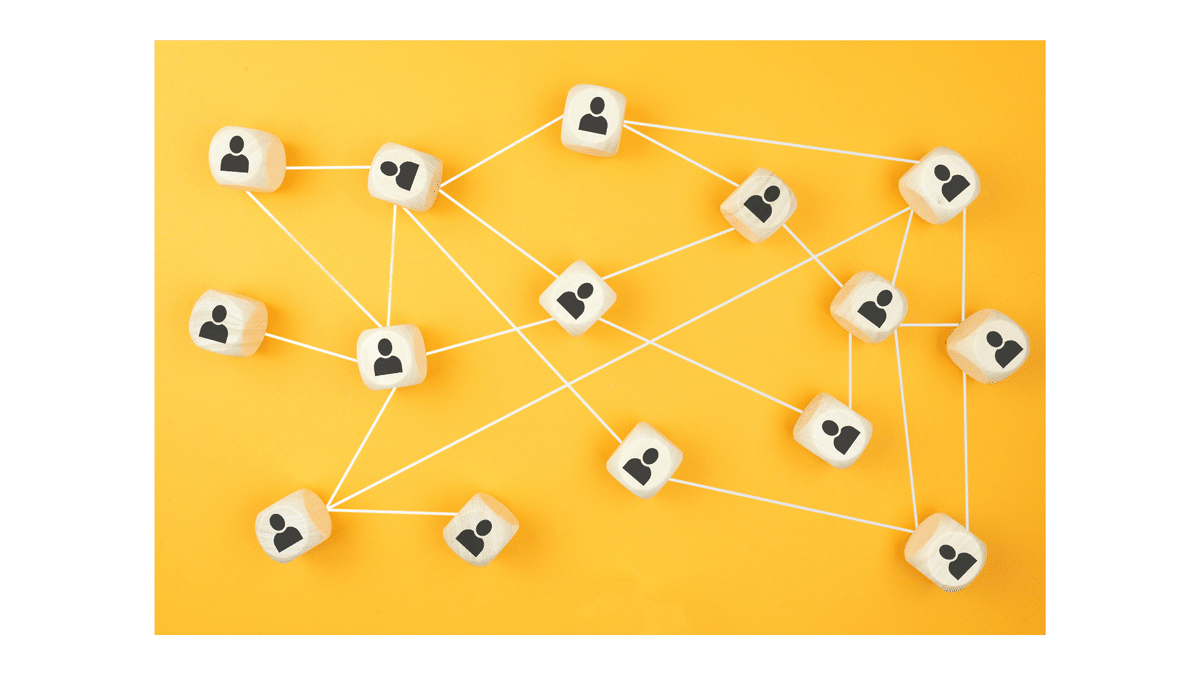
1、なぜフットサルの企画と運営をするのか?
私は、今から約1年前(23年の6月)にフットサルの自主企画と運営を始めました。
なぜ、わざわざフットサルの企画と運営を自分でやろうと思ったかと言うと理由は、大きく3つあります。
・1:気軽にフットサルが楽しめる場所が、地元に欲しかったから。
・2:フットサルを通じて色々な人と出会いたかったから。
・3:人から『感謝される事』を商いにしたかったから。
詳細を話すと、他が運営する『個サル』では毎回イマイチ楽しいと感じれずにいました。
身体を動かせる事は良いのですが、孤独というか、運動をして身体はスッキリするけど、心はリフレッシュした気にならないと感じる事が多かったのです。
知らない人と、同じチームになって時間が来たら会話も無く解散。
バイバイ。
何だかそれは寂しいなぁと。
そこで、この私が抱いた同様の感情を、同じく抱いている人が自分の他にもいるのではないかと思い、『フットサルの企画と運営を自分でやってみよう!』と決心し今に至ります。

2、実際にフットサルの企画と運営をしてみて。
最初は自分の学生時代の友達や、地元の仲間などに声をかけて始めました。
スタートは10名に満たない、7名から始まりました。
フットサルは5人対5人なので人数も足りない状態です。
それでも友人達は集まってくれ、和気あいあいとフットサルを楽しみました。
その後は、このフットサルを『ただ、フットサルをする場所』では無く、『人と人が交流する場、新しく出会う場』という趣旨を参加者が理解してくれ、友達がさらに友達を呼んでくれるようになりました。
参加者が少しづつ増えていき、気づけば約1年を過ぎた今、通常で15名前後はコンスタントに集まるようになり、多い時は20名以上集まる日も出てきました。
こうして、フットサルを始める前には、全く関わりが無かった方とも交流が生まれ、フットサルを通じて『人と人が交流する場所』が育っていきました。
皆さんの協力あっての事なので、現在の状況を大変嬉しく思っています。
そして今、私はこの良い流れをさらに加速したいと考えています。

3、これから取り組む『新たしい挑戦』について。
現状、今のフットサルは、『友達の友達』からなる『紹介制』で成り立っています。
全く知らない人が参加する事は無く、みんな誰かの『紹介』で参加して頂いています。
なので、フットサル中に個人が完全に孤独になる事は無く、そのため会話も生まれやすいと言うのが現状です。
しかし、ここにはいくつか課題もあります。
まず、属人的である事。
『OOさんが行くなら行く!』など、知り合いの参加を理由に参加を決める人も一定数います。
他には、友達の繋がりという事で、近い世代の人が集まる傾向もあります。
なので世代の幅に広がりが生まれづらく、世代間の交流が生まれずらいのも課題です。
あとは年齢を重ねると、怪我をしやすくなったり、怪我が治りづらくなる傾向もあり、長期離脱の人も出ているのも実態としてあるのも気に留めておかなければいけません。
今のフットサルの現状をまとめると、友達が友達を呼んでくれるお陰で、『紹介』で人が増えて、『和気あいあい』と皆で楽しくフットサルが出来ています。
一方で、『紹介』という『属人的』であるが故に、同じ世代の人が集まりがちで『全く新しい人との出会い』と『世代の交流』が今のフットサルには足りない部分である事が見えてきました。
そこで私は、次の挑戦として『全く新しい人との出会い』と『世代間の交流』を進めていきたいと考えました。
この1年で出会い繋がった同世代の仲間達との『コミュニティ』を大事にしながらも、次の挑戦として新しく『サードプレイス』を創りたいと思っています。

4、次は『サードプレイス』づくりへの挑戦。
『コミュニティ』と『サードプレイス』は似て非なるもの。
コミュニティとは?
定義
・共通の興味や価値観を持つ人々の集まり。
・地理的、オンライン、趣味など多様な形態で形成されます。
目的
・メンバー同士の相互作用、協力、支援、共同体の構築が主な目的。
特徴
・コミュニティは継続的に関わり合い、長期にわたって関係を構築。
・これは一時的な集まりとは異なる。
例
・趣味のグループ、町内会、自治体、村などの地域社会。
サードプレイス(Third Place)とは?
定義
・自宅(ファーストプレイス)や職場(セカンドプレイス)以外の、リラックスして人々と交流できる公共的な空間のこと。
目的
・交流や社交、アイデア交換の場を提供し、リラックスした環境での繋がりを育む場所。
特徴
・カジュアルで開かれた空間、アクセスが容易、長時間滞在できる、非公式な交流の場。
例
・カフェ、図書館、公園、バー、コミュニティセンター。
『コミュニティ』と『サードプレイス』の違い
構造 vs 場所
・コミュニティは人々の集まりや関係性に焦点を当てており、特定の場所に限らない一方で、サードプレイスは具体的な物理的空間です。
・つまり、コミュニティは構造、サードプレイスは場所。
目的
・コミュニティは継続的な協力や支援を目的としていますが、サードプレイスは特定の目的がなく、自由な交流を重視します。
・サードプレイスはコミュニティの一部になることが多く、特定のコミュニティがそこを集まりの場にすることもよくあります。
最初は、『コミュニティ』と『サードプレイス』の違いは、私もこんがらがる可能性が多いにありますが、自分もフットサルのメンバーも少しづつ慣れていけば良いのかなと思っています。
『コミュニティ』に参加してくれる人は、住民。
『サードプレイス』に遊びにきてくれる人は、旅行者、遊牧民。
今は、そんなイメージを持って進めていきたいと考えています。
追伸
私が今回『コミュニティ』の他に『サードプレイス』を作ろうと思った出来事がフットサルの他にもありました。
次回、この『サードプレイス』を作ろうと思ったキッカケについても日をみて書き残したいと思います。
