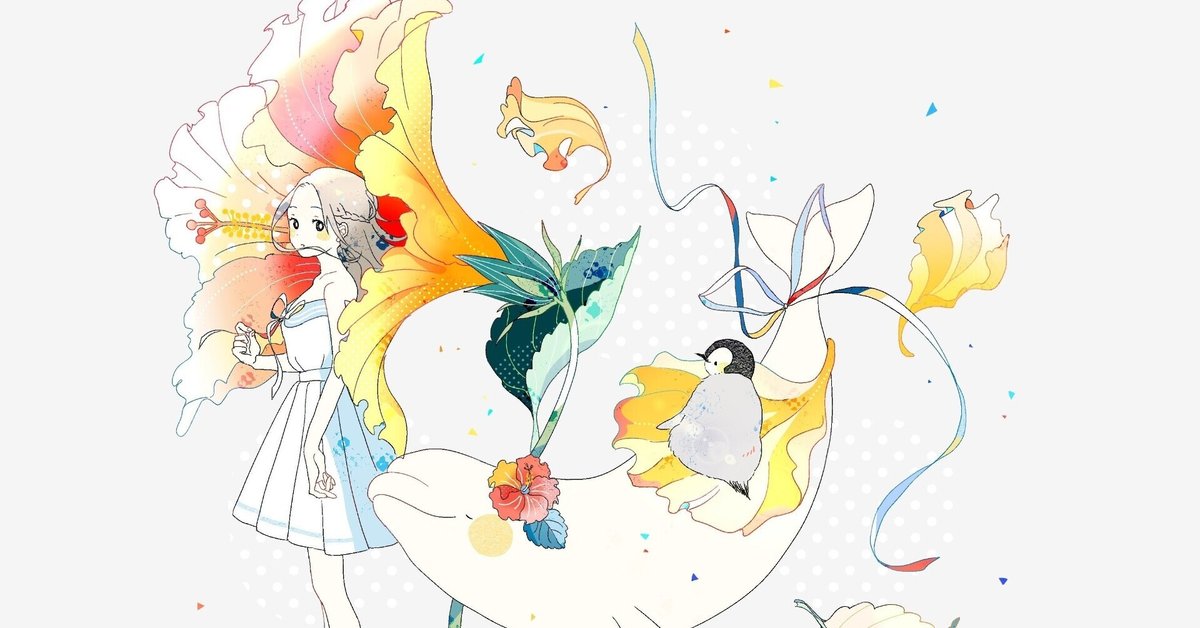
普段と違う人と話すことで生まれる未来。
こんばんは。社会起業家/中小企業診断士の浜俊壱(shun1.hama)です。
このnoteでは、
「社会起業家/中小企業診断士っていいですね。」
「どうやったら独立できるんですか?」
「どうやったら経営は上手くできるんですか?」
「何をどういう風に考えているんですか?」
と、よく聞かれることを
自分の人生の棚卸しや日々考えていることの言語化を通してお伝えしていきます。
ほぼ毎日noteを書き続けて、今日で768日目。3,000日チャレンジ達成まで残り2,232日。
今日から週始まりですね。7月に入り、早速台風が近づいてくる嵐の前の静けさのある一日でした。
はじめましての方はこちらもご覧ください↓↓
さて、本日のテーマは「普段と違う人と話すことで生まれる未来。」です。早速書いていきたいと思います。
社会課題の解決はちょっとしたキッカケから。
私が社会起業家という肩書を使い始めてからもうすぐで3年になります。
今でも社会起業家という呼び方が正しいのかどうかは定かではありませんが、「社会課題を持続可能な形で解決する」という主軸は変わらないため、このままオリジナルの言葉が出来上がるまで使っていきたいと思います。
さて、そんな中、社会課題の解決って言うと、大きなことのように感じるかもしれません。
ですが、その原点というのは至ってシンプルなんです。
なぜなら、自分の身の回りで起こっていること、自分が不便だな、とか苦労したな、とか思っていることが他の人も同じ様に思っている事が多い。
多くの人が思っている課題=社会課題。
社会課題はそこらへんに山盛り落ちているんです。きっと。
まず、自分の意見を持つこと。
社会課題の解決と念仏のように唱えていても、何も始まりません。
まずは、自分が何を問題として捉えているのか、ということを明確ではないにせよ意見を持っておくことが大事だと私は考えます。
例えば、出生率の低下ということは大きな社会問題ですが、家族を持ちたくても経済的や社会的理由で持つ事ができない経験が自分や身近な人に起きたとします。
そういう個別事象を解決していくことの延長線上に出生率の増加というインパクトがあるのであれば十分。
どうやって解決をしていったら良いかという解決策の方向性についても持論があると尚更良いと思います。
自分の周りだけでは話は広がりにくい。
一方で、持論を身近な人たちばかりに話をしていても、そこから広がることは限りがあることでしょう。
そうではなく、普段、あまり話をしないような場面に出ていき、いつもとは違うメンバーで話をすることをオススメします。
そうすると、違う視点での情報提供やアドバイスをもらえて、話が一気に進展していくことも大いに可能性があります。
まとめると、こんなステップです。
ーー
・まず、社会の課題に気づく。
・そのことについて持論を持つ。
・いつもとは違う人と話をする。
ーー
これで社会課題の発見〜解決のアイディアまで、つながる可能性が増えるはずです。
フラットに話ができる場作り
この流れにはもう一つポイントがあります。
いつもと違う人といっても、心理的な安全性が保たれ、それなりに見識のある人たちと話ができる環境というのはなかなか構築されていません。
特に、学生にとって、学校の枠を越えての交流というのは、ほとんど馴染みがないはずです。
そこで、私たちは立場に関係なくフラットに話ができるコミュニティスペースとして「IQOL=糸島九大生オープンラボ」という場所を九州大学のすぐ近くについ最近オープンさせました。
すでに、先日、学生と社会人の交流イベントで、ある女子大生が社会課題の解決プログラムを参加した社会人を含めて話をしたことでアイディアの種として生むことができました。
私もその場にいてブレストに参加していたのですが、けっこう筋が良いプランのように思えました。
こんな風に、社会課題の解決はちょっとしたキッカケから生まれていくんじゃないかなぁと考えています。
この場所が多くの学生の人生と社会を変えるキッカケになる場所としてこれから機能していくことを願っています。
・・ということで、今日はここまでです!
最後まで読んで下さりありがとうございました(^^)
明日も皆さんにとって、良い一日となりますように!!
まとめ
・社会課題を解決するには、まず、社会の課題に気づくこと。
・課題に対しての持論を持つこと。
・いつもとは違う人と話をすること。
・社会課題の解決はちょっとしたキッカケから生まれる。
<過去記事>
