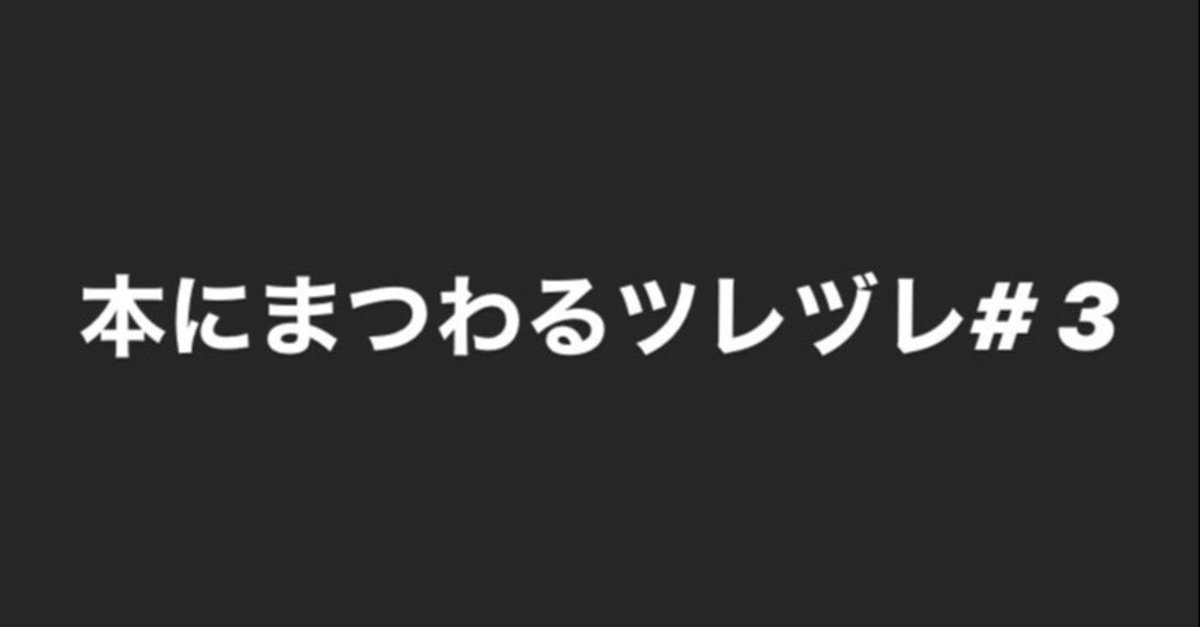
本にまつわるツレヅレ#3 川の流れと発見
どうもこんにちは。
No,No,Yes! 所作生産部の椿です。
(苗字がーーというのは そろそろしつこいでしょうのでやめにします)
この場では先々週から週1で個人的「本にまつわるツレヅレ」を綴ることにしました。
ひごろは主に生産管理やペイントをしています。今週は久々に携わる折りの工程で、スティングレーのカードケースに会いました。折っていて「目」が合う珍しい革であり、カットはスタッフMNにお願いしたのですが、、、制作側にとって(美しいものにはトゲがある的な)クセのある革でもあります。
それでは、#3
。
。
nakabayashi(オンラインショップ中の人)の「最近、家でごはん何作ってる?」という一言から、ほんま家族の食事を担うひとたちを尊敬するよね、なんて話した。
そんな折、手にとったのは
木皿泉+[絵]土橋とし子『二度寝で番茶』双葉文庫、2013年。
こちらの本は友人に薦めてもらった中の一冊である。当時も学生ながら(学生だったからか?)退屈しのぎを模索しており、放送作家を目指していると言った彼に「数冊紹介して」とメールしたのだった。
「木皿泉」の名前を見てまず思ったのは、左右対称だということ。縦書きにして真ん中でパタンと折りたたむと左右対称になる名前を見かけたり、はじめましての方がそうだったりすると密かに(かなり)萌えるのだ。勝手に「あと一字、惜しいなー」と悔しいこと多々あり。
それから、脚本家だと知るのは本を入手してのことになる。流しに食べた後の食器が突っこんである表紙写真が印象的。(余談だがその後 唯一観たテレビドラマは『昨夜のカレー、明日のパン』。私にとっても彼らの代表作。)
本作の対談部分にて
「大福『誰かが言っていましたが、ふだん我々の日常は川のように流れていて、その下に何があるかは見えないそうです。だから、時々、川をせき止めて下に何があるか確かめなければならない(中略) 何が出てくるのか怖いけれど、それを見つめることも必要だということでしょう (後略)』」
とある。お題(「手放したもの」)とは異なるが、普段見えないもの・見過ごしていることをあるタイミングで気づくことは、好機かもしれないととらえている。
不要不急の用事以外、外に出ることなき今日この頃 何かにつけてオンラインでポチッとする機会が増えたと思う。(もともとネット通販好きだけど、さらに増えた自分…) 個人的には運送業者の方にほぼ毎日お世話になっているし、生活を送ることはたくさんのひとたちによって成り立っていると改めて実感する。だから「俺たちもいまできること探して仕事につなげてがんばろうぜ」って冒頭の会話行間を読んだのだが、、、此方だけだったろうか。(えいえいおー)
もう一箇所抜き書き。
「かっぱ『(前略)自分にはない何かを持ってそうな人に惹きつけられる。』
大福『自分では言葉にできないでいる何かを体現してくれる人とかね。何かを発見させてほしいんですよ。新しい自分を発見させてくれそうな人にものすごく惹かれる。』」
回顧してみると、本を薦めてもらった友人に憧れがあった。文学部に所属していながらやりたいことが特に見つからず鬱鬱としていた身上からすると、目標をもって向かっている姿に、彼が読んだ本に、興味を持ったのだ。
結果的に私は文学的な道に進まずに、革製品に特化した会社に身を置いている。それでも 本を読むおもしろさに感謝している。もちろん友人にも。
。
。
。
それではまた次の日曜日に。
椿
