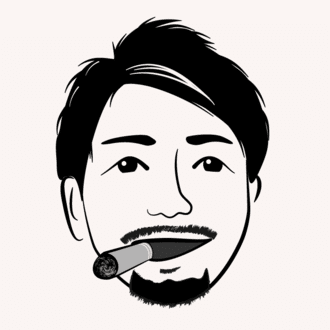2022/11/14週|スタートアップのマーケティング職の人事制度についてのメモ
今日は「スタートアップのマーケティング職の人事制度」について、考えていることをメモしておきます。自分は人事の専門家ではないのと、日々考えながらなので今後考えが変わる可能性はありますのであしからず。。(また、個人の考えですので所属と関係はございません。)
ここでの「人事制度」は下記の解説記事に倣い、下記の定義で用いていきます。
人事制度 = ①等級制度 + ②評価制度 + ③報酬制度
参考:
①等級制度:能力のレベルや職務内容に従って定められた「等級」に基づいて、従業員の社内での位置付けや給与を決定する制度のこと
②評価制度:従業員を“評価”するための制度
③報酬制度:給与・賞与などの報酬を決めるためのルール
スタートアップのマーケ職の評価制度はどうあるべきか?
まず、評価制度は上記の参考記事によると下記のような5つが代表例とのこと。
===
1.能力評価
判断力や統率力のように、仕事をする過程で発揮していた能力を評価の対象とする。定性的な評価となるため、曖昧なものになりやすい。
2.情意評価
積極性や法令順守(コンプライアンス)など、仕事の取り組み姿勢や勤務態度を評価の対象とする。能力と同様に曖昧な評価になりやすい。
3.成果評価(業績評価)
売上目標の達成度や生産個数のように仕事であげた実績(業績)を評価の対象とする。目標管理制度が用いられることが多い。
4.コンピテンシー(行動特性)評価
業績に結び付く行動を評価の対象とする。高業績者の職務行動を分析して評価基準が作成される。実際には能力・情意評価とほぼ同じもの。
5.バリュー評価
会社の経営理念の実践度などを評価対象とする。昇進者を選ぶときの参考情報とされることがある。導入している会社は少ない。
===
自分個人の意見としては、スタートアップのマーケティング職の評価制度は「能力(職能)評価」でするべきだろうと考えています。
と言うのは、ひとくちに「マーケティング」と言っても様々な領域が広がっており、非常に広範かつ高度なスキルセットを保有していることが求められるためです。
参考までに、2年前に書いた記事になってしまうのですが、アプリマーケターとして保有しておきたいスキルセットは一例として下記のようなものがあります。

適切な表現かの判断はできないのですが、どちらかというとエンジニアに近いような職種に分類されるのではと考えています。
ということで、自分としては「能力評価」が基本と思っているのですが、実際はこれまでの経験上、能力評価で運営されたことはありません。。
世の中では3の成果評価が主流ではないでしょうか。その文脈の中で「スキルセット(能力)面をアドオンで加味する(かも)」といった評価が多いような印象を持っています。
では、そういった成果評価に強く反対しているのか、と言われると、矛盾しているように聞こえるかもしれませんが、実はそうではない面もあります。
というのは実態としてマーケティングの仕事は事業の成果を左右するようなインパクトを出す活動であることも多いため、成果評価で運営したとしても運営は可能だからです。
ただやはり主従が逆転している感覚はありますので、徐々に「能力評価」に寄せていくべきかな、という意見です。
また、上の2の情意評価や5のバリュー評価は、行動規範(バリュー)の体現度という観点になるかと思います。これは組織総体としての強さを高める上では必須と考えています。
ということで、下記のような評価制度があるべきと考えています。
💡スタートアップのマーケティング職の評価制度 = 能力評価 + バリュー評価
マーケティング職の能力評価をするためには
仮に能力評価をしていこう、となったときに必要になりそうなことについてです。
まず、人事制度の一つ目の柱である「等級制度」において、等級ごとの定義をする必要があります。
能力で評価するからには必要な能力を言語化しておく必要があり、ここが設計上やや難易度高いところではないでしょうか。
抽象的な書き振りに終始するとよくわからなくなりますし、具体的なスキルセットで定義してしまうと、状況が変わりやすいスタートアップではその具体スキルが不要になったり優先度が下がったりすることは起き得ます。
自分が定義するのであればという仮定ですが、マーケティング職(の特にスペシャリスト)が行なっていることはあくまで「課題発見・定義〜解決の方針検討〜実行を専門性を武器に行なっていくこと、また同時に専門性を磨く努力をし続けること」が基本だと思いますので、その辺りを等級に応じて記載していくというところでしょうか。
この時に、ややもすれば各人の領域で閉じて「個別最適の追求」に倒れすぎてしまう傾向が世の中のマーケティング職のあるあるの一つと思っており、等級の定義もしくはバリュー評価の定義の中で調整しておくことが肝要かなと思います。
少し本題からずれますが、先々週の記事でも触れましたが、下記のように僕らの職種はあまり閉じるべきではなく、むしろ常に自分の仕事を俯瞰する癖をつけるのが望ましいです。
広告宣伝や販売促進は、あくまでプロダクトやサービスの一環であり、広告宣伝・販売促進に閉じた思考であってはならない。
制度より運用が大事
さて、能力評価でも、百歩譲って成果評価だとしても、制度はそれ自体を定めただけではまだその役割の半分も果たしていないと思います。
むしろその先の運用していくフェーズの方が数倍重要です。
運用フェーズで評価者と被評価者で具体的に見ていきたいポイントは下記のようなあたりでしょうか?
等級制度の定義のどこを目指すのかの目線合わせ
何がギャップなのかの目線合わせ
そこを何で満たしていけそうかのプランニング
定期的なモニタリングと修正
蛇足:成果評価での目標設定における留意点
自分は上述のように能力評価派なのですが、世の中の実際を鑑みると「成果評価」が多いと思います。
成果評価の場合も目標設計を行っていくと思うのですが、この時にチェックポイントになるであろうことを最後に記載して終わりたいと思います。
❶目標数値は前提、しかし重要レバーに紐づく設定になっているか?
成果評価の場合、目標を数値で定めることが多いと思います。この時そもそも数値を設定していないのは避けたいところです。また、どの指標を採用するのかにも気を遣うべきで、具体的には事業上重要な指標とどういうロジックで結びついているかを吟味した上でセットしましょう。
プロモーション領域の担当だと、例えば「CTR を xx%アップさせる」といった目標を敷いたりすることもあると思うのですが、CTRが xx%上がると事業の指標のどこに影響するのか?その影響の大きさはどの程度か?本当にそれが事業上のレバーなのか?
といった問いに耐えられることが望ましいと思います。
❷他の影響を受けて達成不可能にならないか?
特に割合の目標を設定する場合に気をつけたいのは、分母や分子が自分達の活動以外の要因によって大きく影響を受けないかのチェックはしたいところです。
完全にゼロにすることは難しいかと思うのですが、評価する上でも他の影響を大きく受ける目標の採用はお勧めしません。
❸HOW(手法)は変わるので握りすぎない
短い期間で目標設定をし直す(隔週とか月ごととか)のであれば心配ないのですが、Q単位以上で目標を設定するときは、手法に紐づく目標は立てない方が望ましいです。
例えば「aaという施策を来月末までに実施する」などです。これはaaという施策自体が変わっていくと言うこともありうるためです。
===
野村監督の名言に下記のようなものがあります。
四番に据えれば、四番らしい風格や自信がみなぎってプレーにも好影響を与える。ヤクルト時代の古田敦也が好例。
正直万人が納得する人事制度(等級制度・評価制度・報酬制度)は存在しないのかなと思います。
万能な制度はないけれど、個人としても会社としても向かう先を明確にしておくのは“運用でカバー” でなんとかできる部分があるし、マネジメントの役割を担っている者の責任だなぁと最近思っています。自分も学びながらより良くしていきたいです。
ではでは今週はこの辺りで。
📓この記事について
株式会社タイミーで執行役員CMOを務めている中川が、マーケティング関連の仕事をしている中で感じたことを綴り、コツコツと学びを積み重ねる『CMO ESSAY』というマガジンの記事の一つです。お時間あるときにご覧いただければ幸いです。オードリーのオールナイトニッポン 📻 で毎週フリートークしているのをリスペクトしている節があり、自分も週次更新をしています。
タイミーは、すぐに働けてすぐにお金がもらえるスキマバイトアプリです。
いいなと思ったら応援しよう!