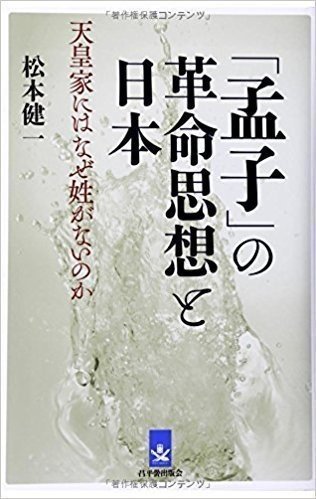『昭和天皇物語』は深読みすると止まらないマンガだった
マンガ『昭和天皇物語』(能條純一)が「緊急大増刷」らしい。2019年4月の天皇退位を前に、一種の"天皇ブーム"なのかもしれない。武田鉄矢が「ワイドナショー」で激推ししていたことで読んだ人も多いらしい。
なかなか「日本にとって天皇とは何か」なんて考えることも少ないので、そんなブームに便乗して、1巻を読んでみたら、とてつもなく面白かった。しかも、いろんなことにつながりそうだったので、noteで深読みしてみることにした。
◆ 昭和天皇とマッカーサー
本書のイントロは、日本が敗戦を迎え、昭和天皇がマッカーサーに出会う昭和20年9月27日から始まる。二人の第一回会見だ。
会見はマッカーサーの筋書き通り進み、その後、”ふたりだけ”の会見が行われる。ラフな世間話から始めるマッカーサーに対して、"ミスター・ヒロヒト"もそれに応じる。タバコを勧めるマッカーサー、丁重に断る天皇裕仁。笑顔の会話の裏にも緊張感が伝わってくる。
立ち上がり、天皇裕仁が力強く言う。
「私は日本の戦争遂行に伴う如何なることにも、また事件にも、全責任を負います」
これを聞いたマッカーサーは後に述懐したという。
「天皇裕仁はあの日”命乞い”の為、私を訪ねたのではなかった。かつて世界の歴史上にいたであろうか。自らの命と引き換えに、自国民を救おうとした国王が・・・!」
マッカーサーは彼の人生がどんなものであったか、どんな人生を贈ったのか、「私は知りたいと思った」と述べている。
読者もマッカーサーと同じように、この天皇物語に引き込まれるというイントロダクションだ。そして、物語は天皇裕仁が「迪宮(みちのみや)」と呼ばれた幼少時代から始まる。
ここでは、物語の展開で気になったことをいくつか探求してみたい。
◆ 乃木大将が贈った山鹿素行の『中朝事実』
冒頭では乃木希典が描かれている。日露戦争で激戦となった、あの203高地の乃木大将だ。天皇に忠義を尽くす姿に、明治天皇から学習院大学の10代目院長を任じられる。
しかし、1912年(明治45年)明治天皇は崩御する。それを受けて、乃木希典も自刃する。本書では、実はその直前に乃木は迪宮に謁見していたというシーンが描かれている。いつか天皇になるであろう迪宮に「日本と天皇のあるべき姿」を伝えたかったのだ。そこで、乃木希典から迪宮に贈られた本は山鹿素行の『中朝事実』という本だったそうだ。乃木大将は渡す時にこう言った。
「皇孫殿! 大切な箇所は私が朱入れしておきました。いずれご成長あそばされた時、もう一度お読みに!」
このあと、乃木大将は自刃することになる。では、なぜ『中朝事実』だったのだろうか? このことを理解するためには江戸の儒学を知る必要があるので、ここから探求してみる。
山鹿素行は江戸時代の儒学者である。徳川時代、儒教思想は重要な思想的基盤だった。中国の思想=儒学を土台として、徳川イデオロギーを確立しようとしていたからだ。幕府の権威はいった何に依拠しているのかを儒学者たちは模索していたのである。山本七平『現人神の創作者たち』によると、慕夏主義、水土論、中朝論という3つの考え方があったという。
慕夏主義は、中国の古代王朝「夏」を「慕う」主義である。日本の歴史や特色がどうだったかなどということと関係なく、夏王朝に代表されるような中国をモデルにすることを主軸とする。この慕夏主義のために、幕府は林家に儒教や儒学をマスターさせた。林家の任務は中国思想や中国体制を国家の普遍原理であることを強調することにあったのだ。
しかし、この考え方には無理があった。徳川幕府の体制の根幹は、"勝手に"家康が覇権を継承して武家諸法度や公家諸法度を決めたということにはなくて、天皇に征夷大将軍に"任ぜられた"ということを前提にしている。そこに”筋”があったからだ。
ここから慕夏主義はねじれていく。林家は「夏=中国」をルーツとした「天皇」の権威を理論付けようとした。(「天皇は中国人のルーツから分家した」というような主張)。こうして「慕夏主義=慕天皇主義」になるような定式が、幕府としては“見せかけ”でもいいから重要になっていった。林家の儒学はそれをまことしやかにするためのロジックになっていったのである。
続いて、水土論は、日本の水土(風土)には儒教儒学は適用しにくいのではないかというものである。熊沢蕃山が主唱した。これは儒学を重んじる幕府にとっては危険分子となっていった。
しかし、その頃、中国では明王朝が崩壊する。本家の中国にも「正統」がなくなったのだ。これでは「慕夏主義」は危うい。ここで登場したのが「中朝論」である。一言でいえば「日本こそが真の中国になればいいじゃないか」というものだ。もはや中国にモデルがないのなら、日本自身をモデルにすればよい。つまり「中華思想」(華夷思想)の軸を日本にしてしまえばいいという考え方である。
これはある種の拡張主義、帝国主義につながりうる。もともとは中華思想で中国中心に拡大していたものが、「日本」を中心としたら、日本が拡張していかなければならない。日本の歴史的発展が、かつての中華文化圏全体の本来の発展を促進するという考え方をつくらなければならなくなってくるのだ。これがのちのちの「八紘一宇」や「大東亜共栄圏」や「五族協和」の考え方のルーツになったという説もある。
詳しくは、松岡正剛の千夜千冊796夜を読んでほしい。
(このnoteでは、松岡正剛の千夜千冊をしばしば引用します)
ともかくも、この中朝論を好んでいたのが乃木希典だったのである。乃木希典を育てたのは、玉木文之進という男だった。玉木家と乃木家は親戚関係にある。それだけでなく玉木の一人息子が慶応元年に戦死したために、希典の弟の真人を養子にもらっていた。厳格きわまりなかった父・希次は、自分が教えることはだいたい叩きこんだので、あとの希典の教育を文之進に任せることにした。
この玉木文之進が山鹿流だったのである。だから乃木は、小さいころから山鹿素行の『中朝事実』や『武教本論』を刷りこまれていたことになる。
これについても、千夜千冊で述べられている。
「山鹿素行は『日本=中華』主義の中朝モデルを胸中に抱いていた。その素行の一冊は、乃木にとっては必殺の日本の“帝王・皇帝”が読むべき帝王学でもあった」
『昭和天皇物語』の1場面として描かれていた乃木希典から迪宮への『中朝事実』のプレゼントには、そういう背景があったのである。迪宮が『中朝事実』をどう読んだかは分からないが、このあとの物語の展開にもきっと関係してくるだろう。
◆ 杉浦重剛の帝王学と孟子
さて、続いて気になったのは、帝王学の御用掛を務めた杉浦重剛の話だ。裕仁親王のためにつくられた「東宮御学問所」の御用掛に選ばれた杉浦は、「倫理・帝王学」を進講(講義)することになる。そのなかで、こんなエピソードがある。杉浦は、「天皇にとって何より大事なのは仁愛・・・天皇ご自身が自らを犠牲にしてでも国民を大切に」ということを裕仁親王に伝えようとする。
しかし、御学問所の総裁・東郷平八郎は大いに反対する。なぜなら天皇は「一ありて二なく、常ありて変なき」存在であるため、天皇が臣民に仕えるような「仁愛」をもつなど言語道断だったからである。
この東郷の主張に対して杉浦は反対する。
東郷「杉浦さん!! あなたの進講はまるで逆だ!! 天皇が臣民に仕えるような教えではないか!!」
杉浦「東郷元帥、あなたは『覇道』と『王道』の違いをご存知か・・・? 『覇道』は武力による統治、『王道』は仁による統治。日本の天皇はこの『王道』を征(ゆ)かねばならなぬ。高徳の君主は王道の必須。」
これは、孟子の思想である。この「王道」をいってほしいというのが杉浦重剛のご進講だった。
孟子思想では、王の道には王道と覇道があり、前者をこそ理想とした。『論語』は「仁」を説き、それを徳目として中庸を生きることを奨める。右に走らず左に寄らず、上に阿(おもね)ず、下を蔑まないようにする。
これを補うのが『孟子』である。上の者(君)が「仁」をもつなら、下の者(臣)は「義」で報いるべきだとした。孟子はこれを「仁義」というふうに重合した。この孔孟(こうもう)の両方で民が治まり、君が仁政を実施できる。古代儒学はこういうふうになっている。それが君主のとるべき「王道」なのである。
この思想は吉田松陰も大事にしたものだった。尊王論の中心に据えられたのである。松陰の『講孟箚記』(こうもうさつき)と、それを編集した『講孟餘話』(こうもうよわ)の「孟」は「孟子」。松蔭にとって孟子の思想こそ、維新の中核だったのである。
この維新によって興った明治政府と明治天皇、その孫である裕仁親王。孟子の思想がどのように継承されていったのか、裕仁親王は「王道」を進むのか、そこはこれからの物語の展開に期待したい。
◆ 天皇の姓と孟子の易姓革命
この孟子の思想には有名な「易姓革命」がある。わかりやすくいえば政権交代のことだが、正確には王朝の交代のことをいう。中国では王や王朝の「姓」が易(かわ)るので「易姓(えきせい)革命」と言った。このとき、平和的なバトンタッチによって王位が継承される場合の「禅譲」の方式と、武力による「放伐」とが認められていて、孟子の王道論はこの放伐思想のことにも言及していたのだ。
この「姓」が「易(かわ)る」というのが問題なのである。天皇は氏姓制度の伝統によって、「姓」を与える側であって、「姓」が無い。つまり、孟子の易姓革命によって、変えられることが無いのである。
実はこのことに目の当たりするシーンも、このマンガでは描写されている。裕仁親王は学校で、学友たちが苗字で呼び合うことに憧れる。そんな「フラット」な関係に惹かれたのだ。そこで裕仁親王は自分で「苗字」を考える。皇族のシンボルである「お印」が「若竹」であったたので、「竹山」という苗字のハンコを作ってみるのだ。これでみんなからも「竹山」と呼んでくれるんじゃないかと、養育係の足立タカに喜んで報告する。
タカ「さて・・・みなさん、殿下のこと、そうお呼びになりますでしょうか?」
裕仁「呼ばすよ!『竹山、おはよう』って絶対呼ばす! ぼくは皇太子なんだぞ!!」
このとき裕仁親王はまだ自分の立場がわかっていなかった。しかし、御学問所で「教育勅語」について学んだ際に、自分の立場を次第に理解していく。
「タカ、ぼくは”竹山”なんかじゃないんだね」
この言葉とともに、作ったハンコを捨てる。「姓」を捨てるのである。そして、こうつぶやく。
「朕は、国家なり」
この言葉をどういう意図で発したか、まだわからない。天皇という存在を理解したのかも、まだ本作では描かれていない。
しかし、天皇に「苗字が無い」というのは、たまたまのことなのだろうか? いや、実は古代日本で「設計」されたものではないのか、という説がある。その問題に向き合ったのが、歴史研究家の松本健一である。松本健一の遺作となった『「孟子」の革命思想と日本 天皇家にはなぜ姓がないのか』(昌平黌出版会)がその問題をえぐっている。
先程の孟子の易姓革命を思い出すと、「姓」があると、「易」えられてしまう。孟子思想は「革命」が許された思想なのである。では、日本に『孟子』を輸入する際に、この「易姓革命」の部分を消したらどうだろうか? そうすれば、「革命」が起きようもない。だから、天皇に姓をつくらなかった、というのが本書の主旨である。また、千夜千冊を引用する。
「天皇に姓がないのは日本の天皇家に易姓革命をもたらさないようになっているからで、姓がなければ皇位の簒奪もおこらないとみなされたからだ。『大鏡』には、嵯峨天皇の子の源融(みなもとの・とおる)が皇位につきたいと言ったところ、関白の藤原基経が「いったん姓をもらって氏姓をもった者は皇位にはつけない」と諭したという話がのっている。姓のない親王(皇太子)しか天皇にはなれないのである」
相良亨の『近世日本儒教運動の系譜』(アテネ新書)や『近世の儒教思想』(塙選書)によると、徳川家康は『論語』よりもずっと『孟子』を好んで読んでいたという林羅山による証拠があげられている。
家康はこんなふうに述べていた。「およそ天下の主たらんものは四書の理に通ぜねばかなわぬことなり。もし全部知ることかなわずば、よくよく孟子の一書を味わい知るべきなり」。羅山が、ではどこが一番感心されたのですかと問うと、湯武放伐のところだと答えたともいう。
戦国の世での家康にとっては、孟子は思想的支柱になりえた。しかしいったん徳川政権が継続されることになると、今度は一転して、放伐などはゆめゆめおこってはならないことになる。そんなことをされては徳川家がヤバい。天草四郎や由比正雪や佐倉惣五郎はこうして粉砕され、キリシタンや殉死は片っ端から禁止されたのである。徳川政権社会こそ日本における放伐思想を「隠そう」としたのである。
その伝統がいまなお続いている。天皇には姓がない。裕仁親王はハンコを捨てた。易姓革命を隠しながらも、仁徳を基本とする「王道」を志す。孟子は日本では、巧妙に編集されてきたのである。
◆ 神代の物語を「歴史ではない」と明言した白鳥庫吉
本書『昭和天皇物語』は純粋に歴史の裏側を楽しめる。乃木大将も養育係のタカも杉浦重剛も東郷平八郎も生き生きと描かれている。東郷平八郎と杉浦重剛が教育方針で衝突するも、杉浦の進講が「検閲」されることはなかったようだ。
さらに、歴史学を担当した御用掛の白鳥庫吉(しらとり・くらきち)は、「神代の物語は神話である。歴史ではない」という進講も行う。神代の物語とはイザナミ・イザナギやアマテラスの物語だ。これらを「神話」と言ったのである。これも天皇の在り方を脅かすものだ。なぜなら、天皇とは万世一系であり、アマテラスは神武天皇の祖先であり、天皇の祖先のはずなのに「神話」というフィクションであるということを明言したからだ。それでも、白鳥が解雇されることはなかった。
白鳥は杉浦に対して、自分たちは考え方が違うということを恐縮しながら、白状する。自分たちは「呉越同舟」であると。しかし、杉浦は、それでいい、と言う。
「白鳥さん・・・お好きなように進講なされ。(中略)殿下は実に聡明だ。殿下の眼を見ていると、時折怖くなる時がある・・・!! このお方は何もかもお見通しだ。何もかも見抜いている・・・と。白鳥さん!! ご自分の進講を信念を持ってやりなされ。良し悪しを決めるのは殿下ご自身・・・」
こんな風に自由にさまざまなことを学んでいたというのは驚きだ。大戦前後のイメージでものすごい検閲や思想統一があったのではないか、という勝手なイメージがあったからかもしれない。
これほど自由に学んでいた天皇の在り方を、現代の人こそ、もっと自由に考えられるといいのかもしれない。第1巻では、まだ1915年までである。ということは、日本はすでに第一次大戦に突入している。しかし、その物語はまだ描かれていない。裕仁親王が天皇に在位するまで、あと10年。第2巻を買いに行くしかない。