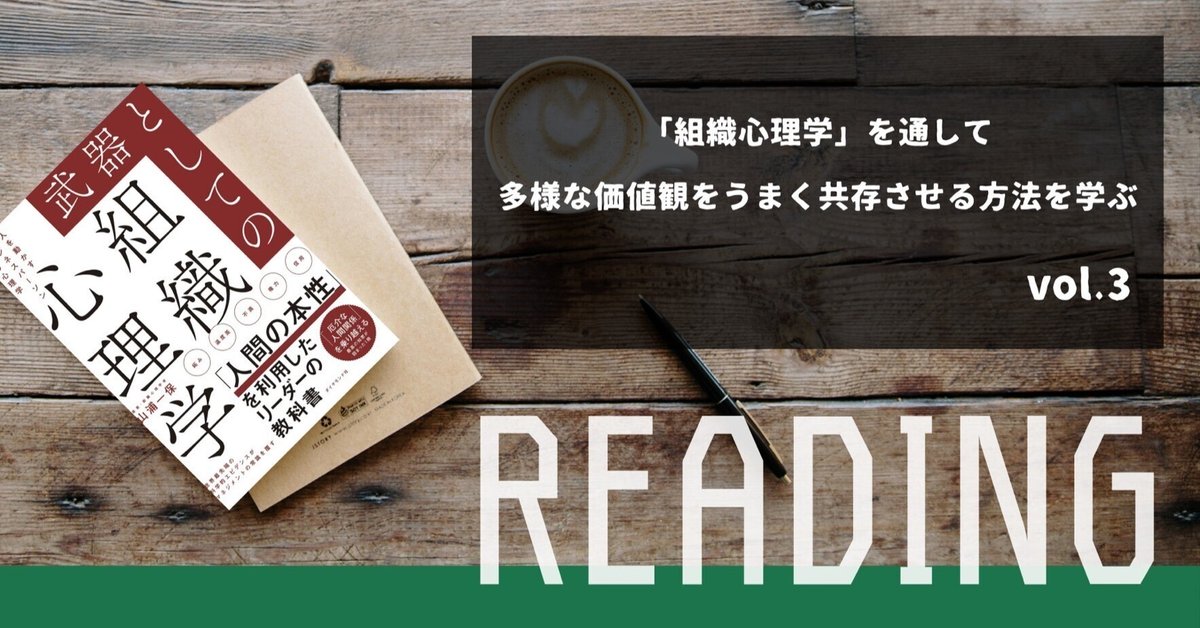
【読書note】「組織心理学」を通して、多様な価値観をうまく共存させる方法を学ぶ vol.3
こんばんは、芝本です。
『武器としての組織心理学』のアウトプットも第三弾になります。この書籍のアウトプットもこの記事で終わりです。人間の理解に努めることが、メンバーやチームの成果に直結すると思ってこの本を手に取りましたが、やはり人間関係が全ての土台にあるという普遍的なことを勉強できました。
興味のある方は上記の第一弾、第二弾も読んでいただければ幸いです。体得できれば、メンバーとの人間関係やチームの在り方なども刷新できる内容になっていると思います。
そして、最後のアウトプットは「もうすでに終焉を迎えた人間関係をどうやって修復していくのか」についてです。第一弾、第二弾で言い続けてきましたが、良い仕事をしていく上で良好な人間関係は必須です。なぜなら、仕事とはだれかのニーズがあって初めて生まれて、それに応えようとして営まれるものだからです。
「失った信用」を取り戻そう

信頼関係を構築することはとても大変だけど、信頼を失うのは本当に一瞬の出来事です。これを体感したことがないという人の方が珍しいのではないでしょうか。
そして、信頼関係を一瞬で崩壊させてしまうのは「第三者からの批判や悪口」だそうです。本人から直接ではなく、第三者から間接的に自分の批判や悪口を聞いた方がインパクトは大きいです。これを「ウィンザー効果」といいます。
そもそも「第三者よりも目の前の人を信じろよ!」とも思いますが、人間の心理だから仕方ない部分もあるのでしょう。第三者は自分自身に対して公平なジャッジをしてくれる存在で、お墨付きをもらえると安心し、そうじゃなければ凹むという心理が働いているんですね。ネット通販のレビューなどがそれに当たるかもしれません。
そして、人間関係の悪化は仕事のパフォーマンスに直接影響します。リーダーやメンバーに対してのネガティブな感情は、体調的にも精神的にも、実に良くない影響が出ますね。つまり、リーダーの仕事はメンバーがパフォーマンスを最大限に発揮する土壌づくりではなかろうかと考えています。
信頼関係を修復するアクション1「謝罪する・赦す」

この書籍の中では、サウスウエスト航空のCEOゲイリー・ケリー氏の謝罪会見が引き合いに出されていましたが、まさに信頼を回復するような謝罪会見です。ケリー氏の謝罪会見で失った信頼を見事回復させたサウスウエスト航空は、そのあと約8%もの需要を向上させました。
一方で、雪印の社長の謝罪会見は良くない事例として書籍の中で取り上げられていました。いったいなにが違うのでしょうか。
<謝罪を成功させる6つの要素>
1、素早く謝罪する
2、言い訳をしない
3、弱い立場を受け入れる
4、相手の立場に立つ
5、変化を約束する
6、贈り物で償いのシグナルを送る
ケリー氏は<謝罪を成功させる6つの要素>を全て取り入れた謝罪会見をおこなった一方で、雪印の社長は真逆をしたということですね。(ちなみに、ボク自身は「2、言い訳をしない」と「5、変化を約束する」を大事にすることでより心証が良くなると感じています。)
謝罪するということが相手にとっても自分にとってもとても大事です。この書籍にも書かれていましたが、謝罪をした側、謝罪を受けた側も心理的に穏やかな気持ちになるそうです。改めて言われると当然のことですが、なにかやってしまったなとなれば、まずは謙虚に謝ることがとても大切だということですね。
信頼関係を修復するアクション2「相談する」

リーダーからよく相談を受けるメンバーは、他のメンバーの手助けを頻繁にしている傾向にあるそうです。これはおもしろい実験結果ですね。
人から頼りにされて心底嫌だと思う人は少ないです。
ましてや、自分を頼ってくる存在が影響力のあるリーダーで、自分の意見が重要な意思決定に反映されるとなるとなおのことですよね。
メンバーの一人として尽力してもらうことが、その部下にとっても職場にとっても大切であるならば、部下の強みを探し、自尊心をくすぐってやることもリーダーに期待された役割の一つです。
出典:『武器としての組織心理学』p.217
つまり、リーダーはメンバー個々人の特徴を理解して、存分に能力が発揮できるポジションに就いてもらい、リーダー自らメンバーに相談を持ちかけるということが関係の修復や構築にとても効果的だということですね。
リーダーはメンバー一人一人の理解に努めることが大事になってきます。
そのために各メンバーとコミュニケーションを取る過程で、愛情が伝わって関係の修復に役立つのかもしれませんね。
おわりに
『武器としての組織心理学』のアウトプットもそろそろ終焉を迎えます。
全体を通して感じたことは、目新しいことはあまりありませんでしたが、「知っていること」と「実践していること」の違いは非常に大きいということです。
第一弾では妬みについて掘り下げて、第二弾では不平不満をプラスに変えることを学び、第三弾では終焉を向かそうな人間関係を修復するための具体的な施策をアウトプットしました。
人間の本質を理解して、良好な人間関係を構築することがチームで仕事をしていく上で非常に大切なことです。どのようなチームの文化を醸成するのかで、仕事の成果は大きく変わります。この本で学んだことを実践して、よりチーム力を高めていきます。
今日はここまで。
最後までお読みいただきましてありがとうございました。
