
三島由紀夫という迷宮⑥ 白亜の邸宅と〈空洞〉の時代 柴崎信三
〈英雄〉になりたかった人❻
三島が日本画家、杉山寧の長女、瑤子と結婚したのは、豊田貞子との3年にわたる関係に終止符を打った翌年の1958(昭和33)年6月である。文学上の師で、のちにノーベル文学賞受賞をめぐって先を越されることになる川端康成夫妻が媒酌人を務めた。知人の紹介による見合い結婚である。
〈5月9日(金) 杉山家と結納をと取り交わす。「結婚」という観念が 徐々に私の脳裏に熟してきたのは、一昨昨年ころからのことと思われる。それまで私は小説家たることと結婚生活との真向からの矛盾をしか見なかったが、私も年をとり、矛盾を少し高所から客観視するようになったのである。‥‥それに真に自由になるには、まず自分を縛ってかからねばならぬという人生上の知恵を、私はおそらく人より永い年月をかけて、徐々に学ぶにいたっていた〉(『裸体と衣装-日記』)
6月1日に行われた挙式と披露宴、その後の箱根、京都、別府、福岡などをめぐる2週間の新婚旅行は、マスコミの取材や各地での招宴、祝賀の訪問客などが相次ぎ、一大メディアイベントとなった。
三島はキェルケゴールの『あれかこれか』のなかの一節、「結婚したまえ、君はそれを悔いるだろう。結婚しないでいたまえ、やっぱり君は悔いるだろう」というアフォリズムを引いて、「遊泳者が全身を脱力して、のびやかに浮身をするように」たどりついた自身の結婚の顛末を語っている。
しかし、それは実のところ「作家・三島由紀夫」に戦後の日本社会が求めた〈結婚〉をようやく受け入れてたどりついた、与えられた選択にほかならない。三島はやがて子を生し、壮麗な屋敷を構え、戦後日本の社交空間のスターとなった。この作家にとっては自身の〈結婚〉も〈家庭〉も、実は「肉体改造」によって彼が身につけた逞しい筋肉のように、〈戦後〉という空間に努力して構築した人工的な伽藍であったのかもしれない。
三島が結婚と前後しながら力を入れて取り組んでいた仕事は、長編小説『鏡子の家』の連載である。これは〈戦後〉という時代に仮構された、もうひとつの〈家〉を舞台に繰り広げる、野心的な同時代の物語である。
〈みんな欠伸をしていた。これからどこへ行こう、と峻吉が言った〉
冒頭のこの台詞が、長い小説の展開を暗示する。主人公たちの乗った車が勝鬨橋にさしかかると、船舶の航行のために道路を開閉する時間にぶつかり、渋滞に巻き込まれている。すでに荒涼とした焼け跡の時代が終わって、その先に広がる晴海の埋め立て地は〈戦後〉の先の迷宮を予感させる。

「一九五四年の四月はじめの午後三時ちかくであった」と、場面の時点が示される。総力戦体制へ向かう1940(昭和15)年に「皇紀二千六百年」を記念して開通したこの跳開橋が、船舶の航行で中央から八の字に跳ね上がる場面が描かれてゆく。主題のイメージを掻き立てる巧みな導入である。
焼け跡からの復興と豊かさへ向かう坂道に挟まれた、凪のような時間。
朝鮮戦争が終わり、成長の坂を上り始めた時代の東京を背景にして、〈鏡子〉という女主人が住む信濃町の高台の洋館に4人の若い男たちが集まり、それぞれの美意識と行動原理をたたかわせながらデカダンスと虚無のなかを生きてゆく―。もちろん、その〈家〉には倫理や道徳は微塵もない。
4人は世界の崩壊を信じる商社のエリート社員の清一郎、肉体の不滅を信じるボクサーの峻吉、童貞の日本画家の夏雄、そしてナルシストの演劇青年、収。それぞれが作者の分身であり、彼らは行動して他者や外界と衝突しながら決して交わることがなく、壁に阻まれて破滅へ向かう。
「時代の壁」に向かって4人はそれぞれの思いを募らせる。
『俺はその壁をぶち割ってやる』という峻吉。
『僕はその壁を鏡に変えてしまう』という収。
『僕はその壁に描く。壁が風景や花々に変われば』という夏雄。
そして『俺はその壁になる。俺がその壁自体に化けてしまうんだ』と清一郎は考える。
三島は『鏡子の家』に大きな自信と野心をもって取り組んだ。
『金閣寺』の成功で自身が〈和解〉した戦後と正面から向き合い、いま置かれている豊かさと繁栄へ向かう時代の虚無と退廃を探ろうとした。
ところが、満を持して発表した『鏡子の家』は文壇やメディアなどから冷淡な評価に見舞われ、もちろん売れ行きもベストセラーとは程遠い水準に低迷した。もっとも大きな理由は4人の主人公が交わることなく物語が進行する、メリーゴーラウンドのような構成である。
そこには4人の独白の積み重ねがあっても、主題の衝突や劇的な発展の起こりようがなく、彼らを取り巻くいくつかの挿話を通してそれぞれの文明批評がめぐり続けるような小説だからである。
折々に1950年代の日本の断面がコラージュのように挿入される。
〈こんな希望のない状態のうちに、記念すべきお祭、思いも設けぬ大盤振舞、あの朝鮮動乱がふって湧いたのである。庫崎の会社はたちまち台をなし、十九万五千円の資本金で発足した中央金属貿易株式会社は、増資に増資を重ね、はじめ二、三十人であった社員は何十倍になった〉
〈日本共産党は「愛される共産党」へ再出発するための方針を決定した。それと一緒に、徳田球一の死が発表された。四国巨頭会談がジュネーヴでひらかれた。各自衛隊の新編成と配置が決まり、陸上自衛隊は合計十五万人になった。幼い兄弟が、常磐線で飛び込み自殺した‥‥〉
〈不況!不況!動乱がやがて終息し、砲弾で穴だらけになった朝鮮の禿山に、最後の銃声がこだまして止んだとき、それは堰を切って溢れ出すだろう。政府はなお甘い見通しに涵っていたが、「物産の人間」は、蟻が洪水を予知するように、あやまつことのない触角を動かしていた〉
こうした時代背景のもとで、〈鏡子の家〉に集まる四人の男はそれぞれに行動し、男や女と格闘しながら「壁」に突き当たってゆく。ボクサーの駿吉は獲得したチャンピオンの座を失って右翼団体に入り、自滅する。俳優の収は母親の借金の代償に女高利貸の愛人となった挙句、殺されてしまう。青木ヶ原の樹海で虚無の底に落ち、神秘思想にとらわれた日本画家の夏雄と、赴任先のニューヨークで同性愛の米国人に妻を寝取られた商社員の清一郎だけが生き延びて、不信と虚無に包まれた「鏡子の家」に残される。
「ヴィクトリア朝コロニアル様式」という意匠で三島が白亜の邸宅を東京・馬込に建てた1959(昭和34)年の秋、『鏡子の家』は刊行された。
原稿用紙1200枚の長編小説で「時代をまるごと描く」という、バルザックやトルストイを思わせる鳴り物入りの作者の意気込みに反して、その反響は期待を裏切るものであった。文壇の批評は小さくシニカルで、作家が期待した「時代を描いた作品」への評価はほとんどみあたらない。
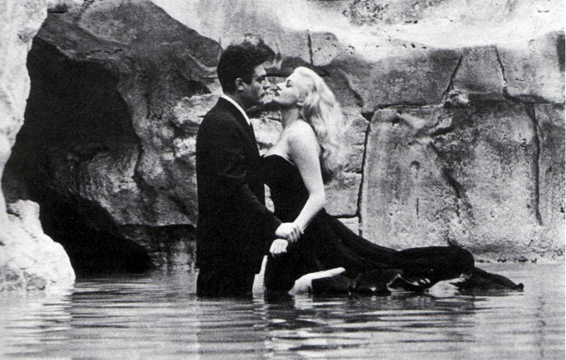
マルチェロ・マストロヤンニとアニタ・エクバーグ
〈『甘い生活』という三時間にわたる大長編映画を見た。我田引水で気がさすが、これを見た印象が拙作『鏡子の家』にあんまりよく似ているので、盗作されたかと思ったくらいである。それは冗談だが、第一に長すぎること、第二に主題や構成や不道徳パーティーがいっぱい出てくるなどの点で、よく似ていること、第三に「鏡子の家」同様、各エピソードがしり切れトンボで発展性がなく、同じ詠嘆の繰り返しに終わっていること‥‥あらゆる点で「鏡子の家」の欠点をみんな背負っているようだ〉
創作の技術的な瑕疵によって自作への世間の不評が生じたことへの言い訳に、話題の映画の『甘い生活』を持ち出したようにも聞こえる。
ところが、大方の批評家やメディアの時評が否定的であったなかで、ここに描かれている「巨大な空白」こそ三島の主題であるとして、この小説を「いかにも燦然たる成功である」と評価したのが江藤淳である。
かつて戦争という〈椿事〉を待ち望んでいた少年が長じて、〈戦後〉の復興と成長の陰の巨大な〈空白〉を証して見せた作品として、江藤は逆説的に『鏡子の家』に一票を投じた。それは10年余りのちに三島が自裁した直後、江藤が示した醒めた反応につながる、ある確信に基づくものだろう。
壁に阻まれて破滅してゆく男たちを見ながら、『鏡子の家』の女主人は心のなかでこう呟く。
〈再び真面目な時代が来る。大真面目の、優等生たちの、点取り虫たちの陰惨な時代。再び世界に対する全幅的な同意。人間だの、愛だの、希望だの、理想だの、‥‥これらのがらくたな諸々の価値の復活。徹底的な改宗。そして何よりも辛いのは、あれほど愛して来た廃墟を完全に否認すること。目に見える廃墟ばかりか、目に見えない廃墟までも!〉
男たちが去った高台の〈鏡子の家〉にある日、永く別れていた夫が何事もなかったように戻ってきて、鏡子の家は一見何の不足もない、かつての満ち足りた山の手の家庭に還ってゆく。
〈玄関の扉があいた。ついで客間のドアが、おそろしい勢いで開け放たれた。その勢いにおどろいて、思わず鏡子はドアのほうへ振向いた。
七疋のシェパァドとグレートデンが、一度きに鎖を解かれて、ドアから一せいに駆け入って来た。あたりは犬の咆哮にとどろき、ひろい客間はたちまち犬の匂いに充たされた〉
「精神が肉体の比喩で語られ、言葉が外在化されたとき、作家の内部にはひとつの明瞭な輪郭を持った「空白」だけが残る」と江藤淳は指摘する。
観客の不満表明で迎えられたこの鳴り物入りの意欲作は、〈戦後〉という同時代に身丈を合わせるように「肉体改造」に取り組んだ三島が試みる〈内面の外在化〉の造形の試みであった。作品は作者の意図を超えて〈戦後〉という時代の巨大な「空白」の壁を描くことに成功した、と江藤は見る。
それはボディービルやボクシングで鍛えて三島が獲得した筋肉と引き換えに、「この世界が瓦礫と断片から成立っていると信じられたあの無限に快活な、無限に自由な少年期は消えてしまった」という認識につながっている。
闖入してくる七匹の猛犬の咆哮とともに〈鏡子の家〉にかつての日常が戻るとき、彼らの〈青春〉が〈戦後〉という家とともにも崩壊する。
壮大な企図を持った失敗作『鏡子の家』の女主人とその舞台は、実は三島の青春期に重要なかかわりを持つ一人の女性がモデルとされている。三島の亡くなった妹の友人で平岡家と家族ぐるみに付き合いのあった、湯浅あつ子である。のちに三島が見合い結婚をする日本画家、杉山寧の長女、瑤子と引き合わせたのも、この三島と同年の女友達のあつ子であった。
男勝りの姉御肌で、日系二世の技術者だった夫が不在勝ちだったこともあり、東京・品川の高台の邸宅にはさまざまな友人、知人たちが出入りした。『鏡子の家』はこの屋敷を信濃町に移して舞台を設定したとみれらる。岩下尚史の『直面(ヒタメン)』などによれば、あつ子は三島とは姉と弟のようなつきあいだったようで、1958(昭和33)年6月1日に六本木の国際文化会館で行った三島と瑤子の結婚披露宴は、あつ子がのちに再婚したタレントのロイ・ジェームズが司会を務めている。
ともあれ、不評にまみれたこの「問題作」に対して一人、江藤淳が「燦然たる成功」といささかの皮肉を含んだ賛辞を寄せたことは、三島にとってせめてもの救いであった。
1962(昭和37)年2月27日付けで三島が江藤に寄せた手紙が残る。
〈あの作品が刊行されたときの不評ほどガッカリしたことはなく、又、周囲の友人が誰も読んでくれず、沈黙を守っていたことほど、情けなく思ったことはありませんが、それも今だからこそ告白できることで、女々しい愚痴は言わないつもりでいましたが、あの時以来、大げさに言えば、日本の文壇で仕事をすることについて、それまで抱いていた多少の理想を放擲する気になった位でした。以後小生が戦線を後退させ、文壇に屈服する姿勢に出たことは、おそらく貴兄も御賢察の通りです。此度の御解説を拝読して、しかし、小生には勇気が蘇った感があり、真の知己の言はかくの如きかと銘肝いたしました〉
東京・馬込に三島が白亜の邸宅を建てて転居したのは1959(昭和34)年の6月である。ちょうど『鏡子の家』が完結して出版された頃であったから、この「ヴィクトリア王朝時代のコロニアル様式」と呼んだ白亜の家と『鏡子の家』の文脈的なつながりが詮索されることは、必然であったろう。
伝説と化してゆく白亜の屋敷の設計にあたったのは、清水建設の設計部にいた鉾之原捷夫である。三島の「ヴィクトリア王朝時代の植民地様式」という要求に、彼が「よく西部劇に出てくる成り上がり者のコールマン髭を生やした金持ちが住んでるあれですか」と応じると、「ええ、悪者の家がいいね」と破顔したという。「ロココの家具にアロハシャツ、ジーンパンツで過すのが理想」と三島は鉾之原を煙に巻いた。
三島は新居を建設するにあたって、明確な一つのイメージを持っていた。
『鏡子の家』の取材でニューヨークに滞在した折に親しんだという、アグリー・ヴィクトリアンと呼ばれる室内装飾の様式の建物である。それはニューヨークに転勤した商社員の杉本清一郎が山川財閥の夫人に誘われて出かけるワイルドパーティーの会場として、小説の中に登場する。
〈清一郎は戦災前の東京の旧市内の一劃が、ニューヨーク郊外に忽然とよみがえったような、常盤木の林に囲まれた古い落ち着いた様式の広壮な館の馬車廻しにパッカアドを乗り入れた。‥‥室内装飾はヴィクトリア朝様式と日本趣味とのまことにぴったりとした混淆で、こういう混淆は日本人の客に古くから馴染のある感を与えた。ダアク・マホガニイの飾棚は漆器ともよく合うし、螺鈿や七宝や古い支那の陶器ともよく合った〉
新しい邸宅は、これに三島の植民地風のラテン趣味を加えて設計された。夫人の瑤子とともに欧州旅行で買い集めたスペイン・バロック風の家具調度や美術品が飾られた屋内と、大理石のアポロ像のレプリカが建つ前庭などを眺めれば、そこにはさながら異国趣味の展示場といった趣きが漂う。
ともあれ、この邸宅は馬込の閑静な住宅街で異彩を放った。
真っ白な外壁にはバルコニーと円形の破風窓が並び、前庭には黄道十二宮のモザイクの上に大理石のアポロ像が立つ。スペイン風のテラコッタや陶板で装飾された石造りのベンチがそれを囲んでいる。屋内の吹き抜けの高い天井からシャンデリアが下がる応接間には、ロココ風の猫足の調度があちこちに置かれている。三島が拘った「ヴィクトリアン王朝のコロニアル様式」という趣味の内部は、あたかも『アポロの杯』で彼が描いた欧米各地の旅土産を陳列したような、きらびやかな混沌に包まれていた。
この家で三島の役割はまず、家族を育む平凡な一家庭の主人として、自らを演出している。
〈現在の私は旦那様である。妻には適当に威張り、一家の中では常識に則って行動し、自分の家を建てかけており、少なからず快活で、今も昔も人の悪口をいうのが好きだ。年より若く見られると喜び、流行を追って軽薄な服装をし、絶対に俗悪なものにしか興味のない顔をしている〉(『十八歳と三十四歳の肖像画』)
いくぶん韜晦のポーズをとりながらも、三島はこの新居で営む家庭の風景を楽し気に記している。伝統主義者にもかかわらずライフスタイルは徹底的に西洋風で、食事はビーフステーキを愛好し、家での普段の服装はラフなアメリカンスタイル、大切な接客にはスーツにネクタイで応じた。
書斎では「勤勉な銀行員のように」と形容したように、毎日定まった時間に精力的に小説の執筆に励み、ボディービルをさらに続けた。『鏡子の家』で描いた、鏡子と四人の男のデカダンスとアンモラルな〈家庭〉とはおのずから異なる、作家の新しい日常がそこに浮かび上がる。

けれども〈三島由紀夫〉が建てたこの白亜の邸宅が、単なる彼と家族の生活の器としてだけあろうはずは、もちろんない。しばしばパーティーが開かれて、屋敷はこの時代の日本を代表する三島の知人の芸術家や知識人たちが集う、華やかな社交の空間となった。
吉田健一、ドナルド・キーン、川端康成、澁澤龍彦、森茉莉、横尾忠則、美輪明宏‥‥‥。記録に残されている来訪者の名前を拾い上げてみれば、おのずからその空気は伝わる。時には鳴り物入りで盛装の舞踏会も開かれたこの館を、近隣では「大森鹿鳴館」などと呼んだというから、それはとりたてて特色のない東京近郊の住宅地に異彩を放ったに違いない。
『鏡子の家』が世間の不評にさらされるなかで、〈白亜の邸宅〉に移り住んだ三島はそのころ、どんな日々を送っていたのか。
1960(昭和35)年3月、俳優として出演した増村保造監督のアクション映画『からっ風野郎』の撮影現場で、誤ってエスカレーター上に倒れて後頭部を強打、虎の門病院に入院した。
東京都知事選の候補になった元外相、有田八郎と老舗料亭の女将の恋愛を描いた『宴のあと』は、のちに日本初の「プライバシー裁判」に発展する。
週刊誌のグラビアに「ぼくはオブジェになりたい」というタイトルで出演。『お嬢さん』『スタア』などの娯楽小説を女性誌に連載した。
1961(昭和36)年1月に2・26事件に取材した小説『憂国』を発表。深沢七郎の『風流夢譚』の皇室風刺をめぐって右翼が版元の中央公論社社長宅を襲った嶋中事件で、三島にも警備がついた。
1962(昭和37)年、UFOの実在を信じる家族を主題にした『美しい星』と〈英雄の失墜〉の時代を少年の目からとらえた『午後の曳航』を書いた。自らが裸体のモデルとなって、ナルシズムを存分に満たした細江英公の写真集『薔薇刑』が出版されたのも、この年である。

確かにフェリーニの『甘い生活』が描いたように、マスメディアの広がりと大量消費が主導する大衆社会は、この国でも熟しつつあった。女性向けのエンターテインメントから映画やグラビア雑誌への自身の〈出演〉、はたまた〈2・26事件〉にUFOまで、ほとんど脈絡のない三島の作家活動の無秩序な広がりは、「時代をまるごと描く」という『鏡子の家』の目論見が頓挫した必然的な結果であったのかもしれない。
精神と肉体の〈等価交換〉によって、彼は〈戦後〉という迷宮に踏み込んでいたのであろう
〈白亜の邸宅〉の外側では、〈戦後〉という時代が大きく転換しようとしていた。占領下から脱した日本は、日米安保条約の改正をめぐって大きな対立をかかえ、条約の自動延長の期限である1960(昭和35)年6月にはその批准をめぐって国論を二分する大きな政治の争点となっていた。
連日国会前は条約の批准阻止を求める野党や労働組合、全学連の学生らによる反対デモが取り巻き、条約改正の自動成立を前にした6月15日には警官隊との衝突でデモ隊にいた東大生、樺美智子が死亡した。列島には騒然とした空気が覆ったが、それも法案が国会を通過して新たな条約が自然成立すると、あたかも熱湯に冷水が注がれたように世情は沈静してゆく。
条約の批准とともに退陣した岸信介に代わって首相の座に就いた池田勇人が掲げる「所得倍増政策」は、高度経済成長の坂を上りつつある国民に「豊かな暮らし」と「平和と安定」へ向けた夢を確かなものにした。
『鏡子の家』でニヒリストの商社員、杉本清一郎は鏡子に向っていう。
〈君は過去の世界崩壊を夢み、俺は未来の世界崩壊を予知している。そうしてその二つの世界崩壊のあいだに、現在がちびりちびりと生きている。その生き延び方は、卑怯でしぶとくて、おそろしく無神経で、ひっきりなしにわれわれに、それが永久につづき、永久に生きのびるような幻影を抱かせるんだ。幻影はだんだんひろまり、万人を麻痺させて、今では夢との堺目がなくなったばかりか、この幻影のほうが現実だと、みんな思い込んでしまったんだ〉
〈戦後〉という迷宮に踏み込んで、豊かな社会へ向かう時代が繰り広げるカーニバルのような大衆文化の坩堝に身を投じた三島にも、夢想した〈世界崩壊〉は逃げ水のように遠ざかりつつあったのであろう。
1960年の日米安保条約改定をめぐる国論の対立と混乱に対しては、多くの作家や知識人も賛否の論陣を張ったが、保守主義者を自認する三島がこれに積極的に発言した形跡は乏しい。藤原定家の「紅旗征戎吾ガ事ニ非ズ」を鏡として、〈迷宮〉の内側で政治への関与を避けたかったのだろうか。
十年後の自決の直前に残した『果たし得ていない約束―私の中の二十五年』と題した一文で、三島が「私は昭和二十年から三十二年ごろまで、大人しいい芸術至上主義者だと思われていた。私はただ冷笑していたのだ」と書いたのは、おそらく正直な告白であったに違いない。彼はこれに続けて「ある種のひよわな青年は、抵抗の方法として冷笑しか知らないのである。そのうち私は、自分の冷笑・自分のシニシズムに対してこそ戦わなければならない、と感じるようになった」と振り返っている。
デモ隊にいた東大の女子学生の死者まで出した1960年の日米安保条約の改正をめぐる騒乱は、その直後から言論をめぐる右翼のテロ事件を誘発させて、それが三島のなかに眠っていたものを覚醒させた可能性がある。
最初は同じ年の10月12日に東京・日比谷公会堂の立会演説会の壇上で、弁士を務めていた日本社会党委員長の浅沼稲次郎に大日本愛国党党員で17歳の山口二矢が刃物で切り付けて刺殺した事件である。

(1960年10月12日、東京・日比谷公会堂)
翌年の1961年1月、作家の大江健三郎がこの事件の犯人をモデルにした小説『セヴンティーン』を雑誌「文学界」に書き、その描写を「不敬」とする右翼の抗議を受けて掲載元の文藝春秋が謝罪文を掲載した。以降近年までこの作品は単行本などから除外されてきた経緯がある。
同年12月には作家、深沢七郎が小説『風流夢譚』に天皇皇后など皇族が斬首される夢を見たというパロディーを書いて宮内庁が名誉棄損と抗議し、一方で出版元の中央公論社に右翼が抗議に押し掛ける騒動となった。右翼団体の抗議はその後も続き、翌年2月には東京・市ヶ谷の同社社長、嶋中鵬二宅に右翼団体に所属する17歳の少年が闖入、応対した夫人と2人の家政婦に刃物で切り付け、家政婦の一人を死亡させた。この事件を機に右翼の言論介入が続き、同社の衰退の一因となったともいわれる。
三島はこの事件の発端となった深沢七郎の『風流夢譚』を事前に出版社から入手して読んでおり、2・26事件に取材して執筆していた自作の『憂国』とのかかわりを疑われて、三島にも脅迫状が届くという顛末もあった。
新婚ゆえに2・26事件への蹶起から外された近衛歩兵連隊の中尉夫妻が「皇軍相撃」を避けるべく割腹心中を遂げるまでを描いた『憂国』は、この一連のテロ事件と連動するかのように、1961(昭和36)年1月の「小説中央公論」に発表された。戦後のシニシズムの迷路から脱皮しようという衝動が三島のなかに生じたのである。そこで彼が期待する新たな〈椿事〉とは何だったのか。
三島の〈白亜の邸宅〉の書斎に、一見この屋敷の佇まいとは異質なイラストレーションの作品がかけられていた。

横尾忠則の『眼鏡と帽子のある風景』で、紙にカラーインクで描いた、アンディ・ウォーホルのポップアートを思わせる同時代の作品である。
三島は生涯でいくつかの絵画と運命的な出会いを経験している。少年時にグイド・レーニの『聖セバスチァンの殉教』と出会った経験や、ヴァトーの『シテール島への船出』への愛着についてはすでに触れたが、このイラストレーションにはいかにも「ヴィクトリア王朝のコロニアル様式」の屋敷とは不似合いな、軽くて不気味な〈昭和〉の平穏が揺蕩っている。
山高帽にロイド眼鏡の男が横目で視線を投げかける画面の下で、日傘をさして振り返る裸女と猫、そして男たちの群像が沖合に船がゆく海辺にたたずんでいる。ローマの古典美術からルネサンス、せいぜいがロココ時代までを贔屓にした三島が、なぜこの現代日本のポップアートに心を惹かれたのか。
〈横尾忠則氏の作品には、全く、われわれ日本人の内部にあるやりきれないものが全部露呈していて、人を怒らせ、怖がらせる。何という低俗のきわみの色彩であろう。招魂社の見世物の看板の色彩の土俗性と、アメリカン・ポップアートのコカコーラの赤い入れ物の色彩との間にひそむ、そのおそろしい類縁性が、われわれの内部にあって、どうしてもわれわれが見たくないというものを、爆発させてしまう。なんという無礼な芸術であろう。このエチケットのなさ〉(『横尾忠則遺作集』序)
1965(昭和40)年5月に横尾が東京・日本橋で開いた個展会場に、ふらりと現れた三島はこの絵の前に立ちつくし、その場を離れないことから会場にいた横尾が進呈を申し出た。作品は三島の書斎の仕事机の横に掛けられた。
どこかで『シテール島への船出』とも重なる、先の見えない〈戦後〉の迷宮に漂うロココ的な不安を、三島はこの絵に見出したのかもしれない。その 奇妙な平穏の先に、彼は何を見ていたのだろうか。
=この項続く
◆標題作品 横尾忠則『眼鏡と帽子のある風景』(1965年、カラーインク、紙、個人蔵)
