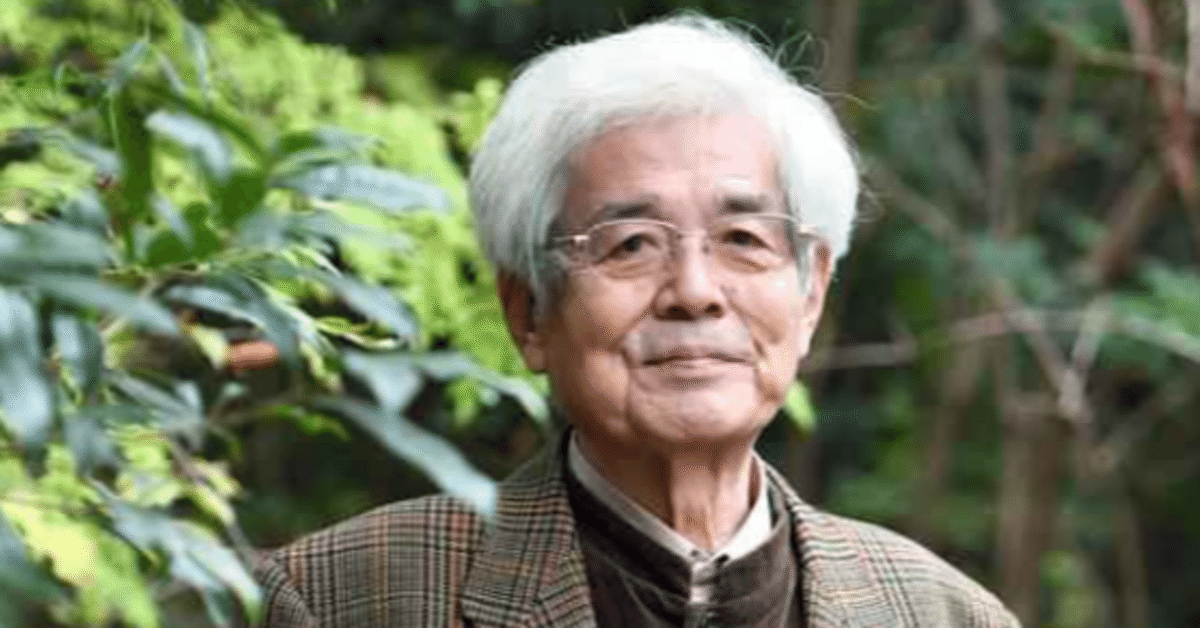
フェイクニュース「いい言葉流行った」
公平客観中立はウソ
「トランプ大統領はいい言葉をはやらしてくれたと思いましたよ。ニュースは基本的にそう見るべきだと思っていますから。NHKは公平客観中立なんて、ウソつけって思う。」
報道機関の切り取り、極端な偏向、誠実そうなアナウンサーのコメントによる印象操作は多くの人たちが認識している一方で、NHKなどのテレビ局のニュース、報道の類を信じて疑わない人もまだまだ多いようです。
30年以上も続いている偏向、切り取り、印象操作
大手のメディアによる報道に違和感を持ったのは湾岸戦争のときですが、このときは特にCNNの偏向報道が話題になっていました。
戦争報道の全体像が見えるようになったころから、テレビ報道に対する批判は高まり、関係者は反省にせまられ た。
その多くは、「テレビはアメリカ政府や国籍軍のお先棒をかついで、ハイテク兵器による戦争のクリーンな面ばかりを強調する報道を行った。
その結果、戦争が持つむごたらしさや悲惨さが覆い隠くされ、戦争の実態について、視聴者に間違ったイメージをいだかせることになってしまった」という批判であり、反省である。
これを見ると、メディアはまったくの嘘や、ありもしないデタラメを報道したわけではなく、あくまでも「視聴者に間違ったイメージをいだかせ」ることに腐心した、ということであり、そのやり方は「ハイテク兵器による戦争のクリーンな面」を強調することだった、とされています。
しかしながら、例えばまったく銃を写さない、などの切り取りが行われていたとても、視聴者は気づきませんし、受け取る印象は大きく違います。
私たちはこのような編集がずっと以前から行われていたことを覚えておく必要があるでしょう。
話題になった捏造事件
大手メディアのジャーナリストによる常習的な記事の捏造、盗用が発覚して、大きく取り上げられることになった事件が2003,2004年に続けて起こります。ジェイソン・ブレア事件(2003年)、ジャック・ケリーの捏造事件(2004年)です。
2003年5月、彼が執筆したイラク戦争で戦死した兵士の家族に関する記事が、当時テキサス州のサンアントニオエクスプレスニュースの記者のマカレナ・ヘルナンデスが寄稿した記事との類似性を指摘され、他紙でもスクープされる事態となった結果、ニューヨークタイムズが調査チームを編成し調査した。
その結果、彼が2002年10月以降に執筆した記事73本のうち約36本が他紙からの盗用・捏造だった事が発覚
2004年3月、ベテラン記者で、ピューリッツァー賞の選考委員も務めるジャック・ケリーが捏造記事を書いてきたというスキャンダルにより、大打撃を受けた。
こうしたニュース、報道の捏造が続く状況はメディアの集中によるものとして、「民主主義にとって毒薬」と、メディア論などで知られるロバート ・マクチェスニ ーは述べています。
アメリカ・ジャーナリズムの変質
巨大メディア企業が豊かに、強力になるにつれ、参加型民主主義の将来の見通しはますますお寒いものになっている。
(中 略)
集中化が際立たせているのは、過度の商業主義が最優先され、ジャーナリズムと公共サービスが軽んじられる、利益追求と広告依存型のメディア・システムである。
メデ ィアの集中は民主主義にとって毒薬である。
映画になった捏造事件
ジャーナリストによるニュースの捏造事件(実話)を映画化した「ニュースの天才」という作品があります。これはスティーブン・グラスという当時若手のスター記者の起こした捏造事件です。
98年、政治雑誌「The New Republic」誌の最年少記者スティーブン・グラスはスクープを続々執筆して注目を浴びるが、彼の記事がすべて捏造だったことが判明する。
戦争、紛争のニュース
現在も続くロシアとウクライナの戦争、ハマスの攻撃に対して反撃するかたちでガザを攻撃し続けるイスラエル軍の様子などを私たちは日々、テレビなどで目にしています。
激しい砲撃の映像には恐怖を感じますし、幼い子どもたちが傷つけば悲しみや、怒りといった「感情」を揺さぶられます。
メディアはこのように、私たちの「感情」に強く訴えるシナリオ、演出を非常に巧に操ります。
感情的になっているときに冷静な判断はできません。もしも「怖いな」とか「ひどいな」と思う気持ちが強くなったらテレビは消すべきなのです。
そして、これはイラク戦争のときの従軍取材によって可能になったという指摘があります。
2002年10月30日,いまだイラクの大量破壊兵器保有に関する議論が展開されていた時期に、ラムズフェルド米国防長官は、イラクとの戦争があったときにジャーナリストを米軍に従軍させる用意があることを発表した。
それが「エンベッド19)式従軍取材」というもの
<中略>
従軍取材を主たる情報源に置くことによって、記者・カメラマンの目が必然的に従軍している部隊の兵士個人に向けられることになったことが指摘できる。
このことは、記者・カメラマンの関心事が一種の「人間ドラマ」に向けられること、そしてその演出としての「迫真映像」を求めるようになることを意味する。
すなわち、メディアは,戦況を断片的に伝えざるを得なくなるのみならず、戦争をドラマとして描くという「客観性」を失った報道を続けることになってしまったのである。
詐欺師は虚実を巧みに織り交ぜて使う
大手のメディアは多くの場合、嘘、でたらめ、根拠のないでっち上げだけはなく、事実やあたかも信用できそうな情報を織り交ぜながら巧妙に出来事や事件の印象をコントロールします。
一流の詐欺師はほとんど嘘をつきません。みんなが知っていることから話し始め、相手に賛同して共感を得る術も持っています。
詐欺師が嘘をほとんどついていないから騙されるのです!
テレビのニュース番組はアナウンサー、コメンテーターがカメラ目線で語り、ちょっと気の利いた流暢な話術や、番組の合間に流れる音楽なども最高の演出になります。
それは、話し方や姿勢、目線にいたるまで日々、トレーニングを積んでいる一流の詐欺師が照明を浴びながら舞台に上がって喋るのを私たちは見ている、ということになるのかもしれません。
アナウンサーには自覚はないのかもしれないですが。。
追記 湾岸戦争への引き金となった15歳の少女の演技と報道
補足 ナイラ証言
ナイラ証言(ナイラしょうげん、Nayirah testimony)とは、イラクによるクウェート侵攻の後、「ナイラ」を名乗る少女が行った証言。
イラク軍兵士がクウェートにおいて、新生児を死に至らしめていると涙ながらに述べたこの証言により、国際的に反イラク感情とイラクへの批判が高まり、湾岸戦争の引き金ともなった。
しかし後に「ナイラ」なる女性は存在せず、クウェート・アメリカ政府の意を受けた反イラク扇動キャンペーンの一環であったことが判明し、今ではプロパガンダの一例としてしばしば採り上げられる。
