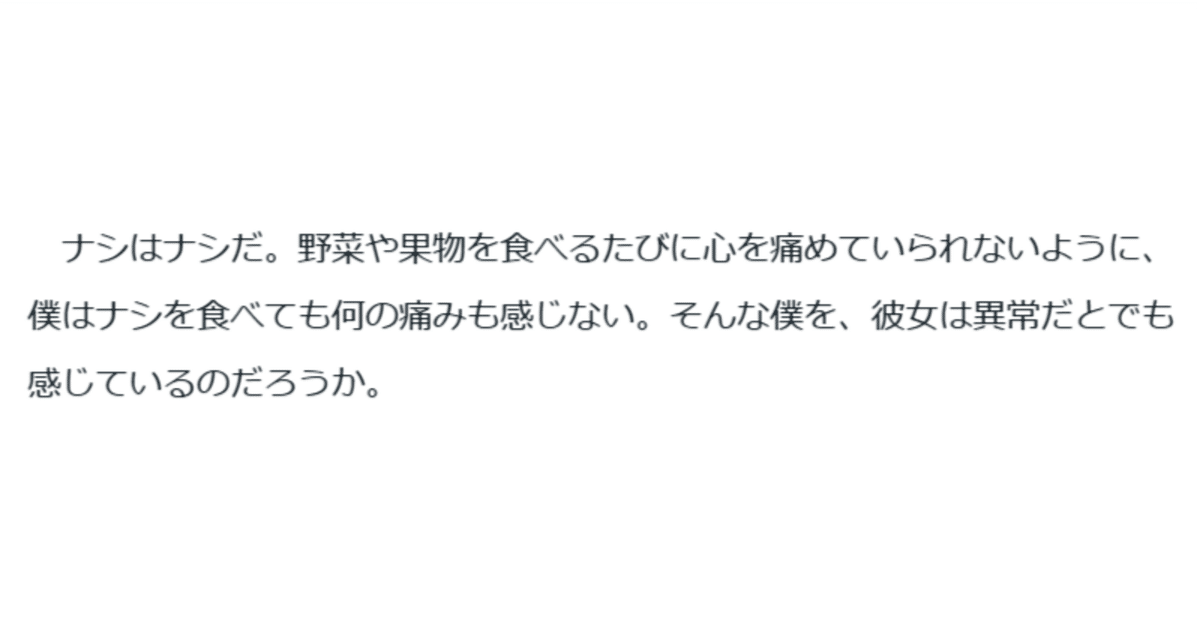
おいしい隣人(小説)
その、本当に言い出しにくいんだけどさ、最近極端に痩せてきている気がするんだけど……だいじょうぶ?
恐る恐る僕がそう伝えると、彼女は、あーバレたかー、と軽やかに笑って、
「ああ……あのね、食べるの、やめてみたんだ。“ナシ”のこと」
「え」
「今はこっそりインターネットで代替の植物由来の偽肉を輸入していて、それに切り替えているんだけど、やっぱり、代替品は代替品でしかないよね。そもそもネットで手に入るものなんて粗悪品だろうしね。はは」
彼女がコーヒーをすする。その頬にひどく濃い影が落ちる。明らかに頬がこけている。カップを握る手元がわかりやすく筋張っている。正直、骸骨みたいだ。
「なんでそんなことしてるの? 君もナシのこと、人間だと思っているとか?」
「うーん、どうだろう、そこがあんまりわかんなくなっちゃって。一回やめてみようかなってくらいの気持ちで絶って、今二か月目くらいなんだけどね。ナシを食べなくても問題なく生きている人もたくさんいるって聞くし、ううん、でもどうだろうな、確かに心のどこかで人間なんじゃないかって思っているのかもね、大元を辿れば……ってのはあるかもしれない」
「そんなこと言ったって、牛だって豚だって鶏だって、元々は人間が勝手に家畜化したものじゃないか。そもそも豚なんか、猪をいじくり回して人間が生み出した、生物の進化で考えればおかしな生き物だ。よく言われているけど、いっそナシより残虐だとも言えるじゃないか。まあ、豚や牛や鶏はもう一般人が食べられるような価格ではなくないけれど……。それにナシは、確かに遺伝子的には人間だったモノけれど、実際には脳もない、感情もない、五感もない、遺伝子を組み替えて人間が食べても一切の害もないように進化させた、完全に無害な、何も無い存在。だから“ナシ”なんだよ? それはわかっているよね?」
「わかってるよ。そんな小学校で習うようなこと言われたって、今更」
彼女が髪を耳にかける。首があまりにも細い。去年の誕生日にプレゼントしたプラチナのネックレスが、その細さを嫌味なほど強調する。
「ナシを絶ってから、爪が割れやすくなった。階段を上ると息が切れるようになった。目がかすむときがある。でも、なぜかもう一度食べようと思えない」
「ほら、弊害が出てる。理屈なんてどうでもいいからさ、食べようよ、ナシ。必要な栄養はきちんと摂らなきゃ。精神的な苦しみからくるものなら、僕も病院、付き添うから」
「精神的な苦しみ、か……ううん、どうなんだろうね」
彼女は依然はっきりしない。
「そうだ、今からハンバーグでも食べに行こうよ。焼肉でもいい。なんでも奢るよ。たくさん食べよう。倒れる前に」
「焼肉……は、かなり、きついかな。ナシの生肉を見て冷静でいられる自信がないよ」
あはは、相当なわがまま言ってるよね。
彼女が笑う。僕は全く笑えない。
彼女がナシを拒むということは、僕らはこのままではいられないということだ。
ナシを食す人間と、ナシを拒む人間とでは、生活する階層が分かれている。僕らはナシを食べる国の、ナシを食べる家庭で育ったからこそこの街に暮らせているのであって、彼女がナシをやめるというのなら、彼女は近い将来それを国に申告し、ナシを食べないという方針を取っている別の街へと強制的に移送されることになる。
それだけナシを食べるか食べないかは人々を断絶させ、互いに負の感情を強く持たせる。
ナシはあくまでも食料でしかないと考える人間と、ナシは元々ヒトであったのだからそれはカニバリズムと同等だと主張する人間が、手を取り合い、優しく支え合って生きていくことは、まず不可能だった。
遥か昔。
温暖化や化学物質の蔓延で急激に減った牛、豚、鶏、その他食用肉とされる生物たち。それに代わる『肉』が、我々人間にはどうしても必要だった。我々は雑食で、草木や水だけで生き永らえるなんてことはどう足掻いても無理だった。いつしか人々は実際の『隣人』を食するようになり、本当に、人が人を食べる時代がやってきた。
凡そ今から五百年前の話だ。
人が人を食らい、そうして次第に脳が蕩けて死んでいく。そういう人間が、何万、何十万人と出て、そして我々は「安全に食べられる人間」を造る必要性を学んだ。
不特定の、様々な人種の、様々な地域の人間の遺伝子を途方もないほどの回数掛け合わせ、人間とは言い難い何かに変質させた。そうしてそれに品種改良を繰り返し、脳を極端に縮小させ、最終的に完全に失くし、同時に感情や五感を失わせ、それは繁殖機関だけを宿し、人間が食しても害がないように遺伝子を組み替えられ――そうして生まれたのが“ナシ”だ。
ナシは思考しない。ナシは自ら行動しない。ナシは人間が生み出さなければ生まれない。ナシは人間に食べられるためだけに存在し、食べられて終える。そこいらにナシ農家が増え、潤沢に供給できるようになったのは百五十年ほど前の話だったはずだ。
最初の数十年こそ、
「人間を食べるなんて」
なんて議論が繰り広げられたが、かつて大量に存在した豚や牛を凌駕するその味のよさ、百グラム数十円という手に入れやすさ、遺伝子組み換えによる効率的な栄養価の向上。
いまやナシは我々人間の食生活に欠かせない必須の食材の一つだ。
それでも、ナシを受け入れない人間はいる。
ナシとは人だったもので、人だったものとはつまり人であると同義で、人とは人間だ。ナシを食べるということは、隣人を食べること、友人を食べること、兄弟を食べること、親を食べること、自らを食べるということ。それと何一つ変わらない。
彼らはそのような主張を繰り返し、ナシを拒み、いつしかナシを食べる、食べない、この分断は人々に深い溝を作り、僕らは住む世界を互いに区別し、極力関わらないように遠く、遠くに互いを追いやった。
僕はナシに対して何の負の意識もない。
勿論、命を戴く、という意味で思うことはある。
けれど、じゃあなぜナシに対してだけ、それ以外の食糧以上に深い敬意を持たなければいけないのか? つまり、ジャガイモやニンジンや苺や小麦はナシ以下の存在だとでも言うのか? いや、それはおかしい。皆、僕ら人間が生きるための犠牲として、食料になってくれた尊い存在だ。どれに対しても同等の敬意を表し、どれに対しても必要以上の深い感情を持たない。食べる、という行為とは、それら全てを包括して、そこに在るのではないか?
彼女の顔をもう一度見る。
「ナシ、食べる気には、戻れない?」
「……どうだろうね」
「はっきりしないと、国に気づかれたら、他の都市に送還されるよ」
「ね、そうだよね。そうなんだよね。どこか遠くの街に……ああ、一体どこだろうね。ナシを食べない地域の情報って、本当、びっくりするくらい入ってこないもんね。野蛮なところだったら嫌だなあ」
彼女の口ぶりはどこまでも他人事のようで、いっそ僕がここまで真剣に向き合っているのが馬鹿馬鹿しいとすら思わせてくるようだった。
「君が今後もナシを食べないと言うのなら、僕は君と別れなければならない。僕はナシを食べることをやめる気はないんだ」
僕が言う。
彼女は、そっかあ、そうだよねえ、そうなるよねえ、と、やはり淡々と話して、それからつらつらと、
「なんかね、うまく言えないんだけど……もし自分が人間じゃなくて、ナシとして生まれていたらって、小さいころからナシを食べるたびに考える癖があって。ナシには脳がないから自分が食べられるだけの存在だとか、繁殖させられるだけの存在だとか、そういう考えを持つことはできないし、だからそもそも思考のできないナシに生まれたら、って考えること自体がナンセンスっていうか……もし私がナシに生まれていたとしても、何も考えずにただ栄養を与えられて、大きくなって、出荷されるだけって、それだけのことだっていうのはわかっていて、それは種を植えたトマトが育って大きくなって、摘果されて、出荷されるのと何の違いもないような些細なことで……でも、なんでかわからないんだけど、私はどうしても、もし自分がナシとして生まれていたらって考えることがやめられなくて……」
彼女が僕の目を見て、
「君は、ナシの肉を見て、これが自分の大切な人のお肉だったら、って、思ったことはない?」
と、そう言って、笑った。
外食には大体ナシが入っているから、と言って、彼女はディナー前に僕と別れて家に帰った。
僕は近くの大衆向けのイタリアンレストランに入って、適当にミートパスタのスパゲティと、生ハム、ワインを頼む。しばらくして届いたそれには、当たり前のごとくナシが使われている。ミートソースの挽き肉はナシの肉だし、生ハムだって塩漬けしたナシを加工したものだ。
生ハムを含み、何度か咀嚼してから赤ワインを少し含む。ナシの上質な油と赤ワインの渋みが具合よく交ざり合い、僕の口内を満たす。パスタのソースも麺とよく絡み、肉や野菜が調和した適切なおいしさを感じる。
彼女は言う。ナシの肉が大切な人だったらと思うことはないか、と。
はっきりと思う。
そんなことはない。
ナシはナシだ。野菜や果物を食べるたびに心を痛めていられないように、僕はナシを食べても何の痛みも感じない。そんな僕を、彼女は異常だとでも感じているのだろうか。
生ハムを一枚、フォークで持ち上げてみる。向こう側が透けるほど薄い肉片に、彼女の面影を見出そうとしてみる。
けれど、いつまで経ってもそこにあるのはただの一枚の肉切れで、僕にとってはそれ以上にもそれ以下にもなり得なかった。
(「おいしい隣人」24.7.10)
ここから先は
¥ 110
頂戴したお金は本やCD、食べ物など、私の心に優しいものを購入する資金にさせていただいています。皆さんありがとうございます。
