
54.クセは強い⁉️オールマイティに使える❗️コマツナを育ててみよう!🥬①
こんにちは〜ラクです😄
今日もお野菜の勉強を一緒にしていきましょう!
今日のテーマはこちら🫑
お手軽❗️どんな味付けにも使いやすい!コマツナを植えてみよう🥬
こういうテーマで話をしていきたいと思います。
前提と今日の話題です🍆
みなさん、改めまして新年度おめでとうございます🙂
世間では桜がもうとっくに散ってしまい、葉桜が咲いてと何だかスピーディーな感じがいたしますね。
4月がスタートして2週間が経ちました。
ですが、保育園、幼稚園、小学校と皆さまは新年度、何かとバタバタする毎日を過ごされて、「もう⁉️」な感じに思われてる方もいるでしょうか?
ちなみに僕もそうでした😅

こんな状況の中で、保育園やクラスの菜園計画バッチリ👌というのは中々難しいかもしれません。
「でも、何か手軽でいいから始めなきゃ💧」
こう考えている人はいますでしょうか?
今日はそんな方向けに、菜園初心者にオススメのお野菜を紹介します。
ズバリ!
菜っぱ類を育ててみよう!🤗
改めて、【菜っぱ類】って何?の方のために簡単にいうと。
葉っぱを食べるお野菜の事。
ほうれん草やニラ、よく知っているチンゲンサイや春菊などなど、葉っぱを食べる野菜は沢山ありますよね👌
よく、アブラナ科の葉っぱの事を【菜っぱ類】と呼ぶ方がいますが、
これは間違いです😯。
アブラナ科というのは、チンゲンサイや大根といった感じのお野菜です。
なので、菜っぱ類というのは葉っぱを食べる野菜全般を指し、とても広い意味で使われます。
ちなみに大根は根菜類ですが、葉っぱの部分も食べれるのは皆さんご存知ですか?
大根菜(だいこんな)と呼ばれる部分です。
「大根の葉っぱも勿体無いから捨てずに食べようね」
なんて昔はよく言われたりしました😄。
スーパーでは葉っぱが付いてないことが殆どですが、
最近では見直されて葉っぱで出すところも増えてきたようです。
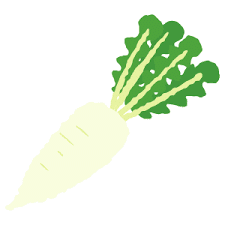
話がそれましたが、今日はそんな菜っぱ類の中でも、日本ではメジャーな【コマツナ】をご紹介します😄

みなさんコマツナっていうと、、、、
「ちょっとクセのある味だよね😌」
「嫌いな子どもも多いよね😜」
と、実は子どもウケが良いわけでもない様子💧だったりします。
実際、子どもの好きな野菜ランキングトップ10には載らず、かと言って嫌いな野菜ランキングトップ10にも載らないといった、立ち位置としては微妙なお野菜です😅

でも、僕ならこう考えます。
「好きになれる伸び代」がある野菜と言えるんじゃない?👌
僕も、お揚げとコマツナの炊いたお料理大好きです😄。

でも個人だとスルーしがちな野菜かもしれません。
ですが、みんなで育てれば
・愛着が持てたり
・みんなで一緒に食べる雰囲気の中で、楽しく記憶に残る
など

普段のお野菜を、より身近にかつ美味しく食べる絶好の機会となります。
今回菜っぱ類の中で「コマツナ」を選んだのにも、ちゃんとした理由があります。
2回に分けてご紹介しますので、ぜひ最後まで見てください。
それでは本題に入っていきましょう!🍅
○土づくりはする?
コマツナの作り方の前に、一つ述べさせて下さい。
コマツナを作るのに、土づくりは必要なのでしょうか?
え?種を撒く前に土づくりするのって「当たり前じゃない❓😯」
普通ならそうなりますよね🙂。
確かにその通りなのですが、コマツナのような菜っぱ類の場合、必ずしもそうとは限りません。
というのも、【菜っぱ類】は成長が比較的早いです。
少ない肥料分でも、作れちゃったりします。
つまり、土中にある肥料を全部使い切れない場合があるんですね😅。
ここで疑問😮。
『菜園でどんな肥料が入っているか覚えてなかった場合、果たして肥料は入れた方がいいのか?』
どうでしょう?
わかりますでしょうか?😯
僕としての答えは「NO」です。
なぜなら、後からでも肥料は足せるからです。
逆に言えば、肥料を一度入れてしまうと、取り出すことは不可能です。
なので
「何を植えようか?」
「準備が大変だ」
「時間がないよ」
そう思っている方には、
悩んでいるくらいなら【菜っぱ類をさっさと植えなはれ〜💪】

今日これがお伝えしたい事なんですね😄
だから、コマツナのような菜っぱ類は
・スコップ
・種
・水
目の前に畑や土が十分に入ったプランターがあるなら、これだけで
たった今からでもすぐに始められるよ〜👌
というわけです。
早ければ1ヶ月程度で収穫できます🥬
・早い
・便利
・美味しい
迷ったらこれをしてみては?とオススメする理由です。
それでは次に、栽培について順番に紹介していきます😄
○コマツナの育て方。
前の作物を収穫してそのままの場合は、一度表面を耕して柔らかくしてから使って下さい。

土づくりしたーいって方はこちらをご参考に👌
①種まき

こちらの写真、大きく見えますが、実際の種は本当に小さいです。
迂闊にこぼしてしまうようなら、拾うのは至難の業になってしまいますw w
ここは慎重にいきましょう😄
子どもたちと一緒にするときは、大事に大事に摘んで使うことも伝えていきましょう。
種の撒き方としては、まず前提としてこうです。
【薄く撒く。そして、土をかけたら鎮圧する】
大事な事なので、覚えてくださいね🤗
順番に解説していきましょう。
まずはこちらをご覧ください。

例えば上の図のように考えると、だいたい横幅30㎝毎に1列植えれるといったイメージです。
30㎝と言いましたが、

要はこんな幅で1列出来るよーとイメージしてもらえれば大丈夫です🙂
手順としてはこうです。
①土にスジをつける。
指の第一関節くらいの深さで一本の線を描くようにスジをつけます。

②種を1㎝間隔で撒く
「細かすぎるわ!💢無理無理❗️」なんて声も聞こえてきそうですね😅
要するに、パラパラと幅狭く撒いていきましょうって事です。
何でこんなに撒くかというと、全ての種が発芽するとは限らないから。
後の【間引き】の作業で、良いのを残していくという目的もあります。

いやいや、後が大変になるからここは頑張りましょう👌
③覆土(土をかける)
ここでポイント❗️👆
土はタネが隠れる程度で、薄ーくかけていきましょう。
理由はシンプルに、【深すぎたら出てこれない】からw w
種の厚みは【1㎜なので3㎜】と種の3倍の厚みが限界と思って下さい。
薄くかけるって事ですね🫳
これ、他のタネにも言える事なので覚えておいて下さいね😄

④鎮圧
トントンと種と土がギュッっとする感じで推していきます。
実はこれも大きなポイント。
目的は次の2点です。
・土と種を密着させて固定する。
・水もちが良くなる。
どういうことかと言うと、地面がグラグラしていると、せっかく根っこが生えても真っ直ぐ伸びにくかったりします。要するに成長が遅くなります。
また、土がしっかり密着していると、ラップで包んだ感じになって、水分が乾きにくくなります。つまり、水やりの回数が減ります。
以上で種まきの手順となります。
一つ一つポイントを押さえることで、しっかり発芽させていきましょう❗️
今日はここまで。
それでは、楽しい菜園ライフを🍅
