
1939年から始まった「国防競技」とはー明治神宮国民体育大会で採用され、その名の通り兵士の素養を高める競技でした
「国防競技」とは何ぞや、という方がほとんどでしょう。中の人も、全容を把握するまではかなり苦労しました。日中戦争中の1939(昭和14)年8月の第十回明治神宮国民体育大会に初めて採用されることとなり、陸軍戸山学校が考案したとみられます。先の見えない泥沼になった日中戦争への臣民の意識を鼓舞する狙いと、将来の精強な兵隊の育成を目的としたようです。
その内容は多岐にわたり、軍事要素を加味した複雑なものです。一方、信濃毎日新聞の関連記事、第十一回明治神宮国民体育大会画報、そして出所不明ながら国防競技の実施要領をまとめた当時のものとみられるガリ版刷りの冊子を入手したことで、ようやく説明できる程度に理解できました。以上の資料から戦時下の「国防競技」を紹介させていただきます。
◇
「国防競技」は、5つの種目からなり、種目別と総合とで順位を競いました。種目は①行軍競争②障碍通過競争③手榴弾投擲突撃④土嚢運搬継走⑤牽引競争ーとなっています。この順に説明させていただきます。

すべての種目とも、参加者は軍服か教練用の服装で、ゲートル着用。装備は軍装ですが、種目によっては剣吊り、教練銃の有無の違いもありました。
上写真は「①行軍競争」の出発直後の場面です。一番左側の選手が握っているのは刀で、指揮者であることが分かります。この種目は5人1組で隊長が刀、他の4人は執銃帯剣弾薬入れ右側1個と装備が決められていました。
距離は四千mですが、クロスカントリーのように起伏のあるコースを2列縦隊で走破し、決勝線400m手前では用意された10㍍ほどの細い綱を持ち、隊形を保って全員がそろって決勝線を超えることとされました。また、このあと装備の点検があり、出発時の服装と比べ特に乱れているものは不合格で1件につき5秒のペナルティーが与えられます。決勝戦到着時に規定の隊形に含まれていなければ落伍者とされ、順位の判定に加えられています。
つまり、早く走るだけではなく、戦闘隊形と装備を維持することも求められました。

「②障碍通過競争」の障碍は、下写真の図のように配置され、走路は120メートル、幅2・5㍍を標準としました。服装は行軍と同じです。

最初の「生籬(いけがき)」は、高さ70㌢のハードルのようなもので、飛び越します。触っても良いですが倒すとやり直し。次に「屈身障害」は長さ10㍍、高さ1㍍、幅1・5㍍の大きさに竹などで組んだものを潜り抜けます。
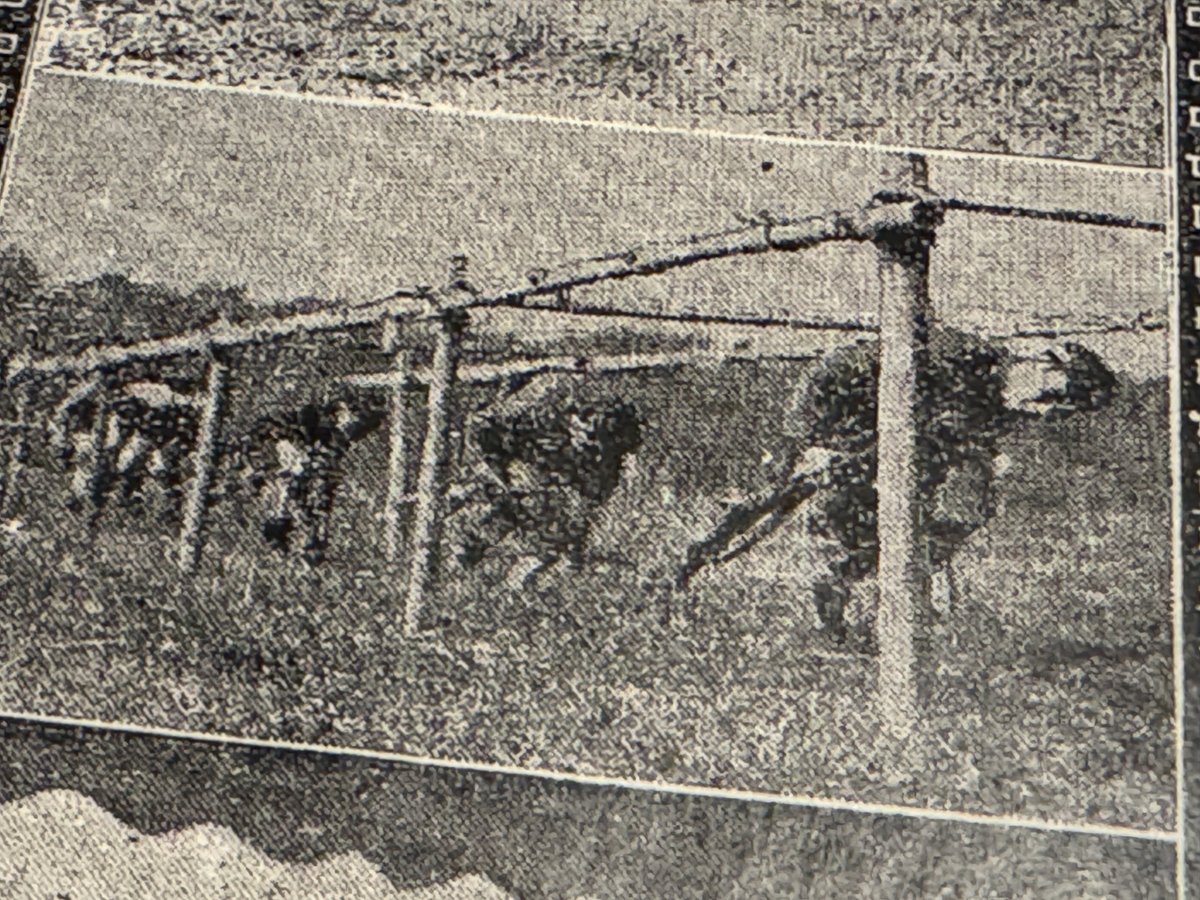
次の「跳箱」=堤防乗越は、高さ80㌢の跳箱の上に足を置いて飛び越えます。そして中国戦線でよく見られた堀のような「クリーク」を想定した「水流通過」。手前に置かれた長さ7㍍、直径8㌢以上の2本の竹を手分けして持ち、水流の両岸に見立てて高さ30—50㌢の跳箱の冠台が4㍍離して2個置いてある「水流」の障碍に1本を渡し、もう一本を手すりの要領で扱い、5人全員が落ちないようにわたるというものです。それぞれいろんな工夫をしたようです。


そして最後の障碍「圍壁乗越」。壁は高さ2㍍、上の幅は40㌢。助け合って超えるのが早いようです。全員が越えたら、長さ4㍍、直径10㌢以上の木「破壊筒」を全員で持って決勝線まで突撃する「破壊筒携行」で終了です。


「③手榴弾投擲突撃」は、一番戦闘色が濃い内容です。下図のように距離を少しずつ変えて直径5㍍の円を4個書き、決勝線には藁束を筵で巻いて縄で縛り、杭で立てた「仮標」を選手の人数分用意します。銃には着剣し、選手は540㌘の「手榴弾」を4個ずつ携行します。(体力章検定で使ったものと同じか)

競技は、出発線に全員が伏せた状態で始め、開始の合図で最初の一人が立ち上がって「手榴弾」を25㍍先の直径5㍍の円内に投げ込みます。投げたらすぐ伏せます。そうしないとペナルティー1秒が加算されます。こうして円内に2発命中するまで繰り返し、命中したら全員で次の線まで前進。これを4回繰り返します。最後の4つ目の円内に2発目が命中したところで、隊長が「突撃、進め!」と号令をかけて、全員が決勝線の先の「仮標」に銃剣突撃をします。これで終了、「手榴弾」を拾い集めて出発線に戻ります。
もし全員が「手榴弾」を投げ終わってもまだ投擲する円が残っている場合は、投げ終わった地点からやはり突撃して終了します。目標に命中した数の多い組から速さの順で順位を決めます。


「④土嚢運搬継走」は、その名の通りで、袋に砂30㌔を詰めた土嚢を担いで100㍍走って、次の走者に渡し、合わせて500㍍の速さを競います。

ようやく最後の「⑤牽引競争」です。距離は120㍍とし、1組5名で40㍍を引きます。これだけは5人3組で1チームを構成します。牽引するのは30㌔の土嚢6個を幅65㌢、長さ1.2㍍の厚板製の台(重量約20㌔)に載せ、長さ7㍍、直径約3㌢の引き綱で引きます。出発時の隊形は下図のように、一列縦隊とします。

競技の説明を見ますと、次の組は指揮者の号令で待機姿勢に入り、12㍍以内で引き継ぐことなっています。

これを持ちまして、国防競技の終了です。ほかにも細部にわたっていろんな点検部分がありましたが、冗長になるため割愛しました。
◇
以上、国防競技を紹介しましたが、この競技が1939(昭和14)年という点が重要かと思います。この年から、それまで入学は自由だった青年学校が義務化されており、小学校を卒業した青年男子は全員、教練をするようになったのです。このため、競技でも青年団、青年学校、中等学校などの単位でチームを組み、参加しています。
示してきた通り、戦闘の基本動作を巧みに取り入れ、持久力や瞬発力も必要な内容です。明らかに、スポーツのように見えて軍事教練にほかなりませんでした。教育の場に、こうしたものはないのが一番です。軍隊教育ではなく、身体機能向上の運動であり続けてほしいと切に願います。
いいなと思ったら応援しよう!

