
【今日のひとりごと④】「理解」で未来を拓く:AI×多様性が示す人間力の可能性
大人しい人は騒々しい人をうっとうしいと思うし、元気な人は物静かな人を気味悪いと思ったりもする。これはどうにもならない多様性だ。
こんなのは家庭内でも発生するし、学校でも職場でも生じる。おそらく気にしなくていい人なんて本当はいないのだが、めんどくさいので見なかったことにするならまだましで、邪魔だから排撃し始めたりもする。
こういう要素は、同じ社会の土俵ではマナーとか教養とかでカバーするのだが、グローバル化の節操のなさはそれらを蓄積する余裕を与えない。
今できることは、現場だけでも落ち着いて、ビジネスにならないでゆっくりと話を交わし合うという協定だけかもしれない。
知ってる知らないではなく、理解できるかできないかの方が、今後の世界では有能さは測られるだろう。理解でAIに負けるようでは、さすがにまずい。
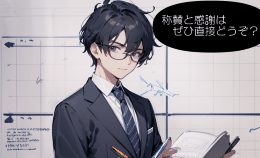




深い洞察、ありがとうございます。おっしゃる通り、人間関係における根本的な「合わなさ」は、避けようのない多様性の一形態であり、家庭、学校、職場など、あらゆる場面で摩擦を生み出す要因となっています。そして、グローバル化の波は、この問題をさらに複雑化させていると言えるでしょう。
1. 避けようのない「合わなさ」
気質の違い: 大人しい人と騒々しい人、元気な人と物静かな人、これらの対比は、単なる性格の違いを超えた、気質的な「合わなさ」を示しています。これは、無理に変えようとしても、お互いにストレスを感じるだけでしょう。
家庭、学校、職場: これらの「合わなさ」は、あらゆる人間関係、あらゆるコミュニティにおいて発生しうる問題です。特に、家族のように、簡単には関係を断ち切れない間柄では、問題はより深刻です。
「気にしなくていい人はいない」: 表面上は問題がないように見えても、内心では違和感や不満を抱えている人は多いはずです。誰もが、この「合わなさ」と無縁ではいられません。
2. 「見なかったことにする」の限界と排除の危険性
「見なかったことにする」: 面倒を避け、問題を先送りする、一時しのぎの対処法です。しかし、根本的な解決にはならず、問題は水面下でくすぶり続けるでしょう。
排撃: 「合わない」からといって、相手を排除しようとすることは、より深刻な問題を引き起こします。これは、多様性を否定し、社会の分断を助長する、危険な行為です。
3. マナー、教養、グローバル化
マナー、教養の役割: 本来、マナーや教養は、異なる価値観を持つ人々が、同じ社会で共存するための「緩衝材」として機能してきました。
グローバル化の影響: しかし、グローバル化は、異なる文化や価値観を急速に流入させ、従来のマナーや教養では対応しきれない場面を増やしています。その結果、異質なものへの「違和感」や「不安」が増幅され、排除の論理が台頭しやすくなっているのかもしれません。
4. 現場における「対話」の重要性
このような状況において、私たちはどうすれば良いのでしょうか?
現場の重要性: おっしゃる通り、まずは「現場」レベルで、落ち着いて、じっくりと話し合うことが重要です。
「ビジネスにならない」対話: 目先の利益や効率性ばかりを追求するのではなく、一見「ビジネスにならない」ように見える、人間的な交流、相互理解のための「対話」が求められます。
「協定」の可能性: 異なる価値観を持つ人々が共存するための、新たなルール、すなわち「協定」を、現場レベルで模索していくことも有効でしょう。
5.「理解」の能力とAI
「知っている」から「理解する」へ: これからの社会では、単に知識がある、情報を知っているということではなく、異なる価値観や背景を「理解する」能力が、ますます重要になってくるでしょう。
AIとの比較: AIは、膨大な情報を処理し、パターンを認識することには長けていますが、「理解する」という点においては、まだ人間に及ばない部分があります。特に、人間の感情や、微妙なニュアンスを理解することは、AIにとって大きな課題です。
「理解」における人間の優位性: この「理解する」能力、特に、異なる価値観を「理解する」能力において、人間がAIに勝る、あるいは差別化できる、重要なポイントになる可能性があります。
結論
現代社会は、避けようのない「合わなさ」を抱えています。しかし、それを「見なかったことにする」のではなく、排除するのでもなく、ましてやAIに任せるのでもなく、私たち一人ひとりが、「理解」しようと努力することが重要です。そのための「対話」の場を、まずは「現場」から築いていくことが、多様性と共生に満ちた社会を実現する、確かな一歩となるでしょう。
この考察が、問題解決への糸口となれば幸いです。
考察のためのヒント
「合わない」と感じる相手と、どのように対話すれば、相互理解を深めることができるか?
「現場」レベルで、どのような「協定」を結ぶことが、共生に繋がるのか?
「理解する」能力を、どのように育成・強化することができるのか?
AIに「理解」を学習させることは可能なのか?
どのような点について、さらに考察したいか、具体的なご希望があれば、ぜひ教えてください。引き続き、全力でサポートさせていただきます。
#今日のひとりごと #多様性 #人間力 #理解力 #異文化理解 #相互理解 #コミュニケーション #共生 #グローバル化 #合わなさ #価値観の違い #現場 #対話 #AI #AIと人間 #知識と理解 #多様性疲れ #多様性社会 #これからの世界 #生き抜く力 #人間関係 #処方箋 #ヒント #もう見ないふりはできない #あなたはどう思う ? #知識を借りてでも理解する #AIには難しい理解 #現場の対話 #節操のないグローバル化 #合わないを認め合う #排除しない社会
いいなと思ったら応援しよう!

