
「社会的共通資本を考える」後記 シリーズ1第2回
第2回「『自動車の社会的費用』を読む」後記
社会的共通資本を考える シリーズについて
京都大学社会的共通資本と未来寄附研究部門では、宇沢弘文が提唱した社会的共通資本を研究し、社会的共通資本の実装可能性を検討しています。2023年2月~「社会的共通資本を考える シリーズ」と題して、社会的共通資本をより深く理解し、実践につなげるために、宇沢弘文の著書や社会的共通資本に関連する本を様々な角度から読み込んでいくイベントを開始しました。
シリーズ第一弾は『自動車の社会的費用』岩波新書が題材です。本書は、宇沢弘文の初の日本語の単著です。人の命といった大切なものをお金に換算しない経済学のはじまりといっても過言ではないこの社会的共通資本の考えの基盤となったこの本を読みました。
3月28日(火)に京都アカデミアフォーラムで「社会的共通資本を考える」の第一シリーズ「『自動車の社会的費用』を読む」の第2回が行われました。今回は、帝京大学経済学部教授の小島寛之さんから『自動車の社会的費用』について講演していただき、社会的共通資本に関する議論を深めました。
ゲスト:小島寛之
帝京大学経済学部教授 東京大学理学部数学科卒業。同大学院経済学研究科博士課程単位取得退学。経済学博士。数学エッセイスト。宇沢弘文の薫陶を受け、経済学の道に進む。著書に、『宇沢弘文の数学』青土社、『使える!経済学の考え方』筑摩新書、『確率的発想法』NHKブックス、『暗号通貨の経済学』講談社選書メチエなど多数。
第2回「『自動車の社会的費用』を読む」後記内容
小島さんは宇沢の「最後の弟子」である。講演の冒頭では、小島さんから宇沢弘文の経歴や、小島さんと宇沢の関係性についてお話しがあった。小島さん自身は経済学部所属でなかったものの、世田谷区の市民講座などを通じて宇沢から教えを受けており、宇沢の最後の講義も聴講していた。それが「最後の弟子」と呼ばれる所以である。このように宇沢との関係が深い小島さんの立場から、個人的な体験も交えながら『自動車の社会的費用』の解釈が提示された。

『自動車の社会的費用』は、宇沢の代表作である。日本の基幹産業であるにもかかわらず、自動車産業を批判的に考察した。この批判的な態度が注目されがちである。しかし、『自動車の社会的費用』は自動車産業の考察にとどまらない。経済学理論のあり方それ自体を自省し、新たな経済学像を提示する書物であった。このような特徴を踏まえて、小島さんは講演のなかで自動車の社会的費用に関する宇沢の指摘を起点に、宇沢の新古典派経済学に対する批判、さらには宇沢が提示した社会的共通資本の理論について解説した。
「自動車政策は間違っている」
まず、宇沢の自動車産業・政策に対する批判から見ていく。宇沢は1970年に『エコノミスト』に「自動車政策は間違っている」という論考を寄稿している。『自動車の社会的費用』出版の4年前だが、すでに構想が出来上がっていたことが読み取れる。宇沢は、この寄稿で自動車がもつ二重のインフレーションを指摘していた。第一の意味は、社会的共通資本が不足することで需要に供給が追いつかなくなることで引き起こされるインフレーションである。これは一般的に指摘されるインフレーションである。一方で、自動車が普及すると、環境汚染が生じる。この影響は価格に表れないものの、生活の質を低下させる。これが宇沢の指摘した影のインフレーションである。宇沢は、『自動車の社会的費用』でも影のインフレーションを論じている。以下、『自動車の社会的費用』の章別に宇沢の議論を追っていこう。
まえがき
宇沢が『自動車の社会的費用』を執筆した1970年代前半は交通事故が多発していた。子どもたちが慣れきってしまうほど、交通事故は1970年代前半ではありふれた風景だった。この時期子どもだった小島さん自身も、交通事故を日常の一部として実感していたという。それほど、自動車が人命や健康を日常的に害していたのだった。
序章
宇沢はミシャンのピストロジーという概念を参照する。ピストルの販売が自由化されたとする。ピストルが普及すると、暴発事故による怪我人が増えていく。すると、医療サービスや保険への需要が高まる。その結果GDPが増加するが、この状態は社会的に望ましい状態とは言えない。ミシャンは、こうした状況をピストロジーと呼んだ。宇沢は自動車もピストロジーのアナロジーで捉える。
自動車が人々の生活に負の影響を与えうることは当時も認識されており、交通政策においてもその負の影響が考慮されていた。そこで使われていたのが、コスト・ベネフィット分析である。例えば、所得水準が高い地域Aと所得水準が低い地域Bがあるとする。政府は、地域Aか地域Bのどちらかに道路を作ることを考えている。道路が社会全体にもたらすベネフィットはどちらの場合も同じである。一方で、コストに関しては異なる。道路が敷かれた地域では、排ガスによる大気汚染でコストが発生する。同じ汚染であっても、主観的な損失(コスト)が地域Aの方が地域Bよりも大きい。地域Aの方が元の生活水準が高いからだ。そのため、コスト・ベネフィット分析に基づくと、地域Aではなく地域Bに道路が敷かれることになる。その結果、地域Bの生活水準はさらに低下してしまう。宇沢は、このような結論を導いてしまうコスト・ベネフィット分析を批判する。
宇沢は、コスト・ベネフィット分析を批判するにあたって、その根本にある新古典派経済学の仮定から疑問を呈示する。新古典派経済学は、生産手段がすべて私有されるような分権的市場を前提とする。しかし、現実社会をみると、道路のような社会資源は私有されていない。このような資源を新古典派経済学では上手く捉えられない。さらに、新古典派経済学では、人間が単なる労働力を提供する生産要素として描かれる。そのため、人間がもつ社会的・文化的・歴史的な側面はすべて捨象される。新古典派経済学は、こうした公理をもとにした演繹で市場均衡のプロセスを議論する理論体系である。当時の経済学においては、新古典派に匹敵しうるような理論体系が存在していなかった。
第1章
道路建設が加速するきっかけとなったのがアメリカで1930年代からはじまったニューディール政策であった。ニューディール政策は、世界的な不況に対応するための公共事業であり、ダムや道路など大規模なインフラ整備が実施された。ニューディール政策は、ケインズ経済学の枠組みで論じられてきた。宇沢は、このケインズ経済学についてアンビバレントな評価を下している。ケインズは、資本主義が慢性的な不況をもたらしうるということを論じた。宇沢は、この点に関してケインズを経済学に新しいパラダイムを持ち込んだものとして評価している。一方で、宇沢はケインズが環境を顧みない公共政策を肯定してしまった側面も指摘している。
第2章
宇沢は本章で自動車が道路にどのような影響を与えたかを論じている。その際、ルドルフスキーの『人間のための街路』を参照している。自動車が次々と開発されたことで、道路上の交通手段は路面電車から車へと変化した。かつての街路は劇場、露店、低所得者の生活場所など多様な機能を持っていた。しかし、自動車の普及によって、街路は自動車のためだけのものになってしまった。ルドルフスキーは、自動車の普及で社会が低所得者、老人、子どもにとって住みづらくなったことを指摘する。『自動車の社会的費用』が執筆された当時の日本では、多くの子どもが交通事故によって命を落とし、また排ガスによる大気汚染も深刻化していた。
第3章
宇沢は外部不経済の観点から自動車の社会的費用を考察する。経済を成り立たせる消費者や企業はお互いに影響を与え合っている。経済主体は生産や消費といった経済活動を行うが、それらの活動はまず市場価格の変化を通じてほかの経済主体に影響を及ぼす。しかし、経済活動が外部に影響をもたらす経路はこれだけではない。市場の価格変化を経由せずに外部に影響を及ぼすことがある。特に環境問題や交通事故などは、この一部である。このように市場以外の経路を通じてほかの経済主体に負の影響を与える現象を外部不経済と呼ぶ。
外部不経済に関しては、ピグーの議論が有名である。ピグーは鉄道がもたらす外部不経済を論じた。鉄道は乗客との間の運賃取引を通じた影響をもたらす。それ以外にも、車輪と線路の間の摩擦によって発生する火花で山火事を起こしうる。この山火事は外部不経済の一例だ。この負の影響は市場価格などに反映されないため、鉄道会社は自社の費用として捉えない。このような費用を経済主体の私的な費用として内部化させるのがピグー税である。自動車による大気汚染や交通事故も同様である。
自動車の社会的費用を計測するには、こうした外部不経済の規模を測定する必要がある。人命・健康への被害、環境破壊といった社会的費用は、もちろん直接的に費用として観測できない。そこで、当時主流だったのがホフマン方式という測定方法である。ある人が交通事故で死亡したとする。その人が仮に事故に遭っていなければ、働いて稼ぐことができていたはずだ。ホフマン方式では、事故時点で予想される余命と期待所得を掛け合わせることで交通事故がなければ稼いでいたであろう所得を測定する(実際は割引現在価値として測られる)。このようにして測定された額を事故の賠償に用いる。しかし、宇沢はこのホフマン方式の測定を批判した。ホフマン方式において、人間は生産要素としてしか見られていない。そのため、余命が短い老人や病人は、価値が極めて小さい人間として扱われてしまう。宇沢はこのような非人道性を指摘する。
その他に、限界的社会費用から自動車の社会的費用を測定する方法もある。限界費用とは、ある状態から微小に生産量を増やした時に追加的に発生する費用のことを指す。自動車の場合、その時点の台数からさらに1台増やしたときに、どれだけ費用が増えるかが限界的費用である。具体的には、前年度からの被害の増加分を前年度からの自動車台数の増加分で割ることで、限界費用を計算できる。しかし、宇沢はこの測定方法も批判する。人命・健康・自然環境は不可逆的なものであり、金銭によって回復しうるものではない。理論的に計測可能なだけでなく、望ましい都市構造の設計に有用な尺度を作る必要があるのだ。
このように、自動車の社会的費用の測定方法には問題がある。宇沢は、これらの問題を新古典派の仮定から再検討する。そもそも、新古典派は、あらゆる生産手段の私有制を仮定している。社会的共通資本を考える場合、この私有制の仮定は満たされない。その結果、新古典派の枠組みで社会的共通資本を考察すると、違和感のある結論が導かれてしまう。新古典派の有名な定理として、コースの定理がある。前述の通り、ピグー税で社会的費用を私的費用として内部化させることで、市場取引での最適供給量と社会的な最適供給量が一致する。しかし、(単純化して言うと)コースの定理は、ピグー税に依らない当事者同士での解決が可能であることを主張する。川の上流に工場があり、その工場からの産業排水が下流の漁民に損害を与えている例を考えてみよう。コースの定理によれば、工場が漁民に賠償金を支払ったうえで自由に生産する場合と、漁民が工場に補償金を支払って生産を控えさせる場合で、どちらも同じ社会的最適点を実現できる。しかし、後者の場合は違和感がある。宇沢はこの違和感の原因として、新古典派が仮定する生産資源の完全私有制を指摘する。川の汚染問題の例でいうと、新古典派は汚染問題を川の所有権の問題に還元している。川が本来漁民の所有物であるなら、工場が賠償金を支払うべきである。一方で、川が本来工場の所有物であるなら、漁民が補償金を支払うべきである。このように、新古典派の議論では、その資源が誰の所有物であるのかを基準に考えることになる。しかし、川は実際誰の私有物でもない。特定の所有者が存在しない社会的共通資本である。
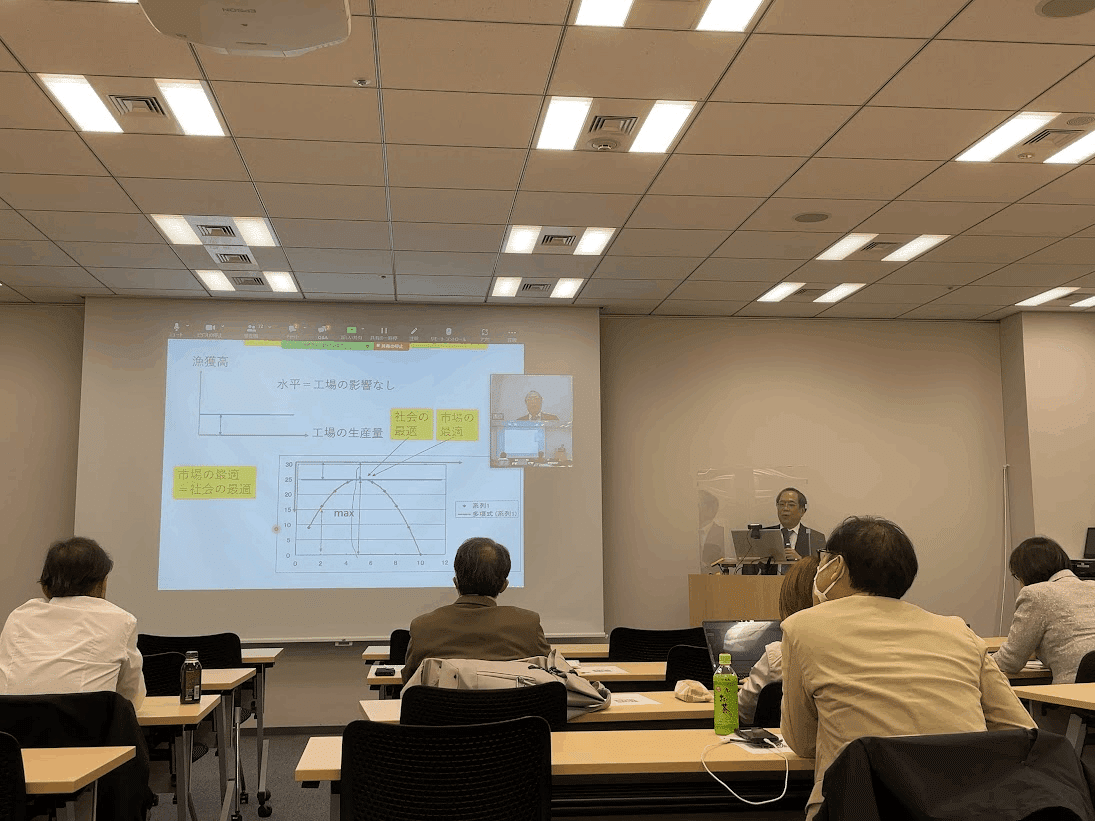
社会的共通資本の観点からは、自動車の社会的費用はどのように計算できるだろうか。自動車が走行していなければ、人々は道路で歩行の自由を享受できていたはずである。しかし、自動車が道路を走行することで、歩行者は交通事故の危険に晒されたり、大気汚染に苦しんだりしている。そこで、宇沢は自動車の社会的費用を自動車の無公害化のためにどれだけの投資が必要かを計算する。自動車を無公害化して人々が歩行の自由を取り戻すためには、道路を拡幅したり、緩衝地域を設置したり、街路樹を植えたりする必要がある。このような投資に必要な総額を自動車1台あたりの額に換算して社会的費用として捉えている。
小島さんは、宇沢の計算方法の背景には「過去の最適化」という考え方があることを指摘した。従来の経済学において、経済主体はこれから先の未来の利益を最適化しようとする。たとえば、ある時点での行動を選択するとき、その行動によって将来健康でいられるか、病気になるかを考慮して利益が大きい方の行動を選択する。これは、経済学の典型的な考え方だ。しかし、小島さんは、人間が将来だけでなく過去も最適化しようとしている可能性を提起した。自動車の例であれば、現時点で路上に自動車が行き交っているものの、仮に自動車走行が認められていなければ、人々は自由に路上を歩けていただろう。また、排ガスによる大気汚染も起こらず、快適な空気の中で生活できていただろう。このように、過去の選択がもし違っていたら実現したであろう世界を想定する。小島さんは、宇沢の計算する自動車の社会的費用の基盤にそうした「ありえたはずの別の世界」が想定されていることを論じた。

質疑応答
講演終了後、小島さんと会場参加者との間で質疑応答・討論が行われた。たとえば、経済学における倫理の扱い方について議論になった。宇沢の『自動車の社会的費用』では、「どのような社会が人間的な生活に寄与するものか」という倫理の問題が扱われている。しかし、今日の経済学において、倫理の問題は経済学の対象外として避けられる傾向にある。この理由を学問と価値観の関係性にも触れながら、現代経済学の構造を論じた。
社会的共通資本と未来寄附研究部門の取り組みをご支援いただく窓口として「人と社会の未来研究院基金」を設けています。
特定の一民間企業からの寄附で運営されることが多い通例の寄附講座とは異なり、様々なセクターから参加をいただくことを目指しております。https://sccf.ifohs.kyoto-u.ac.jp
また、社会的共通資本がなぜ今必要なのか、Beyond Capitalismとして今後どのように社会的共通資本と未来を拡張していくのか、企業に求めることやアカデミアとしてのあり方も再考する各種イベントを実施しております。
https://sccf-kyoto.peatix.com

