
短時間で相手に理解を求める場面で有用な『SDS法』

『SDS法』を解説したPDFデータを無料でプレゼント!
お申込みは上の画像をクリック!
話の主旨を最初に伝え、その後詳細を説明し、最後に要点をまとめることで、聞き手に理解を促す『SDS法』。メリットとデメリット、ほかのフレームワークとの違い、効果を発揮するシーン、ビジネスシーンでの活用例などについて解説しています。
■『SDS法』とは?

『SDS法』(エスディーエス法)とは、要件→詳細→要件(繰り返す)の流れで、話の主旨を最初に伝え、その後詳細を説明し、最後に要点をまとめることで、聞き手に理解を促すフレームワークです。
特に「話がまとまらない」「言いたいことが伝わらない」とお悩みの人にとって有用な、聞き手が全体像をイメージしやすくなる汎用性の高い手法です。
◆SDS法を構成する3つの要素

このSDS法は、以下の3つの要素で構成されています。
S=Summary(要点)
D=Details(詳細)
S=Summary(要点を繰り返す)
つまり、①伝えたい「要点」を最初に述べて、②その要点の「詳細」を伝え、③最後に「要点」を繰り返して念押しする、という一貫性を有する手法です。
短い時間で端的に相手に理解を促したい時に適しています。
■『SDS法』のメリット

SDS法には、以下のメリットがあります。
◆「要点」を絞ることでスピーディに伝えられる

まず挙げられるメリットとしては、要点を絞ってスピーディに伝えられる点です。
最初に話の「要点」を伝え、続いて詳細を説明し、最後に再び「要点」を述べるという、3つの少ない要素であるため、短い時間で伝えられます。
◆話が伝わりやすい

「要点→詳細→要点」の流れで伝えることから、聞き手・対象は集中力を持続したまま情報を受け取ることができ、内容を理解しやすくなります。
■『SDS法』のデメリット
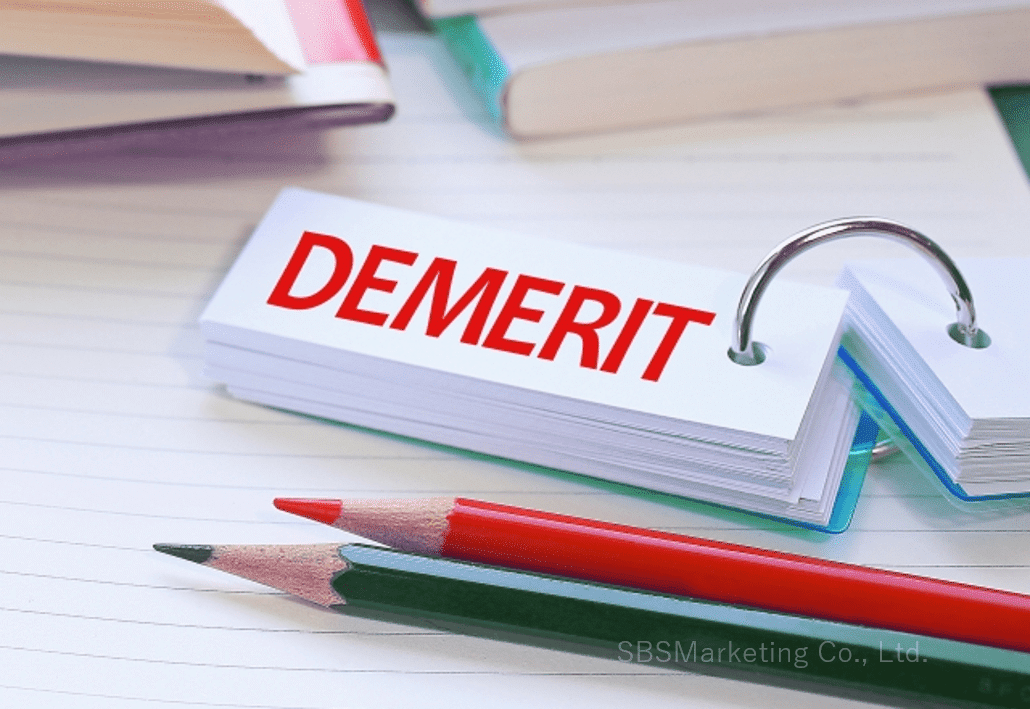
逆に、デメリットとしては、以下の点が挙げられます。
◆詳しい情報を伝えるのには不向き

このSDS法の「D」で詳細を相手に伝えるとはいえ、短い時間で事実をわかりやすく伝える特徴がある手法であるため、詳しい情報を伝達するには不向きと言えます。
◆意見や主張するシーンには向かない

『SDS法』というフレームワークには「主張」する要素が含まれていません。
そのため、下述の『PREP法』や『DESC法』のように、訴えたい意見や主張があるシーンの活用には向いていません。
■ほかのフレームワークとの違い

使い分けが曖昧になりがちなフレームワークとして、SDS法のほかに『PREP法』や『DESC法』があります。
比較すると最もシンプルで汎用性が高いのが『SDS法』です。それぞれのフレームワークの詳細は以下の通りです。
◆『PREP法』

このPREP法は、以下の4つの要素で構成されています。
P=Point(結論)
R=Reason(理由)
E=Example(具体例)
P=Point(結論を繰り返す)
つまり、①結論を最初に述べて、②その理由と③それを裏付ける例を挙げ、④最後に結論を繰り返して念押しする、という手法です。
最初と最後に「結論」を示す、「理由」と「具体例」を示すことから、『SDS法』と比較して、より納得感・説得力を得られやすい点が違いと言えます。
◆『DESC法』

DESC法は、以下の4つの要素で構成されています。
D=Describe(模写)
E=Express(説明)
S=Suggest(提案)
C=Choose(選択)
DESC法は、相手の状況や言動を示し、それに対する客観的な説明を行い、解決策としてのアイデアを複数提案し、その中から選択・行動を促す際に有用なフレームワークです。
物事を端的に示す『SDS法』とは異なり、『DESC法』は自身の意見を主張しつつ、相手へ行動変容を促す点が違いと言えます。
↓
この続きでは、『SDS法』が効果を発揮するシーン、
ビジネスシーンでの活用例について解説しています。

『SDS法』を解説したPDFデータを無料でプレゼント!
お申込みは上の画像をクリック!

株式会社SBSマーケティングでは、中小規模企業様、個人事業主・フリーランス様向けに集客や販売促進、マーケティングに関連したコンサルティングサービスをご提供しております。


『心理テクニック』を販売中!
■中堅・小規模企業様向けサービスはこちら
■個人事業主様・フリーランス様向けサービスはこちら
ご興味ありましたら、まずはお問い合わせください。

株式会社SBSマーケティング コンテンツマーケターより。
