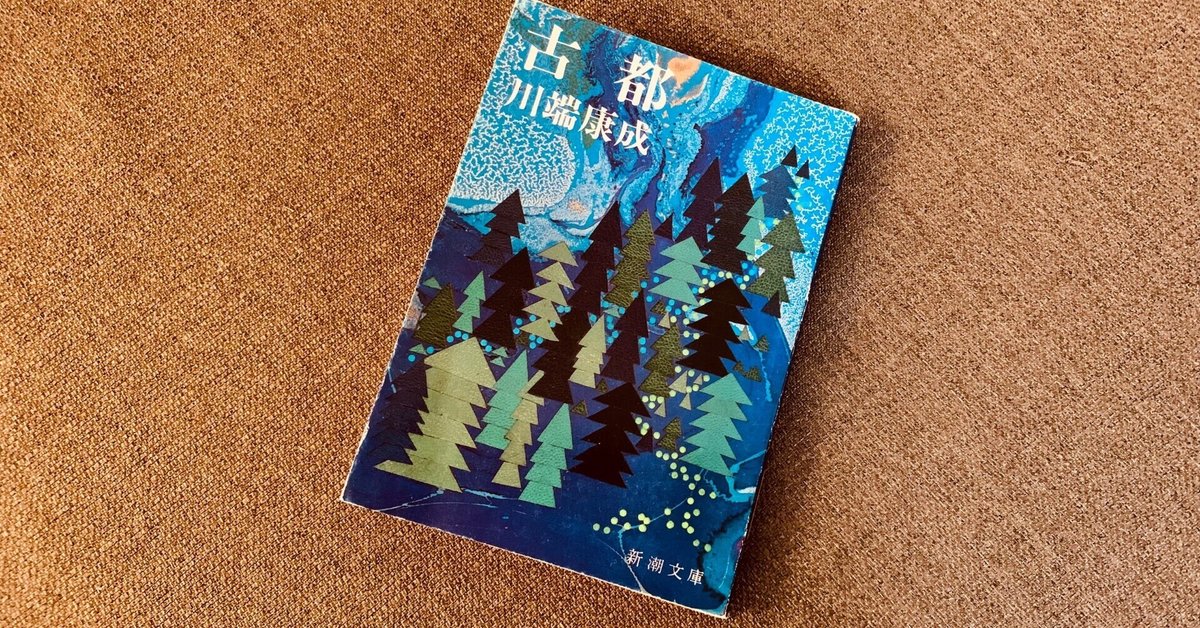
【読書録】『古都』川端康成
今日ご紹介する本は、日本の誇るノーベル賞作家・川端康成の小説『古都』。昭和36年から37年にかけて、朝日新聞に連載された長編小説だ。私が持っているのは、何十年も前から実家にあった、古い新潮文庫版(昭和60年、47刷)。これを久しぶりに読んでみた。
タイトルの「古都」とは、京都のことだ。ストーリーとしては、京都を舞台とする、商家の若いお嬢さんにまつわるお話(ネタバレ防止のため、あらすじは書きません)なのだが、とにかく、美しい小説だ。
京都の名所、風景、花や植物、祭り、食材や料理。それらが、春夏秋冬すべての季節にわたって、鮮やかに描かれている。着物や帯の柄にまつわるやり取りや、京言葉などは、とても優雅だ。そういった京都の風物は、現代から見ると浮世離れしているようでありながら、日本人のDNAが刺激されるのか、どこか懐かしい感じがする。
この小説には、難解な言葉は全く出てこない。きわめて平易な日本語を使っている。登場人物の会話や、風景や風物の描写だけで、登場人物の心の動きをありありと連想させる表現力たるや、圧倒的だ。その時代、京都のその場所で展開する物語を、実際に目の前で見ているような錯覚に陥る。
特に、「庭のもみじの木の幹のくぼみに生えている、2株のすみれの花」については、繰り返し出てきて、主人公千重子の感情の機微とシンクロする。
もみじの古木の幹に、すみれの花がひらいたのを、千重子は見つけた。
「ああ、今年も咲いた」と、千重子は春のやさしさに出会った。
大きく曲がる少し下のあたり、幹に小さいくぼみが二つあるらしく、そのくぼみそれぞれに、すみれが生えているのだ。そして春ごとに花をつけるのだ。千重子がものごころつくころから、この樹上二株のすみれはあった。
上のすみれと下のすみれは、一尺ほど離れている。年ごろになった千重子は、
「上のすみれと下のすみれは、会うことがあるのかしら。おたがいに知っているのかしら」と、思ってみたりする。
(・・・)庭を低く飛んでいた、小さく白い蝶のむれが、もみじの幹からすみれの花の近くに舞って来た。もみじもやや赤く小さい若芽をひらこうとするところで、その蝶たちの舞の白はあざやかだった。二株のすみれの葉と花も、もみじの幹の新しい青色のこけに、ほのかな影をうつしていた。
花ぐもりぎみの、やわらかい春の日であった。
「そのもみじみたいな強さ、千重子には……」と、声にかなしみがふくまれて、「もみじの幹のくぼみに生えてる、すみれくらいのもんどすやろ。あ、すみれの花が、いつのまにや、なくなってしもた」
「ほんに……。来年の春は、きっとまた咲きまっせ」と、母は言った。
今夜は、中庭のキリシタン灯籠にも、火が入れてある。もみじの大木のくぼみの二株のすみれも、ほのかに見える。
花はもうないが、上と下の、すみれの小さい株は、千重子と苗子であろうか。二株のすみれは会うこともなさそうに見えていたが、今夜、会ったのだろうか。千重子は二株のすみれを、ほの明かりに見ていると、また、涙ぐんできそうである。
千重子は奥の座敷に、炭火をととのえて、あたりを見まわした。狭い庭もながめた。もみじの大木の苔は、まだ、青々としているが、幹に宿った、二株のすみれの葉は、薄黄ばんでいた。
「兄さん、もみじの幹の、すみれを見てみ」と、真一は指さして、「二株、あるやろ。あの二株のすみれを、千重子さんは、なん年か前から、可愛い恋人と、見といやしたんやと……。近くにいながら、決していっしょになることは出来ん……。」
「ふうん」
「女の子て、可愛いことを、考えはるもんやね」
「いややわあ、恥ずかしいやないの、真一さん」千重子は立て終わった茶碗を、竜助の前に出す手が、こころもち、ふるえた。
**********
ところで、川端のあとがき(昭和37年6月)は、必読だ。日本画家の東山魁夷が、本作品に登場する北山杉を描いた「冬の花」という作品を、川端の文化勲章のお祝いに贈ったこと。川端がその作品を本人の許しなく口絵としたこと。川端がこの作品を睡眠薬を使って書き、「眠り薬に酔って、うつつないありさまで」書いた「異常な所産」と表現していること。読み返すのが不安で、出版もためらっていたこと。校正にかなり骨を折ったこと。京言葉は地元の人に監修してもらったこと。こういったエピソードから、舞台裏を覗くことができたような気がして、この隙のない完成された文学作品が、少し身近に思えてきた。
ちなみに、東山の「冬の花」という作品は、このような絵だ。以下の2つのサイトに紹介されているのを見つけた。

http://suesue201.blog64.fc2.com/blog-entry-1013.html
そして、私の持っている文庫版に収載されている山本健吉(文芸評論家)の解説も、また良かった。特に次のくだりは、この作品の特徴をとてもよく表現している。
かつて馬琴の八犬伝が、舞台を多く江戸近郊に取り、そのことが江戸の読者たちの興味を搔き立てたように、これも京都に住む人、京都を知る人に、既知の風物に作中で出会うという快感を、ふんだんに味わわせてくれる。これはある意味では、地理的、風土的小説と言ってもよい。そして作者は、美しいヒロインを、あるいはヒロイン姉妹を描こうとしたのか、京都の風物を描こうとしたのか、どちらが主で、どちらが従か、実はよく分からないのだ。
この美しい一卵性双生児の姉妹の交わりがたい運命を描くのに、京都の風土が必要だったのか。あるいは逆に、京都の風土、風物の引き立て役としてこの二人の姉妹はあるのか。私の考えは、どちらかというと、後者のほうに傾いている。
**********
この令和の日本は、何事につけグローバル化の影響を受け続けているし、インバウンド真っ盛りで、外国人向けのサービスなども充実してきた。それは良いことではあるが、そのために、この作品の世界観のような、情緒豊かな古き良き京都の良さ、日本の良さが失われないように願うばかりだ。
読了して、すぐにでも京都に行きたくなった。また、老後に、京都に住んでみたいとさえ思った。京都が好きな方、京都への旅行を検討されている方には、特におすすめだ。
ご参考になれば幸いです!
私の他の読書録の記事へは、以下のリンク集からどうぞ!
この記事が参加している募集
サポートをいただきましたら、他のnoterさんへのサポートの原資にしたいと思います。
