
調味料は味と健康の基本〜上手に使おう味付けの基本『さ・し・す・せ・そ』
※noteでは漢方的養生コラム毎日配信しております。
一つ100円の有料記事が月額500円ですべて読める定期購読オンラインマガジン『早川コータの漢方Labo』がとってもお得です。
☆定期購読の方には特別特典として早川コータが開催するオンライン漢方養生セミナー(通常参加費1回1000円・税込)に無料でご参加いただけます。
今回は無料記事として配信させていただいておりますのでぜひ最後まで御覧ください。
*************************************
どうも!
先日友達が山梨に来てくれたので和食を食べに言ってきたのですが、そこで始めて『クエ』を食べて美味しくて死にそうになった
さわたや薬房の早川です。
#クエ凄いなぁ

クエをしゃぶしゃぶで食べたり、頬肉は並べて煮込んで、お刺身も食べましたが流石に貴重な素材だけあってめちゃくちゃ美味しかったです。

(Twitterの音声配信番組『癒やしていいとも』などを一緒にやってる相方のやすおたんと一緒に)
普段は粗食に耐えているのですが、たまには高級な和食を食べるのも良いですね。
今回はそんな美味しいお料理を食べたので、食養生の中でも重要な『味付け』についてお届けしたいと思います。
調味料は味と健康の基本〜上手に使おう味付けの基本『さ・し・す・せ・そ』
というテーマでお届けしたいと思います。
【どんな良い素材も調味料で変わる】
今回の特集は食の基本である「調味料」についてお届けしたいと思います。
前述の和食を食べた際、本当に色々な味付けを巧みに使い分けており、改めてプロの味付けの素晴らしさに感動したのですが
どんな良い素材でも料理次第で当然ですがその価値が変わります。

(先付けですが、これだけでもいろんな味を楽しめます。和食すごい)
健康的な食材も味付けなどで使う調味料の使用方法を間違えると不健康な食事になってしまうから不思議ですよね。
調味料を使用する場合、煮物などに調味料を加える順序としてよく使われる言葉が「さしすせそ」です。
「さ」は砂糖あるいは酒/砂糖です。
「し」は塩。
「す」はお酢。
「せ」は醤油(昔の仮名遣いの「せうゆ(しょうゆ)」に由来します。
「そ」は味噌の「そ」を指しています。(このあたりはちょっとこじつけっぽいですよね笑)
それではここからはそれぞれの調味料の特徴を見ていきましょう。
①砂糖
砂糖は調味料のかなでも非常に面白い特性を持っています。
最大の特徴は酸味や苦味を和らげる働きです。
甘言(かんげん)という言葉をご存知でしょうか?
「うまくいいくるめる」といった意味を持っていますが、この言葉通りの性質を砂糖だけでなく甘いものすべてが持っています。
甘味の性質は、甘味によって酸味や苦味がすっかり覆い隠されてしまうところです。
このことは食べ物の味そのものを隠すことになります。
したがって、良い材料に対して甘みを強く加えて調理すると、せっかくの素材の良さが隠されてしまいますし、逆に少し古いとか、クセのある材料だと甘みでその悪さを隠してくれます。

料理の際、素材の持ち味を生かすには、まず甘みを抑えることが大切です。一般家庭では
①お酒②砂糖③みりんの順で使われますが
みりんは照りを出すものであまりつかうとこってり味になりますし、タンパク質を固くします。
どうしても甘みが足りない時に砂糖は使うようにしましょう。
中医学では砂糖は甘い味なので脾を養いますが、中医学での『甘味』は砂糖というよりも米やイモ類などが持っている自然の甘さのことを指します。
生成された白糖よりはミネラルを含んでいる黒糖などを上手に活用するとより健康的でしょう。また、砂糖のかわりに質の良い蜂蜜を使うこともおすすめです。
醤油や味噌のような日本独特の調味料は別ですが、日本は料理の味付けに砂糖を非常に多用する珍しい国です。
欧米では砂糖は味付けにはほとんど使いません。なので、砂糖補給のためにデザートが発展した、というふうにも言われています。

日本は砂糖を非常に料理で多用するので、それにプラスしてお菓子を食べるとかなり砂糖のとりすぎになるので、そのあたりも注意をしたいですね。
②塩
塩は食品の味を向上させ貯蔵性を高め、人の体に対してはナトリウムの体液量を決め、筋肉の収縮、神経の刺激伝達にかかわり、塩素は胃液を作るなど、生命維持(1日の最低摂取量は3~5g)に必須のものです。
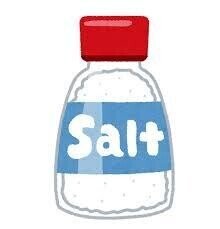
汗をかきすぎたときに『塩分補給』を言われていることは熱中症がポピュラーとなった今では多くの方が知るところです。
しかし、過剰摂取が高血圧の発症など健康を大きく害するすることから今では『減塩』という言葉が主流となっております。
実際に家庭で塩分を減らすにはまず調味の甘味を少なくすることが重要なのですが、塩さえ減らせば良いと思われているのが現実です。
人間には無くてはならない成分だからこそとり方にも注意をしたいですね。
塩味は『鹹味』と言って中医学では『塩辛い味』として腎を養うと考えます。これは『塩』いわゆる塩化ナトリウムだけの味でなく、海水などに含まれれているミネラルの味すべてを含むようなイメージを持っていただけると『塩味』と『鹹味』の違いが少し伝わると思います。
塩はできるだけ塩化ナトリウムだけの塩でなく、ニガリもしっかり入った、ミネラル豊富な天然塩、岩塩などを使うようにすると塩化ナトリウムの摂取を減らしたり、効果的にミネラル補給ができるでしょう。
③酢
酢は料理の味にとって欠かすことの出来ない物です。
酢の味のする料理でなくても少し料理に酢を加えると味に深みがでるなど、「かくし味」によく使われます。

むかしからよく使われる言葉の「あんばい(塩梅)」ですが
この「あん」は塩のことで、「ばい」は梅、つまり酸味のことを指しています。
これは昔、酸味に梅酢が使われていた時代に、塩味を良くするために梅酢が使われていたのに由来している言葉ということです。
酸味は中医学では『肝』を養う味と言われてす。
肝は血液貯蔵庫であると同時に、気分のコントロールもする場所と中医学では考えます。
なので、酸味は、中医学でも気分のすっきりしない時などにそれを整える働きもあると言われています。
酸っぱい味の物を食べたり飲んだりすると口の中や気分がさっぱりした感じになるのはそんな酸味の薬膳的なストレス緩和作用なのかもしれませんね。
その他にも酸っぱい酸味は味の強いものを食べたあとの口直しや箸休めでも使われる味です。特に甘みの強いものをとったあとはその次の料理の味がぼけやすいと言われており、和食のコースなどでは甘みの強い料理のあとにの箸休めに酢の物がよく使われるのはこのような理由からと言われています。
④醤油
醤油は、いろいろ多くの種類の香り成分を持っています。

そのため、ほんのわずかそれを加えるか、そうでないかによって、料理の味は著しく違いが出ます。
『ホンのちょっと』のつもりで醤油を入れたら味全体がかなり変わってしまったという経験ありませんか?
なので実は料理の各自味としても醤油は非常に重宝されており、料理番組などで、有名な料理人の方が「かくし味」として醤油を使う場面もよく見られます。
醤油は料理の味を増強する作用があり、特にイノシン酸などの旨み成分と合うと、その味が大変強くなります。
その結果、ダシに醤油を加えると料理の味がすごくなるのはそのためと言われています。
⑤味噌
味噌は醤油とならんで日本で古くから使われてきた独特の調味料です。

それだけに味噌が調理に加わることで、日本独自の料理が出来ますよね。善玉菌豊富な発酵食品なので味噌汁以外でもっともっと料理に活用してほしい調味料の人うつです。
味噌はご飯のおかずにもなるほど非常に完成された味をもっています。
なので注意が必要なのが、調理の際、味噌の使い方を誤ると材料の持ち味が消えすべての味が味噌だけの味になってしまいかねないので、使う量などには注意をしましょう。このあたりは醤油とちょっとにているかもしれません。
味噌も全国に様々な種類がありますので自分の好みの味を探したり、今は手作り味噌をつくる教室などもあるので、手づくり味噌を楽しむのも良いでしょう。
使用の際、味噌を入れてから沸騰をさせてしまうと味噌の善玉菌が死んでしまうので注意しましょう。
生臭い物のニオイ消しで使う場合は煮立てる事が大事なので場面場面で上手に使いましょう。
薬膳的な効能では清熱解毒作用と言って体にこもった余分な熱をとり、毒を解消する働きがあると言われています。
番外編:酒
調味料の『さしすせそ』の特徴をご紹介してきましたが、最後は『さしすせそ』には入っていませんが、料理をする際によく活用される『お酒』です。

酒を用いると料理の出来上がりが艶よくなり風味も良くなります。日本ではもちろん日本酒、中国では紹興酒なども料理に使われますし、欧米ではワインも調味料の一つとして活用されます。
お酒は生臭みを消したり、タンパク質を主成分とする肉類を柔らかくする作用もあります。
【調味料は上手に活用・質にこだわっても良い】
今回はちょっと視点を変えて調味料を健康的に、上手に活用するポイントをお伝えさせていただきました。

(お刺身も醤油、金山寺味噌、など調理料を変えるとグッと味が引き立ちます)
調味料は使い方しだいでカラダを健康にも不健康にもしてしまいます。
バランスよく調味料を使うのと同時に、どの調味料も様々な品質のものがあるので、できるだけ良質の物を活用するよにしたいですね。
調味料の選び方についてはまた別の機会にお届けしたいと思います。
調味料のお話をしてきましたが、中医学でも『5つの味』という物が食養生の基本です。
酸味・苦味・甘味・辛味・鹹味(塩味)
この5つの味と今回の調味料の活用をうまく組み合わせて楽しみながら食養生をしていただけたらと思います。
味付けの基本は「ご飯なしで食べれるぐらいの薄味・食べた後に飲み物を欲しくならない程度の薄味」が基本です。
食べた後にご飯をかき込むような濃い味は外食の時ぐらいにして、家庭ではぜひ薄味、おかずだけで食べられるような調理を心がけましょうね。
(参考文献:柏木晃先生『せらび』)
☆『さわたや養生茶シリーズ』&『さわたや養生おやつシリーズ』オンラインストアーにて好評販売中
☆漢方相談・健康相談のお申込みは『漢方専科・さわたや薬房』HPを・オンライン相談も実施中
☆オンライン漢方セミナーのお申し込み
☆漢方相談のご予約
☆noteマガジンメンバー登録
☆さわたや養生茶オンラインショップ
☆Podcas番組&You Tube番組・Twitter&InstagramなどSNS
各種リンクはこちらから
↓
ここから先は

早川コータの漢方Labo
【週刊誌1冊分の金額でオンライン漢方セミナー&有料記事が読み放題】 ☆オンライン漢方セミナーと有料記事がセットになったお得なマガジン☆ …
この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?
