
有機農業とお金についてマクロに考えてみる
有機農産物の価格は今後どうなる?
近年国が示したみどりの食料システム戦略。
その中で有機農業を推進していくことを明記している
現状の環境問題という大きな課題に対して国がそのような指針を示すことは素晴らしいことだと私は思う。
しかし有機農業を広げるには農家自身のインセンティブが働かないことには難しい。
では有機農業のインセンティブとはなにか?
それは一般作物より高い価格で取引されることだ。
しかしこの高価格での取引は基本的に希少価値によって担保されている。
有機(オーガニック)市場は需要も供給も少ないのだ。
では仮に有機農業がみどりの食料システム戦略で示した通り拡大したときには市場はどのようになるだろうか。
ひとつ考えられることは有機農産物の価格が下落することである。
シンプルに供給が増え需要が変わらなければ価格は低下する。
さらに今後日本の人口が減っていくことを考慮するなら需要が増えることは見込めないだろう。
しかし、人口が減れば農家も減るので全体の生産量も減少するとの見方もあるかもしれない。
全体の生産量が減れば需要と供給の関係で価格は維持される可能性がある。
しかし私自身は今後全体の生産量は横ばいか少し増えるのではないかと予想している。
以下のデータがその根拠だ。


https://www.maff.go.jp/j/wpaper/w_maff/r3/r3_h/trend/part1/chap1/c1_1_01.html
この2つのデータからわかるように2005〜2020年にかけて農業従事者がおおよそ半減しているが、生産量はほぼ横ばいとなっている。
この事象は農業分野で2つのイノベーションが起きていることに起因する。
イノベーションのひとつには農業機械の技術的進化がある。
日々農機具の性能は向上している。
それらのイノベーションは基本的に人員を減らす技術だ。
トラクターの自動操舵やドローンによる技術革新は今後農業従事者を減らしていくことだろう。
もうひとつのイノベーションは農地の集約だ。
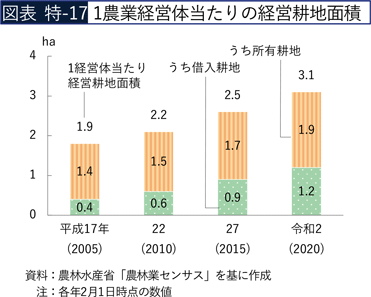
https://www.maff.go.jp/j/wpaper/w_maff/r3/r3_h/trend/part1/chap1/c1_1_04.html
1経営体あたりの耕地面積は拡大の一途を辿っている。
それにより少ない農業従事者で効率よく作業することが可能となっている。
これらの理由から農作物の価格は今後も下落していくことが予想される。
ただし農業従事者も減っているので大規模で農地を集約している経営体の利益は上がっていくかもしれない。
有機農業拡大の懸念点
有機農業が拡大していくことはソーシャルグッドという点でいえば素晴らしいことだ。
色々な見方があるだろうが、有機農業が広がることは基本的には環境保全になるだろう。
農業従事者自身も農薬の影響(農薬のドリフト)を受けにくいので、農家の健康寿命も伸びるかもしれない。
では有機農業が広がっていくことでどのような問題が予期されるだろうか。
有機農産物の価格下落
これは先ほど述べた通り有機農産物の供給が増えれば価格は今より下落するだろう。
特に北海道が本気で有機農業に舵を切れば農作物全体のパワーバランスが一気に崩れる可能性さえある。
肥料、堆肥の高騰
有機農業では有機JASの規定に合致した肥料しか使用できない。
しかし現状有機JAS対応資材は入手が難しい。
故に有機農家が増えれば肥料価格が高騰する可能性もある。
また有機農業では堆肥を使用することが多いが、同じ理由で堆肥が入手困難になることが予想される。
なお良質な堆肥に関しては現状においても入手困難である。
それでも有機農業が広がらない理由
ここまでは政府が示したみどりの食料システム戦略により有機農業が広まった場合の懸念を挙げてきたが、実は私自身有機農業がそれほど広がっていくとは思っていない。
その理由は以下の通りだ。
温暖化
有機農業で使える農薬の効果は非常に限定的である。
そこで多くの有機農家は季節に合わせた作付けを行っている。
その理由は虫害が少ないからだ。
虫は気温が上昇することで活動が活発になる。
なので気温が涼しいうちに虫害に遭いやすい葉物野菜等を作付けることが定石となっている。
しかし近年の温暖化により秋になっても虫の活動が活発で農作物に被害が出ている。
今後気温が上昇していくことで農作物の虫害は間違いなく増加していくだろう。
そうなるとますます有機農業を行うハードルは上がっていくことが予想される。
固定観念
現在慣行農業を行っている方が有機農業に理解を示すことは非常に難しい。
その理由は除草と防除だろう。
有機農業では除草剤は使わないので、畑の雑草の量は慣行農業と比較して多い。
慣行農業においては雑草とは忌むべき存在であり、徹底的に除去していくというスタンスの方は非常に多い。
雑草の種が飛んでくるとの理由から近くの有機農業を排除しようという圧力もかかる可能性さえある。
また有機農業では作物の病原菌に対して十分な対策が取れないことから、それらが自分の畑に広がることを警戒している農家も多い。
雑草や病気に対する観念は有機農家と慣行農家では大きな隔たりがある。
そもそも有機農家の中には雑草があることが良いという立場の人さえいる。
それらの大きな認識のずれが今後大きく変わっていくとは思えない。
今後について
様々な課題のある有機農業であるが、国が示したとおり2050年までに有機農業を全体の25%(現状の25倍!)に拡大させるにはどのようにしたらよいのだろうか。
そのためには現状の環境問題に対する意識と有機農産物の価格が大きな課題となるだろう。
短期的に得する仕組み
ヨーロッパでは国境炭素税を導入する議論が行われている。
これは炭素を排出しているものに多く課税するというものであり、
要するに環境に配慮する企業ほど税金対策ができるという仕組みだ。
それを今後有機農業に応用した仕組みづくりをしてみてはいかがだろうか。
例えば有機農産物に対して消費税を免税するなど。
そのように短期的に得する仕組みがなければ大きく世の中をかえることは難しいだろう。
国民の長期的な視座
環境問題を解決するには短期的な得と長期的な視座が必要だろう。
では長期的な視座を人類はどのように持ってきたのか。
ひとつには伝統、宗教などの倫理観がある。
"In our every deliberation,
we must consider the impact of our decisions
on the next seven generations."
「どんなことでも7世代先(セブンス・ジェネレーション)のことを考えて決めなくてはならない」
上記のとおりインディアンは7世代先を考えるというプリンシプルをもっていたと言われている。
我が国でも孫の代まではという言葉は一昔前までよく言われていたのではないだろうか。
その長期的視座がなくなった理由は少子化、過度な資本主義経済、伝統破壊などが考えられる。
一度壊れた長期的視座を復活させることは非常に難しい。
この問題について考察しているのが物理学者の長沼 伸一郎氏である。
現代経済学の直観的方法という著作の後半部において、縮退という概念を提示し、現在の失われた長期的視座について考察している。
なおご興味があれば以下の記事から縮退について一部紹介されているのでご一読されたい。
このように長期的視座に基づいた消費行動がエシカル消費という形で国民に受け入れられれば有機農産物の需要が増加して価格が維持される未来もあるのかもしれない。
「倫理的消費(エシカル消費)」とは?
消費者それぞれが各自にとっての社会的課題の解決を考慮したり、そうした課題に取り組む事業者を応援しながら消費活動を行うこと。
自然農法を真剣に考えてみる
有機農業には様々な流派があり、さながら仏教の宗派のような趣さえある。
その中で最もプリミティブな宗派は自然農業だろう。
しかしこの自然農業という言葉自体にも当然様々な宗派がある。
そこで私がここで紹介したい農法は長崎県で菌ちゃんふぁーむを経営している吉田俊道さんが提唱している菌しゃん農法である。
この農法は窒素を糸状菌という菌で固定するという方法で、必要な資材は丸太、籾殻など日本中にいくらでもあるものしか使わない。
人口的な資材としてはビニールマルチを使うが、現代農業においてビニールマルチしか資材を使わないなんてことは、にわかに信じがたいものである。
しかしこの農法は実際全国的に広まりつつあり、実際に栽培がうまくいっているケースも多いと聞く。
ただし商業的に考えて既存の農家がこの農法に完全に切り替えるにはいくつものハードルはあるだろう。
しかしこの農法は資材費を大幅に減らすことによって経費を極限まで削減することができる。
経費を削減することができれば、収量が減ったところでしっかり利益がでる可能性がある。
そしてなにより資材の高騰という外部要因に左右されない頑健な経営を目指すこともできる。
自然農法は最も原始的でありながら、まだまだ仕組みが解明されていない領域といえる。
この農法を一度国をあげて真剣に研究して、日本の農業の数%でも置き換われば世の中が変化するかもしれない。
最後に
有機農業に批判的な意見が世間に多くあることは承知している。
スリランカのように有機農業を急激に推し進めて失敗した例もある。
また有機農家が今後収益を上げることができるかという課題も先ほど述べた通り不透明な部分が多い。
しかし環境問題という壁は厳然として人類の目の前に立ちはだかっているのものであり、7世代先までの未来を考えた時、人類にとってなにが最善なのかを全農家、いや全国民が膝を付き合わせて語り合う必要があることは間違い無いだろう。
