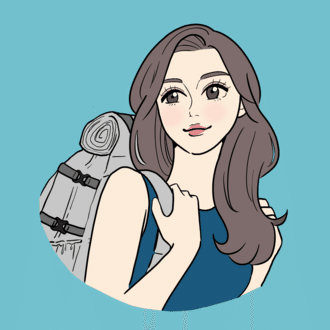おじいの木の食器 #未来のためにできること
いつも木の匂いがする子ども時代だった。
香ばしくて、清々しい、背筋がまっすぐ伸びるような匂い。
人肌のようにすべすべで、いつまでも抱いていたくなる手触り。
重みのある木の塊を人形のように抱いてみたり、板っきれをとんかちで叩いてみたり、釘を打って、ロボットや椅子を作ってみたり。
木がわたしの子ども時代のおもちゃだった。
いつでも木の匂いと、あのあたたかさを思い出すことができる。
わたしの実家は大工で、おじい(祖父の呼び名)は寺を建築できる宮大工だった。

「格天井」と呼ばれる美しい天井。日本建築の平安時代から残る様式なんだとか。
家を建てたり、寺を建てたり、なにかを作ると、木の切れ端や建築には向かない木が必ず大量に余った。
おじいは現役引退後、そんな木の廃材や残材を使って、木の食器を作り始めた。
木からお椀やお皿を作る工程は、至ってシンプル。
木を電動ノコギリで切って、木工旋盤で削って形を整えて、あとはひたすら磨くだけ。

玄能(大型のかなづち)でたたいてしまって、爪は変形した。
磨く時間が長かった。
「もう完成?」とわたしが何回聞いても、おじいは黙ってやすりをかけていた。

電動やすりを使って磨いて、さらに紙製のやすりで磨く。
磨いて、
磨いて、
もっと磨く。
いつまでたっても、完成しないようにみえるのに、いつのまにか出来上がっている。
職人は、頭の中のゴールテープをなかなか言語化しない。
おじいが木から食器を作るようすは、魔法みたいだ。その道数十年の人だから、かけることができる、「技術」という名の「魔法」。

捨てられるはずだった木が、おじいの手によって宝物のようなお椀に生まれ変わる。
売るとか贈るとか、そういうものではないけれど、おじいはただ作り続ける。
エコなんて真新しい言葉は、おじいの頭の中にはない。
木を余すことなく使おうとしているだけだ。
山のようにある廃材を次から次へと器に変えていくおじいを見ていると、おじいにとっては、ただ当たり前のことをしているだけなんだと気付かされる。
ひいひいおじいから、ひいおじいへ。
ひいおじいからおじいへ。
古来から、人間ならだれしも魂に刻まれている「余さず使え」という、その祈りのような教え。
現代人が忘れつつあると同時に必死で取り戻そうとしてる、昔からのその教えに従って、おじいは今日も木の器を作り続ける。
いいなと思ったら応援しよう!