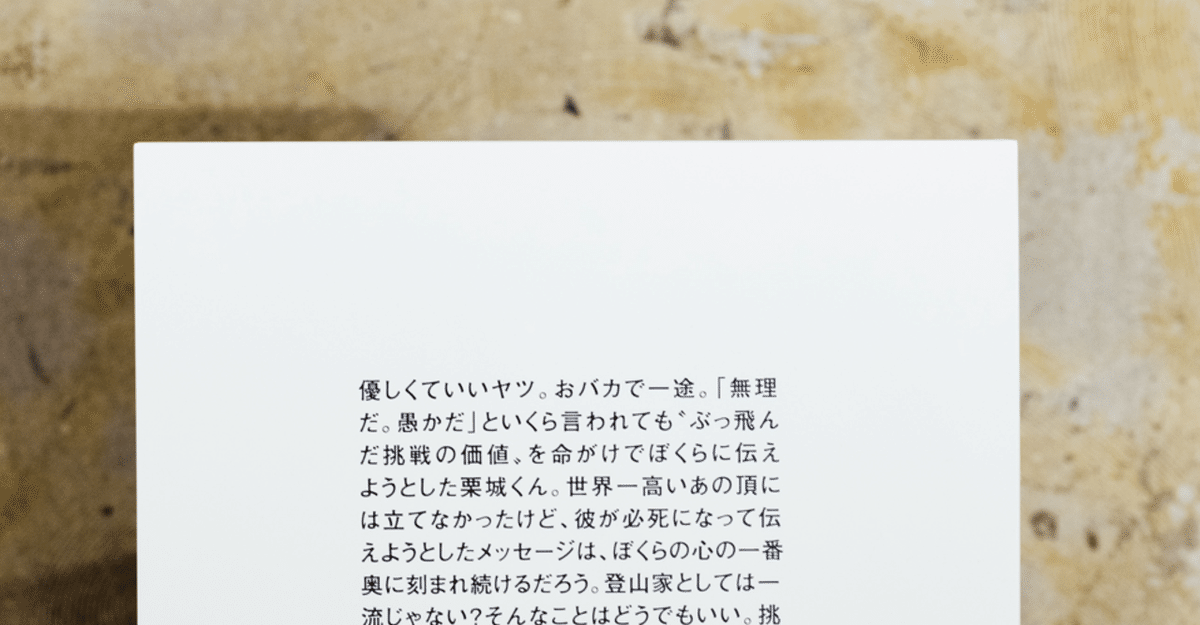
死の知らせを聞く側
「〜の結婚式の新婦さんが亡くなった」と仲間からのLINE。「ひゃっ」と小さな悲鳴と共に、携帯を落としそうになる。というよりも、私自体が世界の隙間に落ちてしまいそうな気持ちになる。「何で?なんで?」そうすぐ返信するも、その仲間も理由はわからない、という。この1ヶ月でそんな風に2人の死の知らせを受けた。死の外側で急に死の知らせをもらった側に、その死に関する情報はあまりにも少ない。近くにいる人たちは、急にそこに転がってきた想像もしていない死をいきなり引き取り・受け入れるのに必死で、それを漏れ聞く周囲の私たちは、絶望と「なぜ」の気持ちの中に、取り残される。その死の原因を、それを受け止めた人たちの悲しみを、お別れの会で目を凝らし耳を凝らし、紐解き受け止めていく以外にない。
人が死ぬことを、私は知らない。
人が死ぬという事実を、私は知っている。でも、自分の動揺ぶりに、死は日常に存在しないことにしているのだと私は強く認識した。だから、得体が知れなくて、怖い。結婚式を作った新婦さん、ずいぶん前に辞めているものの数ヶ月一緒に働いた元仕事仲間。考えてみればちゃんと話したことも数回しかないし、2人きりで会ったことなど、むしろ無い。その人の死を、そしてそれを通してすべての人が死ぬという事実を、受け入れられていない私を認める。「なんで?」と、こんなに強く思うのは、それを聞いて落ち着きたいからだろう。この、がくがくと震えてしまうような、準備していないこの死というものを、受け止める方法をどうにか模索しているのだ。こんな時にも人間は、いや私は、こんな風に自分でいっぱいいっぱいで、弱くてちっぽけな生き物なのだと笑えてしまう。
私はとても近い人を突然亡くしたことがない。死と遠くに生きてきた私が、初めてその死と向き合ったのは、奇しくもこのプロデュースという私の天職で、だった。数ヶ月にわたりその死と向き合い・紐解き、仕事を受けたことを嘆くほど悩んだのは、登山家の栗城史多さん、その人の死だった。彼と私は生前、たった一度の交流しかなかった。一度会食にお会いしただけの、彼の死を知ったのはFacebookだっただろうか。栗城さんの訃報を聞いて残念で仕方ない、という誰かの投稿を見て、「え?」と思った。「ちょっと待って、どういうこと?」と。その文字を見て、瞬間的に理解できなかった。会ってから2年以上やりとりもない。仲良いわけでもない。そんな彼の死は、瞬時に私を混乱させ、そのことを受け入れることを体が拒否しているようだった。それでも即座に、ネットでそのニュースを検索する。複数のそれらを読む。状況を理解する。一旦の「そういうことだったのね」がないと私はまた息ができないような気持ちで、幾つかの記事を貪るように、でも冷静に読んだと思う。私の頭が彼の死を理解して、彼の死が私に落ちてきた。そして、Facebookを見ると改めて多くの人が彼の人柄や彼とのエピソードを書いており、一気に実感が追いかけてくる。まだ上手に感情につながらないまでも、涙がつーっと流れた。たった一回、栗城さんを含む4人の会食の様子がフラッシュバックする。
無くしたばかりの包帯だらけの指。私はあの時、この人あまり好きではないな、と思った。なんだか疲れていたのかなとも思う。素晴らしい話だけど講演会みたいに、みんなから求められる、何度もしたであろう演目を、いつもと同じように話しているように、言いすぎると、演じているように感じて、私の中になにか違和感が残った。今から思うと、意気揚々と話をする彼は、この話を聞かれることと、それにこんな風に生き生きと答える自分に、嫌気がしていたようにも思えた。
あの時の、生っぽくない感じを私は今でも覚えていた。だから余計に気になった。彼の死の真相には何があるのだろう。そのまま、まだ狭かった自宅のベランダのそばに座り込み、それを検索した。こうだったのだ、と思い込むには十分な、誇張も含むストーリーがたくさんネット上にはあって、私はそれを強く欲してやみくもに飲み込んだ。苦いけど実態があるようで、自分の中に成立した不幸なストーリーは、私に死を取り巻くものを、納得させるだけの実感を与えてくれた。あの時はそれらに感謝した。私はそれくらい混乱していた、同時にどうにか自分を落ち着かせなくてはと思っていた。そのあとも、なんとも言えない死の恐怖みたいな、正体の無い黒いもやが私をずいぶんと取り巻いていた。
腹を括るしか無い瞬間というものが、ある。
それから程なくして、私は大切な友人に栗城さんのマネジャーさんを紹介された。小林幸子さん、とその方は言って、お別れ会の展示の準備を始めたけれども、これでいいのか不安だという相談を受けた。私は、お別れ会の内容の前に、栗城さんはどんな人だったのか、死が訪れて小林さんがどう思ったか、何を誰に伝えたいと思うか、ということを聞いた。色んなエピソードに、初めて人としての彼が見えた気がしたし、死の周辺にある人々の声が聞こえた。そして、彼を失って思うことや悔いていることが周囲に溢れている、それに触れた時、その追悼の場で何を残すべきなのかのヒントがあった。とても頑張って生きてきて、時に無理をしてきた栗城さんが初めて、心からの声で周囲とコミュニケーションを取れるようなイメージが私の、頭の中に浮かんだ。
小林さんはその場で涙をたくさんたくさん流した。「お別れ会の準備をしていて初めて泣けました。ずっとこうやって泣きたかったのだと思います」それを聞いて、私は人間として決意をした。死を通して、栗城史多が生きた証を描くという決意。そして、その人に彼の事務所の代表として賭けたこの人の小林幸子さんの人生もが報われる作品を作ろうという、仕事を超えた決意。それは、死を人間として受け止め、それをプロとして表現するということを意味していた。お別れ会や弔いの展示の経験はない。でも、私は誰よりも人生を受け止め深堀る、人生編集のプロであるという自負があった。だから不思議と、話を聞いて絶対私がやるべきだという確信があった。聞くと力を貸してくださっているのは素敵な会社さんではあったが、展示が得意な会社さんには、決してつかめない何かを、私はもう掴みかけてしまっていた。だから、私がやる以外に選択肢がないように思えてならなかった。
今でも私は、人の死に意味なんてあってはいけないと思う。全ての、必ず誰かに愛されている人々が、1日でも長く生きて欲しいし、そのあとに何が生まれたとしても、死んで良かったなんてことはない。そして、子を持つ親として、そう信じたいとも思っている。でも、死が訪れてしまった以上、この死が他の時ではなく今だったからこそ、残された方々に、そして死んでいった故人に伝えられる何かを作ろう、そんな風に思った。「何もできなくてもカッコ悪くても栗城さんのことがみんな大好きだったよと、本人に伝わったら本望です」、小林さんのそんな言葉が、頭の中に残っていた。きっとそうなんだろうな。彼自身が見せたかった栗城という人間は、調べればどこかしろにいた。でも、本当の栗城史多という人間は、彼が死ななかったら現れることがなかっただろうと、2時間のヒアリングでなんとなく思った。天国にいる彼に、それでも愛されているんだということがこの展示を通して伝わったらいいな、きっとそんな方向に向かうだろうなという気持ちで、コーヒー屋さんを、小林さんとの固い握手で後にした。
なぜ、その死は訪れたのか。
そこから私は改めて、彼の本をすべて読み、雑誌・ネットの記事を読みあさった。見えてくるのは、一人称としての「こうありたい」という彼と、過去の出来事、そして周囲の善意・悪意のこもったストーリーだった。ネットで叩かれ、称賛もされていた彼をちゃんと理解することは難しく、彼の本心も見えてこなかった。「彼は何を思い、山に挑み続けたのか、なぜ死んでしまったのか」きっと多くの人たちの中で、フリーズしたこの疑問を、投げ出さず、手の中で丁寧に何度も転がした。私は、彼の死に、いや彼の死までの生に、清濁飲み込んで向き合う覚悟をして、小林さんに周囲の人に実際に話を聞きたいと申し出た。私は彼の地元北海道の今金町にまで行き、お父さんやご近所さん、当時の教師や幼馴染たちに会った。それ以外にも、彼に密着したいたカメラマンや友人、出資してくれていた経営者、ファンの方々にもコンタクトを取った。私はこの死の答えを出したかった。本当のストーリーを紡ぎたかった。でも、見えてきたのは幾重にも折り重なるたくさんの人たちが見た、異なる真実だった。
彼はヒーローであり、怖がりであり、ひょうきんものであり、無謀であり、打算的であり、馬鹿ものであり、ネガティブであり、純粋であった。とても目指していた「これ」だというクリアなものにはまとまらない、複雑な人間の深淵に迷い込む。私は、無力さを感じて落ち込んだ。でも、制作しているチームで話し込むうちに、その闇は少しづつ晴れていった。そして、考え抜いた末に、すっと心が解放される瞬間があった。「そうなのだ」と思った。こんなにも複雑で、こうだというストーリーにできない。それが人間という生のリアルであり、もう語れない死者を表現することなのだと、理解できる瞬間があった。プロデューサーとしてゲストに伝えようとしてきた、「彼はこう生き、こう死んだ」という一筋縄にはまとめられ無い、幾重におりかさなる現実を私は受け入れた。
「栗城史多は、誰?」
私は、「栗城史多は、誰?」という、題名で追悼ギャラリーを提案した。この私が自分の体で体験した、理解しえない諦めを、ちゃんと体験にするのだ。という気持ちで。部屋は前室とメインの展示に分かれており、前室には皆が知る栗城さんの展示がある。年表があり、遺品としての愛用していた登山用品や書籍がある。そこにあるのは、誰もが向き合うことができる客観的な事実だ。そして、メインの展示には50本の低い柱を立てた。そこには、覗き込めるように彼の周りにいた人たちの言葉が書いてある。彼とつながる誰かの心のうちにある言葉。覗き込むように置かれたその言葉たちは、飾られた言葉とは違って、ひっそりと覗き込んだものにしか見えない誰かから見た真実。その真実たちのつじつまを合わせようと躍起になっていた私は、このつじつまが合わない見え方の無数の総和こそが、人間の正体なのだと理解した。彼を取り巻く、人たちの中にある言葉を私が聞き、それをここに連れてくることで、あなたはどう思うかを、来てくれた一人一人に問う...それが私が出した答えであり、この展示という作品になった。


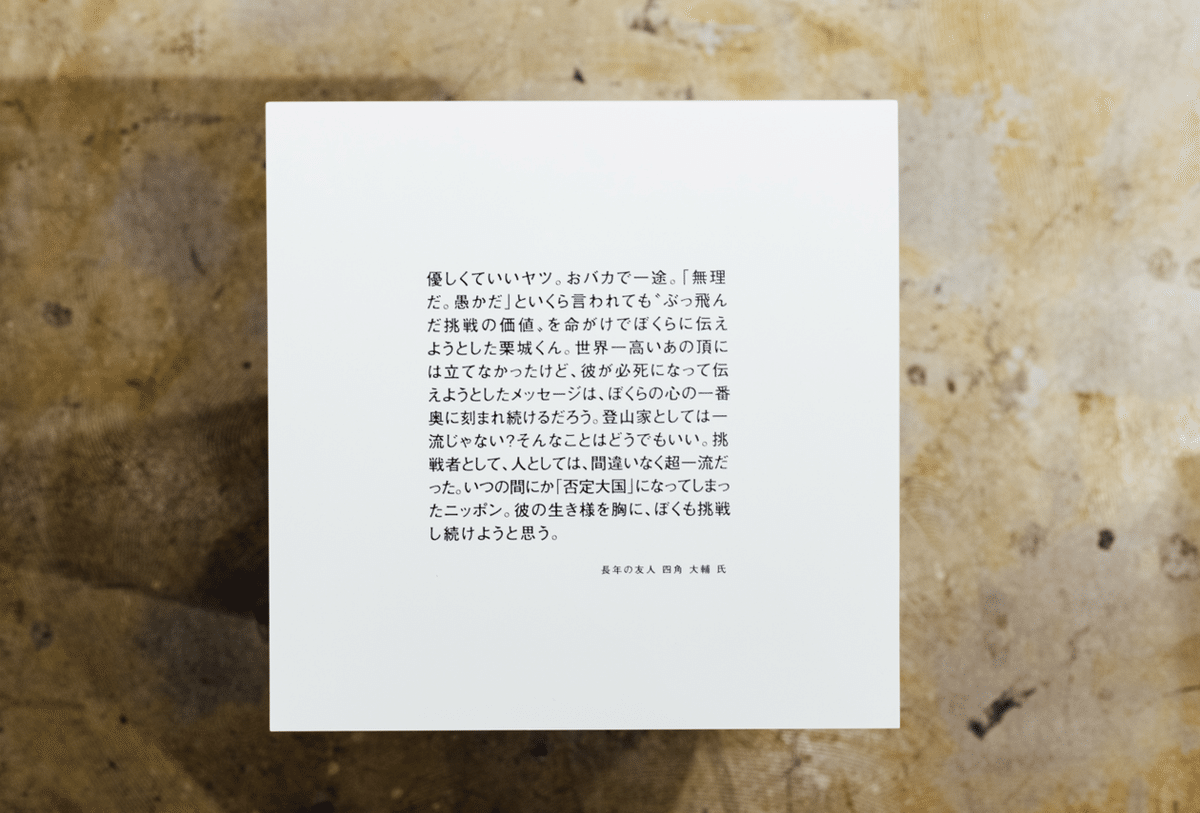

私は今でも、この追悼の答えも、なぜ山に登り続けたかも、死の真実も、分からない。でも、それぞれが彼を思って、いろんな人たちの中にいる彼に出会いながら、自分の中にある気持ちを見ようとする。彼を想うこと、自分の中にある気持ちを認めること…それこそが、追悼なんじゃないかと思ったし、それが栗城さんに贈りたいことだった。生っぽさをかんじなかった生前の栗城さんは、多くの人の中でリアルに、懸命に、生きていたのだと私は知った。
「栗城史一は誰か」
その答えは、まだない。
その答えは、もうない。
追悼のギャラリーでするべきことは、
彼が誰だったのかを定義することではなく
彼を改めて模索することだと思いました。
追悼とは、その人を思うこと。
人々が彼を思い出し 考え 悩み 表現すること
その時間の総和が追悼なのだと思うのです。
彼だけが特別ではない人生の複雑性に向き合うこと。
死の前で 自分の人生の「生」を感じること。
今回のこの展示が「あなたが生きること」に
つながっていましたら幸いです。

これは多くを経て私が、展示の終わりに寄せた言葉。
たった1人、栗城さんという本人を除く、彼を構成する周囲の人たちを描いたとき、一つだけ欠けたジグソーパズルのように、おのずと栗城史多という人間が浮かんでくるみたいだった。生きている時には、つかめなかった彼に、私は死後やっと出会うことができた。人の死は、真っ暗闇な絶望であり、でもそこであきらめないで目をこらすと、絶望を超えてそれだけでは終わらない生の光がかすかに見える。見えてきたかすかな光をここに書き残したいと思う。今でも私を容易に混乱させる死を、私が、私たちが、これからの人生で迎え入れられる願いのように。
<一部抜粋>
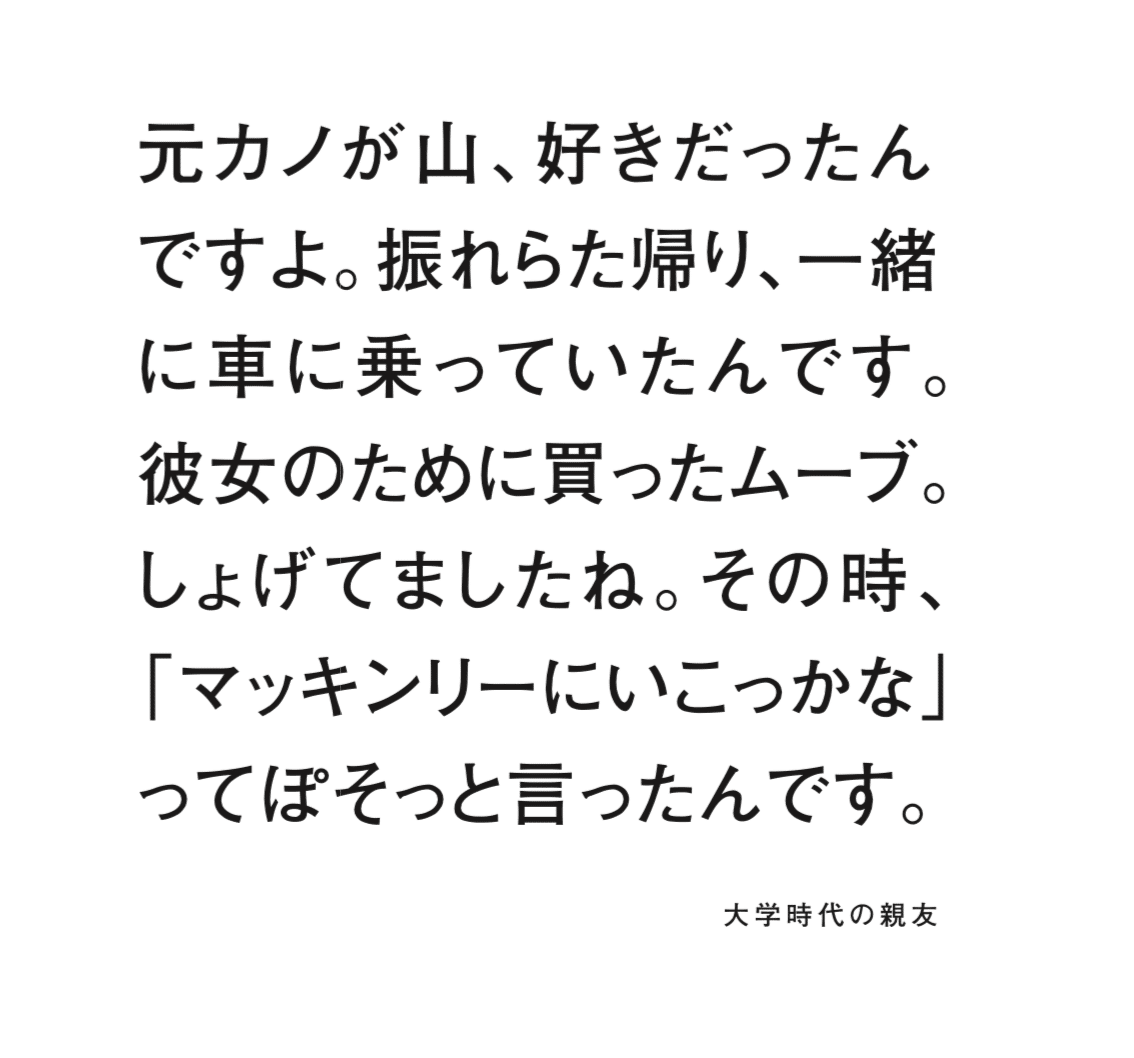


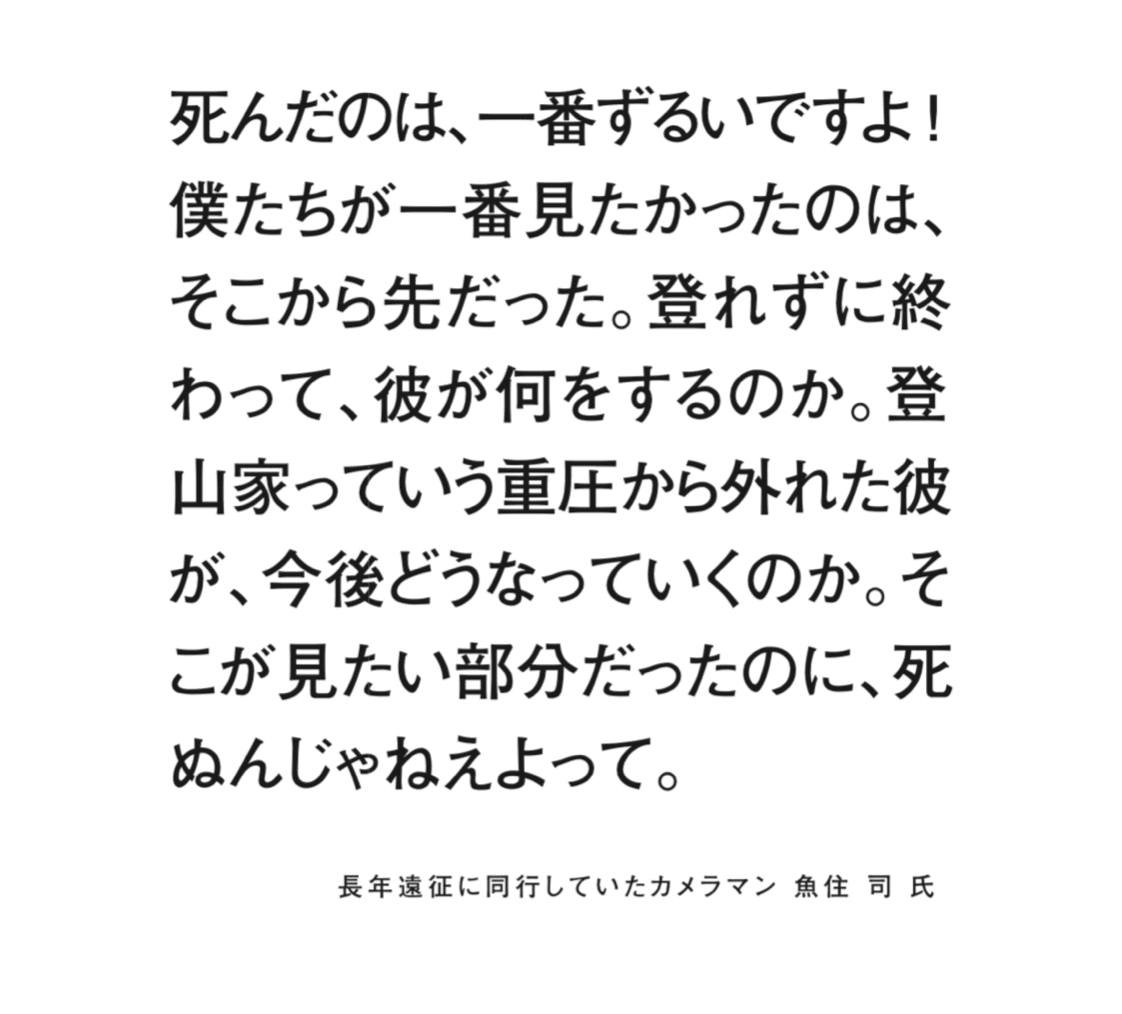









(あとがき)
子供を産んで、2年半命がけで育ててきた、そのリアリティの中で私は、死に意味なんてあってたまるか、と思う。でも私が結婚式を通して描いてきた、すべての命に意味が有るということを、私はそれこそ命を賭けて、これからも伝えていきたいと願う。いつか、私や親しい人が死の知らせを聞く側からあちら側に飛び越えてしまう日が、確実に来るのだから。そしてこの文章の最後に、その死を表現する仕事=人生を表現する仕事、にいよいよ足を踏み入れたいという気持ちを、自分の中に認め、それを静かに受け入れた。それは、もう実に中学二年生からの20年越しの夢でもあった。有限の世界を、懸命に生きる、これからの日々が、また始まる。
