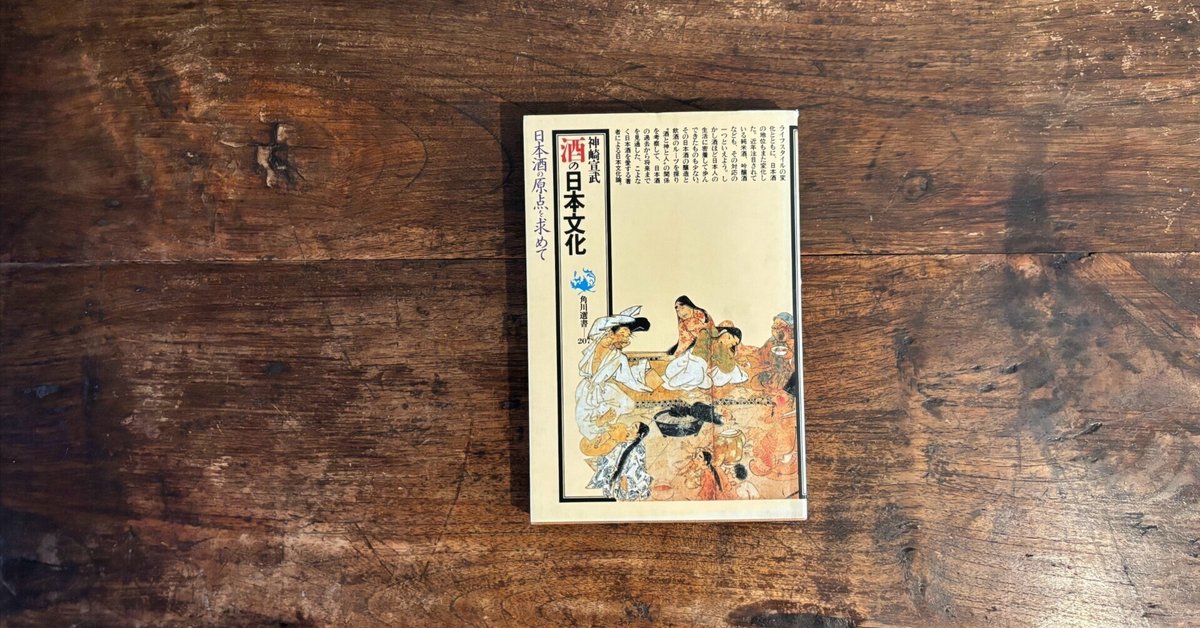
ハレとサケ|神崎宣武『酒の日本文化 日本酒の原点を求めて』|呑ん読#05
映画「君の名は。」にも登場する、口噛み酒。一連の厳粛な神事の中でも、巫女が米を喰むシーンは特に象徴的なシーンである。米や酒が、神事において重要な位置を占めているということがわかる。
とくに、われわれ日本人の社会は、古来そのつながりが密接であり大事であった――という形跡がある。たとえば、神酒徳利(瓶子)とか角樽とか雄銚雌銚、三々九度盃(三ッ重ね盃) など、神々と人々をつなぐ専用の酒器をこれほどに発達させている民族は、世界でも稀なのである。
酒は、神聖な飲み物として古くから重要な役割を果たしてきた。それは単なる飲料としての側面を超えて、神と人を繋ぐ特別な媒介として機能している。酒は神様に供えられる神饌の中で、飯、餅とともに最上位に扱われている。
神前に神饌が献じられる状態をみるのがよい。正中(中央)が最上位であり(それから右左に分かれ、正中からいちばん離れたところが最下位)、酒は上段の正中に置かれているはずである。
そもそも古来祭りの期間は、酒造りにはじまり、酒干しで終わっていた。つまり、酒造りに失敗したら、祭りや行事ができなくなる。重圧のかかる酒造り、失敗は絶対に許されないだろう。
祭りでは、厳粛な直会(なおらい)と、無礼講の饗宴がはっきり分かれていて、これらは祭り以外の飲酒文化にも踏襲されている。現在でも結婚式の披露宴では、前半は挨拶や形式が多く直会的で、後半は余興や踊りが行われて饗宴的になっていく。二次会となるともっと無礼講で、新郎新婦との距離も近い。会社の送別会なども同様の形式をなぞることが多いだろう。
直会と饗宴とは、本来は別な次元で行なわれるものであった。当然、そこでは酒の飲み方にもちがいがあった。直会では席次や作法の制約があり、饗宴ではそれほどの制約がない。粛々と飲む酒と騒々しく飲む酒のちがいである。
本書では、そこで飲まれる酒の温度に違いが現れるという指摘がある。祭りの進行にしたがって、冷やから熱燗へと推移していくという。
何よりも、直会の酒は冷であり(献饌の神酒をおろしたもの)、饗宴の酒は冷である場合もあるが、燗をして量を飲むことが一般的である。
昔、米は今よりもっと貴重だった。だからこそ、米を原料とする飯や餅とともに、酒は神々に捧げられる最上の馳走であり、特別な意味を持つ食べ物であったのだろう。日々の晩酌に、少し畏敬の念を持ちたい。
こぼれ話
江戸時代の飲酒文化については、飯野亮一『居酒屋の誕生』(ちくま学芸文庫, 2014)とはだいぶ異なる記述がある。
なお、江戸などの都市部においてさえ、酒は特別な日に料理屋か料理茶屋、あるいは居酒屋にでかけていってあらたまって飲むものであった。三田村鳶魚などの考証によれば、江戸の町で、一般の町人は市中ではそばやすいを屋台で食べたぐらいで、それにあわせて酒を飲む習慣はほとんどなかった、という記事も一方にある。
どちらが実態に近かったのだろうか。もっと詳しくならねば。
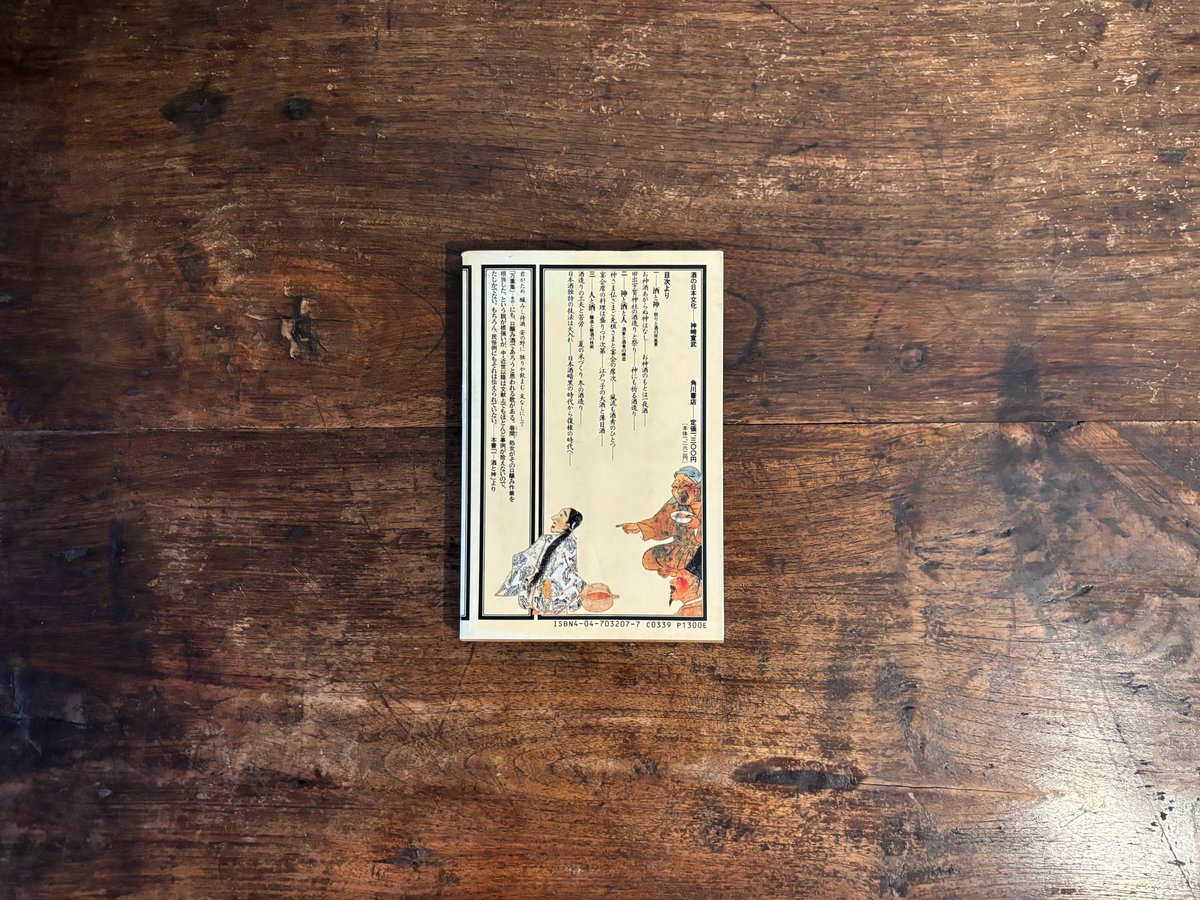
参考文献
神崎 宣武, 酒の日本文化 日本酒の原点を求めて, 角川選書, 1991
美味求真, 渟浪田(ヌナタ), 2017年4月28日, 閲覧2024年9月15日
家に積まれた酒に関する本を、一つ一つ順番に読み干していこうとする「呑ん読」。一つ一つ紹介していきます。
