
「Desolito」のメインメカニクスのゲームデザイン
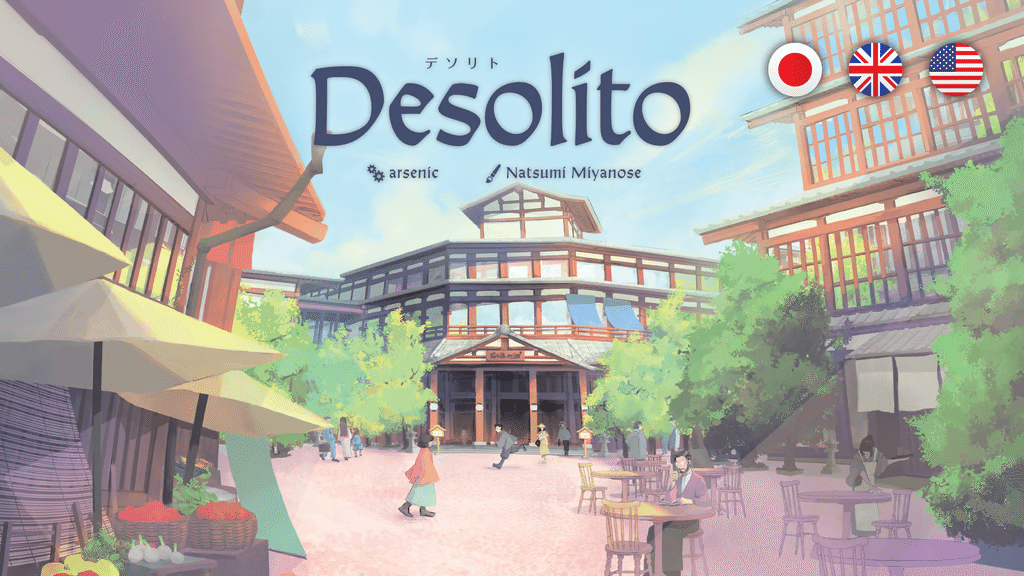
ゲームの簡単な紹介
こんにちは。arsenicと申します。普段は、このnoteで毎週土曜日に記事を投稿したり、ゲームマーケットで自身がデザインしたゲームを発表したり、というようなことをしています。
このたび、機会がありまして、Sui Works様の方で、「Desolito」(デソリト)というゲームデザインを担当させていただきました。(Kickstarterを予定されているそうで、ページはこちらとなっております)
https://www.kickstarter.com/projects/sui-works/desolito
この記事では、このゲームがどのような意図をもって、どのようなメカニクスを採用しており、どのような特徴のゲームになっているのかを簡単紹介させていただこうと思っています。
ゲームの詳細は、先日公開されたSui Works様の記事が正確で、わかりやすいので、そちらを参考にしていただければ幸いです。
しかし、主に紹介するゲームメカニクスに対しては、こちらの記事でも簡単に触れようと思います。
まず、本作を最も端的に説明しようとすると、少し特殊なドラフト+少し特殊なタイル配置というゲームです、という言い方になると思います。プレイ時間はインスト込みで1時間前後、プレイヤー人数は2~4人という規模感のゲームです。
このゲームでは、メインとして、ドラフトをするフェイズと、タイル配置をするフェイズに分かれており、これを規定回数繰り返すことでゲームが終了し、勝利点が最も高いプレイヤーが勝利します。
ドラフトをするフェイズでは、各プレイヤーは、左隣のプレイヤーと共有しているプールと、右隣のプレイヤーと共有しているプールを使って、1枚ずつタイルを取っていきます。
その後、タイル配置をするフェイズになり、ここでは先ほど取得したタイルを取得したのとは逆順に置いていきます。この時、置く場所が制限されており、自身のプレイヤーボードにある駒を1歩だけ動かし、そこに隣接するタイルにのみ、置くことができる、という形になります。
この2つのメカニクスは、ドラフト+タイル配置というわかりやすく、採用も多いものですが、上述のように、少し変わった仕様があります。
この記事では、どうして、その少しだけ異なる仕様になっているのか、どういった意図でそのような実装になっているのか、というのを簡単に紹介させていただきたいと思います。

両隣とのドラフト
ドラフトプールの仕様
ドラフトと一口に言っても、色々な実装方法があり、色々な側面・効用があるのは、皆さんご存知の通りです。
本作では先に軽く紹介したように、少し特殊なドラフトを採用していまして、両隣のプレイヤーとの間にドラフトのプール(タイルを取り合う場所)がある、という形になっています。(2人プレイの場合は、2人のプレイヤーの間に2つに分割されたドラフトプールがある、という形です)
つまり、各プレイヤーは自身が関与するドラフトプールが計2つあり、それぞれのプールからタイルを取り合うプレイヤーは2人のみである、ということになります。
一方、一般的なドラフトの場合、ドラフトプールは全プレイヤーで共有することが多いです。
まず、ドラフトと聞いた時に真っ先に思い起こす人も多いであろう、ブースター・ドラフト(「マジック:ザ・ギャザリング」のブースター・ドラフトや、「世界の七不思議」のドラフト)の場合、カードが複数の束(ブースター)に分かれているため、プールが分割されていると言えますが、これを全プレイヤーの元に回していくので、段階的にですが共有されています。
また、ワーカープレイスメントを始めとしたオープン・ドラフトの場合もゲームボードの中央などにカード(やアクションスペース)を公開し、それらを各プレイヤーは取っていきます。この場合、プールは分割されておらず、共有化されています。
本作における『両隣とのドラフト』の場合、プールは分割されており、かつ、両隣だけという限られた共有化になります。
なぜ、本作でこのようなドラフトを導入したかと言えば、それはドラフトに存在する一部の面を強化し、逆に一部の面を弱化させるためです。
ドラフトの住み分け
まず、何が弱化されるのかと言えば、それは『住み分け』であると考えています。
ドラフトにおける『住み分け』というのは、ドラフトプール内に存在する要素(カードやアクションスペース)に対し、それぞれのプレイヤーが別々の方向を志向し、同じようなものを取り合う競合状態を避けることで、結果として自身の利益を上げようとする手法です。
つまり、どういうことかと言えば、たとえば、プレイヤーAが青のカードを集めているのに対し、プレイヤーBも同じようなカードを集めようとすると、青のカードは2人で分け合うことになり、結果的に弱くなります。これはAとB以外のプレイヤーがより優位になる行為であるわけであり、避けたい状態にあります。
よって、両者が競合しないように、プレイヤーBは青ではなく、緑のカードを集めることにする、という戦略を取ることがあります。これを『住み分け』と俗に言います。これは(もちろん、他の構造などにもよりますが)ドラフトの大きな側面を担っており、重要な要素であると紹介されることも多いです。
筆者としても、特に「マジック:ザ・ギャザリング」のブースタードラフトにおける色の住み分けのように、秘匿情報下でのやり取りがメインである場合、このような側面を楽しむことも多いです。
ただ、この『住み分け』には、色々な問題もあります。
よくあるのが、住み分けが重要すぎると、それを最重要視するために、自分のやりたいようなことができない、という問題です。
たとえば、農業戦略をやりたくてそのゲームを始めたのに、他のプレイヤーが農業戦略を始めたために、泣く泣く別の戦略を取らざるを得ない、というような例はよくあります。
また、プレイ人数による影響が大きくなりがちである、という点もあります。もちろん、様々な調整がされることも多いですが、全体的な戦略の数などから、ベスト人数から外れると体験が極端に悪くなるゲームもあります。特にボードゲームでは、メインのプレイ人数が2~4人ぐらいであることが多く、人数の増減における影響が大きくなることも多いです(7人が8人になるより、2人が3人になる方がゲームに与える影響が大きくなりやすいと言えます)。また、そもそも、人数が少ないと、ゲームに登場する要素・戦略数の関係で、ランダム性に対する許容幅が狭くなりやすいです。
これは、ドラフトの特徴により大なり小なり発生する問題で、他のメカニクスの導入や、カード・アクションスペースの効果などを調整することで調整することが多いですが、根幹的な解決は難しいです。
本作では、このような特徴のある『住み分け』を、両隣とのみドラフトを行う形式と、取り合うタイルの特性などから、弱めようと試みています。
つまり、一般的なドラフトによく見られる(ということはすでに多く存在している)『住み分け』を重視したドラフトではなく、ドラフトの他の側面の方に焦点を当てて、さらに、プレイヤー人数によらず、ある程度一定のプレイ感が得られるようにするために、このような仕様にしています。
ドラフトのパズル性
このような住み分けや、それに関連する駆け引きに着目されることも多く、それがドラフトの面白さだ、と感じている人も多いと思います。
しかし、個人的には、ドラフトには、別の種類の面白さを求めていることも多いです。
たとえば、「メギド72」のフォトンドリヴン・システムなどがこれに含まれていると思っています。
以下の記事で、ボードゲーマー向けに「メギド72」のシステムを紹介したことがあるのですが、ここでも『ドラフト』という用語を使用させていただきました。
この記事を読むのに必要なぐらい、簡単に「メギド72」のシステムを紹介させていただきますと、このゲームの戦闘は以下のようになっています。

味方・敵で共有化している場が中央にあり、その要素を1個ずつ取り合っている、という点はドラフトそのものですが、少し特殊性のあるドラフトだと思っています。
まず、第一に相手はCPUで、そのピックを推測することは事実的にできないという点が挙げられます。
CPUの動きは、一定のルールを持っているであろうことはわかるのですが、それはハッキリとはわかりませんし、考えを読む、というようなことは事実的にできません。事実的には、ランダム性によって、自身が獲得しうる要素が脱落している、という風に考えることができます。
つまり、基本的にはドラフトはインタラクションを発生させるメカニクスですが、CPUと戦っているのであれば、これはランダム性になっているということです。
第二に、当然ながら、味方と敵しかいない状態でドラフトをしている、という点も多いです。『住み分け』というのは、一般的には3人以上のプレイヤー(あるいは勢力)が存在する時に意味をなす戦略です。
なぜならば、2人プレイの場合には、相手の損は自身の得であり、相手の得は自身の損です。つまり、ゼロサムゲームであって、互いが利益を得られるようになる『住み分け』のような戦略は取りにくいです(これは、前述したように一般的なドラフトがプレイヤー人数に強く影響を受けやすい理由の一つでもあります)。
第三に、取り合っているものが、フォトンという3種類しかない要素であり、それぞれが根幹的なものである、という点もあります。
それ自体に戦略の方向性があるようなものではなく、そもそも、要素の数としても少ないもので、『住み分け』が起こるでもありません。
それでも、「メギド72」のドラフトは面白いと感じています。「メギド72」の固有の経済を除いたとしても、この入力メカニクス自体が一定の面白さを持っている、という意味で面白いです。それはなぜでしょうか?
一つは、取得順が重要である点だと考えています。各メギドの行動順はそれを取得した順序になっており、つまり、スキル・アタックと獲得した場合、スキルを使ってから、アタックを使います。このような制限が、場に出てきた資源の種類や数と合わせ、パズルを構成しています。
もう一つは、リスク管理という側面で十分に楽しめるからだと思っています。たとえば、スキル(要素の種類の1つです)が2つ、アタック(同じく)が1つという状態にあれば、自身がアタックを取れば、次に必ずスキルが獲得できることは保証されています。一方、スキルを2個取ろうとすると、それが取れないリスクが生じます。上述した順序性の兼ね合いもあり、各リスクをどの程度許容するのか、というリスク管理が重要になります。
このような仕様があるからこそ、どのタイミングでどれを取得するのか、どの行動をどれだけ優先するのか、というパズル性が増しています。
本作「Desolito」の『両隣とのドラフト』も、これに近い特徴を持っており、パズル性を強めていると思っています。
本作のドラフトのまとめ
長くなってしまったので、簡潔にまとめます。
本作のドラフトは、左隣のプレイヤーとのドラフトプールと、右隣のプレイヤーとの間にドラフトプールがあり、それぞれから交互にタイルを獲得していく、というメカニクスを採用しています。
これの目的としては、『住み分け』のようなインタラクションを弱め、代わりにどの程度のリスクを許容し、どのタイミングでどのタイルを取るかというパズル性を高めるために行っています。
なので、基本的には、相手のピックが想定でき、互いにそれを考えながら住み分けを行う、といった類のドラフトではなく、相手のピックはあくまで多少は予測できるランダム性に近いものであり、自身の盤面におけるパズルをどうするのか、どの程度のリスクなら許容できるのか、ということを考えるゲームになっていると思います。
制限のあるタイル配置
タイル配置の理由
プレイヤーが要素を取り合う部分が、両隣とのドラフトになっている理由は先に挙げた通りなのですが、では、どうして、その後で行うことをタイル配置にしているかにも理由があります。
たとえば、「マジック:ザ・ギャザリング」のようなライフの削り合いとかにしてもよいはずですし、エンジンビルドのようなゲームにすることもできるとは思います。
ただ、『両隣とのドラフト』を採用しているゲームが少ないことからもわかるように、これは結構癖のあるメカニクスです。
まず、多くのゲームが、上述したようなブースター・ドラフトやオープン・ドラフトを採用しているのは、プールを全プレイヤーの元に共有化することで、機会の平等を維持し、ドラフトを全プレイヤーが参加している競り(オークション)にしている、という点が大きいです。
本作の場合、要素(タイル)を各プールに配るのは完全にランダムで、そこには当然、偏りが生じる可能性が生まれます。
たとえば、拡大再生産の側面が強いような経済にしてしまうと、適切なタイミングで適切なタイルがプールに追加された、というような影響が大きくなりすぎり、不平等になる可能性が上がります。(もちろん、世代化を行ったり、他のメカニクスで調整したり、ということはできますが)
そのため、本作においては、ゲーム経済をシンプルにして、タイル配置という配置された結果だけに注目するようなメカニクスを採用することで、理不尽に感じるような状態をなくそうと試みています。
タイル配置のパズル性
また、タイルを配置する時には、一般的にあるように、『すでに配置してあるタイルから繋がるように配置する』というような形ではなく、プレイヤーボードに駒があり、それを移動させながら、それに隣接している枠にタイルを置く、というメカニクスを採用しています。
加えて、前のドラフトフェイズで獲得したタイルを、獲得したのとは逆の順番で配置していきます(いわゆる、後入れ先出し=スタックです)。
これらはタイルを配置する時に位置関係という順序性を意識する必要があり、そのためには、ドラフトで獲得する順序性を意識する必要がある、という意図でデザインされています。
たとえば、すでに配置されているタイルから隣接するように置く、という形では、タイルを置く順番が1~2枚変わっても、あまり大きな影響を与えませんし、タイルを置くことのできる場所はどんどんと増えていくのが一般的です。
本作の場合、プレイヤー駒を動かしながら置く必要があるため、駒の移動経路が、実際にはタイルを置いていく順番になり、タイルを取得する順番を考える必要がある、というような形になっています。
本作のタイル配置のまとめ
まとめますと、本作のタイル配置は、少し特殊なドラフトを採用していることによる不利な特徴を緩和するために採用されたものです。
また、配置時は、ドラフトにおける取得した順序や、プレイヤー駒の位置、タイルを置く枠に制限されることによって、パズル性を高めることを目的としており、これは比較的次に獲得できるタイルが把握しやすい『両隣とのドラフト』における特徴とも加味されたものとなっています。
これらの両輪が、本作のメインのメカニクスです。
総合的なまとめ
この記事を総合的にまとめます。
少し特殊なドラフトと、少し特殊なタイル配置を採用することによって、インタラクションを弱め、パズル性を高めるような構造になっています。
よって、ドラフトのゲームではありますが、戦略の住み分けなどを他のプレイヤーと行う、というゲームではなく、その時々、そのラウンドに公開されたタイルを見て、自身の状況を鑑み、リスクを管理しつつ、最適なタイルを選び続けていく、というパズルを連続して解いていくようなゲームの構造となっています。
このような特徴と同時処理の関係から、プレイヤー人数が2~4人に変化しても、ゲームへの影響は比較的大きくなく、同じようなプレイ感が維持できていますし、プレイ時間も変わらない形になっています。
いわば、各プレイヤーは自身のボードと左右とのドラフトプールとの繋がりだけを持って、モジュール化されているため、それが2つ・3つ・4つと増えていっても、他の構造に比べて、影響が少ない、ということです。
もちろん、プレイヤーが2人の場合は、ドラフトプールが事実的にすべて共有化され、3人の場合には、連鎖的にすべてのプレイヤーと、4人の場合には、まったく共有化がされていないプレイヤーが対角上に存在するなど、変化がないわけではありませんが、相対的に影響は少ないです。
実際には、ここでは書ききれなかったことも多くありますし、物事は単一のメカニクスで決まるわけではなく、色々な組み合わせであったり、要素の効果や、経済のバランスなども影響します。
Sui Works様のディレクションのお陰様で、ドラフト+タイル配置という親しみやすいメカニクスを採用したゲームにはなっていますが、その実際の印象やプレイ感と比べて、なかなか珍しいメカニクス・構造を採用したゲームになっています。ボードゲームにあまり習熟していないプレイヤーでも遊ぶことのできる軽さなので、そういった手軽さの一方で特殊性がある、というボードゲームになったと感じています。
近日中にKickstarterのプロジェクトを開始予定ですので、よろしければ、ご注目いただければ嬉しいです。
https://www.kickstarter.com/projects/sui-works/desolito
最後になりますが、本記事は、あくまで「Desolito」のゲームデザイン担当者は、このようなことを考えて設計を行った、というだけであり、皆さんが実際にプレイした際に抱いた感情や考えを否定するものではありません。あまり気になさらず遊んでいただけることを願っています。
本記事が、このゲームを遊ぶきっかけとなれば幸いです。
