
井上ひさし『東京セブンローズ』が書かない「美しき国語」の歴史──東條内閣の国語政策に抵抗した神道人(「正論」平成11年10月号から)
(画像はかつてGHQが置かれた第一生命ビル)
■小説より奇なり「国語改革」の歴史■
いつぞやの「天声人語」に、「クイーンズ・イングリッシュ」といえば「純正な英語」の基準だが、当のイギリス女王の英語に間違いがあって、「筋金入りの守旧派」を嘆かせている、とあった。「守旧派」かどうかは知らない人が、どこの国であれ、人々が母国語に深い関心を持つのは健全だろう。
日本でも一昨年の平成11年、著名な国語学者・大野晋氏の『日本語練習帳』が100万部を超える大ベストセラーになった。ただボクには、やはり一昨年、知られざる日本語の占領史を取り上げて、話題を呼んだ井上ひさし氏の小説『東京セブンローズ』の方がむしろ痛快である。内容について、若干の留保をつけた上でのことだが……。

物語のなかで、主人公である東京・根津のうちわ屋店主・山中信介は、敗戦後、GHQ民間情報教育局(CIE)の言語課に勤めることになり、担当官のロバート・キング・ホール少佐から日本語ローマ字化の計画を聞かされる。
ホールは「日本人が『化け物』のような漢字を捨てて、ローマ字化すれば、漢字習得にかけられていた時間が浮いて、民主主義の勉強ができる。アルファベットに慣れたところで『サタンのことば』である日本語を退治して、外国語を採用する計画だ」と説明する。
アメリカから教育使節団が来日するのに際して、ホールは漢字廃止、ローマ字化を提起するのだが、1カ月後、日本の教育事情の視察を終えた使節団からマッカーサーに提出された報告書は、「ローマ字採用を要求しつつも、国語の変更は国民の中からわき出てくるべきものだ」とし、学識経験者らによる国語委員会委員の設置を提案する穏やかのものとなっていた。
このトーンダウンの背後に何があったのか。それが17年をかけて完成したという800ページの大作のテーマだが、圧巻は言うまでもなく、米兵に春をひさぐ7人の日本女性たちが、文字通り身体を張って、日本語のローマ字化を阻止したとする最後のヤマ場であろう。
GHQによる日本語改造の企てが小説のテーマならば、占領史の叙述だけで十分のはずだが、戦争末期の昭和20年4月から書き起こし、戦時中の日本政府による外地での日本語化推進に言及することを忘れない点も井上氏らしく、ボクとしては深い共感を覚えずにはいられない。
ある雑誌インタビューで、井上氏は、「いくらなんでも7人の娼婦が日本語を守ったというのはウソだけど、細部は全部本当です。でも、小説全体を呼ぶと『ウソ話を読まされた』というのを描きたかったんですよ」と語っている。この小説にはノンフィクションの側面があり、歴史批判の性格を持っている。
『私家版日本語文法』や『ニホン語日記』などの優れたエッセイで知られ、国語問題に造詣の深い井上氏の作品には、日本軍部であれ、GHQであれ、強権による理不尽な言語破壊の企てに対する怒りと批判が込められているようだ。けれども、史実はまさに井上氏自身が語られるように、物語の通りではなかった。いやある意味では、井上氏の小説以上にもっと数奇なる日本語の歴史があった。

■忘れ去られたもうひとつの歴史■

漢字制限あるいは国語改良の議論は、占領期に初めて起こったわけではもちろんないが、国語改革がいつどのような観点で論じられるようになったのかは、複雑な国語国字問題の歴史を考える場合に、きわめて重要なのではないかと思われる。
井上氏は小説で、高橋巌という新聞社の写真部主任に、「とにかく江戸の中頃からこっち、世の中は、漢字廃止もしくは漢字制限に向かって大きく動いてきたことは間違いないと思いますよ」と語らせている。
前述した国語学者の大野氏は、丸谷才一編『日本語の世界16 国語改革を批判する』で、戦前の国語改革の歴史を解説しているが、そこでは江戸時代中期に西洋語の学習とアルファベットの輸入とに刺激された新井白石、本多利明などが西洋の文字数が少ないのを見て驚き、日本語の漢字の多いことを批判的に論ずるようになった。それが国語改良論の起こりだ、と説明している。

このように「西洋文明との出会いを契機として、西洋的近代合理性の精神がここ200~300年にわたる日本語改革の原動力となってきた」とする理解がだいたい一般的のようだが、もうひとつ大きな流れが見落とされている。
もうひとつの潮流というのは、江戸期の国学者による漢字批判である。戦後唯一の神道思想家といわれる葦津珍彦が指摘していることだが、漢字批判で白石以上に激しかったのは、国学者の賀茂真淵であるらしい。真淵は『国意考』に、漢字は数が無限に多くて不便だが、表音文字の仮字はアルファベットに似て便利だ、と書いている。また、本居宣長は『玉勝間』で、漢字に対するカナ文字の優位を説いている。平田篤胤も、大和言葉の音韻が漢語に対して優れている、と『伊吹於呂志』で論じている(葦津珍彦「漢字、仮字と国学者」)。

こうした国学者による国語論が明治以降の国語国字問題に大きな影響を与えていることを、現代の国語学者たちも、そして井上氏も忘れていないだろうか。そのため、一方の開明派による合理主義的国語改革に対して、もう一方の保守反動派による伝統盲従型の反対論という図式的な理解に陥っていないだろうか。
戦後50年、保守反動の最たるものが「神社」だと考えられてきたことは、いまさら強調するまでもない。井上氏の小説には、反動中の反動としての神道あるいは神道人が、時代状況を物語るうえでしばしば効果的に登場する。
主人公の長女、絹子の結婚式が日本橋三越で行われたとき、式の前に神主は東亜の開放、帝国不滅、特攻精神の大演説をぶち、一同が聞きほれる。敗戦後、アメリカの空襲を憎む者たちが集合するのは、城東区大島の愛宕神社である。貧相な社務所は雨漏りがしていた。新聞社の写真部主任をしている隣組の高橋巌から、主人公が漢字制限の歴史の手ほどきを受けるのは、空襲をまぬがれた根津権現(根津神社)である。
井上氏は「靖国神社は軍国主義」と教科書に書きたがるような歴史研究家とはひと味もふた味も違うだろうが、それでも日本の神社こそは愚かな戦争政策を強力に推し進める政府にもっとも忠実で協力的な支持勢力であり、そのため戦後は一転して占領軍からにらまれる立場に転落した、という理解があるのではないか。
けれども、歴史は必ずしもそうではない。逆に、戦時内閣が占領地域で推し進めようとした日本語政策に猛反対ののろしを上げたのが、ほかならぬ神道人であった。
■朝鮮統治を批判した神道思想家・今泉定助■
井上氏は、かつて日本政府が外地で日本語化を推進した歴史に矛先を向けることを、忘れてはいない。

戦争末期にふとしたことから思想犯に仕立て上げられて刑務所に放りこまれ、敗戦後、出所してきた主人公に、町会長の青山基一郎は「大日本帝国にしても、朝鮮、台湾、そして満州で、現地の言葉の使用を禁止したでしょう。米国も日本と同じことをやるだろうと思いますわ」と語っている。
新聞カメラマンの高橋は、明治以来、文部省、軍部、新聞の3つが手を組み、漢字制限を推し進めたが、満州事変をきっかけに逆流し、漢字制限が崩され、難解な漢字・漢語で奪う下院が発表文や声明文を出すようになった。敗戦を境に、軍部と右翼の重しが取れて、漢字制限の国是が表面化し、連合軍の後押しでいっそう強力化した、と述べている。
さらに、占領軍の日本語ローマ字化推進の中心人物であるCIEのホールはローマ字化に反対する主人公に、「あなたたちは朝鮮半島の人々に、母語である朝鮮語を捨てて、日本語を使えと、強く迫ったではないですか。インドやシナやタイやビルマやインドネシアの小学校で日本語を必須科目にしたではないですか。大東亜共栄圏の標準語を日本語にしようとしたではないですか。他人にしたことをケロリと忘れて、同じことを他人から要求されると激怒する。なんだかおかしいじゃないでしょうか」と語る。
たとえば、戦前、「日本が朝鮮の言語を奪った」という歴史理解は一般的である。しかし、日本政府が進める強権的朝鮮統治政策に、日本の神道人が強く反対したという歴史もある。朝鮮神宮に朝鮮民族の祖神ではなく天照大神をまつることに抵抗し、日韓併合に反対したのは、神道人である。
戦前・戦後を通じて、もっとも偉大な神道思想家といえば、今泉定助である。「憂国慨世の神道思想家」ともいわれ、歴代首相のほとんどがその国体論に耳を傾け、官僚、軍人、財界人が教えを乞うたと伝えられる。それほどの影響力を持った神道思想家は、昔も今も、今泉以外にはいない。
その今泉が昭和8年暮れから翌9年正月にかけて、陸軍参謀本部の要請で5回にわたって「国体の本義」を連続講演しているのだが、講演の中で今泉は、日本政府の朝鮮政策を厳しく批判している。
「明治天皇が日韓を併合されたのは両民族の平和幸福のためであることは言うまでもないが、その後の朝鮮総督政治は御趣旨に反しているのではないか。歴代総督は施政の大方針を誤っている。朝鮮人の生命たる信仰、倫理、道徳、歴史、風俗、人情、習慣などはほとんど無視して顧みられない観がある。一も二もなく、ことごとく日本化せしむることをもって政治の要諦とするかのような観があるのは、長嘆息を禁ずることができない」というのだ。
ずいぶん思い切った内容だが、講演録は「取扱注意」と表書きされたうえで参謀本部から刊行され、陸軍部内に配布されたという(『今泉定助先生研究全集3』)。

雑誌「正論」平成10年3月号掲載の拙文「朝日新聞と神道人」に書いたことだが、日米開戦後、東条内閣は宮内省の官僚が唱えた天照大神信仰に統一する一神教的な合理主義的神道論を正統とし、17年2月、今泉の神道論などを発禁処分とした。「神道人のなかの神道人」というべき今泉が、戦時体制下では東条内閣の極端な統制政策の標的とされたのである。
このとき戦時政府の思想言論統制に昂然と立ち向かったのは、葦津珍彦ら神道人であった。やがてくだんの宮内省官僚は依願免職となり、東条内閣の検閲方針は撤回される。
思想統制に引き続いて持ち上がったのが、国語国字問題である。
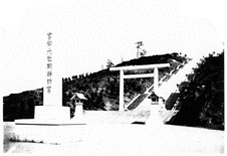
平井昌夫『国語国字問題の歴史』などによると、この年、国語審議会によって漢字制限、かなづかいの改定が進められた。3月、審議会は漢字制限の中間発表をする。これは国民生活に関係の深い「常用漢字」1,112字、生活に関係が薄く、読めればいいという「準常用漢字」1,320字、皇室典範や帝国憲法などに含まれる「特別漢字」71字の3本建てとする合理化案で、趣旨は漢字が無制限に使用され、社会生活上、少なからず不便なため、整理統制して標準を示したと説明された。

これに対して、保守陣営がこぞって反対を表明する。「大法輪」「公論」「大東亜圏」「日本及日本人」「理想日本」「国学院大学新聞」などがたびたび特集を組み、反対論者の所説を掲載した。
国語学者の平井は「いわゆる大戦緒戦の赫々たる戦果に酔い、おごりたかぶった国粋思想家たち思想問題として反対ののろしを上げた」と説明するのだが、どうだろうか。緒戦の戦果に舞い上がったのは軍部であって、いうところの国粋思想家たちすべてではないのではないか。
批判の集中砲火を浴びて国語審議会は6月、中間発表の漢字制限を修正し、橋田邦彦文部大臣に答申する。
翌7月には審議会は新字音かなづかい(字音かなづかい整理案)を発表、同じく文相に答申する。現代の標準的発音によってかなづかいを整理したもので、たとえば蝶(てふ)は「ちょう」、甲府(かふふ)は「こうふ」と改められ、また左横書きが決められた。
新かなづかい答申の翌日、頭山満、今泉定助、市村鑽次郎、松尾捨次郎ほか12名の連署による漢字制限反対の建白書が橋田文相に提出される。
「国学院大学新聞」に転載された建白書は、特別漢字71字で皇室の御事を限定する結果を招く。審議会幹事長の保科孝一が日刊紙(朝日新聞)で「準常用漢字は将来、だんだんなくしてしまう」と公言しているが、準常用漢字の中には教育勅語はじめ皇室典範、帝国憲法、歴代天皇御追号、勅諭、詔書の文字が多数含まれているのはどうするのか--などを改革反対の理由に挙げている。
建白書には頭山、今泉のほか葦津正之、西角井正敬、千家尊宣など、当時の代表的な神道人がそろって名前を連ねている。平井は「建白書を起草したのは元朝日記者で後に国学院大学教授となる島田春雄だと書いているが、のちに葦津が書いた非公開の文章によると、本当の目的は国語改革反対というより、東条内閣の統制政策に風穴を開け、言論の自由を回復させるところにあった。
親しかった朝日新聞主筆・緒方竹虎の情報によって、葦津らはこの戦争に勝ち目はないと考えていた。早期に「名誉ある和平」を図るためには、戦時内閣の無責任とも見える言論統制を打ち破らなければならない。そのための国語審議会批判であった。当局の矛盾をつき、権威主義的な政府にひと太刀を浴びせようとしたのだ。
建白書の反対論は朝日新聞掲載の保科談話が根拠となっていたから、情報局や文部省は「朝日の誤報」として朝日新聞に記事の修正を迫った。けれども葦津の目的に共鳴する緒方は、「否定しがたい証拠のある記事で、当局のミスはミスとして認めてください」と受け付けなかったと伝えられる。
複数の審議会委員が辞任するなどごたごたの末、12月になってようやく文部省は「標準漢字表」を決定発表する。けれどもそこでは、常用漢字、準常用漢字、特別漢字の区別がなくなり、漢字数も答申案より141字多い2,669字と後退した。橋田文相は、「漢字の使用を制限するものではない」と弁明に終始し、字音かなづかいや左横書きは文部省がさらに研究を重ねることとなった。
政府の改革には、日本語を占領地政策の道具に使おうとする軍部の思惑があった。この年、政府は日本語南方進出用「ニッポンゴ」をタガログ、マライ、安南、タイ、ビルマ語で刊行し、フィリピンの公用語は日本語かタガログ語と決定され、ビルマ、ジャワでは英語、オランダ語の使用が禁止された。南方に派遣される日本語教師の養成も始まった。こうした目的のためには、複雑な日本語の整理・合理化が必要であった。しかし、そのもくろみは葦津ら保守派によって阻止された。
こうした隠れた戦時下の国語史を、井上氏はご存じないのではあるまいか。
■なぜローマ字化は実現しなかったのか■
さて、戦後である。

井上氏の小説にあるように、日本語のローマ字化を画策した張本人はCIEのホール少佐らしい。
先の雑誌インタビューで、井上氏はこう語っている。
「あるとき文部省を辞めた人が神田の古本屋にやってきた。それが占領軍のローマ字化計画に関する秘密資料だった。われわれの世代は軍国主義の大きな流れにさらされ、その後、今度はローマ字旋風に巻き込まれた。どうしてこうも右往左往しなければならないのか。手にいれた資料で『ああそうだったのか』と分かった。それでどうしても書きたいと思った」
じつはGHQのローマ字化計画については、井上氏の発掘した資料によらずとも、アメリカの公文書研究によってかなりのことが分かっている。
東洋英和女学院大学の土持ゲーリー法一教授によると、ホールは1945年6月、カリフォルニア州モントレーの民政集合基地の日本占領教育計画主任であったときに、漢字廃止、カタカナ統一の計画を陸軍省民事部長に送付している。軍国主義、国家神道、超国家主義の検閲が容易になるだけでなく、日本語学習が容易になって、教育効果が上がる、というのが利点とされた。国務省極東課の日本担当官にも送付されたが、受け入れられず、最終的に陸軍省はホール案を却下した。
終戦後、来日したホールは日本国内の言語改革、すなわちローマ字による改革の動きが盛んなことを知り、ふたたび情熱を燃やし、今度はローマ字化を提唱し始める。昭和20年11月、ホールは文部省の有光次郎教科書局長らと教科書のローマ字化について討議し、口頭でローマ字化を指令する。しかしこれはCIE内部で統一された考えではなかった。12月、マッカーサーによる組織の再編成でホールは計画課に左遷され、教科書のローマ字化はいったん終止符が打たれる。
ところが、ローマ字化に執着するホールは、翌21年3月に来日するアメリカ教育使節団にローマ字化を勧告させようとひそかに準備する。
ホールは、使節団の来日直前に、「暫定的研究・言語改革の研究」と題する44ページの部内研究をとりまとめる。そこでは、日本の民主化のためにはローマ字の採用が必要であることが強調されていた。これに対して、ニューゼントCIE局長代理は、結論は使節団にゆだねるよう指示する覚書を出す。
使節団の言語特別委員会は報告書の起草にあたって、言語改革を取り上げ、最終的に「使節団は小学校にローマ字を導入し、教科書を2つの言語で作成することを勧告する」という草案をまとめる。ところが、これらは3月末の最終報告書ですべて削除され、柔軟な勧告に変更された。
なぜ使節団報告書の「言語の改革」が緩和されたのか。土持氏は、国務省代表で、使節団顧問のボールズの意向が働いたとみる。ボールズはローマ字化に基本的に反対で、「言語改革は日本側に任せるべきであって、外部から強制するものではない」と考えていた。
同時に、教科書の横書きやローマ字化には賛成しかねるとした日本側教育委員会や、漢字制限、国字改善などを南原繁総長に答申した東京帝国大学教育制度研究委員会の意向も尊重された。教育使節団報告書の公表にあたって、4月7日、マッカーサーは「教育原理および言語改革に関する勧告の中にはあまりにも遠大であって、長期間の研究と今後の教育に対する指針として役立ち得るに過ぎないものもあろう」という声明文を発表している(土持『米国教育使節団の研究』)。
■左横書きをリードした大新聞■
結局、ローマ字化は推進されなかったものの、21年11月、「当用漢字表」と「現代かなづかい」が内閣訓令・告示として公布された。

興味深いのは、これらの戦後改革が東条内閣時代の精神と人材を引き継いでいることである。
たとえば当用漢字実施の趣旨は「漢字数が多く、複雑であるため、教育上または社会生活上、不便であり、漢字制限は国民の生活能力や物価水準を向上させる」と説明している。戦時内閣の国語改革と同工異曲というべきである。
また、現代かなづかい案作成にあたった主査委員長の安藤正次は、17年の字音かなづかい整理の際、「20年来の懸案」という論考を朝日新聞に寄稿したほどの改革推進派である。国語学者たちは東条内閣の力をもってしても果たせなかった自分たちの悲願を、GHQの強権を借りて実現したということであろうか。
井上氏の小説では、新聞カメラマンの高橋が「戦前の漢字制限は文部省、軍部、新聞が進めた」と主人公に語っているが、国語学者の存在を見落としてはならない。占領下の国語改革はGHQ、文部省、国語学者、大新聞の4者によって進められたのである。
とくに大新聞の力は隠然たるものがあった。「君子は豹変す」というが、戦時体制下では軍部の戦争政策に積極的に協力し、敗戦後はGHQにおもねたのである。権力に対してどこまでも弱いのが、大新聞の体質なのだろうか。
口火を切ったのは、読売報知らしい。昭和20年11月12日の社説で、読売は「漢字廃止論」を書いている。レーニンを引用し、「トルコの父」ケマル・パシャの例を挙げて、漢字廃止は民主主義運動の一翼だと主張している。毎日新聞は翌21年4月16日、「国語の改革」という社説で、伝統に執着していては文化国家の進歩も向上もないとして、ローマ字化への道を唱えている。
その点、日経新聞と朝日新聞は慎重である。日経は21年4月9日の社説「教育使節団の報告を見る」で、漢字学習の負担軽減とローマ字化は別問題、と戒めた。
左横書きをリードしたのは、やはり大新聞であった。
日本語には本来、横書きはない。横書きは1行1字であって、当然、右書きになるといわれる。昭和17年に国語審議会が左書きを答申したが、実現されなかったことは前述した。戦後、アメリカ教育使節団の報告書を受けて、吉田内閣は当用漢字と現代かなづかいを公布しているが、左書きについては触れていない。
朝日新聞が左書きを始めるのは22年元旦で、「おことわり」に「本社はさきに当用漢字、新かなづかいを採用し、紙面の平明化をはかってきましたが、新春の紙面から『左横書』を併用することにしました」とある。欄外の発行日付に西暦が加えられたのもこの時である。読売は1年前の21年元旦から左横書きを始めている。戦時中、広告面の「米英的左書き」追放を推進したのは毎日、朝日であったようだが……。
すっきりしないのは文部省の対応である。省内刊行物の基準を示した昭和25年発行「表記の基準」の「付録」に、「横書きの場合は、左横書きとする」と記されてあるだけらしい。大新聞に追随し、省内基準とすることで官僚たちは責任逃れをはかったのであろうか。
さて、井上ひさし氏の『東京セブンローズ』が全編を通して漢字は正字、カナは歴史かなづかいで書かれていることは重要である。井上氏にとって、正字、歴史かなで書かれたほとんど最初の作品らしい。少し厳密に言えば、丁度(ちょうど)は「ちやうど」、庄内(しょうない)は「しやうない」と、和語だけでなく、漢語も字音かなづかいを避けているから、国語審議会を基準にすると、大正時代以前のかなづかいを意識しておられるのだろうか。
井上氏の『私家版日本語文法』に「ふたつの仮名づかい(ひ)」という一章がある。その末尾に「新カナと旧カナのどちらを支持するかといえば、歴史かなづかいに決まっている。それは日本国憲法が歴史的かなづかいで書かれてあるからだ」と井上氏は書いている。
いかにも井上氏らしい理由だが、新カナか旧カナからという選択は昭和21年の内閣告示を基準としたもので、厳密な議論とはいえまい。大正13年に臨時国語調査会(のちの国語審議会)が決定した「仮名遣改定案」などは、昭和21年制定の「現代かなづかい」をさらに上回る発音重視の、時代を先取りしたかなづかいであった。
言葉は生き物である。祖先から受け継がれた生きた文化財としての日本語の伝統を守りつつ、現代性を取り入れ、生命感あふれる美しい国語を実現していくためにはどうすればいいのだろうか。
追伸 この記事は「正論」平成11年10月号に掲載された拙文に若干の修正を加えたものです。
日本はかつて外国に侵されたことのない国で、「神州不滅」ともいわれましたが、60年前、ほとんど全世界を相手の無謀な戦争に突入し、結果的に数百万の尊い人命を失い、国土が焦土と化す無惨な敗戦を味わい、そのうえ外国軍隊による占領を史上初めて体験することになりました。
その過酷な占領時代にあって、「ローマ字化」という国語変革の干渉に抵抗した日本人たちの存在は重要ですが、そうした歴史をいまかえりみることにむなしさを感じるのは、ボクだけでしょうか。
考えてもみてください。インターネット・エクスプローラーを立ち上げれば、デスクトップの片隅で星条旗がはためいています。ボクはカナ入力にこだわっていますが、多くの日本人ユーザーはローマ字入力でコンピュータを利用しているのではないでしょうか。コンピュータ導入によって、日本語はすでにローマ字化しているのです。
