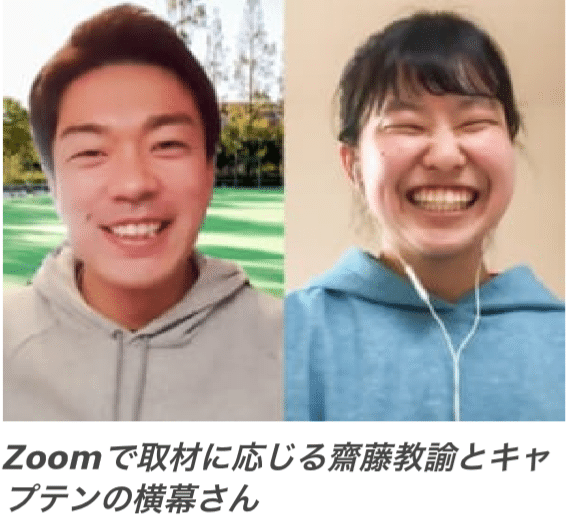もしも、高校女子ハンドボール部が、オンライン部活を1か月続けてみたら。
7都府県には約1か月間の緊急事態宣言が出され、緊迫した状況が続いています。春休みを含め、「コロナ休校」は早くも6週間近くとなりました。新年度、4月に入ってからはオンラインでの教育活動も数多く目にして、勇気づけられます。
ところで、休校中の部活動についてはどうなのでしょう。ちょっと前の記事ですが、「闇部活」は大きな批判を浴びました・・・。教育課程外であるため優先順位が低く、元々「働き方改革」「ブラック部活」などの問題点が指摘されているためか、部活動に関する実践は圧倒的に目にしない、というのが個人的な印象です。
勤務校でも集まっての部活動はできませんでしたが、有り難いことに「休校中も生徒たちのモチベーション維持に努めること」というお墨付きを頂戴したので、生徒たちにも「どうする?」と振ってみました。結果として、最低限度「部活を止めるな!」を達成できたので、小さな成功と、数々の失敗について書き留めておこうと思います。
「まずは学級や授業でしょ!」というご指摘は十分承知です。ただ、高3となったハンドボール部員5人にとっては、コロナによって引退試合がなくなるかもしれない、という切実な問題でもあるのです・・・。
中1から今まで続けてきた部活動引退までの花道を、なんとか飾りたい。「部活をやってきて楽しかったし、成長できた」という成功体験にして欲しい。ただ、その一点の想いだけで始まった挑戦であることはご理解下さい。
①オンラインミーティング by Zoom
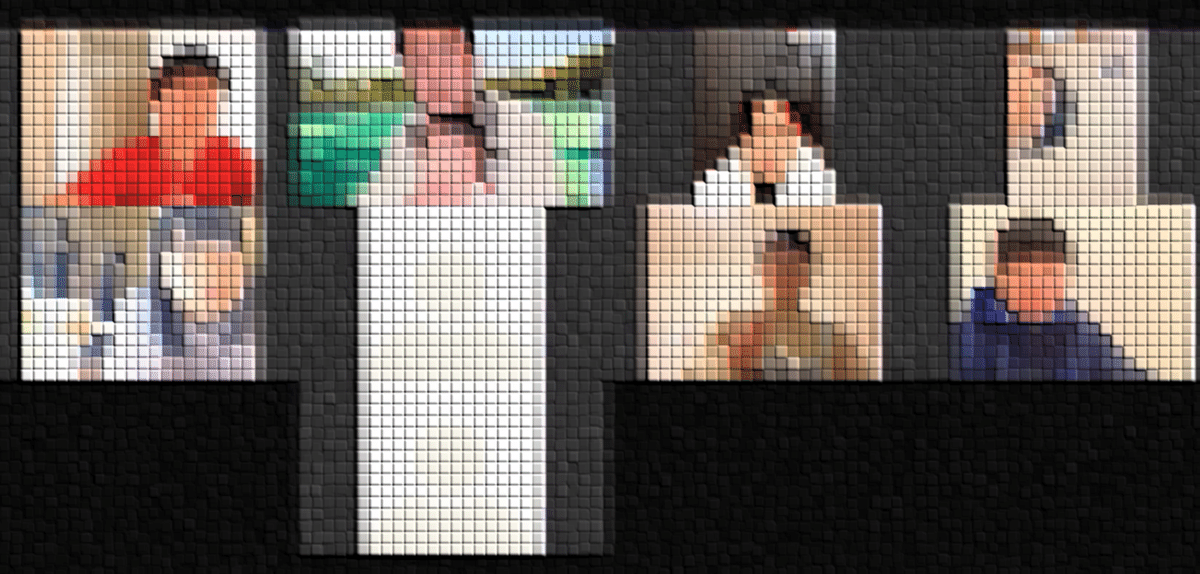
3月初旬、緊急事態宣言が発令される1か月前。まずは「生徒が元気かどうか、確認する」ところから始めました。
「調整さん」というサービスを使い(わずか11人の部員なので)全員が参加できる日を調整しました。
↑調整さん
↑Zoomの使い方(和歌山大学教育学部附属中学校・矢野 充博 先生より)
↑Zoomの注意点(東京大学 情報基盤センターより)
キャプテン・部長と事前に相談した上で、
A.どんな風にトレーニングを進めていくか
B.(事前に共有した)ハンドボール動画の振り返り
C.筋力トレーニング
をオンラインミーティングで行うことにしました。
しかし、いざチャレンジしてみると・・・
「なかなか発言できない」「顔を出す生徒と出さない生徒がいて、生徒が困惑する」「トレーニング中もリアクションがない」などの課題が・・・。
それでも、トレーナーにも協力してもらい、週1回のペースでミーティングを重ねました。生徒の振り返りをもとに少しずつ改善し、3回目くらいからは積極的に議論できるようになりました。失敗を踏まえ、以下のようなことを事前に検討しておくと良いと思います。
1.顔を出すことは強要しない:顔を出してくれたら、元気な様子が見れて嬉しいは嬉しいですが、それはこちらのエゴかもしれません。プライバシー保護の観点もあるため「出さなくてもいいよ!」と告知しておくと良いと思います。「場」を作ることを優先しました。
2.小グループでの活動を入れる:よく考えたら、これはオンラインじゃなくても同じです。Zoomには「ブレークアウトセッション」という機能があり、小グループに割り振ることができます。3人程度のグループに分け、全体の場は「議論」ではなく「共有」に徹したことで、ミーティングが活発になりました。
3.振り返り&次回への展望:オンラインミーティングは、顔を出していなかったりリアクションが見えなかったりする分、参加者は普通のミーティングよりも神経をすり減らします。だからこそ、指導者から一方的にコンテンツを配信して「やらせる」のではなく、生徒たちの方から「今やるべきこと/やりたいこと」を出すことを心掛けました。
②セルフトレーニング

週1回のオンラインミーティングに加え、上記リンクのようなGoogle formを活用して、日々の活動記録を共有するという取り組みを行いました。こちらも、気を付けた点がいくつか。
1.ちょっとずつでも続ける:トレーニングについても、正直なところやれることは限られています。しかし、活動を「ゼロ」にしてしまうと、体力面だけでなく精神的にも自信が失われてしまうことが懸念されるため、「細くても、長く続ける」ことを大切にしました。毎日、生徒たちが取り組んだ成果は、Excelを画像データにしてフィードバックしています(spread sheetsの共有でも十分だと思います)。

2.勇気づける:これは生徒たちからの反応がないので少し寂しいですが(笑)、トレーニングの結果を送ると「格言」が登場する画面を毎日更新しています。言語は、思考の種です。そして、「今日はどんな言葉を贈ろうかな」と思索するのは、僕にとっても楽しい時間です。

3.強要はしない:生徒によっては、都合が悪い日もあるでしょうし、気乗りしないこともあるでしょう。生徒たちには事前にゴメン!と断った上で、毎日フィードバックすることにしています。本当は「連絡しない日」を作りたい気持ちもありますが、バラバラにやる以上、個々人の事情によってオフの日も違うので。必ずしも毎日、トレーニング結果を送らなくても良いと伝えています。
また、(学校のある)神奈川県の黒岩知事は、「散歩やジョギングが問題ない」としていますが、抵抗がある生徒もいるかもしれないので、強要はしません。
オンラインになって、いっそう主体的で自律的な活動であるべき部活動の真価が突き付けられました。ただし、「自立」と「孤立」は違います。どうして良いかわからずに「孤立」し、「何も出来ない」という状況だけは避けたかったのです。ちなみに、部員たちは僕が連絡する前に、既に行動していましたが。本当にもう、感服です。
③全員リーダー制
「ボトム・アップ理論」で著名な畑喜美男氏に倣い、今年のチームでは「全員リーダー制」を導入しました。今回のように集まることも出来ない状況で、トップダウン型の中央集権的な組織では個々の主体的な行動は期待できません。
部員が少ないからこそできた側面もありますが、部員が多ければ「班」に分けて実施するのも一案です。
・キャプテン・部長:ミーティング内容の検討
・戦術班:動画の選定や分析
・トレーニング班:トレーニング動画作成と実施
・、まとめ班:ミーティング内容のまとめ・共有
・予定調整班:ミーティング日時の調整
などにキャプテンが分けてくれました。役割意識をもって活動することで、休校中でも「チームの一員」としての自覚を持てます。休校中の部活だからこそ、それぞれが自分のプロジェクトを持ち、リーダーシップもフォロワーシップも発揮することが求められているのだと思います。
④生徒たちの声
部員から掲載の許可を得たので、「ふりかえり」を一部紹介させてもらいます。
Q.休校中もZoomやGoogle formで部活を続けて良かったのは、どんな点ですか?
チームのメンバーと話したり一緒にトレーニングを行うことでモチベーションが上がった。単純に元気になった。
いつも会っていたので、みんなの顔が見えたり声が聞けるのが嬉しいと初めて思いました。
今、外でみんなそろって体を動かすということができない中でも、チームの底上げを意識して、メンバーひとりひとりが筋トレをしたり、今までの試合を振り返ったり、チームの目標やモチベーションの維持の再検討を行う、といったような関わり方をできたというのは自分の中で自信となっています。
部活の参加に対して多角的な捉え方ができるようになりました。部活とは、チームや自身で決めた目標などのために様々な方法や手段を用い、自分らしく参加することだと、今回のZoomやGoogle formでの部活で改めて感じました。
いま、最後の引退試合、ましてや普通の部活をせずに受験生になってしまいかねない状況です。最後に振り返った時、「コロナのせいで何もできずに中高の部活終えるんだね」ではなく、「最後まであの状況の中、自分たちの部活を出来たよね」と、コロナバケーション中もZoomやGoogle formで部活を続けたおかげで振り返ることが出来そうです。
「つながり」「刺激」「モチベーション」「安心」といったキーワードが数多く見られました。
ちなみに、「自己評価を10段階で」と伝えたところ、11人の平均は「6」でした。もともと、キツいトレーニングも手を抜かずに取り組む意識の高いメンバーなので、自己評価は厳しめにつけたのでしょう。「十分にできなかった」と答えた生徒も少なくありませんでした。
でも、そんな数字、どうだっていいのです。時にトレーニングできない日があったって、彼女たちは「1か月の自主練」を、支え合いながら続けました。ボールにもロクに触れられず、大会もあるかどうか分からない中でも「諦めない!」という意地を、存分に見せてくれました。

⑤最後に~部活動の目的って、なんだっけ?
学年末試験前の休みに入った2月下旬。突如、安倍首相によって出された休校要請。その頃は「1か月部活出来ないのか・・・」くらいに、生徒も僕も捉えていたと思います。それが、今や緊急事態宣言が出され、部活動どころではない緊迫した状況となっています。
考えたくもないですが、もしも最後の大会がなくなってしまったとして、引退する生徒たちに「残念だったね」という言葉で締め括っていいのか・・・。この問いが、頭から離れませんでした。
窮地に追い込まれたとき、人は本質にブチ当たります。そもそも、部活動の目的って、なんだったっけ・・・と。中高の学習指導要領には、このように書いてあります。
「生徒の自主的,自発的な参加により行われる部活動については,スポーツや文化,科学等に親しませ,学習意欲の向上や責任感,連帯感の涵養等,学校教育が目指す資質・能力の育成に資するもの」
「勝つこと」にはもちろんこだわりたいし、部員も目標達成を目指して「トレーニングを止めるな!」でやっているけれど、それは目標であって目的ではありません。
多くの指導者の方々は、部活動を通して「やり抜く力(GRIT)」や「レジリエンス」が身に付くこと、そして『Most Likely to Succeed』に引けを取らない「最高の日本版PBL」であることを、経験則としてもご存知でしょう。
集まって部活動ができない状況になっても、発想を変えれば部活動の「目的」は(ある程度)達成できます。目的を達成するため、目標は柔軟に検討するしかないのです。
状況を嘆くだけでは、何も変わりません。「人事を尽くして天命を待つ」という言葉がありますが、いま出来る最大限のことを尽くす以外、選択肢はないと思うのです。僕自身、まだまだ人事を尽くし切れたとは言えません。挑むべき壁がたくさん残っています。

この記事をご覧になった方からは、「ネット環境がない場合はどうするんだ?」「休校中も部活動で縛るのはどうなんだ?」というご指摘を受ける可能性があることも、承知の上で書いています。そういうマクロな議論は別に譲り、最初に述べた通り「目の前の生徒と対峙した」一例として、本実践を紹介することにしました。
Zoomでのオンラインミーティングも、手段であり目的ではありません。セキュリティやインフラ面でZoomが難しければ、電話でもいいし、手紙だっていい。そもそも、指導者が介入していなくても、生徒同士で繋がっていればいいかもしれません。
ただただ、学校生活のコミュニティとして重要な「部活動」の機能を何とか維持するため、その想いを共有したくて、記事にしました。
一刻も早く、新型コロナウイルスを収束させるために可能な限りStay homeしながら、これからもピンチをチャンスに変えていきます。ここまでお付き合い頂き、本当に有り難うございました!
【追記:4/22教育新聞に掲載されました(有料記事です)】
【コロナと学校】女子ハンド部がオンライン部活に挑戦