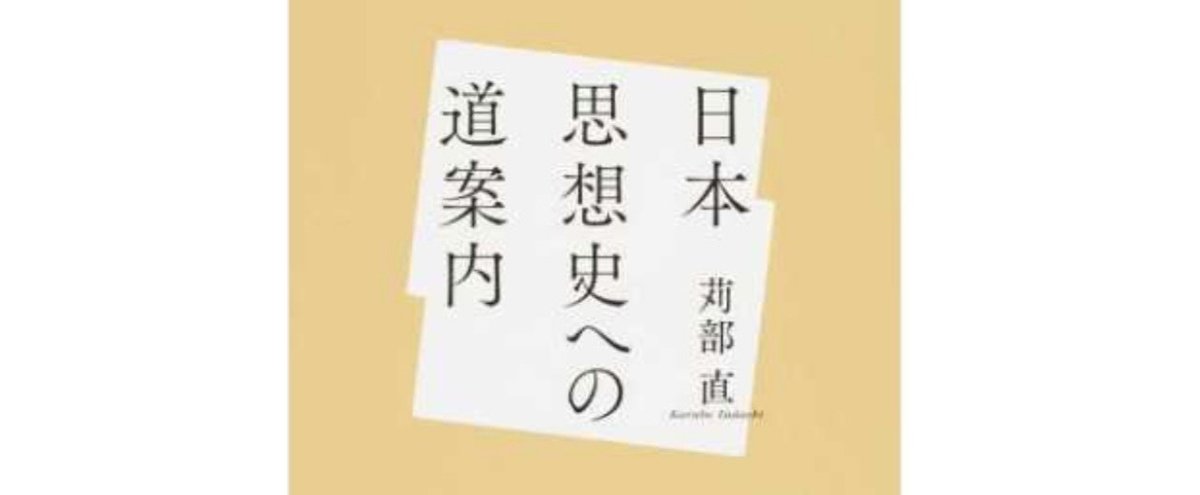
神話、武士道、儒学、明治維新……『日本思想史への道案内』
◆苅部直著『日本思想史への道案内』
出版社:NTT出版
発売時期:2017年9月
日本の思想や哲学などの人文科学は、口の悪い人からは「ヨコのものをタテにしただけ」としばしば指摘されてきました。西洋語で書かれたものを日本語に置き換えただけだではないか、というわけです。そのような認識もあってか、日本の思想を歴史的に検証するということはあまり熱心に行なわれてこなかったようです。「日本思想史」なる学問が確立されたのはそんなに昔ではなく、1930年代といいます。
私たちの社会で営まれてきたものでありながら、親しみやすいとは言い難い日本思想史について、本書はその魅力の一端を示そうというものです。体裁としは日本思想史のなかで「重要な話題を選んで時代順に並べ、それぞれに関して、いくつかの読み方を提示」していきます。
そうして〈日本神話〉や〈武士道〉〈儒学〉など日本思想史のキーワードとなるものが俎上にのせられているのですが、それらを吟味するにあたっては主に二人の読みの名手──和辻哲郎と丸山眞男のテクストが多く参照されています。
学界ではすでに常識とされていることでも初学者にとっては「へぇ〜」と思えることはいくらでもあるもの。本書に関していえば、個人的には儒学や朱子学など江戸期の日本で展開された思想に関するステレオタイプの認識を改めさせられることがいくつかありました。
たとえば、一般に儒学は江戸時代の身分制による支配体制を支えた思想と言われることが多い。私自身も日本史の授業でそのように習ったと記憶しています。しかし「朱子学どころかそもそも儒学が一般に、徳川時代の身分制による支配体制とあいいれない性格をもっていること」は、津田左右吉が指摘していました。儒学とはそもそも身分制批判の要素を含んだ思想なのです。
また明治新政府が行なった西洋を規範とする政治体制の刷新を思想史的にはどう考えればいいでしょうか。明治維新によって人びとが突然、西洋由来の政治理念に目覚めたわけではもちろんありません。
江戸時代の末期には民間から新たな学問を創造する動きが活発化し「身分の別を無視した知識階級といふ如きもの」が現われました。そうした背景があったからこそ、王政復古の後ただちに廃藩置県を導いて封建制に終止符を打つことが可能になったとする和辻の見解は興味深いものです。
本書の記述は、良くいえば手堅い筆致、悪くいえばいささか辛気臭い読み味ながら、日本思想史の勘所をかいつまんでガイダンスしてくれるという点では文字どおり良き道案内の書といえるでしょう。
