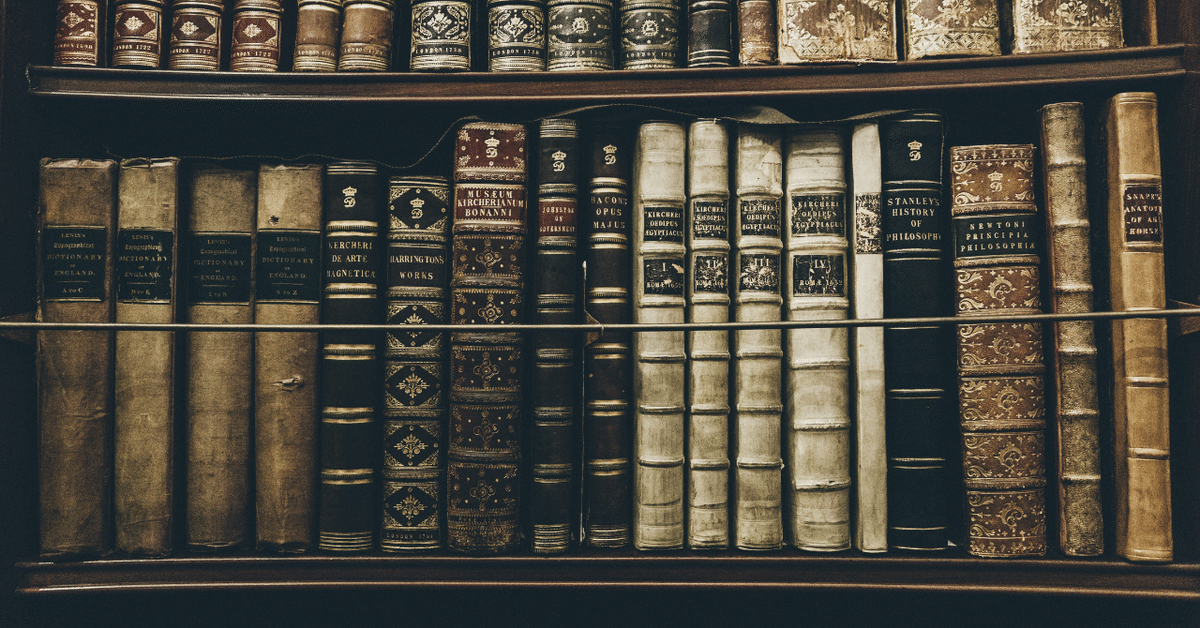
図書・図書館史レポート
図書・図書館史のの合格レポートです。
レポートの丸写しは評価の対象外や不正行為とみなされる恐れがありますので、参考程度にとどめてください。
◆設題
日本または西洋のどちらかを選び、それぞれの時代(古代、中世、近世、近代以降)の図書館発展の特徴をコンパクトに要約し、かつ私見(400字程度のまとめ)を述べてください。
◇解答
1.はじめに
本稿では,日本における図書館の歴史をそれぞれの時代ごとに分類し,図書館発展の特徴をまとめ,最後に私見を述べる。
2.日本における図書館発展の特徴
⑴古代
古代の日本には独自の文字はなく,朝鮮半島より漢字が伝来され,4,5世紀頃には漢字と書物が使用されていたと考えられている。
5世紀中頃には仏教の伝来により,紙や墨を使用した経典が普及し,聖徳太子によって仏教は保護され興隆していった。また仏教の伝来は,仏典などを保管する経蔵や文庫の発生を促した。その後遣隋使により大陸の諸文化が伝えられ,大化の改新で文書中心の律令制度を構築した。行政文書を扱う部署として,図書寮が大宝律令によって定められた。図書寮は図書の保管,書写などを専門に扱う一寮であり,役人には図書の閲覧・貸出も行われた。
奈良時代は,年代が特定できる世界最古の印刷物とされる『百万塔陀羅尼』が製作され,石上宅嗣により日本最初の公開図書館である「芸亭」が設けられた。
平安時代の貴族である菅原道真は「紅梅殿」という文庫を所有し,私塾としての機能を備え,一門の子弟に公開していた。
⑵中世
鎌倉時代になると貴族に代わり武士が台頭し,封建制度が確立された。印刷出版事業では中国との交流が深まり,文書の複製技術が一段と高められた。また,武家の文化が成立したことにより,文化の庶民性が強くなった。文学作品では『平家物語』,『方丈記』など様々な書物が発表された。
鎌倉中期,北条実時によって代表的な武家の文庫である「金沢文庫」が設けられた。学僧たちに利用されたが,利用には厳しい規定があり,公開図書館としての側面は薄かった。図書には蔵書印が押され,所有の主張が示された。
室町時代に上杉憲実が再興したことにより大きく発展したのが,現存する日本最古の学校図書館,「足利学校」である。儒学中心であり,特に易学と兵学に力を入れた。学生は僧侶のみに限定されたが,ここで学んだ学僧は,戦国武将の軍事顧問として重用された。足利学校の文庫にも利用規約があり,厳しい制限があった。
⑶近世
江戸時代は,徳川氏のもと約270年間天下泰平の世が続き,封建社会における平和は,江戸庶民にも文化の花を咲かせた。これまでの文化は,貴族や僧侶の掌中に帰していたものが,下級層にまで伝播し,国民文化,町民文化として栄えた。この時代は商業出版が確立し,整版本が盛況を迎えた。
家康により江戸城内に設置された「富士見亭文庫」は,最初の官立図書館であり,江戸幕府の参考図書館でもある。三代将軍家光は現代の司書に当たる「御書物奉行」を設置し,書物の管理に当たらせた。この他,大名諸藩の文庫,朝廷・公家の文庫や幕府直轄の昌平坂学問所の文庫など多数設けられた。
江戸末期になると読者人口が増え,武士階級だけじゃなく庶民にも書物が普及した。公共図書館のきっかけとなる庶民の文庫として,「浅草文庫」が一般に公開された。貸本屋も登場し,広く庶民に親しまれ,図書館的な機能を果たした。
⑷近代以降
慶応4年,徳川氏の長きに渡った封建社会もついに崩壊し,明治維新という近代化を目指す大改革が行われた。福沢諭吉は著書『西洋事情』において,欧米諸国の図書館事情を紹介した。以後にに与えた影響は大きく,当時のベストセラーとなった。
明治5年,後の国立中央図書館の礎となる,最初の図書館である「書籍館」が開設された。また同年,わが国最初の一般公開図書館と言われる「京都集書院」,この他近代公開図書館の先駆けには,新聞縦覧所や貸本屋などがあった。
1899年,日本で初めて図書館の法律である「図書館令」が公布された。以降,戦後の図書館はアメリカの指導のもと再出発した。図書館の民主化が高まり,1950年に「図書館法」が制定され公共図書館のありかたが示された。設置及び運営に関して必要事項を定め,司書の職務規定と資格,図書館奉仕など今日へと至っている。現在も試行錯誤を繰り返し,更に充実した図書館運営の取り組みがなされている。
3.おわりに
それぞれの時代に分類し,図書館が発展するまでの歴史を振り返ってきた。図書館のありかたは時代によって異なり,様々な変化を得て現在の姿へと移り変わってきた。今もなお時代の変化に対応し,終わりのない課題に挑戦し続けている。
レファレンスサービスの充実が求められる一方,課題の一つとして大きく挙げられているのが,図書館の電子化である。情報化社会の今,公共図書館にも電子サービス機器が普及し,利用も増えている。コロナ化以降電子図書館サービスの利用も増加し,利用者が自ら選択し図書館を利用できる仕組みがとられている。また,近年AI技術の進歩により,人と機械の相互利用の図書館運営がなされている。しかし,このAI技術を生かした取り組みは,新規の図書館には導入しやすいが,既存の図書館にはなかなか導入が難しいのが現状である。時代の波に乗りつつも,利用者が利用しやすく,職員が働きやすい環境を整え,これからの図書館を皆で共に考えていくことが重要である。
文字数 2085文字
文献 編著:千 錫列『ベーシック司書講座・図書館の基礎と展望10 図書・図書館史』学文社
~感想~
設題のポイントをしっかり押さえ、日本の図書館史を大変分かりやすくまとめられています。特に初期の図書館が限られた特権階級のためのものから、現代の誰でも自由に使えるものに変化してきたことを理解している内容であり秀逸でした。私見も納得できる内容でした。
との講評をいただき小躍りしました!ただ、欲を言うと『中小レポート』『市民の図書館』などに言及して欲しかったとのことで、この字数内におさめるのはムズイやろ~~‼と、思いました。
本当に、字数内に歴史をコンパクトに要約するのは大変でした。
また、参考文献情報で、図書情報には刊行年を必ず書きましょうとのことでした。みなさま、書きましょう!
図書館概論のレポートと添削者が同じ方らしく、とても丁寧なお言葉で講評を頂けて感激でした。添削までは日数がかかるのでの~んびり待ちましょう。
