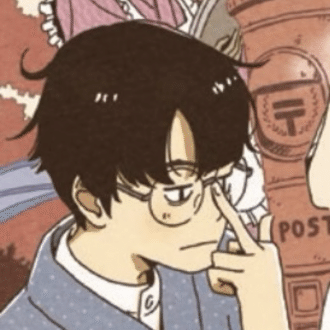note連続小説『むかしむかしの宇宙人』第36話
前回までのあらすじ
時は昭和31年。家事に仕事に大忙しの水谷幸子は、宇宙人を自称する奇妙な青年・バシャリとひょんなことから同居するはめに。幸子とバシャリは喫茶店に向かう。
お父さんの隣に女性がいる。想像すらしない場面に出くわし、頭がまっ白になった。
二人はこちらに気づくことなく、わたしたちと対角線上にある窓際の席に座った。ちょうどこの位置からは、彼女のうしろ姿しか見えない。
そういえば、あのマッチはお父さんのだった。ここはお父さんの行きつけの店なんだ。今さら気づくなんて、とんだまぬけだ。
「周一_」
呼びかけようとしたバシャリを、あたふたと止める。
「何やってるのよ。早くかくれて」
バシャリがきょとんとした。
「幸子、周一ですよ。生物学的にあなたの父親にあたる人物ですよ」
「わかってるわよ。とにかく気づかれないようにしてちょうだい」
わたしのあせった口調に、バシャリはようやく身をかがめた。植木鉢の隙間から顔を覗かせ、彼女の様子を観察する。
髪の毛を上でまとめ、背筋を伸ばして座っている。服装も質素で派手な印象もない。夜の商売ではなさそうだ、とひとまず安心した。
顔をたしかめたいが、お父さんに気づかれる危険性が高くなる。しかたなくあきらめた。
ただ、彼女の顔はうかがえなかったけれど、首もとの白さがやけにあざやかに感じられた。
お父さんの口元にほとんど動きはない。時折、小さく頷くだけだ。
けれど少ない会話にもかかわらず、それにともなう気まずさは感じられない。初対面じゃないんだ。握りしめた手のひらから、汗がじわりとにじむ。
お父さんがかばんに手を入れ、何かをとりだした。それを机の上に置く。よく見えないのでぐっと目に力を込めた。
ずいぶんと厚みのある封筒だった。封筒の隅にぼんやりと判子らしきものが見える。見覚えのある封筒だった。彼女は深々と頭を下げると、その封筒を受けとった。
「……行きましょう」と、わたしはぼそりと言った。
「えっ、いいんですか?」と、バシャリはお父さんとわたしを交互に見やった。
「いいのよ、出ましょう……」
お父さんの視界に入らないように注意しながら店を出た。
帰り道、わたしは黙々と歩き続けた。さっきの光景の意味を考えると疑問が嵐のようにうずまき、あの封筒とその厚みが心にべたりとはりついた。
あの封筒は、お父さんが生活費を入れる封筒と同じだ。
さらに封筒の厚みから察すると、相当な金額だった。つまり、お父さんは家にお金を入れず、彼女に援助しているのだ。
わたしが日々のやりくりに苦労しているのを知りながら、見知らぬ女性に大金を渡している。博打だけではなくそんなことまで……
ぐるぐると思考するわたしの心中にも気づかず、バシャリがのんびりとした口調で言った。
「あの女性は周一の恋人ですかねえ。手をつないでいませんでしたが、周一もなかなかやるものですよ」
じとりとバシャリをにらむ。バシャリはびくっと体をふるわせ、おそるおそる訂正した。
「冗談ですよ。冗談……あくまで宇宙人特有のたわいもない冗談ですから……」
両肩に大きな憂鬱がのしかかる。はあと息を吐いた拍子にバシャリがつぶやいた。
「ですが、あの女性_どこかで見た気がしたんですが……」
終わりまで聞かず、わたしは足を速めた。
「待ってくださいよ。幸子」バシャリの声が背中に響いた。
家に帰ると、早速茶だんすの上にある封筒をたしかめた。間違いなく、喫茶店で見た封筒と同じものだ。
ふいに遺影のお母さんと視線が合った。嫌な予感がむくりとわきあがる。もしかして、お母さんが生きているときもお父さんはあの人にお金を送っていたんじゃ……
いや、いくらなんでもそんなはずはないわ……そんなはずは……
不安を、死にものぐるいでかき消した。お母さんが亡くなってからあの女性に援助するようになったんだ。
そう自分に言い聞かせた。だが、嫌な想像はぬぐいきれない。お母さんのためにも、お父さんを信じたかった。
けれどそんな決意をあざわらうかのように、疑念が喉元にまとわりつく。わたしは、それをふりきることができなかった。
「幸子、ちょっと来てください!」
バシャリの大声が聞こえた。深く息を吐き出し、くすぶった想いを追いはらってから「一体、何事なの」と振り向くと、玄関に立つ星野さんの姿が目に入った。
上等な生地で仕立てられていそうな純白のシャツの袖を無造作にまくりあげ、右手の帽子で顔をあおいでいる。空とぶ円盤研究会の月例会以来だった。
「星野さんどうかされたんですか?」
「近くまで寄ったものだからね」
星野さんは柔和な笑みを浮かべた。
作者から一言
周一は家にお金を入れず、女性にお金を渡していました。そのことが幸子にはショックでならなかったようです。ますます幸子と周一の間に溝が深まりました。そしてバシャリは恋人という概念に興味津々の様子です。
いいなと思ったら応援しよう!