
アマチュアのことばの特権と意味について 2023/12/28
「人生ではアマチュアであることが、また1つの職業である。」という格言を残してるのは、詩人•萩原朔太郎(1886-1942)です。格言それ自体をつぶさに眺めているだけでは、あちらこちらで平積みにされている自己啓発本にも似たようなことが書いてあるような気がしなくもないのですが、こう喝破したのが、スタートアップの起業家でも、セミナー・コーチング講師でもなく、“詩人”たらんとした大正時代の人間であることにいくらか注目を払う必要があるように思えます。
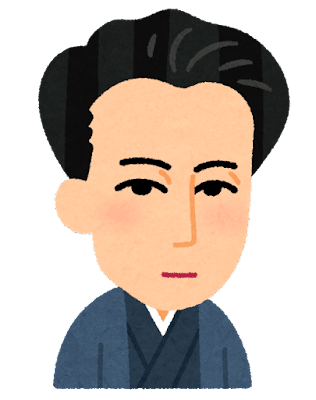
もしも朔太郎が、詩人ではなく、小説家と呼ばれる存在として名を馳せていたなら、彼は同じことを言ったでしょうか。“アマチュアであること”を人生におけるもう一つの職業として真摯に位置付けることが出来たのは、彼が他でもない“詩人”だったからではないでしょうか。
然らばアマチュアたるのとをもう一つの職業として生きることを提言する詩人とはどんな性質をもった存在だったのか。
いやいや、“詩人の条件”なんてものを語るような資格は自分には少しもないし、じぶんのちからではとても手に負えない問いです。かといって、じぶんのなかに、詩人のアーキタイプが、明確なイメージとして蟠踞していることもまた否定できないことです。
朔太郎より二回り歳下に、けれども30歳の若さでこの世を去った詩人•中原中也(1907-1937)がいます。長らく中也の友人だった小説家•大岡昇平(1909-1988)は、中也の死後、はじめて彼の生家に訪れた際に、彼の写真を目の前にして、こう振り返ります。
中原の写真が出された。告別式の時棺の前を飾り、創元社版『中原中也詩集』の巻頭に載せられた、あの無帽背広の半身像である。
十年振りで見る中原の顔は、かつて棺の前で私を打ったのと同じくらい強く私を打った。私の彼に対する考えは変わった。
生涯を自分自身であるという一事に賭けてしまった人の姿がここにある。常にその決意と力の意識を通して、自己にも他にも向けていた厳しい眼を今撮影室の壁間に移し、諦念を以て世間の前に置き続けたと同じ姿勢を、そのままレンズに晒しているのである。(強調は引用者)

大岡は、中也の詩と、詩に貫かれた生涯を「不幸」だと云います。“生涯を自分自身であるという一事に賭けてしまった人の姿がここにある”という一節を読んで、私は、なぜ、百年も前の詩人のことばが、いまもなお私たちの孤独を慰め、触発するのか、ということが少し分かったような気がしました。大岡の回想は、先に引用した朔太郎のことばと深く呼応しています。アマチュアであること、朔太郎はそれを“また一つの職業”であると言いましたが、朔太郎にとって、それは“もうひとつ”の職業ではなく、詩人たらんとする限り“ただひとつ”の職業だったのではないでしょうか。だとすれば、中也は、アマチュアであること、すなわち“自分自身であるという一事”に生涯を賭けてしまった、そうであるが故に中也は百年経っても詩人のアーキタイプであり続けているのではないでしょうか。
それは、ある意味残酷なことではないのか、私は時々そう感じます。中也や朔太郎によって慰められる百年後の私達は、“自分自身であること”を彼らを身代わりにすることでしか回復出来ず、彼らは百年経っても、抑圧した精神のいけにえとして費やされる運命にあるからです。
(※以下、話が行ったり来たり脱線したりしていますので、どうかお見知りおきください)
生活の内々でふつうに用いられている言葉を、日常の語法からは到底導き出せないような意味へと抽象化してから、慎重に、割れ物を扱うかのように使用する学問のお作法は、じぶんのような門前の小僧にとって大きな壁として現れます。もちろん、そうしたお作法を継承し続けることでしか守られないある種の質や伝統があるのでしょうから、それに対して異議申し立てをする権利は、門前の小僧には当然ありませんし、するつもりも毛頭ありません。知に携わろうとするなら、最大限の尊敬を持って習得しなければならないトラディションであることを忘れてはならないと考えています。
(日本語の“しかし”あるいは“でも”“だけど”etc...という接続詞から文章をはじめると、それだけでどことなく前述の内容にプロテストしているように見えて、その度にいつも嫌な感じがするので、できればそれ以外の、つまり“否定するわけじゃないけど他のルートもありますよね”というような意味合いを含む等位接続詞があったらいいな、と日々思っているのですが、いまのところ見つかりそうにないので、しかたなく“しかし”から文章を始めますと)しかし、その種の“お作法”にこの身を浸していないからこそ、むしろそれゆえに、生きてくる言葉の特権の如きものがあるのではないか、門前の小僧はそのように考えます。そしてその言葉の特権とは、煎じ詰めれば“質的世界”への注視、じぶんの身体から離れない限りでの、あるいは離れた際にはカッコつけずに“いま、離れました”と正直にいえるような、そんな言葉だけを使うことをじぶんに対して課す、そのことが許されている、ということではないでしょうか。
じぶんで言っていて、それはどこか“告白文学”あるいは“自然主義”の条件と似ているような気がしてきました。質を手放さないこと、量的データや外来の概念を経由するのだとしても、最終的には(この私としての)質へ帰っていくこと。ここではあえて、“実存”や“主体”といった仰々しい言葉ではなく、“質”という一字に切望を託しておきたいと思います。
生まれも育ちも大阪という生粋の関西人の友人に、(標準語しか使えない自分には憧れの)関西弁のレッスンをお願いしたところ、とりあえず、すべての文末に「知らんけど」をつけておけ、と言われたことがあります。私達はすべての事柄に対して“専門家”たることなど到底不可能である限りにおいて、おおよその事柄に対する言明には潜在的に“知らんけど”という末尾が隠れています。

この“知らんけど”を無責任さの現れと受け取ることも確かにできますが、私は、むしろ、ある種の謙虚さの提示ではないかと考えます。わたしはこう思う、感じる、考える、、、知らんけど。“知らんけど”は、当事者自身の質的実感に基づく言明を完全に否定することなしに、“訂正”されることを積極的に受け入れることに成功しています。“知らんけど”は、自分がアマチュアであることを認めながら、それでも自分の現在における暫定的な考え、感じていることを述べるための、ひとつの方法です。
『応答、しつづけよ。(Correspondences)』と題された、理論と詩的直感の融解がアルバムのように構成されたエッセイ集の冒頭(招待-アマチュアの厳密さ)で、人類学ティム・インゴルドは次のように記しています。
この本の主題である応答しつづけること(コレスポンデンシーズ)の中で、私は学術的な伝統の束縛を解き放って、アマチュアとして恥ずかしげもなく書く自由を楽しんできました。真の学者は皆、アマチュアであると私は信じています。文字通り、アマチュアとは、プロフェッショナルのように、キャリアを積み上げていくためではなく、関心、個人的な関与、責任の感覚に突き動かされて、愛するがためにそのトピックを研究する人のことです。
短絡的なアマチュアリズムの強調が、粗野なポピュリズムに陥る落とし穴を孕んでいるということに注意を促しながら、それでもインゴルドは、“アマチュアの厳密さ”ということを訴えかけます。ふつう、“アマチュア”という言葉と“厳密さ”は、両極に位置しているように見えます。“厳密さ”の担い手はアマチュアではなく“プロフェッショナル”であると見なされているからです。そのような認識は自明であり、間違いではありません。しかし、だからこそ、ここでインゴルドが執拗に“アマチュア”という言葉に託そうとしている別の“厳密さ”を、私はまっすぐに受け取らなければならないと思いました。
厳密さには、事実上、正反対の二種類があるように思えます。一つは、客観的事実の不屈の世界を記録し、計測し、統合することに精密さを求めるものであり、もう一つは、意識的な気づきと生き生きとした素材との間の継続的な関係において実践的な気づかいと注意を求めるものです。前者ではなく後者にこそ、応答(コレスポンデンス)の厳密さがあります。そしてここではまさに、的確さが求められるのです。それは精密さと混同されてはなりません。
アマチュアの厳密さとは、柔軟で、生を愛する厳密さであり、硬直と麻痺を引き起こすプロフェッショナルの厳密さとは対照的です。(強調は引用者)
インゴルドは本書の中で、詩作も行なっています。インゴルドの“私的≒詩的厳密さ”と、理論的な精密さがいかに統合されているのかということをここで紹介し尽くすことは(正直めんどくさくて)出来ないので、ご興味のある方はぜひ一度本を手に取ってください。
おわりに、アマチュアとしての、私的≒詩的厳密さが、あるいは“知らんけど的言明”が、単なるロマンチシズムや反知性主義に陥るのではなく、ポジティブな可能性として、むしろ考えることの公性に深く関わっているのではないかという仮説を残して、今年最後のnoteを結ぼうと思います。
朔太郎、中也、大岡昇平から太平洋を飛んでインゴルドに会いに行き、最後に登場してもらうのは19世紀、ドイツの大哲学イマニエル•カント先生です。

『啓蒙とは何か』と題されたエッセイの中でカントは、有名な、“理性の公的使用”と“理性の私的使用”という区分を示しています。啓蒙を成就させるために必要なものは、実に自由に他ならない、それも、“自分の理性をあらゆる点で公的に使用する自由である”とカントは言います。
ここで私が理性の公的使用というのは、或る人が学者として、一般の読者全体の前で彼自身の理性を使用することを指している。また私が理性の私的使用というのはこうである。公民として或る地位もしくは公職に任ぜられている人は、その立場においてのみ彼自身の理性を使用することが許される、このような使用の仕方が、すなわち理性の私的使用なのである。(強調部は紙面では打点)
ここでカントは“学者”という言葉を使っていますが、ここでの“学者”は、通常イメージされる“スペシャリスト”としての“学者”ではなく、むしろそれとは正反対に、自らの社会的立場を離れた、“素人”のヴェールを被った存在として位置付けられていることが判ります。それは、先のインゴルドが、“アマチュアの厳密さ”と呼んでいたものと、(二人の学問的方向は全く違うにもかかわらず)呼応してはいないでしょうか。アマチュアというアプローチは、スペシャリズムと相反するものではなく、私たちの生と知を結びつけるための、補完的で不可欠な立場のひとつです。そのことを真に引き受けることによって、はじめて、日常の、雑多な断片に対しても誠実であろうとする生が開けるのではないでしょうか。
